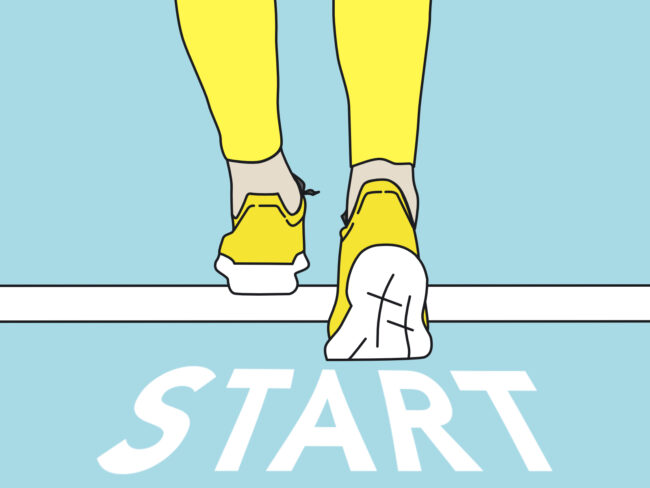「10年前の自分へ-ゼロからで大丈夫だから-」《週刊READING LIFE「タイムスリップ》

記事:青木文子(天狼院公認ライター)
「そうねぇ……」
その人はすこし遠くをみた。何かを思い出しているようだった。
事務所の机の向かいに座るその人は93歳。今日はその方の遺言作成が終わり、最後の打ち合わせの日だった。
「青木さんにも食べていただきたくて」
いただきものだというシャインマスカットを二箱手にさげて、バスを乗り継いでやってきて下さった93歳。そのエネルギーは眩しいほどだった。
司法書士として仕事をする中で、女性の大先輩に出会うことがある。
県職員を退職して70歳の方。これから終活をはじめたいからといって相談に来られた85歳の方。自分の遺言を書きたいといって、バスに乗って自分の足で歩いてこられたこの93歳の方。
仕事が一段落して、最後の書類をお渡しする。そしてご挨拶の時に私が人生の大先輩たちに尋ねることにしている質問がある。
「もし、目の前に、今の私と同じ年の自分が座っていたら、その自分に何と声をかけます? アドバイスがあるとしたらどんなアドバイスをしますか?」
そう私が尋ねると、みなさん、ふと遠くを見る眼差しになる。
歩いてきた道、出会ってきた人。脳裏には幾つもの場面が浮かんでいるのだろう。真剣な顔でその道のりの中の、何を言葉ですくい取ろうか迷っているようにみえる。
ほどなくして、ふっと顔が柔らかくなる。真向かいに座っている私に目線を戻したときは、もう言葉が決まっているようだった。
そして、もらった言葉たちは私の宝物だ。
私に、かつての自分を重ねているのであろう。言葉を口にしたあとの顔は、みんなとても優しい顔になるのだった。自分が歩いてきた道を愛おしみ、そして誇りに思い、なにより、歩いてきた自分自身に「よくやってきたね」と心のなかで言っているのが伝わってくる顔だった。
私は、目の前に10年前の自分がいたら、なんと声をかけるだろうか、なんとアトバイスをするだろうか。
10年前の私は必死だった。
右も左もわからず無我夢中で走っていた。
子どもたちを守るために自分で稼ぐことができるようになりたかった。仕事をできるように資格を取りたくて目指した司法書士。法学部出身でもなく、法律の授業は大学でひとつもとったことがない私にとって、司法書士受験は簡単ではなかった。
産まれたばかりの下の子はまだ0歳の乳飲み子で、子どもたちが保育園に行って家にいないときだけが勉強時間。なんとか、かんとか4年がかりで司法書士に受かったのが11年前のことだ。
司法書士に受かったのはもちろん嬉しかった。全身の力が抜けて「あぁ、もう勉強しなくていいんだ」と脱力した。合格してしばらくは合格の余韻に浸っていた。それはそうだろう。来る日も来る日も勉強して4年間。ようやく受かった司法書士試験。嬉しくないはずはない。合格してしばらくは合同研修があったり、特別研修があったりして、新しい出会いや目新しい出来事でにぎやかに日々は過ぎていった。
司法書士には現場の研修がある。各県によって違うが、例えば私が所属する岐阜県司法書士会では、6週間の配属実務研修というものがある。現役の司法書士の方について実務をさせてもらう研修だ。
私はかつて司法書士会の会長をされた、大重鎮の司法書士の方の事務所に配属になった。ここで私が気づくのだ。「あぁ、もう勉強しなくていいんだ」というのが全くの勘違いであったたことを。司法書士合格は、ようやくスタートラインに立ったに過ぎないということを。
司法書士の11科目はクリアして受かったものの、知識と実際の実務とは全く違う。実際に配属研修にはいって実務に携わってみると、とにかく何もかもがわからない。それに関する法律の条文は探せるけれども、ではどこに職印を押すのか? この場合は誰に何を確認するのか? 具体的なことがなにひとつわからない。
司法書士受験をはじめたときもわからないことだらけだった。でも受験であればひとつ知識を身に着けて問題の解き方をクリアしていけば良かった。ところがどうだ。いざ司法書士の仕事をはじめてみて、まったく違う世界に放り出されたことに気がついた。私の目の前にあるのは、受験問題に対して解答をすることではなく、仕事という間違えられないアウトプットをするということだった。アウトプットといえば聞こえがいいが、それはひとつひとつの細かい事実関係のチェックや、事務作業や、書類の作り方だった。そして私はそういった仕事がとても得意では無かった。
全くのゼロから何かを身につけるというのは途方もない作業だ。特に最初が簡単ではない。遠くにみえる富士山を登ろうと、来る日も来る日も歩いても、まだ登山口までたどり着けない、そんな心境だった。
右往左往するうちに6週間の配属研修は終わった。新人の研修だから、大目にみてもらったこともあるだろう。でもその時の私には全く余裕が無かった。かつて抱えていた円形脱毛症がまた再発しそうな勢いだった。
6週間の研修が終わると、事務所の先生が「このまま事務所を手伝わないか?」と言ってくれた。そして、その事務所で司法書士見習いとして仕事を始めることになった。
その事務所で手伝うことを決めたのはある人の存在があったからだ。
Aさんという。その事務所の事務員をされていた私とほぼ同年代の女性の方。もともと金融機関にいたといい、事務の手際も、判断も素早くてそつがない。このAさんは優秀なのはもちろんのこと、なにより素晴らしいのが人への教え方だった。
まず説明をして、仕事をひとつ任せてくれる。わからないことだらけの私はいちいち尋ねる。それに嫌な顔ひとつせずに答えてくれる。そして、またよく私が失敗をする。小さな失敗から、迷惑をかけるような大きな失敗まであった。
Aさんはいつも短く、はっきりをそれを指摘してくれた。でもそれを一切引きづらない。午前中どんなに私がひどい間違いを起こしても、隣同士の机で昼食をとるときにはそれはそれでいつもにこやかに会話をしてくれていた。今振り返っても、私が登山口に辿り着く前に登山を諦めたり、登りかけの山をもう無理だといって逃げ出さなかったのはAさんの存在が大きかった。
Aさんに教えてもらいながら、覚悟した。できないことは、ひとつずつ覚えていくしかない。仕事の中、走り書きでメモをとるようにした。毎晩、自宅に帰って子どもたちが寝静まってから、その日覚えたことをA5の方眼のルーズリーフに書き写す。
登記の手順や考え方、揃える書類の印鑑を押す場所から、ホッチキスの位置まで。少しでもぼんやりしていることはノートに書けない。すると自分が、何がわかっていないか、何がはっきりしていないかがよく分かる。翌日にAさんにノートを見せながらその部分を再度教えてもらう、そのくりかえしを続けた。
あるときAさんに尋ねたことがある。
「どうしてそんなに優しく教えてくれるんですか?」
「え? 私? 全然優しくないよ」
とAさんはおどけて笑った。
そしてこういった。どんな人でも最初はわからないのが当たり前だから。すこしずつできるようになっていくから。だから大丈夫だよ、と。
今もその頃にとったノートが残っている。
そのノートを開けると10年前のことが蘇ってくる。よくまとめてあるノートだ。今でもふと事務の書類の作り方を忘れると、このノートにお世話になることがある。その筆跡や、修正ペンのあとを指先でなぞると、その時の感情まで蘇ってくるようだ。
そう、私は必死だった。まったくの自分の経験が通用しないところに置かれた私。司法書士受験の時も、司法書士業務のはじめのときも、ターニングポイントになったのは「ゼロからやる」ことを覚悟したところだった。
人は今までの自分の経験値でできることをやろうとする。それがうまく機能しないと「向いていない」とか、「得意でない」とか、「もっと他の事がいいのでは」と考えたりする。もちろんそれが合っている場合もあるだろう。でもそれは時に劣化への道だ。だって、人は生まれたときは何一つ経験値がないのだから。どんな人も、人はまったくやったことがないことを積み上げて、ここまで来ているのだから。
今思うと、強制的に「経験がない世界に」置かれたことは私の力を引き出してくれた。そしてその連続が私をここまで連れてきてくれたのだった。
「もし、目の前に、今の私と同じ年の自分が座っていたら、その自分に何と声をかけます? アドバイスがあるとしたらどんなアドバイスをしますか?」
今までその質問を尋ねた方たちには、それぞれの人生とそれぞれの物語があった。司法書士の仕事をしながらも、つい身の上話を聞いてしまうのが私の長所であり短所だ。かつて大学時代に民俗学のフィールドワーカーとして、農村や漁村で聞き書き調査をしていた癖が出てしまうのだ
ある方は貧困の中、自分で学費をため、苦学し、最後大学の教授までになった女性であった。ある方は経済的にも何もかも恵まれた人生を送ってきたが、今子どもたちのいがみ合いの中で悩まれている方だったりした。ある方は家柄のいい生まれであるが、そのあと結婚が破綻して自分で仕事をはじめて今はもうその仕事も人に譲ってやめている方だった。
人生の大先輩たちが歩いて来た道は一つとして同じ道が無かった。私の質問への答えはもちろん、それぞれに違っていた。でも同じであったのは、そのどれもが私の背中を押してくれる響きを持った言葉だったことだ。
「迷わなくて大丈夫よ」
「頑張っているわよ、あなた」
「まだまだ走れるから、自分を信じて思い切っていきなさい」
私は目の前に10年前の自分がいたら、なんと声を書けるだろうか、なんとアトバイスをするだろうか。
ちょっと深呼吸をしてみる。
自分の目の前に10年前の自分がいると想像してみる。
必死で司法書士の仕事を覚えようとしていた私、5歳と9歳の子どもを抱えながらフルタイムで仕事をしていた私。まったく経験もなく、やり方もわからない司法書士という仕事で右往左往していた私。
そんな私に、今ならこういうだろう
「ゼロからで大丈夫だから」
私に言葉をくれた多くの先輩方が優しい顔になるのは、きっと自分自身のゼロからの道、ゼロからの途上の道を思い出すからだ。人は皆その道を歩いて生きていく。
そして今、私はまた全く新しい学びをはじめている。もちろん飛び込むのに勇気もいったし、わからない事だらけだし、それが上手くいくかどうかも自分に向いているかどうかもわからない。
それでも、10年後の私はきっと今の私に同じようにこう言うだろう。
「ゼロからで大丈夫だから」
そう、ゼロからで大丈夫。
どんなことも必ずゼロからはじまるのだから。そのゼロをイチにする勇気とエネルギーこそが人生を変えていくのだ。
◽︎青木文子(あおきあやこ)(天狼院公認ライター)
愛知県生まれ、岐阜県在住。早稲田大学人間科学部卒業。大学時代は民俗学を専攻。民俗学の学びの中でフィールドワークの基礎を身に付ける。子どもを二人出産してから司法書士試験に挑戦。法学部出身でなく、下の子が0歳の時から4年の受験勉強を経て2008年司法書士試験合格。
人前で話すこと、伝えることが身上。「人が物語を語ること」の可能性を信じている。貫くテーマは「あなたの物語」。
天狼院書店ライティングゼミの受講をきっかけにライターになる。天狼院メディアグランプリ23rd season及び28th season総合優勝。雑誌『READING LIFE』公認ライター、天狼院公認ライター。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/event/103274