あなたがよりよく生きるための遺言のススメ《プロフェッショナル・ゼミ》
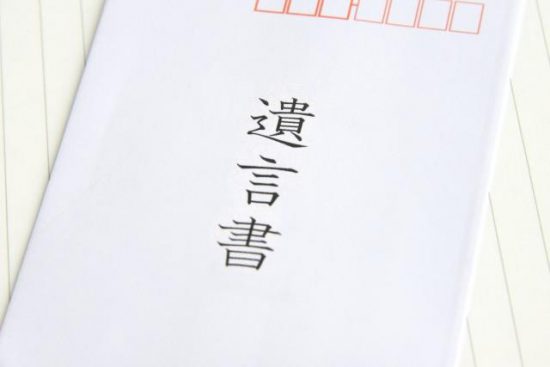
*この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
記事:青木文子(プロフェッショナル・ゼミ)
「いえ、あの方の遺言は私は預かってここにあります」
「おかしい! 父の遺言はこちらが本物のはずだ!」
突如不可解な死を遂げた大富豪。愛人が持参した遺言と息子に託された遺言。複数の遺言、どれも間違いなく本人の直筆であり、署名と押印がされている。一昔前のテレビドラマに火曜サスペンス劇場というドラマがあった。その中でみた一場面。遺言というと多くの人はお金持ちのものとか、ドラマの中のもの、とイメージする人が多いかもしれない。
「遺言を書こうと思うんです」
そう言って私の事務所に相談に来る人は多い。
私の仕事は司法書士だ。司法書士になって9年目。新人とはそろそろ言えないキャリアになってきた。司法書士としての仕事の中で、割と多い仕事のひとつが遺言をつくるお手伝いをする仕事だ。
元々、法学部出身ではない。二人目の子どもを出産後司法書士受験生になった。そこから4年間勉強して司法書士になった。大学時代も法律の授業はひとつも受けていないので法律的素養はゼロだった。なので「法律ってなんだか難しいよね」「そもそも専門家になにを聴いていいかもわからないんだよ」という気持ちはどの司法書士よりもよく分かる司法書士だと自分自身思っている。
お声がけを頂いて、年間十数回は遺言に関する講演会で登壇する。参加者の皆さんに遺言のイメージを聞いてみるとこんな言葉が帰ってくることが多い。
「なんだか遺言っていうとお金持ちのつくるものじゃないですか?」
「遺言の話をもちだすと、なんだか相手の死を待っているように思われると気まずくて」
「うちは財産がないから遺言はいらないかなって」
私も実は司法書士の仕事に就くまで、「遺言」というと、なにか死を想像させて縁起悪い感じ、とか、お金持ちでない人は別に書かなくて良いんじゃないの? と思っていた。
でも、今はそう思っていない。できるだけ多くの人が遺言をかいたら良いのに、と思っている。遺言だからといって高齢の方だけでなくて、できれば若者にも書いて欲しいと思っている。実際に私は司法書士として一時期「30代から書く遺言セミナー」というセミナーをやっていた。なぜ、30代からの遺言と言っていたのか。30代と言えば財産もそうあるわけでもなく、独身であったり、まだ実家に住んでいる人もいる。財産をどう分けるか、という意味で言えば、確かに遺言を書かなくてもいいといえば良い。
メメント・モリという言葉がある。日本語では「死を想え」などと訳されることが多い。ラテン語で「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」という意味の言葉だ。私がこのメメント・モリという言葉に出会ったのは中学校の図書室だ。写真家藤原新也。彼の写真集についていた題名がこの「メメント・モリ」だった。アジア放浪の間に取られたという写真は時に荼毘にふされる遺体が写され、時に犬に喰われる遺体が写されていた。決して美しい写真ではないが、その写真集から目を離せずに何回も開いたことを覚えている。
遺言を書くということは死を想うことだ。他のだれでもない、自分の死を想うこと。この自分の死ぬことにきちんと向かい合うことが、よりよく生きることにつながるのではないかと思っている。。もちろん、遺言を書くことは法的な書面として残された遺族の相続争いを避けることができたりする。でもそれだけではなくて、「死を想う」ことで、遺言は、その遺言を書く人の生き方を変える可能性をもっていると思うのだ。
数日前にSNSでどこかのお寺の掲示板の写真が載っていた。よくお寺の前にある掲示板。警句や短いお説法がかかれて張り出されていたりする。その写真に載っていたのは、黒々とした墨で「お前も死ぬぞ」と大きく書かれた紙が張り出されている掲示板だった。「お前も死ぬぞ」というのはとても直接的な言葉だけれど、遺言を書くことはそれを自分の胸に引き受けることなのかもしれない。
遺言というのは新しく書き直すと新しい遺言が有効になる。だから遺言は何通書いても良い。「30代から書く遺言セミナー」の中では毎年誕生日に遺言を書くということを提案していた。誕生日に自分の今までの生き方と、自分の最後を考えながら今できる自分の財産の残し方、誰に感謝の言葉を書いて、誰にどんな言葉を伝えておきたいかを考えながら紙に向かう。こういうことを表立っていうと、もうそれは司法書士のセミナーではなくて自己啓発のセミナーに近くなってしまうかもしれないけれども。
私にとって「遺言」の仕事はその人の物語を聴く仕事でもある。ただのシンプルな遺言であっても、その方がどんな人生を歩んできたのか聞く。これは私が大学時代、民俗学のフィールドワークをしていて、農村のおじいちゃん、おばあちゃんから話を聴くことをしてきた感覚が残っているからかもしれない。
ある日遺言をつくりにこられた方がいた。80歳の男性の方。メーカーの技術者として活躍されていたそうで、険しい表情で、小さなことも事細かに質問をして、説明を求める方だった。
ひとつひとつ説明をしながらふと思った。いつも思うのだ。この人はどんな人生を歩んでこられたのだろうか。この人はどんな風景をみてきたのだろうか。司法書士業務から離れているので、やや遠慮がちに聴く。
ある程度の高齢の方に、こういうとき私が最初にする質問は決まっている。実はその答えは計算すればわかるのだけれど、あえてその質問をする。
「あの、ひとつ質問させてもらってもいいですか」
「終戦の年に、おいくつだったんですか」
この質問をすると、その人の雰囲気がふっと変わる。もちろんそこにその人のつらい思い出があることもある。だからそっとそっと表情をみながら聴く。そしてその人がそれ以上話さなければもうこの質問はそこで終わりだ。でもこの質問された方の多くはそこからその時みたもの、聞いたことを話はじめる。まるで長い間、その人の中に貯められた水が急に堰を切って流れ出すように。
その80歳の男性の方はこういった
「ちょうど小学校の3年生のときでね」
「私はね、終戦で満州から戻ってきたんですよ」
「親がね、僕たち兄弟3人の手を引いてね」
「10歳だからもう何がなんだかわからなかった」
「でも日本の陸地が見えたときは、よくわからないけれど涙がでましたね」
その物語が語られ始めると、私はもう一気に引き込まれてただの一聴衆になってしまう。もうあとはところどころ短い質問をするだけだ。その人は自分の人生の話をし続ける。30分ほどだろうか。その人は話を終えた。そしてすこし沈黙した。10畳もない小さい事務所はシンとした。でもその静寂は暖かかった。
「こんな昔の話、今まで人にしたこと、なかったかもしれんね」
その人はそう言ってふっと短く息を吐いた。
もちろん遺言をつくるために、そんな話を聴く必要はない。大学時代にフィールドワークをしていた名残で、私がただ、人の物語を聞きたいだけなのかもしれない。でも私は何度も見ているのだ。人が物語を語った後に表情が変わることを。そして知っているのだ。人は物語を語った後に何かを手放せることがあることを。
その方の遺言が出来上がった。
「これで思い残すことはないね」
「あとは僕が死んだら、青木さんのところにこの遺言持っていくように息子に言っておくから」
その方にお礼をいって、帰られる背中に向かってお辞儀をする。そのお辞儀は仕事が終わったあとの依頼者を見送るお礼だけれども、その人の生きてきた人生への尊敬と敬礼の気持ちが混じっている。
遺言にはいろいろな書き方がある。純粋にどの財産を誰に渡す、という内容だけの遺言もある。そして日本の遺言にはそういった遺言が多い。でも遺言は「遺す言葉=遺言」だ。私は遺言には、残される人たちへのメッセージを入れて欲しいといつも伝えている。
「お子さんに、なにか伝えたい言葉とかないですか?」
「いやぁ、そんなのはないねぇ」
「でも例えば、こういう感謝の言葉とか、こういうこととか伝えたいと思いませんか?」
それを聞いて
「じゃあ私、その言葉を紙に書いてくるから青木さん見て頂戴」
という人もいれば
「うんうん、青木さんのその感じが良いと思うから、ひとつわしが今からいうように文章かいてくれ」
と私に代筆を頼む人もいる。
私のところで遺言をつくるお手伝いをした方は、ほとんどが必ず遺言の中に家族へのメッセージが書かれている。司法書士になって9年目にもなると、遺言を書くお手伝いをさせていただいた方で亡くなる方も出てくる。先日、何年か前に遺言のお手伝いをした方が亡くなられた。遺言のお手伝いの時にお会いした息子さんが、私のことを覚えていて、お父さんの遺言を持ってきてくださった。遺言に書かれてあるように自宅 の建物や土地、預貯金の相続の手続きのお手伝いをした。相続の手続きが一段落したところで息子さんがこういった。
「青木さん、うちの親父は家族に「ありがとう」とか言わない人でね」
「もちろん家族に手紙を書いてくれたことなんか一度もないんですよ」
「でもね、青木さんにいわれて、遺言の中に手紙みたいな言葉を書いたじゃないですか」
「子ども二人に恵まれて嬉しかったとか、みんなに感謝しているとか、これからも家族仲良く過ごしてくれとか」
「あれ読むと泣けてきちゃうんですよね。なんだか親父の声が聞こえてくるような気がして」
あなたは普段人に自分の伝えたい言葉を伝えているだろうか。自分の言葉を遺しているだろうか。言葉を文章にして遺すということは、もう会えなくなった後でもその人に言葉が伝わる可能性が残る行為だ。
文章の中でも遺言は特別な文章だ。人は遺言を書くとき。「自分が死ぬ」ことを必ず意識する。あなたが遺言を書くことは、あなたが「死を想う」こと。あなたが遺言を書くということは、生きているうちにつながっている人たちへ思いを馳せること。
日常の中で「死を想う」ことはなかなか出来ない。毎日の仕事、毎日の暮らし。変に病気にならなければ「おまえも死ぬぞ」という事実からは目をそむけていられる。でも間違いなく人は死ぬ。そこから目をそむけてもそこからは逃げられない。逆に目を大きく見開いてそれを受け止めた時に、その向こう側に鮮やかな「生きる」道を歩けるのかもしれないと思う。そのためのひとつの方法が遺言を書くことなのかもしれない。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ プロフェッショナル」にご参加いただいたお客様に書いていただいております。
「ライティング・ゼミ」のメンバーになり直近のイベントに参加していただけると、記事を寄稿していただき、WEB天狼院編集部のOKが出ればWEB天狼院の記事として掲載することができます。
http://tenro-in.com/event/50165
天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
東京天狼院への行き方詳細はこちら
天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
【天狼院書店へのお問い合わせ】
【天狼院公式Facebookページ】
天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。


































































