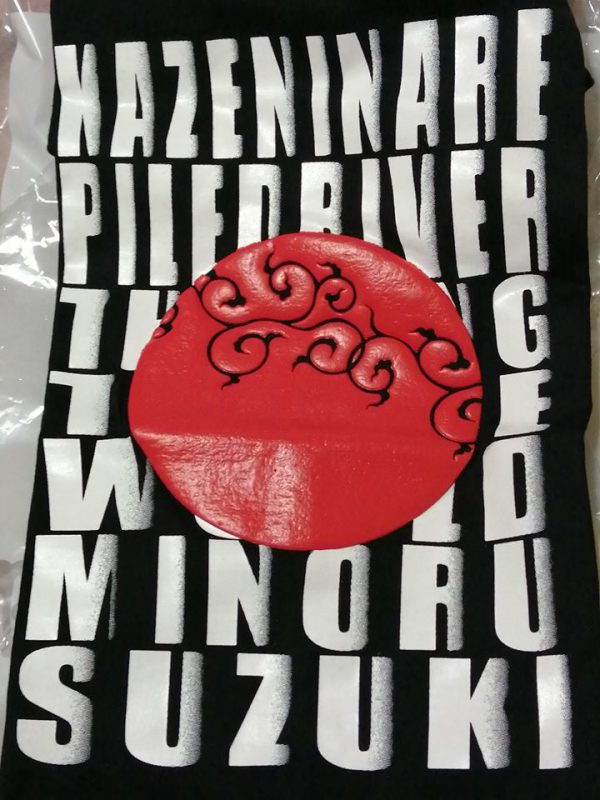「あなたのその言葉が届くように」《週刊READING LIFE Vol.72 「人間観察」》

記事:青木文子(天狼院公認ライター)
広い体育館だった。一番後ろの壁に向かって立っている相手の背中が見えた。
「こんにちはーーーー!」
私は思い切って言葉を投げた。
「あ、言葉が相手の頭を飛び越えましたよ。相手に届いていませんね、わかりますか?」
淡々とフィードバックするのはこのレッスンの主催者竹内敏晴さんだ。うむむ、わかったようなわからないような。ならばと今度は相手の背中を狙い澄まして、ゆっくりと声をかけてみる。
「こ、ん、に、ち、は」
「今度は相手とのちょうと真ん中あたりに言葉が落ちましたね。届いてませんよ」
舞台を背にした私から一番向こうの壁まではゆうに30mはある。その途中のどこかに私の言葉が落ちているのが竹内さんには見えるらしい。言葉とは目に見えない。キャッチボールの公式球のように相手に投げたボールが見えるのだろうか。
竹内敏晴さんはからだとことばの専門家だ。自分自身難聴から言葉を習得する中で培った感覚を研ぎ澄ませて、演劇を通したレッスンを行っていた。通称竹内レッスン。竹内さんの歩いてきた道のりとその深さを簡単に説明することはできない。ひとついうのであれば、竹内さんとの出会いは、私が関わっていた鳥山敏子さんが、竹内レッスンを通して、自分を取り戻していったことからだった。
竹内さんは「声の産婆」と呼ばれていた。その人が本当の声をどこで出せなくなっているか、身体のどこをこわばらせているのかが、自分の身体に鏡のように写しとって感じる力を持っていたという。竹内さんの本を何冊も読んで、鳥山さんからも話を聞いて、ずっと憧れていた人が竹内さん本人が、今、目の前にいる。
「では、今度はひと組づつやってみましょうか」
レッスンの参加者は10名。5組が1組づつあいさつのワークをする。
「こんにちは!」「こんにちはー」「こんにちは」「こーんにちはー」
背中を向けている側は、そのあいさつを聞く。そして、ひとりづつ、その言葉がどこに届いているか、言葉にして相手に返す。
自分の横に並んでいる同じレッスン参加者が「こんにちはー」と相手の背中にあいさつをしては、竹内さんからつぎつぎにフィードバックをもらう。ひとりも相手に言葉がきちんと届いている人はいなかった。
自分も相手にあいさつをし、相手からのあいさつを背中で受けているうちに身体の感じが変わってきた。すこしづつ見えてきた。いや感じられるようになってきたと言っていいかもしれない。
ある時の「こんにちは」はまるで相手が受けとることを考えていない暴投の野球ボールのようだ。ある時の「こんにちは」は相手は言っているものの、どうせ届かないと思って言っていることがわかる。
そうか。これは見るんじゃないんだ。その言葉が投げられたときにできた磁場が私の身体の中に電流を起こす。その電流を身体全体で感じると空間に言葉が3Dでみえてくる感覚。
「この中の一人にあいさつすることもできるんですよ」
竹内さんが言った。向こうの壁側に背中を見せて立っている5人。竹内さんが私のそばに来た。私は横並びの5人の一番真ん中に立っていた。
「いまから右から2番目の人にあいさつします」
竹内さんはこちら側の5人を集めて小さな声で言った。その小さな声はもちろん体育館の向こう側には聞こえないような小さな声だ。竹内さんが壁の方に向き直った。
え? この中の一人にだけあいさつをする?
「あいさつしてみるので、自分にあいさつされたと思った人は手を上げてくださいね」
竹内さんが向こうの壁の5人にそう言った。
「こんにちは」
その瞬間、右から2番目に立っていた人がスッと手を上げた。そしてこちらを振り返った。目を見開いているのがわかった。
「今、自分はあいさつされました」
壁側のほかの誰も手を上げなかった。残りの4人は一斉に振り返った。その人の隣の人が言った。
「今、僕の隣の人にあいさつしたってわかりました」
もう、口があんぐりである。その頃の私にとって、これは超能力のように思えた。まっすぐに言葉が届くことなんてあるのだろうか。いやいやいや。でも確かに届いた人はわかっている。心の中で、問答を繰り返す。
そう思った私の心の中が見えるように、竹内さんがこちらを向いた。
「青木さん、背中を向けて立ってみてください。僕があいさつしてみますね」
え? 私? ドギマギしながら体育館の舞台に向かって立った。胸の位置ぐらいに舞台があった。舞台には分厚い緞帳が降りていた。竹内さんが体育館の反対側の壁まで歩いていくのが気配でわかった。リズミカルな足音が聞こえてきた。ほかの参加者は座ってことの成り行きを見守っているようだった。
私はゆっくりと目をつむった。身体の感覚、耳の感覚に神経を集中したかった。体育館が一瞬静かになった。
「こんにちは!」
言葉が飛んできた。いや、言葉が届いた。まっすぐに、私の背中に。私の心に。思わず目を見開いた。緞帳が少し揺れたような気がした。力強い言葉だった。その言葉は投げつけられたものではなかった。ほかの誰かに言うのでもなく私に、私自身へ「こんにちは!」という言葉が届いた。言葉が届いたというよりもあいさつが届いた。なんといったらいいのだろう。それは握手のために差し出された暖かい手のようだった。私は心の中でおもわずその手を握った。
これがあいさつなのか。振り返って竹内さんをみた。
「届きましたよね」
竹内さんは言った。竹内さんは私に言葉が届いたことをわかっていた。あいさつをうけとったあとに急に竹内さんはのことを近く感じるようになったのが不思議だった。
言葉は音として耳に聞こえるものではあるが、聞こえているからといって、言葉が届いているとは限らない。この発見は私にとって驚きだった。
あなたのその言葉は届いているのだろうか。わたしのその言葉は届いているのだろうか。
そこから私の言葉を届けられる身体への旅がはじまった。レッスンとワークを重ねる中で、すこしづつ私の身体はひらかれていった。言葉は身体から発せられる。言葉を発する側が、言葉を届けられる身体を持っているかどうか。そしてもうひとつ、受け取る側が受け取る身体を持っているかどうか。
どんなに相手が言葉を重ねていても、こちらに届いてこない言葉がある。もちろん言葉としては理解できるけれども、届けられた身体に響かない。相手の身体を感じると、その言葉の源がみえてくる。
私は相手に届けられる言葉を発しているだろうか。いまもそのための旅の途中である。あの体育館のレッスンから20年以上経った。竹内さんのあいさつがまっすぐに身体に届いたあの瞬間を思い出す。目を見開いたときに揺れた緞帳。あの緞帳は風にゆれたのか、言葉に揺れたのか。
人間観察とは身体観察だ。身体を観察するためには、何が必要なのだろう。それは自分の感覚に嘘をつかないこと。それはあの日の竹内さんのように。そして、あの日レッスンの中で、相手の言葉が届くことがすこしずつわかっていった私たちのように。
◽︎青木文子(あおきあやこ)(天狼院書店公認ライター)
愛知県生まれ、岐阜県在住。早稲田大学人間科学部卒業。大学時代は民俗学を専攻。民俗学の学びの中でフィールドワークの基礎を身に付ける。子どもを二人出産してから司法書士試験に挑戦。法学部出身でなく、下の子が0歳の時から4年の受験勉強を経て2008年司法書士試験合格。
人前で話すこと、伝えることが身上。「人が物語を語ること」の可能性を信じている。貫くテーマは「あなたの物語」。
天狼院書店ライティングゼミの受講をきっかけにライターになる。天狼院メディアグランプリ23rd season、28th season及び30th season総合優勝。雑誌『READING LIFE』公認ライター、天狼院公認ライター。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/103447