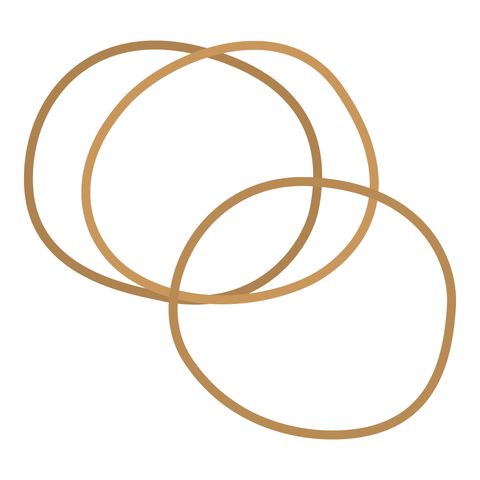道を踏み外してみたら《週刊READING LIFE Vol.74「過去と未来」》

記事:石崎彩(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
足元から目が離せない。
ゴツゴツとした石が露わになった山道。
段差が一定でないため、腿を上げて足を着地させる場所に神経を使う。
なるべく体力を消耗させないように教わった歩き方もすでに効果はない気がする。
足を上げるたびに筋肉が絞られるような痛み。
酸素が足りず、自分の息の音なのにうるさく感じる。
前を行くその人はいつになったら歩みを止めるのか。
足元に注意しながら、ちらりと目線を上げると、腕を胸あたりで組んでリズミカルに足を運ぶ姿が目に入った。鼻歌でも聞こえてきそうな軽さだ。
まだしばらく休憩するのは先になりそうだなと、顔をがっくりと足元に戻して、再び足に力を込める。
「とんでもない所に連れてこられてしまった……」
私が勤める飲食店に度々やってくるお客さん。
同年代ぐらいだったこともあり、いつも軽く話しを合わせる関係だった。
ある日「山に行こうよ」と誘われた時も、冗談半分に「いいですよ」と返した。
それが、数日後に詳細な日程が決まり、断るのをためらっている間に登る山も決まった。
「まあ、ハイキングみたいな感じだったら楽しいかもな」と、気楽に構えていたのだが……。
ずっと山道を登りっぱなしで、平らな道がない。
おまけに整備されていないからステップが一定の間隔を保てない。
2時間、3時間階段を上るのよりもさらにキツい。
唯一良かったのは、話さなくていいことだろうか。
正直、たくさんのお客さんに関わる仕事ではあるものの、私は人と打ち解けるのが得意ではなかった。その場で話しを合わせることはできるけど、話しを続けるのは苦手。プライベートは休みが合わないこともあり、かつての友人たちをほとんど失っていた。
密かに悩んでいた人間関係の不得意さ。
登っている合間に「息上がりますね」と軽く交わすだけで、なんとなく一体感が生まれる。
アウトドアはそれだけで話題に困らなくていいかもなと思っていると、ようやく頂上にたどり着いた。この時にはもう足の痛みも汗も疲れもピークに達していたが、頂上からの見晴らしと達成感で、全ての不快感がどうでも良くなった。
私を誘った彼は、涼しい顔をしながら笑顔で「よく頑張ったね」と、汗拭きシートを差し出す。そして着衣を脱ぎだし、体をシートで拭き始めた。
目のやり場に困って、視線を山々の稜線に向けたが、彼の綺麗に引き締まった腹筋から胸筋にかけてのラインは目に焼き付いたまま。私は着替えるわけにいかず、上着だけを脱いで体が冷めるのを待った。
「私、変な態度になってないだろうか?」
急に焦ってきて、動揺している自分に驚いた。
普通に話さなくては、変に思われる。
せっかく誘ってくれたのだから、喜ばなくては……。
筋肉の酷使がストップしたのと、山からの風で少し寒さを感じ、ザックから上着を取り出そうとする。すると、それより早く彼が上着を私の肩にかけようと手を差し出した。
急に距離が近くなった瞬間、とても懐かしい感情が通り過ぎた。
「山の上は夏でも冷えるから、早めに着替えた方がいいよ」
そう言って、コーヒーを沸かし始める動作は無駄な動きがない。
通り過ぎた感情の後を追うように、再び視線を青々とした稜線の風景に戻す。
かけられた上着を握ったまま、しばらく彼の方を向くことができなかった。
山から帰ってきてから、すっかり何かが変わってしまった。
それまで、親しい友人もいなくて、この先ずっと1人でひっそりと暮らすのだと漠然と考えていた。昼から夜まで働き、人が楽しむ時間にサービスする。その楽しい時間が私にサービスされることはない。
当時、貧困層の女性たちが盛んにノンフィクションで取り上げられていたこともあり、暗い将来しかないのだと思うようになっていた。ノンフィクションに出てくる悲惨な女性たちは、将来の私。働けなくなり、貯金も底をつき、借金だけが膨れ上がる。
そんな悲惨なイメージは、現在の自分にも投影され、今の自分は不幸でなくても不幸の直前にいるのだと思っていた。
最悪の事態を防ぐために、将来の不安を和らげるために、節約し真面目に働いて、毎日をやり過ごす。
それがどうだろうか。
山から帰ってきてから、1日、1日に期待している自分がいる。
「今日は、あの人は来るだろうか」と。
いつ来ても恥ずかしくないように、きちんとメイクをするようになった。
今度会った時、もっとたくさん話せるように山のことを調べるようになった。
あの人の知り合いが来たら、積極的に話すようになった。
毎日が楽しくなっていることに、気が付いた。
今思えば、人付き合いがあまり好きではないのに誰かの誘いを受け入れたなんて不思議だ。
それまで誘われたことがないわけではない。自分なんかと話しても楽しくないし、がっかりさせるのだったらと、言葉を濁して逃げるのが常だった。
だけど、その人の誘いから逃げなかった自分。
多分、将来の不安を解消するための毎日に、知らずのうちにストレスを感じていたのだと思う。
「どうなるかわからない未来のために、1日1日を消耗しているのではないか?」
未来は予想できないけど、明日は今日と同じルーティーンをこなす。
朝起きて、昼に店に行き、準備をして深夜まで働く。
予約が入っているから、働く。人がいないから、働く。明日も、働く。
ある人が話していた。
過去の積み重ねが現在。現在の積み重ねが未来。
過去と同じ繰り返しをしていて、訪れる未来が劇的に変わることなんてない。
未来を変えたいのだったら、今現在の「角度」を変えなければいけない。
ある本にも書いてあった。
個人の努力よりも、環境を変えることが一番手っ取り早く人を変えることができる。
何かを変えたくて、一歩だけ現在の道からはみ出してみた。
そうしたら、見事に生活の色が変わってしまった。
「彼は、私のことを変えてくれる人かもしれない」
しかし、それから半年間、彼が店を訪れることはなかった。
山から帰って1ヶ月後、より頻繁に来店する彼の知り合いと仲良くなり、それとなく話しを聞いた。
「彼は本気で山が好きだからね。海外の山に挑戦したいんだって。仕事終わりには毎日ジムに行っているからなかなか捕まらないんだよね。鍛錬のために週末は必ずどこかの山へ登りに行っているよ。今度また誘ってみるね」
それを真面目に受け取り、私はいつ会えるともしれない彼を待った。
日帰りで行ける山にもよく足を運ぶようになった。
「もしかしたら、この山の頂上に偶然彼がいるかもしれない」
バカみたいだが、そんな妄想を期待して登るのは楽しかった。
今日登った山のことをいつか彼に話せるように、しっかりと目に焼き付けて毎度下山した。
けれど、いつまで経っても彼には会えない。どうしているのかもわからない。
期待はだんだんと絶望に変わる。
彼は私を変えてくれる人ではなかった。
私は何も変わってはいなかった。
実は、私は彼の連絡先を知っている。
知っているのに、連絡ができなかったのだ。
私のことを知って残念に思われたら、辛い。
興味を持ってもらえていないことが、辛い。
日が経つにつれて悶々とした想いはどんどん膨らみ、限界がきた。
「今の角度を変えなきゃ、未来は変わらない。また、私は変わりたい」
彼にどう思われようと、何か行動を起こさなければ自分がダメになる。
そう決意した矢先、彼が店を訪れた。
彼は一緒に山に登った時と同じような笑顔を見せて、話しかけてくれた。
私がこれまでに登った山について話すと、うれしそうな顔をして「今度、また一緒に登ろうね」と告げて帰って行った。
有頂天になった私は、今までしたくてもできなかった彼への連絡をした。
「〇〇さんと山に行きたいです。いつなら一緒に行けますか?」
「もちろん! 春になったら一緒に行こう」
その時は年末だったので、まだずっと先。
それでも、自分の行動が現実を変えたことに高揚した。
ものすごく大きな一歩。
彼が私を変えてくれるのではない。私が私を変えるのだ。
そうして、長い冬を過ごし、春が来た__。
朝5時、まだ辺りは暗い。練習通りアイゼンを登山靴に装着し、ピッケルの使い方をあらためて復習。時間を確認し、山頂までのおおよその時間を計算する。ヘッドライトを灯すと、おぼろげだった白い輪郭がはっきりと雪の形となる。
深呼吸。冷たい。けど、頭が冴える。
アイゼンをはめた、ロボットみたいな足を雪面に一歩踏み出す。
ガシガシと、雪を引っ掻くように登っていく。
先ほど出た山小屋には、私の他に年配の女性が2人と若い男性が1人いた。
誰よりも早く出たので、私より先に進む人はいない。
こんなに早朝に出るのも、雪山も、前後に誰もいないのも初めて。
怖いと自覚してしまったら、先には進めない。
「あの人も、この道を登ったのかな?」
初めての雪山は足がうまく運べない。ピッケルを杖のように使って、足を助ける。
林を抜けると、そこは森林限界の先。
高木がなく、白い世界が広がっていた。
標高2千メートルを超えるのも初めて。こんな世界があったのだ。
真っ白な雪は、ルートを非常に分かりづらくする。
昨晩雪が降ったため、昨日の登山者の足跡はほぼない。
尾根道だと思われる輪郭を頼りにさらに進む。
傾斜はどんどんきつくなり、雪の斜面にピッケルを刺して腕に力を込めないと登れなくなってきた。
まるで壁を登っているみたい。
本当にこのルートでいいのか?
不安がよぎる。
この坂を登り切ったら、見晴らしが良くなる。そこで、地図を確認しよう。
必死の思いで登り切ると、私が目指すピークが見えた。
そして、遥か先に人がいる。
「あの人は……」
一瞬、妄想が浮かぶ。
けれどすぐにその妄想を振り払い、私の先をゆく人影の存在に勇気付けられる。
このルートであっていた。あの人を追えばいい。
鋭角に切り立った尾根。その側面にピッケルを刺して体を支え、慎重に一歩ずつ進む。
私のすぐ右下、滑らせたらしばらく止まらないだろう。
いや、下手したら岩にぶつかって死ぬかもな……。
今、まさに自分の命を自分で運んでいる。
死なないように、自分に神経を張り巡らせて動かしている。
生まれて今まで、こんなにも自分の命を意識したことがあっただろうか。
そして、この感覚がこんなにも充実した気力を自身に与えてくれることを初めて知った。
「あの人は、いつもこんな感覚で登っていたのか。……そりゃやめられないよね」
切り立った尾根を渡り終えて視線を上げると、前方のその人がピークに立っているのが見えた。そして、降りてくる。
すれ違う時、私はその人に笑顔で「ありがとうございます」と告げた。
その人は軽く挨拶を返し、下山していった。
もちろん「あの人」じゃない。
わかっていたけど、感謝せずにはいられなかった。
頂上にたどり着いた時、達成感とともに奇妙な感覚に見舞われた。
風の音しかしない。
動くものが何一つない。
雄大な雪山の重なりが、ただ延々と続いている。空の青さが鮮やかすぎて、本物かと思うくらいだった。
たった1人、私しかこの世界に存在しないみたい。
1年前に感じていた孤独感とは全然違う。1人だけど、私はどこへでも行ける。自由だ。
登る前に感じていた空虚さは、もうなかった。
あの人と約束していた登山の前日、彼の友人から連絡があった。
自宅で倒れていたところを発見され、そのまま帰らぬ人になったと__。
蜘蛛膜下出血だったそうだ。
突然すぎて、何もわからず、しばらく自分がどう生活していたのかも思い出せない。
人の命の儚さに、ただただ呆然とした気がする。
しばらくして山に登ろうと思ったのは、自分なりの弔いだった。
私は、その人のことを山以外で知らなかったから。
だけど、私はその人からたくさん過ぎるほどのことを教えてもらった。
現在からはみ出すことで、生まれるたくさんの感情、そしてその感情がこれまでと違った現実を作っていくということ。
雪山に1人で登る日が来るなんて思ってもみなかった。
そして、自分がこんなにも自由であるなんて思ってもみなかった。
未来は無限に可能性が広がっている。
けれど、過去の繰り返しの中では、想像できない未来はやってこない。
今の角度を変えて、これからも私は道を外れ続けていきたいと思う。
□ライターズプロフィール
石崎彩(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。 http://tenro-in.com/zemi/103447