短編小説『海のカイブツ』
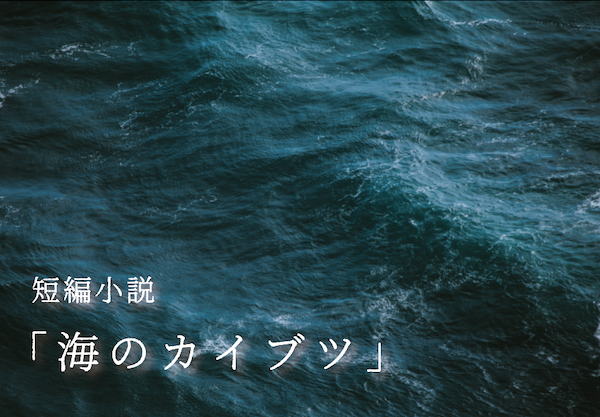
*この記事は、「ライティング・ゼミ」を受講したスタッフが書いたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
文:斉藤萌里(チーム天狼院)
*このお話はフィクションです。
怪物に喰われた。
いつの頃からから、正確には分からない。けれど奏太(そうた)の通う凪浜(なぎはま)小学校では、こんな物騒な噂が流れ出した。
満月の夜に凪浜に行くと、悪いことをした人間は、怪物に喰われる。
教室の片隅で集まる女子グループが、「えー」「うそー!」とはしゃぎながらそう話していたのを、奏太はたまたま聞いたのだ。
「悪いことをした」の基準を、奏太は知らない。
例えばそれは、学校で遅刻や欠席を繰り返す行為かもしれない。
それとも、友達の悪口を言ったり誰かを傷つけたりすることだろうか。
家では家事の手伝いをせず、休みの日にぐうたらテレビやゲームをやる、ということもありえる。
奏太は自分の頭で考えられる、ありとあらゆる「悪いこと」を想像してみた。
でも、そのどれもが、自分にとっては些細なことだと言わざるを得ない。
奏太の心のうちにある「罪悪」は、遅刻や怠惰のように軽いことではないと、思い込んでいた。
「悪いことをした」の基準が分からない奏太にとって、「悪いこと」をありったけの想像で 補うしかなかった。クラスの女子たちや、また男子までもがおよそ現実的でない話をしているというのに、誰も真実を知らない。
奏太は知りたかった。
凪浜の海に潜む、怪物の正体。
それから、「悪いこと」とは一体何なのか。
知らなければならない理由が、奏太にはあったから。
噂が流れ始めたのは今から2ヶ月前、5月始めのことだった。
「ねえ、米倉くん今日どうしたの」
5年2組の教室。給食時間に入り、当番が給食を運んで来てくれる時間帯。当番じゃない人たちは各々友達と喋ったり、席について本を読んだりして、自由に過ごしていた。
奏太はこの時間が好きだった。
お腹が少し減ってきてお預け状態にされているけれど、ちょっと待ちさえすれば当番の人が温かい給食を持って来てくれる。父親と一緒にレストランに行った時のように、お客さん気分でご飯が運ばれてくるのを待つだけの時間。
奏太はこの時間に、決まって本を読む。最近はまっているのは、江戸川乱歩の「少年探偵団シリーズ」だ。他のクラスメイトたちは、あまり本を読まない。男子は男子で集まって今日の昼休みに何をして遊ぶかで盛り上がっている。大抵はその中に一人、給食当番であるはずの人が紛れていて、先生から怒られるのが相場だ。
人間、お腹が少し空いているぐらいの方が、何事にも集中できるものだ。
しかもこの後美味しいご飯が食べられると決まっているなら、なおさら。
本を読んでいる間、いつもなら誰も話しかけてこないのだが、この日は三枝愛菜(さえぐさまな)が本を読んでいた奏太の左横から顔を覗かせた。女の子からこんなふうに突然話しかけられたことのなかった奏太にとって、それは珍事以外の何ものでもなかった。
「米倉くんが、何だって?」
江戸川乱歩の『透明人間』を読んでいたのを一時中断し、奏太は三枝愛菜の方を見た。
「今日、ずっとぼーっとしてるじゃん」
「そうだっけ?」
「うん。先生に呼ばれても気づかないし、宿題やってないし。皆川(みながわ)くん気づかなかった?」
「……ごめん、気づかなかった」
「仲良いのに、へんなの」
奏太にとって、米倉くんに対して「仲が良い」と感じたことはなかった。普通に話はするけれど、放課後に遊びに出かけるような仲じゃない。ならば、どうして三枝さんは奏太と米倉くんを仲良しだと思ったんだろう。一度でも奏太と米倉くんが話すのを見たからかもしれないし、体育の授業で一緒にペアを組んでラリーをしていたのを見たからかもしれない。
いずれにせよ、三枝さんの勘違いだ。
「まあいいや。とにかく、いつもと違うの!」
奏太は三枝さんの強い口調に押されて、思わず米倉良太の方を見た。
しかし、米倉くんは席についていない。そうか、彼は今日給食当番なのだ。
「たまたまじゃないかな。体調が悪いとか」
「そんなんじゃないって! だって、あの米倉くんが、だよ」
三枝さんは、ぐいっと奏太の方に顔を寄せた。
奏太は反射的にちょっとだけ上半身を後ろに反らした。
三枝さんの言いたいことは、奏太にも分かる。
米倉良太は5年2組のムードメーカーで、時にクラスで問題を起こし、時に消沈している運動会での練習を盛り上げてくれる。
良くも悪くも、クラスの中心人物なのだ。
その米倉くんが、元気がなくぼうっとしているとなれば確かにおかしい。
どうやらこれは三枝さんだけが感じていることではなく、米倉くんと本当に「仲良し」である岸田翔(きしだしょう)がムズカシイ顔をしているのを見ても事実らしかった。
「言われてみれば確かに今日、米倉くんの声聞いてないな」
今日一日を振り返ってみると、奏太の頭の中に米倉良太の騒がしい声が録音されていない。
「ね。絶対なんかあるんだって」
それだけ言うと、三枝愛菜はたったと自分の席に戻っていった。
同じタイミングで給食当番の人たちが戻って来て、配膳台に鍋を並べ始めた。
ばたん、という嫌な音。
教室で待機していた奏太たちは一斉に顔を上げる。
「米倉大丈夫か!?」
見れば、教室の前方で、膝をついて倒れている米倉良太がいた。彼の視線の先には、鍋からぶちまかれたカレー。クラス中の人がおそらく楽しみにしていたであろうカレーの香ばしい香りがじゅっと教室に充満していた。
おかしいのは、それからだった。
普段の米倉くんならばそこで「うわー! 最悪」と雄叫びを上げるところなのに、今回ばかりは放心状態で、もはや美味しい食べ物でも何ものでもないカレーを見つめるだけだった。衝撃すぎて、言葉が出ないという感じに。
「……カレーはもらってくればいいよ」
担任の先生がフォローに入り、何とか立ち上がった米倉くんは無言のまま教室から出ていった。
奏太を含め、クラスの誰も彼の背中の小ささについて、語り合うことなどできずに。
米倉くんの人が変わった事件は、その後2ヶ月も尾を引いた。つまるところ、彼の様子がおかしい日々がずっと続いていた。三枝愛菜が奏太に米倉良太のことを告げてから少しはましになったものの(少しずつ仲の良い男子同士で群れるようになったぐらいだ)、やはりまだどこか違う。
例えるなら、自分よりも強い何者かに怯えているように見えた。
米倉良太はこれまでずっと「クラスの中心」で、彼を怖がる人がいても、彼が怖いと思う人間はいない。そう思われても仕方のない人だったのに。
一体彼は「何に」出会ってしまったんだろう。
奏太はあれからずっと米倉良太を観察していたけれど、なぜ彼の性格がこんなにも変わってしまったのかという検討がまるでつかなかった。
けれど、奏太の周囲では少しずつ、とある噂が立ち始めていた。
「米倉良太は『海の怪物』に会ったらしい」
女の子だったか男のだったのか、最初に言い始めた人が誰なのか、誰にも分からない。
彼の変わりようを面白がって広めたい誰かのいたずらだったのかもしれない。
ただ一つ言えることは、米倉良太の様子がおかしくなってから、彼と同じような症状にあう人が数人出てきたということだ。
「ねえ、知ってる? 夜に凪浜に行くと、性格が変わっちゃうんだって」
「性格が変わるんじゃないよ。『怪物』に出会うんだよ」
「そんなの嘘でしょ」
「いやいや、だって、聞いてよ。米倉も岸田も白藤さんもみんな最近おかしいんだよ。いつもと違うよ。私、三人に聞いてみたの。三人とも最近夜に凪浜に行ったんだって」
いろんな場所で、いろんな時間に、皆が口々にそう言っているのを奏太は半信半疑で聞いていた。奏太に対して直接凪浜の夜の怪物の話をしてくる人はあまりいなかったけれど、クラス中の人がそれについて話しているので嫌でも耳に入って来た。
凪浜は、奏太が暮らす凪浜町にある浜辺だ。
自宅から歩いて10分もしないうちに出られる場所なので、凪浜小に通う人ならば毎日とは言わないが、結構な頻度で凪浜を訪れていても不思議じゃない。
だから、学校での噂話を聞いても、そんなの偶然なんだと思った。
たまたま同じ時期に夜の散歩か何かで凪浜を訪れた人たちが、たまたまイメージチェンジでも図ってか、性格を変えてみただけだ。
それか、最初に性格が変わってしまった米倉良太を見て、岸田くんも白藤さんも彼の真似をしたら面白いだろうなって思ってしまっただけなんじゃないか。
岸田くんは米倉くんと仲が良かった。二人でつるんで教室で騒いでは先生に怒られる。優等生の女子からは厄介者、問題児と思われているだろう。
白藤さんは、クラスの女子の中でトップクラスに可愛い。しかしわがままな一面があり、女子側からはちょっと扱いが難しい子だと認定されているらしかった。
奏太はなるべく心を乱さないように、三人の変化を偶然や意思で説明をつけようと躍起になった。
躍起になればなるほど、奏太の心は常に「海の怪物」に奪われていた。
最終的に、クラスメイトや他のクラスの人たちも一緒になって、彼ら三人の変化は「海の怪物に心を喰われた」ということになった。
「海の怪物? なんだそれ」
その夜、学校から帰った奏太は、夜ご飯の最中に父親に海の怪物のことを話した。今年小1になった妹の遥香(はるか)が「カイブツ?」と首を傾げている。その手にはカレースプーン。父の得意料理。3年前、奏太が8歳の頃に母親が亡くなってからずっと、皆川家のご飯は父親の誠司(せいじ)が作っている。
遥香の小さな手に握られたカレースプーンを見て、奏太は米倉良太のカレーぶちまけ事件を思い出す。あの日は結局、米倉くんと先生が他のクラスと給食のおばさんたちのところから余ったカレーをもらいに行ってくれて、無事にクラスメイト全員にカレーが行き渡った。
奏太の家族でも、家庭料理の中でカレーが一番好きだという意見は全員の総意なので、誠司は一番最初にカレーを作ることを覚えたのだ。それまではまったく料理をしない父親だった。
奏太の記憶の中で、母が亡くなった次の日に、ぎこちない包丁遣いで野菜を切る父の姿がフラッシュバックする。悲しい気持ちを奏太たちに見せないように、母親がいなくても限りなくこれまでの「日常」に近づけるように、彼は努力していたのだ。ということを、奏太
は幼いながらも気づいていた。
「お父さんのカレー、辛い」
最初の一口で舌にピリつく刺激が、奏太を襲った。
「からーい」
当時3歳だった遥香もぺっぺ、と舌先を口から出して眉を寄せた。
「ごめんな。うまくできなくて」
申し訳ない、と頭を下げる父親の姿。
なんだかとても、小さく見えた。
お父さんはお父さんなりに自分たちを励まそうとしてくれたに違いない。奏太は、自分の言葉一つに消沈してしまった誠司を見て、「辛いけど、おいしい」と言い直した。
「本当か?」
「うん。お父さんのカレー、辛いけど味は好き」
とたん、父の表情が和らいで、「ありがとうな」と笑った。
多分母には、母だけの特別な調味料があったのだ。もしかしたら、味をマイルドにするために、チョコレートでも入れていたのかもしれない。
けれど奏太は、あえてそのことを誠司に伝えなかった。
お父さんのカレーはお父さんのカレーとして、記憶に残して置きたかったから。
「海の怪物に喰われるっていう噂が、5年生の間で流れてるんだ」
「ほう」
誠司が顎に指を添えて興味深げに奏太の目を見ている。
「最近の小学生は、なかなか面白いことを“想像”するんだな」
誠司のその言葉を聞いて、奏太は些かむっとした。父親が自分たち子供の考え信じてくれていないと思ったからだ。
「お父さんは、嘘だと思うの?」
奏太は、話の合間にカレーを一口すくった父親に訊いた。遥香は、初めて父親のカレーを食べた時のように、もう「辛い」とは言わない。辛いけど我慢している、そんな感じだ。きっと、いなくなった母親の代わりに誠司がカレーを作ってくれているという事実に気を遣っているのだ。
「いや、本当だと思うよ」
「えっ」
奏太にとって、誠司の回答は意外だった。
まさか、小学生の間で流れる噂を、そのまま信じてくれると思わなかった。
「奏太たちがそう思うなら、父さんもそう思う。父さんは奏太の友達やクラスメイトのことはよく知らないけど、自分が子供だった頃のことを思い出すんだ」
「お父さんの子供の頃?」
「こども、こども!」遥香がはしゃぎ声を上げる。
「ああ。みんなで作った宝の地図をもとに、町内を探検したり秘密基地をつくって世界の平和を守ろうとしたりな。全部想像だったけど、その時は本気でそんなことが起きると信じてたんだ」
「へえ。お父さんにもそんな時代があったんだ」
「もちろん。まあ、もう何十年も前の話だけどな」
誠司がスプーンを持っていない左手で奏太の頭をわしゃわしゃ撫でた。奏太は、このゴツゴツした手触りが嫌いじゃなかった。
「奏太も、自分が信じるものを信じなさい。それで十分」
自分が信じるものを信じなさい。
奏太の心に、ぽっと灯火が一つ。
お父さん。
……お母さん。
少年のように笑う父親の顔を見て、ある決意が生まれたのは、まだ彼だけの秘密だ。
翌朝、5年2組の教室に入ると、例のごとくクラスの女子たちが寄り集まって、「海の怪物」の話で盛り上がっていた。
梅雨が明け、蒸し暑い中でもいよいよ夏本番が近づいてきた7月。普段以上に海に行く人も多いため、「海の怪物」に喰われる子どもが多いかと思いきや、どうやらそうでもないらしい。
「最近分かったことなんだけど」
三枝愛菜が懲りずに朝イチで奏太のところにやってきた。奏太はとりあえず「おはよう」と挨拶。
「あ、おはよう」
でね、と彼女は続ける。
「海の怪物に出会うのは、満月の夜だけなんだって! 7月だと今日になる」
どこかで聞いたことがあるような設定。
満月の夜。
「どうしてそんなことが分かったの?」
「そんなの簡単だよ。実際に様子が変わっちゃった人たちに聞いてみたら、みんな満月の夜に凪浜に行ってたから」
「なるほどね」
確かに、簡単な検証だと奏太も思う。
でも、どうして満月の夜に凪浜に行くと怪物に喰われるのか、肝心なところが分かっていない。
米倉くんや岸田くん、白藤さん、それからまたちらほら同じような症状に見舞われたメンバーに聞いてみても、彼らの重たい口からは何も出てこない。よっぽど怖い目にあったのか、何があったのか覚えていないのか。
どちらにせよ、話を聞いて奏太の身体はぶるっと鳥肌が立った。
「みんな、どうしちゃったんだろうね。海の怪物は本当にいるのかなー」
心配しながらも、三枝さんの目には「ワクワク」が宿っているのが隠しきれない。
人間、非常事態とか非日常に遭遇すると、どこかしら“期待”してしまう。ちょっと退屈な日常を変えてくれるんじゃないかって。
実は奏太も、この事態に「期待」をした一人だ。
幼い頃に奏太の胸に宿った科を、「海の怪物」なら取り除いてくれると思ったからだ。
「皆川くん、どうしたの?」
気がつくと三枝愛菜が、奏太の瞳をじっと覗き込んでいる。それも、先ほどよりも純粋に心配そうな表情をしていた。
「いや、なんでもない」
必死に取り繕ったが、三枝さんは首を傾げていた。
奏太は幼い頃からずっと、心の底から、自分は「悪い子」なのだと思っていた。
幼い頃——具体的に言えば、8歳で母親が亡くなってからだ。
母親が死んだのが、自分のせいだと思っている。
消えなかった。
その考えは、1年経っても2年経っても、3年経った今でも、根深く心の奥底から湧き上がってくる。
僕は悪い子だ。
奏太の中にある消えない考えが、彼の胸に灯した決意とともに、動き出そうとしていた。
その日の午後7時前、奏太は学校から帰った後に出かける準備をした。誠司は仕事でまだ帰ってきていなかった。妹の遥香がくまのぬいぐるみを手に、「お兄ちゃんどこいくの?」と不安そうな目で言った。
「お兄ちゃんは、ちょっと『カイブツ』に挨拶してくるんだ」
「カイブツ!」
小学1年生。さすがに怪物の意味ぐらいは分かっているだろうが、およそ現実離れした言葉に、一体何のことだかは分からないに違いない。
「そう。だから遥香、ちょっとお留守番しててくれない? できるよね」
「うん!」
遥香は、この歳の女の子にしてはしっかりしている。たぶんそれも母親がいないせいだ。3歳という幼さで最愛の人と死別した遥香。寂しいはずなのに、それが逆に彼女を強くした。
いや、無理やり強くさせてしまったんだ。
遥香は転んでも友達と喧嘩しても決して泣かない。そんな彼女の姿を見るたびに、奏太は自分の罪を思い出さずにはいられなかった。
「大丈夫。兄ちゃんはちゃんと帰ってくるから」
「だいじょうぶ!」
くまのぬいぐるみを抱きしめて、先ほどよりも元気に声を上げた。
「じゃあ行ってきます」
「いってらっしゃ〜い」
間延びした声で手を振る遥香を背に、奏太は歩き出した。
まだ日の落ちていない凪浜町の空が、凪浜の海までの道のりを十分に示してくれていた。
昼間はうだるように暑くて、蝉の声なんかも聞こえ出した季節なのに、夜になると涼しく心地よい。
奏太の家から凪浜まで、歩いて10分もかからない。
住宅街からすぐに、浜辺まで抜けられた。
近所の人たちの中にはこの辺りで犬の散歩をしている人もいるので、一人で浜辺に行くのにまったく抵抗はないのだが、さすがに夜の海ともなれば、奏太も少々怖気付いていた。
自宅から浜辺に向かうまでに、薄暗かった空が一気に暗くなっていた。
海にたどり着くと、その空の闇に、奏太は心ごと呑まれそうだと感じた。
波のざぶんという音が、カラッと晴れ渡る空の下で聞くよりも、おどろおどろしい怪物の唸り声みたいだ。
もしかしたら、米倉良太や岸田翔も、こんなふうに夜の海と空の暗闇に溶けてしまったのではないかと錯覚する。
奏太は不安になりながら、「海の怪物」に会えるように心の中で祈った。
海に棲む怪物さん。
どうか僕の心を、喰ってください。
僕はお母さんを殺しました。
僕のせいで、お父さんは悲しみ、遥香は寂しい思いをしています。
だから怪物さん。
僕をこの場から、消し去ってください。
そうするのが正しいかなんて、奏太には分からない。
けれどもう、奏太の心を慰められる方法はそれしかなかった。
ざざっという波が、奏太の心の声に答えるかのように、彼の足下を濡らし、引いていった。
サンダルの中に染み込む冷たい水と砂。
夜の海と一体になって、そのままさらわれてしまってもいいかもしれない。
「お母さん」
海の怪物さん。
お母さんを殺したのは僕です。
あの日、僕が8歳になった誕生日。
お母さんと一緒に、ケーキを買いに行きました。
僕と妹とお母さんで、三人並んで街へ出かけ、8本の蝋燭とネームプレート付きの大きなケーキを買いに。
誕生日だから、特別でした。いつもは遥香のことでいっぱいいっぱいのお母さんも、僕の誕生日には、きっと僕のことだけを考えてくれると思って。
けれど現実は全然違った。
ケーキを買いに行く最中、お母さんは疲れてぐずる遥香をなだめるのに精一杯。
電車が混んでいて、大きな大人に囲まれた遥香は、怖かったんだろうと思います。
なんとか遥香を連れてケーキを買ったあと、とうとう「歩きたくない」と言い出してお母さんは「仕方ないわね」と遥香を抱っこしました。
遥香の背中をさすって、僕の方へは見向きもせずに歩いていたので、僕はずっともやもやした気持ちでいました。
それがいけなかったんです。
とうとう僕も、寂しい気持ちの歯止めが効かなくなって、あることをしていまいました。
ちょうど交差点に差し掛かっていたところです。
遥香が「ママぁ」と一際激しくぐずり出したとき。
お母さんの気を引きたくて、僕はとっさに道路に飛び出しました。
すぐそばに、車が迫っているとも知らずに。
その時はちょっとだけ、お母さんの気を引こうとしただけだったんです。
声にならない悲鳴が、僕の耳元に飛び込んできた気がします。
気がつくと、遥香を腕から下ろしたお母さんが、僕を庇うために、道路に飛び出していました。
そこから先、僕が覚えていることといえば、遥香が泣き叫ぶ声と、ウーウーという救急車のサイレンだけです。
僕が、殺しました。
お母さんを、僕のわがままで殺しました。
だから僕を、喰ってください。
怪物さん。
海の、怪物さん。
奏太はそうしてずっと心の中で願い続けた。
夜空には想定通り、まん丸の月が不気味に輝いている。
「……」
しかし、どういうわけか、海は何も言わない。
米倉くんや岸田くん、白藤さんにしたように、奏太にだって、構ってくれてもいいのではないか。
「……」
満月のせいか、確かに普段より満ち引きの大きな波が、奏太の足を浸しては引いてゆくのに、奏太の気は凪浜に来る前とちっとも変わらなかった。
どうしてなんだ。
これじゃあ「海の怪物」どころじゃない。
ただただ自分の心の内を、吐き出してしまっただけじゃないか!
輝かしい月明かりに照らされながら、奏太は吠える。
怪物!
海の怪物!
僕をここからさらえっ!
僕を、喰ってくれ!
「……」
へとへとになるくらい、奏太は叫んだ。
叫びながら、自然と溢れてくる涙の海。
ああ、ここから出たい。
ここから、母を殺してしまった現実から逃れたい。
泣き叫び、ざぶんという波音を聞き砂の上にひざまづく。
「怪物っ! 海の怪物! いるなら返事をしろっ! 僕はここにいる。僕はここに、ここにいるんだ。……母さん! お母さん、お父さん……!」
右も左もわからないまま、一心不乱に叫び続けた奏太。
しかしそれでも、何も告げない海が、悠々と目の前に広がっているだけだった。
「なんだよ、嘘つき! 悪い子は海の怪物が喰ってくれるんじゃなかったのか。最悪だ、もう、僕は一生悪い子でいるしかない」
慟哭し、これ以上海の怪物に期待することもできないと感じた奏太は、絶望しながら両手を湿った砂浜の上についた。
「嘘じゃないさ」
不意に、後ろから聞こえてきた声。
奏太ははっとして振り返る。
耳に馴染んだ、奏太を安心させてくれる声。
「……お父さん」
奏太の後ろには、誠司がいた。
肩で息をしていて、ここまで走ってきたんだということが分かった。隣には遥香もいる。彼女はもう、くまのぬいぐるみを抱えていなかった。
「どこに行ったのか心配したぞ。遥香が『カイブツに会いに行った』って教えてくれたからここが分かったけどな」
「……ごめんなさい」
奏太は父に心配をかけてしまったことが申し訳なくて、素直に謝った。
「『海の怪物』は嘘じゃない。怪物は本当に、悪い子の心を喰う。いや、これはすごい想像力だと感心したけどな。子供ってすごいよ」
「どういう意味」
奏太は種明かしを始めた父親をまじまじと見た。
「満月の夜、人の心は不安定になりやすいんだ。母さんが亡くなった日——お前の8歳の誕生日も、今日みたいな満月だったな」
誠司は右手を月のある方にかざし、その強い輝きを感じた。
「不安定になった心は、その人の精神をちょっとおかしくしてしまうことがある。だから、奏太の学校の友達も、変わってしまったんじゃないかな。まあそれも一時的なものだと思うから心配することないと思うけど」
父の言葉に、奏太は驚いた。
米倉くんや岸田くん、白藤さんたちの身に起こったのは、「怪物」に出会ったことじゃない。
満月の夜の海で、大きく唸る波音を聞いて、どっと不安が押し寄せてきただけなのだ。
「だからな、奏太。奏太は『海の怪物』に心を喰われなんかしない。奏太には思いやりの心があるだろう? 悪いことをしたと思って悔いているなら、怪物はやってこない。奏太はそのままでいいんだ」
自分が信じるものを信じなさい。
昨日の晩、誠司が放った灯火が、再び奏太の胸に蘇った。
「自分がいけないことをしたと思ったら、反省すればそれで終わりだ。奏太は悪い子なんかじゃないよ。母さんはいつも俺に言ってた。『奏太は優しい子だから大丈夫』って」
父の優しい瞳。
奏太は心がすっと軽くなるのを感じた。
波音が、先ほどよりも鮮明に、耳に心地よい音として聞こえてくる。
海の怪物は、どこにもいない。
いるとすればそれは、自分の心に棲んでいる。
奏太の新しい発見。自分の信じるものを信じること。
奏太は父を、心から好きだ。
そんな父が好きだった母のことも。
だから母が父に言った言葉、「奏太は優しい子」だというのを信じられる。
「……分かったよ、お父さん。ごめんね、お母さん。もう『海の怪物』なんて、信じない。僕はこのままでいる」
月の光は、奏太の頬を照らしている。ここに来た時からずっと。
誠司の隣では遥香が「お兄ちゃん泣かないで」と可愛らしい声で言った。
海の怪物。
満月の夜に、“悪い子”の心を喰らうもの。
そして、怪物は「自分自身の心」。
奏太は立ち上がって、父親と妹のところに駆け寄った。
奏太の心に、怪物はもういない。
【終わり】
■著者プロフィール
斉藤萌里天狼院書店スタッフ。
1996年生まれ24歳。福岡県出身。京都大学文学部卒業後、一般企業に入社。2020年4月より、アルバイト時代にお世話になった天狼院書店に合流。
天狼院書店では「ライティング・ゼミ」受講後、WEB LEADING LIFEにて『京都天狼院物語〜あなたの心に効く一冊〜』を連載。
『高学歴コンプレックス』でメディアグランプリ1位を獲得。
現在は小説家を目指して活動、『罪なき私』販売中。
***
この記事は、「ライティング・ゼミ」を受講したスタッフが書いてます。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
小説家を目指すあなたへ
http://tenro-in.com/zemi/131995
26名様お申し込み!【7/23・24・25/3日間集中コース】初心者から300枚以上の小説を書き上げる!天狼院「長編小説講座」プロット制作から見直しの作法まで《小説家養成ゼミビギナーズ/全国通信》
http://tenro-in.com/event/118909
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325
■天狼院書店「シアターカフェ天狼院」
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-1 WACCA池袋 4F
営業時間:
平日 11:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
電話:03−6812−1984






























































































