もう止められないのに普及しないのはなぜ?《週刊READING LIFE Vol.294 もう止められない》
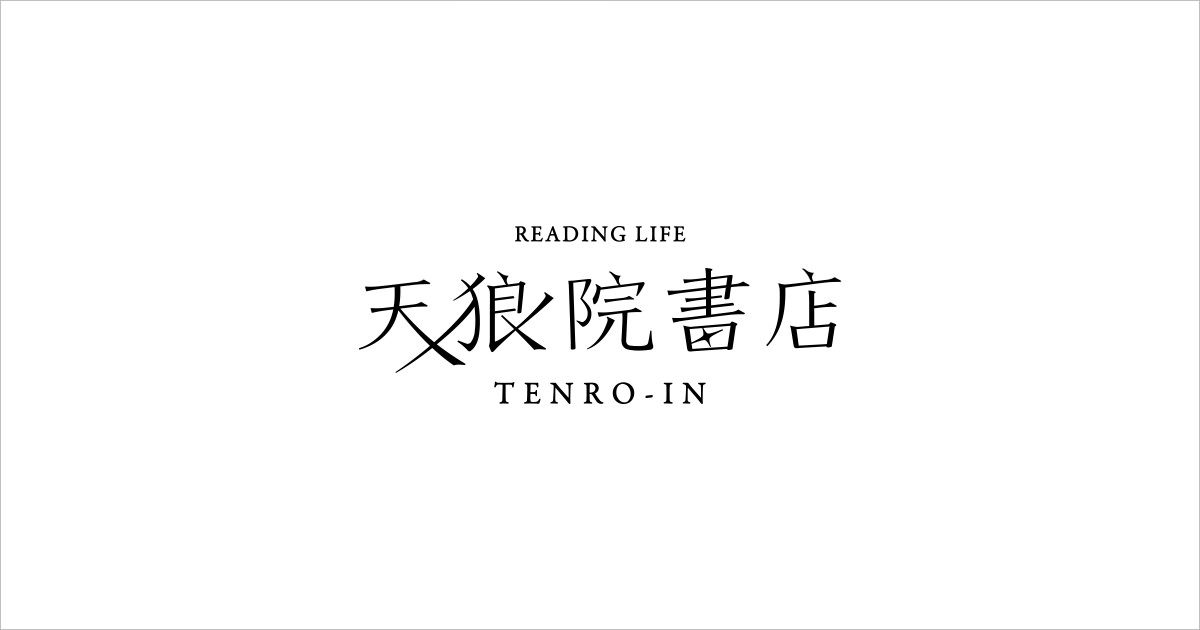
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「新・ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/2/3/公開
記事:服部達哉(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
「AIの進歩はもう止められない」、この言葉を聞いた時、何を感じるだろうか。輝かしい未来? 漠然とした不安? 何か怖い?
まず、人工知能(AI)が私たちの生活を急速に変えつつあることは変えられない事実であり、そして、この変化の流れに逆らうことが不可能であることも、また事実だ。
AI技術は驚異的な速度で進化し、ついこの前までできなかったことができるようになっていたり、想像もしていなかったことができるようになっていたりする。AIによる自動化は、今までの単純作業の自動化とは次元が違う。例えば、AIを駆使した顔認証技術が社会の隅々にまで導入されると、決済、交通、セキュリティなど、日常生活のあらゆる場面で活用できるとともに、超監視社会も遠い未来のことではなさそうだ。AIは、もはや一部の専門家だけしか扱えない特殊な技術ではなく、気軽に会話ができる程度にまでなっている。
しかし、驚くことに、日本におけるAIの普及率は、これでも世界平均と比べて著しく低い水準らしい。なぜ、かつて「技術立国」と言われた日本が、AIの分野では世界から後れを取ってしまうのか? 不思議でならない。どうやらこの遅れの背景には、いくつかの複雑な要因が絡み合っているらしいのだ。
日本人は失敗を恐れる。これは日本特有の文化で、変化を嫌う国民性の現れでもある。そして新しい技術の導入には常にリスクを懸念してしまうらしい。未知のリスクを恐れるあまり、AIのような革新的な技術の導入に慎重になりすぎる傾向が、日本企業には見られるんだとか。また、前例踏襲や出る杭は打たれるといった、日本社会に特有の文化が、AIとは相性が悪いようだ。
さらに、未だに根強く残る終身雇用や年功序列といった従来の仕組みが、特に中小企業においては、長年培ってきた人間中心の業、匠の技が根強く残っており、AIによる自動化や業務効率化が進みにくい状況を生み出しているともいえる。技術の継承自体は素晴らしいことで、誇るべきであることも間違いない。ただただAIとは相性が悪いだけなのだ。
しかし、技術の進歩は、日本の文化や慣習、都合などお構いなしに、常に前進し続けている。たとえ日本がどれだけ慎重であろうとも、AIの波は、着実に、そして確実に、世界規模では「もう止められない」状態なのだ。
「AIが人間の仕事を奪う」、という議論もよく聞く。メディアは、AIによって職を失う人々の不安を煽る。しかし、歴史上、新しいテクノロジーの登場によって、人間の仕事が脅かされる、奪われるということは、これまでも繰り返し叫ばれてきた。18世紀の産業革命では、蒸気機関や機械の導入によって、多くの手工業者が職を失った。当時も、「機械が人々の仕事を奪う」という不安や反対運動が各地で巻き起こった。しかし、結果はどうだっただろうか? 機械が単純労働を代替したことで、むしろ新しい職業が生まれ、経済発展した。AIもまた、産業革命と同様の、あるいはそれ以上の、大きな変化をもたらす。
確かに、AIによってなくなる仕事があることは事実だろう。しかし、重要なのは、仕事が「AIに奪われる」のではなく、「変わる」ということであり、仕事を奪うのは「AIを使いこなす」人であり、結局人が人の仕事を奪っているに過ぎない。AIは、人間のできないことをしてくれるだけだ。産業革命において、機械が単純労働を代替したことで、より高度な知識や技術を必要とする新しい職業が生まれたように、AIの時代にも、AIを開発、運用、管理する仕事や、AIを活用した新しいサービスを創造する仕事など、これまでには存在しなかった多様な仕事が生まれるはずだ。
一部の人々は、「AIには創造的な仕事はできない。クリエイティブな分野では人間の代わりにはなれない」と言う。確かに、創造性は、人間にしかできない、最後の砦のようなものだ。豊かな感性や経験、直感から生まれるものであり、無から有を生み出す能力だというわけだ。しかし、最近の「AIは創造性に欠ける」のだろうか? 近年、AIは、音楽、アート、文章作成といった、これまで人間が独占してきた分野で、次々と創作が可能になっている。
例えば、AIを用いた音楽作成では、特定のジャンルやアーティストのスタイルに特化した曲を自動生成することが可能だ。また、絵画やデザインの分野でも、AIの進歩が驚異的だ。しかし、AIに創造性を発揮させるためには、それを使う人のクリエイティビティが必要になる。AIと人間は協働することで、これまでには想像もできなかったような、新しい創造が可能になるのだ。
AIと人間の関係を考える上で、古代ギリシャにおける哲学の発展と奴隷制度の関係性を考えてみる。古代ギリシャでは、哲学が著しく発展した。ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった有名な哲学者たち。この時代の哲学の発展の背景には、奴隷制度の存在があるといわれていたりする。つまり、当時は、奴隷が多くの労働をしていたことで、市民階級や知識階級は肉体労働から解放され、考えたり、議論したり、創造的な活動をする時間的余裕があったのだ。この時間的な余裕があったおかげで、哲学者たちは自由に考え、深い洞察を得られたのだ。もちろん、奴隷制度自体は良いものではない。この点では、奴隷とAIを単純に比較することはできない。AIは、あくまでも「道具」である。AIは、人間に代わって労働を行うことができるので、人間に時間的余裕を与えられるという点では、古代の奴隷と似ているかもしれない。
AIによって生産性が爆上がり、労働時間が激減することで、膨大な「時間的余裕」を手に入れることができるだろう。これは、古代ギリシャの市民階級が、奴隷のおかげで哲学する時間を確保できた状況と、ある意味似ていると言えるかもしれない。AIによって生み出されたこの余剰時間を、私たちはどのように使えるだろうか?
AIの急速な発展は、社会に様々な課題を突きつけている。例えば、自動運転車の事故責任、AIによるプライバシーや著作権の侵害など、解決すべき問題は山積みだ。AI時代における新たな倫理観作り、人間とAIが共存する社会を作ることこそ、人間にしかできない重要な仕事だ。また、音楽、アート、文学などの創造的活動は、人間の精神を豊かにし、社会に彩りを与える、かけがえのない営みだ。AIは、これらの分野においても、人間の創造性を支援する強力なツールとなってきている。AIによって時間的な余裕が生まれれば、より多くの人々が創造的な活動に没頭し、新しい文化や芸術が花開く可能性がある。さらに、AIは、業務の効率化や自動化を通じて、私たちが人間同士のコミュニケーションや、社会貢献活動に費やす時間を増やすことを可能にする。現代社会では、孤独や孤立、人間関係の希薄化が深刻な問題となっている。AIによって生まれた時間的余裕を、人間同士の絆を深め、コミュニティを活性化するために活用してはどうだろう?
AIの進歩を「止める」ことはできない。しかし、私たちには、「どう使いこなすか」を選ぶ自由がある。AIを拒絶し、恐れるのではなく、これを学び、活用することで、大きな利益を得る側にまわる方が良くないですか?
もう止められない未来の労働環境では、AIを使いこなすスキルが必須となり、使える人と使えない人の格差が広がりそうだ。プログラミングやデータ分析といった、AIの開発や運用に関わる専門的なスキルはもちろんのこと、AIツールを効果的に活用し、業務の効率化や、新しい価値の創造に繋げる能力が、あらゆる分野で求められるようになる。AIを活用することで、私たちは、これまで多くの時間を費やしてきた単純作業や反復的な業務から解放され、より人間らしい、創造的で、感情的な仕事に集中できるようになる。これは、私たち一人ひとりが、自らの能力を最大限に発揮し、より充実した人生を送るための大きなチャンスだ。AIは、私たちの仕事を奪う敵ではなく、人の時間と能力を拡張し、より人間らしい生き方を実現するための強力なパートナーだ。
私たちが目指すべきは、AIに支配される社会でも、AIを完全に排除した社会でもない。人間とAIが、それぞれの得意分野を活かし、互いに補完し合いながら、共に進化していく社会だ。「AIの進歩はもう止められない」という事実を受け入れることは、新しい時代への第一歩だ。AIがもたらす変化は避けられないが、それをどのように受け止め、どのように対応するかは、私たち次第だ。AIを敵ではなく味方として受け入れ、共に進化する道を選ぼう。私たちが目指すべきは、AIに反発することではなく、その進歩を利用し、自分たちの生活をより良いものにすることだ。古代ギリシャの哲学者たちが、奴隷労働によって生まれた時間的余裕を活用して、後世に大きな知的遺産を残したように、私たちもまた、AIによってもたらされる「時間の余裕」を、人類のさらなる発展のために活かしていこう。
□ライターズプロフィール
服部達哉(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00






