「声なき父の贈り物 ― 自分らしさを守る“セルフケア”とは?」《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
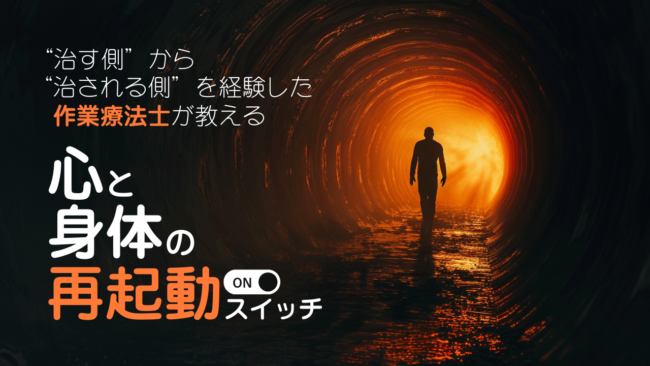
*この記事は、天狼院書店のライティング・ゼミを卒業され、現在、天狼院書店の公認ライターであるお客様に書いていただいた記事です。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/8/25公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
※人物・やりとりの部分はフィクションを含みます。
やりたいことが突然できなくなった時、心と身体が”自分”とつながらなくなる「停電」状態に陥る。そんな時、元に戻ることではなく、もう一度つながる「再起動」が必要だ。神経難病を患った50代のKさんは、進行性の身体機能低下により、手が動かなくなった。声も出せなくなった。しかし「父親として子どもに生き様を伝える」という役割だけは手放さなかった。手帳から動画へ、そして最期まで続けた「父の声」の軌跡とは。一人で抱え込まず、誰かの手を借りてでも貫き通したい「あなたの役割」は何ですか?
真のセルフケアの意味を問い直す。
—
「先生、僕はもう父親として何もできないんでしょうか」
Kさん、50代。商社マンとして海外を飛び回り、3人の子どもを育てる家族の大黒柱だった。そんな彼が神経難病の告知を受けたのは、長男の大学受験を控えた秋のことだった。
前回までにお話しした「停電」——心と身体が”自分”とつながらなくなり、日々の行動に「気持ち」や「意味」が乗ってこない状態。そして「再起動」——元に戻ることではなく、心と体、そして自分自身の価値ともう一度つながること。Kさんもまた、大きな「停電」の中にいた。
しかし、Kさんの停電は進行性だった。今日できることが、明日にはできなくなる。今日話せる言葉が、来月には出なくなる。そんな現実と向き合いながら、彼が最も恐れていたのは、「父親としての役割」を失うことだった。
「子どもたちにはまだ伝えたいことがたくさんあるんです」Kさんの声は震えていた。「仕事のこと、人間関係のこと、挫折の乗り越え方。でも、このままでは何も残せない」
そんなKさんに、僕は一つの提案をした。それは、従来の「セルフケア」の概念を覆すものだった。
「Kさん、毎朝起きたら、まず何をしますか?」
「コーヒーを飲んで、新聞を読んで、出勤の準備をしていました。でも今は…」
「今は何もない時間があるということですね。だったら、その時間を『父親の時間』にしませんか?」
僕はKさんに、毎朝手帳に短いメッセージを書くことを提案した。ただし、それは自分のためではなく、子どもたちのために。
「日記ではなく、手紙です。今日子どもたちに伝えたいことを、毎朝一つだけ書いてみてください」
最初、Kさんは戸惑っていた。
「何を書けばいいのかわからないんです。説教みたいになりそうで」
「説教ではなく、お父さんの『今日の気持ち』でいいんです。今朝見た空の色、昨日のニュースで思ったこと、子どもの頃の思い出。なんでも構いません」
3週間後、Kさんの家に大きな変化が起きていた。
「お父さん、今日はどんなお話?」
毎朝、末っ子がKさんの手帳を楽しみに見にくる。
「今日のメッセージは…『雨の日こそ、心の中に太陽を作ろう』だって」
次男が読み上げると、末っ子が「お父さんの太陽、見えるよ」と笑顔で答える。そんな日常の積み重ねが、Kさんにとって何よりのセルフケアになっていた。
小学3年生の末っ子は、まだ漢字が読めないので、中学生の次男が読み聞かせてくれる。読み終わると、末っ子が手帳にハートマークや星の絵を描いてくれる。
「先生、これがセルフケアなんですね」Kさんは涙を浮かべながら言った。「子どもたちの顔を見るために朝起きる理由ができました。何を書こうか考えることで、一日一日を大切に生きている実感があります」
それから半年後、Kさんの手指の機能は徐々に低下していった。字を書くことが困難になり、毎朝の手帳も続けられなくなった。
「先生、もうダメです。何もできません」
Kさんは深く落ち込んでいた。しかし、僕はまだ諦めていなかった。
「Kさん、手は動かなくなりましたが、声はまだ出ますよね?」
「でも、だんだん聞き取りにくくなってきています」
「だったら、今のうちに声を『保存』しませんか?」
僕はKさんに、動画メッセージという新しい方法を提案した。看護師のNさんと協力して、毎週末にKさんの話を録画する。内容は、仕事で学んだこと、人生で大切にしてきたこと、子どもたちへの応援メッセージ。
「どんな話をすればいいか、最初は分からなくて」Kさんは奥さんと相談しながら話題を決めていった。「でも、Nさんが『普段子どもたちに話していることを、そのまま話してください』って言ってくれて、肩の力が抜けました」
「最初は恥ずかしくて、何度も撮り直しました」Kさんは苦笑いを浮かべた。「でも、Nさんが『お父さんの声は、子どもたちにとって一番の宝物になりますよ』って言ってくれて」
声も次第に出しにくくなったKさんは、視線入力システム——目の動きでパソコン画面の文字を選択し、それを機械の音声で読み上げる装置——を使って文字を入力する方法も覚えた。医療スタッフ、家族、そして最新技術——多くの人の手を借りながら、Kさんは「父としての声」を届け続けた。
「これまで『セルフケア』は自分一人でやるものだと思っていました」Kさんは語った。「でも違うんですね。自分の大切な役割を続けるために、他の人の力を借りることも、立派なセルフケアなんだと気づきました」
Kさんが亡くなったのは、診断から2年後のことだった。最期まで、彼は「父としての声」を子どもたちに届け続けていた。
葬儀の日、長男が弔辞を読んだ。
「お父さんは、病気になってから僕たちにたくさんのことを教えてくれました。毎朝の手帳、動画のメッセージ。お父さんの声は、今でも僕たちの心の中で響いています」
そして驚くべきことが起きた。子どもたちが、お父さんの習慣を引き継ぎ始めたのだ。
現在、Kさんの動画は家族のタブレットに保存され、リビングの特別な場所に置かれている。子どもたちが悩んだ時、迷った時、そのタブレットを手に取り、お父さんの声を聞く。
「進路で迷った時は、このお父さんの話を聞くんだ」と長男。
「部活で辛い時は、この応援メッセージを見る」と次男。
「お絵かきする時は、お父さんと一緒にやってる気持ちになる」と末っ子。
動画は単なる記録ではなく、家族の新しい日常の一部として生き続けている。
長男は大学で、毎朝日記をつけるようになった。次男は部活動で後輩に「今日の一言」を伝える役割を買って出た。末っ子は、お父さんの動画を見ながら絵日記を書いている。
「お父さんが教えてくれたんです」長男が言った。「大切なことは、誰かに伝え続けることで生き続けるって」
【POINT】セルフケアの真の意味——つながりを維持すること
Kさんの体験から、セルフケアの本質が見えてくる。
セルフケアとは「すべて自分でやること」ではない。
従来のセルフケアの概念では、「自立」「自己完結」が重視されがちだ。しかし、Kさんが教えてくれたのは、真のセルフケアとは「自分らしい役割を維持するために、あらゆる手段を活用すること」だということだった。
Kさんのセルフケアの特徴:
– 手帳 → 動画 → 視線入力システムと、手段は変わっても目的は一貫
– 家族、医療スタッフ、技術の力を積極的に活用
– 「できないこと」ではなく「まだできること」に焦点
– 自分のためだけでなく、家族のための行動として継続
これは、作業療法の根本理念でもある。人は社会的存在であり、誰かとのつながりの中でこそ、自分らしさを発揮できる。機能が低下しても、そのつながりを維持する方法は必ずある。
【実践プログラム】あなたの「役割維持」セルフケア
Phase 1:役割の明確化(1週間)
– あなたにとって最も大切な役割は何ですか?
– 親として、パートナーとして、職業人として、友人として
– その役割を通して、何を誰に伝えたいですか?
– なぜその役割が大切なのか、理由を明確にしてください
Phase 2:現在の手段の確認(2週間)
– その役割を果たすために、今使っている方法は何ですか?
– もしその方法ができなくなったら、どんな代替手段がありますか?
– 誰の助けを借りることができますか?
Phase 3:新しい表現方法の実験(4週間)
– 手紙、音声メッセージ、動画、SNS、直接対話など
– 週に1つ、新しい伝達手段を試してみてください
– その効果と相手の反応を記録してください
Phase 4:支援ネットワークの構築(2ヶ月目以降)
– あなたの役割を理解し、支援してくれる人は誰ですか?
– 技術的なサポートが必要な場合、どこに相談できますか?
– 継続可能な仕組みを、周囲の人と一緒に作ってください
【読者参加型】あなたの「大切な役割」を守る計画
STEP1:役割の棚卸し
現在のあなたが担っている役割を書き出してください。
例:
– 子どもの親として
– 部下の指導者として
– 高齢の親の支援者として
– 地域のボランティアとして
STEP2:優先順位の決定
その中で、「どんなことがあっても手放したくない」役割を3つ選んでください。
STEP3:継続方法の検討
各役割について、以下を考えてください:
– 今の方法が使えなくなったら、どうしますか?
– 誰の力を借りることができますか?
– どんな技術やツールが活用できますか?
STEP4:実践計画の作成
– 今週から始められる小さなアクションを決めてください
– 1ヶ月後の目標を設定してください
– 支援してくれる人に、協力をお願いしてください
大切な役割を守るための質問
– あなたがいなくなっても残したいものは何ですか?
– その「残したいもの」を、今どんな方法で表現していますか?
– もし今の方法が使えなくなったら、どんな方法で続けますか?
Kさんが教えてくれたのは、セルフケアの新しい定義だった。それは「自分で完結すること」ではなく、「自分らしい役割を維持し続けること」。そして、そのためには他者の力を借りることも、立派なセルフケアなのだということ。
現在、Kさんの動画は家族の「家宝」として大切に保管されている。子どもたちが迷った時、悩んだ時に見返す「お父さんの声」として。
やりたいことができなくなった時、私たちは往々にして「もう何もできない」と思いがちだ。しかし、Kさんが示してくれたのは、手段は変わっても、想いを届ける方法は必ずあるということだった。
大切なのは、一人で抱え込まないこと。周囲の人の力を借りること。そして、諦めずに新しい方法を探し続けること。
あなたにとって大切な役割は何ですか?その役割を通して、誰に何を伝えたいですか?今日からでも、小さな一歩を踏み出してみてください。きっと、想像以上の可能性が見つかるはずです。
次回は、「創造性の解放 ― アート&クリエイティブセラピーの力」をテーマに、表現活動を通じた心の再起動について考えていきます。言葉だけではない、新しい自己表現の可能性について、現場での体験を通してお伝えしたいと思います。
あなたの声が、形を変えても誰かに届き続けることを信じて。
***
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-
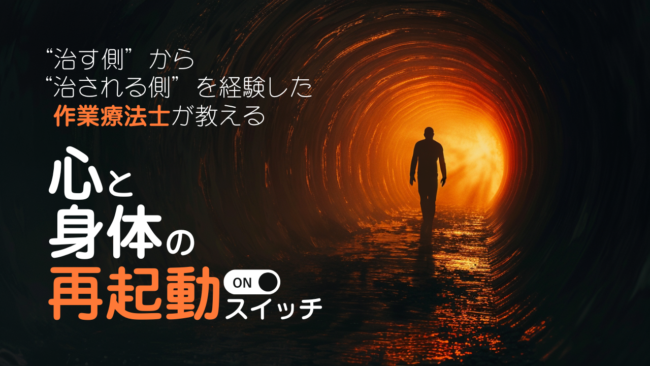
慢性痛に苦しむ女性が”花を活ける”喜びに出会った日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
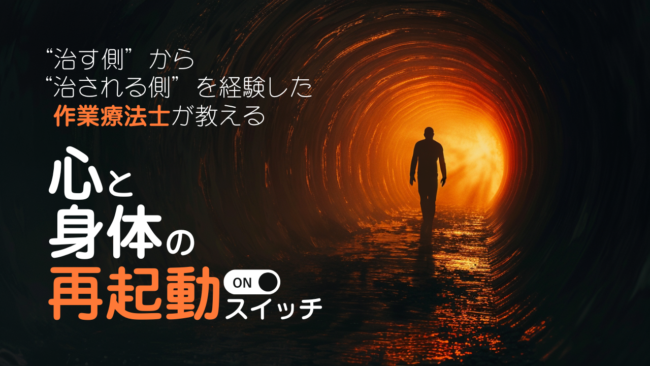
片麻痺の若者が”洗濯バサミで服を干した”午後《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
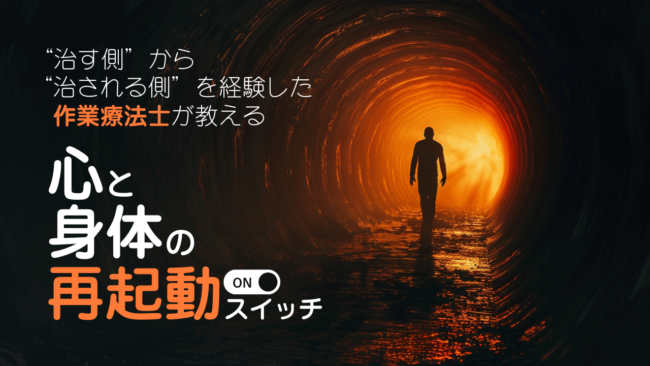
パーキンソン病の男性が”椅子を拭いた”日常動作の意味《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
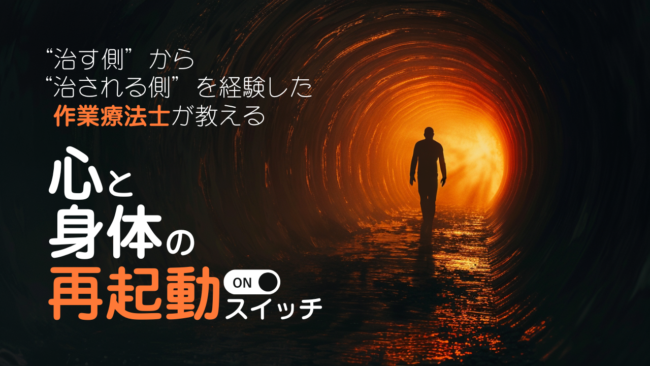
脳卒中で利き手を失った女性が”左手でおにぎり”を握った朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
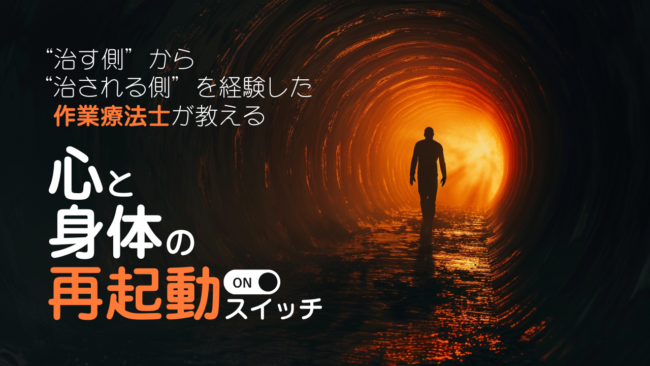
感情表出できなかった男性が”絵”に怒りを描いた日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》



