「母であり、介護者である ― 二重の責任を担うあなたへ」《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
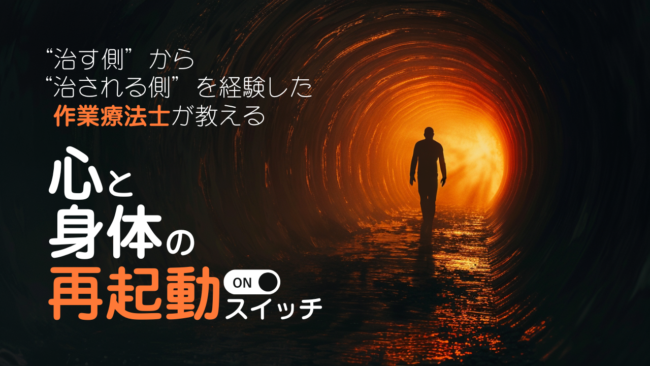
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
2025/9/29/公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
※一部フィクションを含みます。
「家族だから私が頑張らなきゃ」――そう思い込んでいませんか? 母として、そして介護者として二重の役割を担う日々は、心も身体も限界に追い込みます。支える側でありながら、実は誰よりも支えを必要としているのは介護者自身。セルフケアは利己ではなく共生のためのもの。介護の中で自分を見失いそうなあなたに贈る再起動のヒントです。
——
「朝5時に起きて認知症の義母の世話をして、子どもたちを学校に送り出して、パートに行って、夕方帰ってきたらまた義母の夕食の準備。夜は宿題を見て、義母を寝かせて、やっと自分の時間と思ったら夜中に徘徊が始まる——いつまで続くのでしょうか」
Kさん(45歳)の声には疲労困憊という言葉では表現しきれない深刻さが滲んでいました。中学生と小学生の母親でありながら、3年前から義母の介護も担っているKさん。夫は激務で平日は帰宅が遅く、週末も仕事が入ることが多い状況です。
Kさんのような「ダブルケア」(子育てと介護を同時に行う)状況にある人は、内閣府の調査によると全国で約25万人存在するとされています。その約7割が女性で、平均年齢は40代前半。働き盛りでありながら、家族の最も重要な支え手としての役割を担っているのです。
「最初は『私がしっかりしなきゃ』と思っていました。母親として、嫁として、当然の責任だと。でも3年経って、自分が誰なのかわからなくなってしまった」
Kさんの言葉は、多重ケアの現実を端的に表しています。複数の役割を同時に担うことで、「母親としての自分」「介護者としての自分」「働く女性としての自分」「一人の人間としての自分」の境界が曖昧になり、本来の自分を見失ってしまうのです。
この状況は決して珍しいことではありません。高齢化の進展と晩婚化・晩産化により、子育て期と親の介護期が重複するケースは今後ますます増加すると予想されています。しかし、社会的な支援体制は十分に整っておらず、多くの女性が孤立した状況で二重の負担と向き合っているのが現状です。
「子どもの運動会の日に、義母が転倒して病院に行かなければならなくなった。息子の晴れ姿を見てあげられなくて、すごく申し訳なかった。でも義母を放っておくわけにもいかない。どちらを優先すべきなのか、その瞬間は本当にわからなくなりました」
Kさんが語るこのエピソードは、多重ケア者が直面する最も辛い葛藤を象徴しています。どちらも大切な家族であり、どちらもKさんを必要としている。しかし、時間も体も一つしかない現実の中で、常に何かを犠牲にしなければならない状況が続くのです。
心理学者のナンシー・チョドロウが指摘するように、女性は社会化の過程で「ケア役割」を内面化しやすい傾向があります。「母親なら子どもを最優先すべき」「嫁なら義理の親の面倒を見るのが当然」という社会的期待が、個人の選択の自由を制約し、罪悪感を増大させるのです。
Kさんも例外ではありませんでした。子どもの学校行事に参加できなければ「母親失格」と自分を責め、義母の世話で疲れ果てて夕食が手抜きになれば「嫁として情けない」と落ち込む。常に「誰かに申し訳ない」という気持ちが心の底に蓄積していました。
「完璧な母親でありたい、良い嫁でありたい、そう思えば思うほど、現実とのギャップに苦しくなる。でも手を抜くことは家族への裏切りのような気がして、どうしても頑張りすぎてしまう」
この思考パターンは「全か無か思考」と呼ばれる認知の歪みの一種です。「完璧にできないなら意味がない」「少しでも手を抜いたら失格」という極端な基準が、柔軟な対応を妨げ、持続可能な介護を困難にしているのです。
「自分の時間なんて、もう何ヶ月もありません。美容院に行くのも罪悪感があるし、友人とお茶することなんてとんでもない。家族のために頑張るのが当たり前だと思っていたけれど、最近は鏡を見るのも辛くなってしまった」
Kさんの変化は外見にも表れていました。以前は明るく活発だった彼女が、疲労と睡眠不足で表情を失い、体重も10キロ近く減少していたのです。
介護者の燃え尽き症候群(バーンアウト)は深刻な社会問題となっています。継続的なストレス、睡眠不足、社会的孤立が重なることで、うつ状態や身体的な健康問題を引き起こすリスクが高まります。厚生労働省の調査では、介護者の約6割が「介護による健康への影響」を感じており、特に女性介護者でその傾向が顕著です。
Kさんの場合、自己犠牲が当然という思い込みが悪循環を生み出していました。「家族のためなら自分のことは後回しで当然」→「疲労と睡眠不足が蓄積」→「判断力や体力が低下」→「介護の効率が悪化」→「さらに時間と労力が必要になる」→「自分を責める」という負のスパイラルに陥っていたのです。
「ある日、買い物の途中で意識を失って倒れてしまった。病院で『過労と栄養不足』と診断されて、初めて自分の状況の深刻さに気づきました。私が倒れたら、子どもたちも義母も困ってしまう」
この出来事がKさんにとっての転機となりました。医師からの「介護者が健康でなければ、良い介護は続けられません」という言葉が、彼女の価値観を揺さぶったのです。
病院での診察をきっかけに、Kさんは地域の介護者支援団体を紹介されました。最初は「弱音を吐くようで恥ずかしい」「他の人に迷惑をかけたくない」と躊躇していましたが、担当ケアマネージャーの勧めで参加した介護者の集いで、人生観が大きく変わりました。
「そこで出会った人たちは、みんな私と同じような状況にいる人ばかりでした。『一人で頑張らなくていいんだよ』『助けを求めることは恥ずかしいことじゃない』と言ってもらえて、初めて肩の荷が下りた気がしました」
同じ立場にある人たちとの交流は、Kさんに大きな気づきをもたらしました。完璧を目指さなくても家族は愛してくれること、時には他人の手を借りることが家族全体のためになること、そして何より「介護者である前に一人の人間である」ということの重要性を学んだのです。
心理学の研究では、「社会的支援(ソーシャルサポート)」が介護ストレスの軽減に大きな効果があることが明らかになっています。情報的支援(有用な情報の提供)、道具的支援(具体的な援助)、情緒的支援(共感や励まし)、評価的支援(肯定的な評価)の4つの要素が組み合わさることで、介護者の心理的負担が著しく軽減されるのです。
Kさんは支援団体での交流を通じて、これらすべての支援を得ることができました。デイサービスや訪問介護の利用方法(情報的支援)、近隣住民による見守り体制(道具的支援)、同じ境遇にある仲間からの理解と励まし(情緒的支援)、そして「頑張っている」という承認(評価的支援)です。
セルフケアエクササイズ「自分の時間を10分つくる」
介護と育児に追われる毎日の中で、「自分の時間なんて無理」と諦めていませんか? Kさんが実践した「10分間セルフケア」は、忙しい介護者でも無理なく続けられる現実的な方法です。
【ステップ1:時間の見つけ方】
まず、1日のスケジュールを振り返り、10分だけ確保できそうな時間を見つけてください。
候補時間の例:
– 朝、家族が起きる前の10分
– 昼食後、被介護者が昼寝をしている間
– 夜、家族が寝た後の10分
– 通勤電車の中
– 買い物の合間(車の中など)
【ステップ2:セルフケアメニューの準備】
10分でできるセルフケア活動をリストアップしておきます。体調や気分に応じて選べるよう、複数のオプションを用意しておくことがポイントです。
身体のケア:
– 肩と首のストレッチ
– 深呼吸(4-7-8呼吸法など)
– 好きな音楽を聴きながら軽い運動
– アロマオイルでハンドマッサージ
心のケア:
– 日記を書く(今日良かったこと3つ)
– 瞑想アプリを使った短時間瞑想
– 好きな本を数ページ読む
– 友人にメッセージを送る
【ステップ3:「罪悪感」との向き合い方】
最初は「家族のことをほったらかしにしている」という罪悪感が生じるかもしれません。そんな時は次のように考え方を転換してみてください。
「この10分で心の余裕を取り戻すことで、残りの23時間50分をより質の高い時間にできる」
「疲れ果てた私よりも、少し元気な私の方が家族も嬉しいはず」
「介護は短距離走ではなくマラソン。適度な休憩が必要」
【ステップ4:家族の理解を得る工夫】
可能であれば、家族にもセルフケアの必要性を説明してみましょう。
子どもたちには:「お母さんが少し休憩することで、皆にもっと優しくできるようになる」
パートナーには:「お互いが健康でいることが、長期的な家族の幸せにつながる」
被介護者には:「少し休ませてもらうことで、より良いお世話ができる」
【ステップ5:記録と振り返り】
セルフケアを実施した日には手帳やスマホにマークをつけ、1週間後に振り返ってみてください。たった10分でも、心の状態や家族との関わり方に変化があることを実感できるはずです。
応用編:「セルフケア貯金」
時間に余裕がある時に、20分、30分のセルフケア時間を確保し、それを「貯金」として考える方法もあります。忙しい日が続いても「先週ゆっくりお風呂に入れたから大丈夫」という心の支えになります。
重要なのは、完璧を目指さないことです。毎日できなくても、週に数回でも構いません。小さな積み重ねが、大きな心の余裕につながっていきます。
現在のKさんは、以前とは全く違う表情をしています。疲れ切っていた3年前の彼女と比べて、穏やかで自然な笑顔が戻ってきました。義母の介護は続いていますが、デイサービスやヘルパーサービスを活用し、地域の支援ネットワークにも支えられながら、持続可能な形で家族と向き合っています。
「完璧な介護者でなくていいんだと気づいた時、肩の力が抜けました。私も一人の人間で、疲れることもあれば、時には助けが必要なこともある。それを認めることから、本当の意味での家族の支え合いが始まったんです」
Kさんの変化は、子どもたちにも良い影響を与えました。母親が無理をしなくなったことで、子どもたちも「お母さんを手伝おう」「おばあちゃんの話し相手になろう」と自然に協力するようになったのです。介護が「Kさんだけの責任」から「家族みんなで支え合うこと」に変わったのです。
「子どもたちが『お母さん、今日は疲れてるね。僕が夕食の準備手伝うよ』と言ってくれた時、涙が出ました。私が弱さを見せることで、家族の絆が深まったんだと思います」
これは決してKさんだけの物語ではありません。今この瞬間も、多くの女性が母親として、介護者として、時には働く女性として、複数の役割を懸命に果たしています。その責任感と愛情の深さは尊敬に値するものですが、一人で背負い込む必要はないのです。
社会保障制度、地域のサポートネットワーク、家族の理解——これらすべてを活用することは、決して「甘え」や「逃げ」ではありません。持続可能で質の高いケアを提供するための、賢明で勇気ある選択なのです。
もしあなたが今、Kさんのように一人で複数の役割を担い、疲れ果てているとしたら、まずは10分だけ自分のための時間を作ってみてください。そして、「助けを求めることは家族への愛情表現の一つ」であることを思い出してください。
支える人を支えること、それが真のコミュニティの力です。あなたも支えられて当然の存在であり、あなたの幸せが家族全体の幸せにつながっているのです。
明日は少しだけ、自分にも優しくしてみませんか?
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/8/28/公開
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-
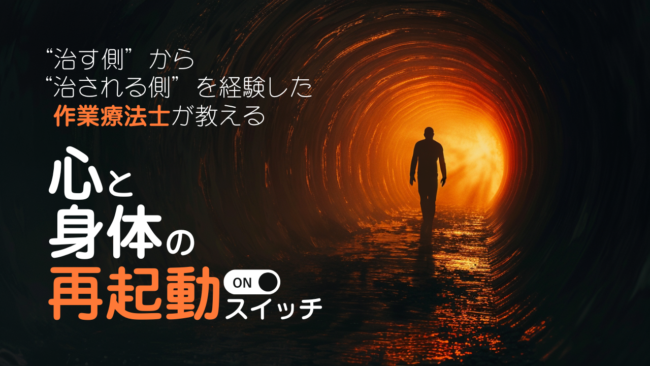
慢性痛に苦しむ女性が”花を活ける”喜びに出会った日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
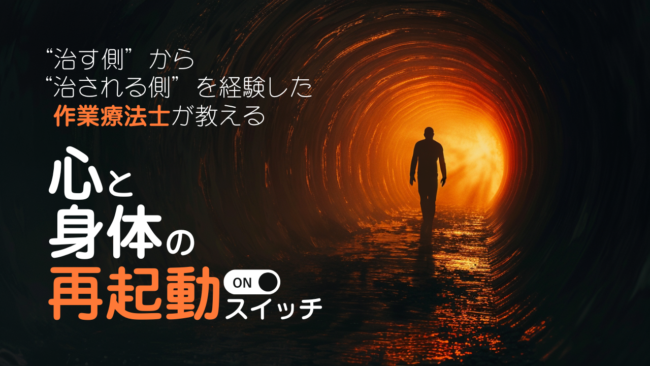
片麻痺の若者が”洗濯バサミで服を干した”午後《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
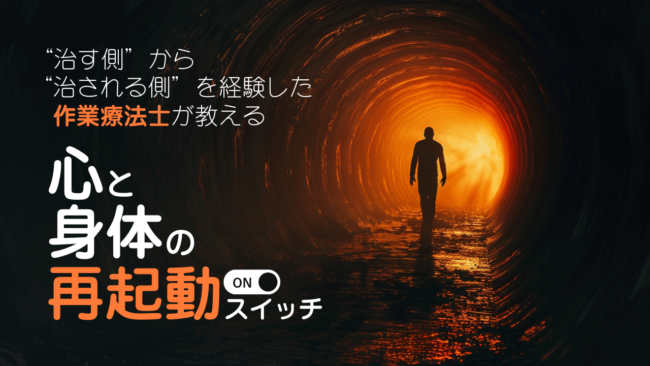
パーキンソン病の男性が”椅子を拭いた”日常動作の意味《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
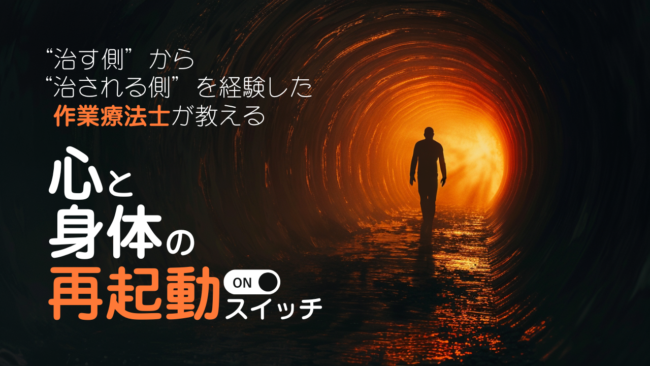
脳卒中で利き手を失った女性が”左手でおにぎり”を握った朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
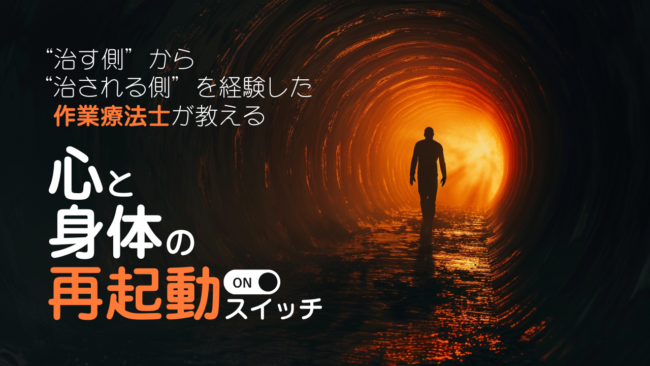
感情表出できなかった男性が”絵”に怒りを描いた日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》



