「復帰はゴールじゃない ― 職場で居場所を取り戻す再起動スイッチ」《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
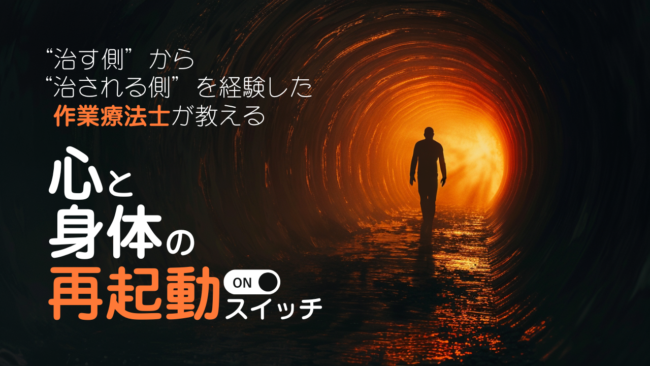
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
2025/10/6/公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
※一部フィクションを含みます。
「復職できた」――それはゴールではなく、新しいスタートです。職場に戻っても、かつての居場所がそのまま残っているとは限らない。休職を経て復帰した人たちが直面するのは、見えない孤独と役割の喪失です。必要なのは「元通り」ではなく「新しい居場所を築く」こと。働く意味を再構築することこそが、復帰後の再起動なのです。
——
「おかえりなさい」「お疲れ様でした」――同僚たちの温かい言葉に包まれて職場に戻ったHさん(42歳)。うつ病で8ヶ月間休職し、ついに復職の日を迎えました。しかし、期待していた「元の日常」は、そこにはありませんでした。
「みんな歓迎してくれたのに、なぜか居心地が悪い。以前のように自然に会話に参加できないし、仕事のペースについていけない。復職したのに、まるで職場に溶け込めない自分がいました」
Hさんが感じていた違和感は、復職者の多くが経験する現象です。厚生労働省の調査によると、メンタルヘルス不調で休職した労働者のうち、復職後1年以内に再び休職する人の割合は約30%に上ります。この高い再休職率の背景には、復職=ゴールという誤った認識があるのです。
復職は確かに大きな一歩ですが、それは治療の終わりではなく、新しい生活の始まりです。休職前の職場環境、人間関係、仕事内容は時間の経過とともに変化し、復職者自身も病気や治療を通じて以前とは異なる存在になっています。この「変化した現実」を受け入れながら、新しい働き方を見つけることこそが真の復帰なのです。
Hさんの場合、休職前はチームリーダーとして10人のメンバーを統括していました。長時間労働と重いプレッシャーが発症の要因でもありましたが、同時にそれが彼のアイデンティティの中核でもあったのです。復職時には配慮により一般職に戻されましたが、この「役割の変化」が想像以上に彼を苦しめることになりました。
「復職して1ヶ月経った頃、以前の部下が私を気遣って『Hさん、無理しないでください』と言ってくれた。親切な言葉だとわかっているのに、なぜか惨めな気持ちになった。私はもう、頼られる存在ではないんだと思い知らされました」
Hさんの体験は、復職者が直面する「役割喪失」の典型例です。心理学者のアーヴィング・ゴフマンが提唱した「役割理論」によると、人は複数の社会的役割を通じて自己アイデンティティを形成しています。職場における役割の変化は、単なる業務内容の変更ではなく、自己認識そのものを揺るがす出来事なのです。
Hさんにとって「チームを引っ張るリーダー」という役割は、単なる職務以上の意味を持っていました。それは「有能な自分」「必要とされる自分」「価値ある存在としての自分」を証明するものでした。その役割を失うことで、彼は職場での存在意義を見いだせなくなってしまったのです。
さらに複雑なのは、周囲の「配慮」が時として復職者の疎外感を増大させることです。「無理をしないで」「ゆっくりやって」という言葉は善意から発せられますが、受け取る側には「以前のあなたとは違う」「期待はしていない」というメッセージとして伝わる場合があります。
「同僚たちは私を『病気から回復途中の人』として見ている。でも私は『普通に働ける人』として見てほしい。この微妙な温度差が、職場にいても孤独を感じる原因でした」
この状況は「スティグマ(偏見・烙印)」の問題とも関連しています。メンタルヘルス不調への理解は深まっているものの、依然として「完全に治っていないのではないか」「また倒れるのではないか」という不安が職場に潜在的に存在する場合があります。復職者自身もこのような視線を敏感に感じ取り、それが居場所のなさにつながるのです。
Hさんの転機は、復職から3ヶ月後に訪れました。新入社員の研修担当を任されたのです。最初は「大した仕事ではない」と落ち込みましたが、研修を進めるうちに新たな発見がありました。
「新人たちは私の説明を真剣に聞いてくれる。『わかりやすい』『丁寧に教えてくれてありがとうございます』と言ってもらえた。久しぶりに『役に立っている』と感じることができました」
この体験が示すのは、「承認欲求」の重要性です。人間は本質的に「認められたい」「価値ある存在だと思われたい」という欲求を持っています。マズローの欲求階層説でも、承認欲求は自己実現欲求に次ぐ重要な位置を占めています。
Hさんにとって研修担当という新しい役割は、以前のリーダーポジションとは異なるものでしたが、「誰かの役に立つ」「認められる」という承認体験を提供してくれました。これにより、彼は「リーダーとしての自分」から「教える人としての自分」へとアイデンティティをシフトさせることができたのです。
「最初は『格下げされた』と思っていた研修担当の仕事が、実は私の新しい強みを発見する機会になった。病気を経験したことで、人の痛みがわかるようになった。それが新人指導に活かされているんです」
Hさんのこの気づきは、復職における重要な原則を示しています。それは「以前と同じ役割」にこだわるのではなく、「今の自分に適した新しい役割」を見つけることの大切さです。
新しい役割を得たHさんでしたが、それだけで全ての問題が解決したわけではありません。同僚たちとの関係修復には、さらに時間と努力が必要でした。
「復職当初は、みんなとの距離感がわからなかった。以前のように気軽に話しかけていいのか、仕事の相談をしてもいいのか迷っていました」
この問題を解決するため、Hさんは「小さなアクション」を積み重ねる戦略を取りました。まず始めたのは、毎朝の挨拶を意識的に丁寧にすることでした。
「おはようございます」の後に「今日もよろしくお願いします」を付け加える。帰る時には「お疲れさまでした。明日もよろしくお願いします」と言う。些細なことですが、これらの言葉には「私は普通に働ける」「チームの一員として参加したい」というメッセージが込められていました。
次に実践したのは、他のメンバーのサポートでした。自分の仕事が早く終わった時には「何かお手伝いできることはありませんか」と声をかける。資料作成で困っている同僚がいれば、積極的にアドバイスを提供する。これらの行動により、Hさんは徐々に「頼りになる存在」としての評価を取り戻していきました。
「最初は『大丈夫ですよ、無理しないで』と遠慮されることが多かった。でも続けているうちに、『Hさん、これお願いできますか』と普通に仕事を頼まれるようになった。その時、やっと職場に戻れたと実感できました」
心理学の「相互作用主義」の観点から見ると、Hさんのアプローチは理に適っています。人間関係は一方向的なものではなく、互いの行動と反応が循環的に影響し合います。Hさんが積極的に「普通の同僚」として行動することで、周囲も彼を「普通の同僚」として扱うようになったのです。
セルフケアエクササイズ「役割の再定義」
復職後の居場所づくりに悩んでいるあなたへ。Hさんが実践した「役割の再定義」エクササイズを紹介します。このワークを通じて、新しい自分の強みと可能性を発見してみてください。
【ステップ1:以前の役割の棚卸し】
まず、休職前にあなたが担っていた役割や業務をリストアップしてください。
例:
– チームリーダー(10名の管理)
– 企画書作成
– クライアント対応
– 新人指導
– 会議の進行
– トラブル対応
【ステップ2:現在可能な要素の抽出】
上記の役割から、現在も実行可能な要素を抜き出します。完全に同じでなくても、部分的に活かせるものも含めてください。
例:
– リーダーシップ → 少人数グループでの調整役
– 企画力 → アイデア出しやブレスト参加
– 対人スキル → 新人のメンター役
– 会議運営 → 資料作成のサポート
【ステップ3:新しく獲得した強みの発見】
病気や治療の経験を通じて得られた新しい強みを書き出してください。
例:
– 共感力の向上(同じような困難を持つ人への理解)
– ストレス管理スキル
– 優先順位をつける能力
– 自分と向き合う力
– 人の支援を受け入れる謙虚さ
【ステップ4:新しい役割の仮説設定】
ステップ2と3の結果を組み合わせて、あなたが担える新しい役割の仮説を立てます。
例:
– メンタルヘルス相談窓口担当
– 新入社員の心理的サポート役
– ワークライフバランス推進委員
– 効率的な働き方のアドバイザー
【ステップ5:小さな実験の実施】
仮説を検証するため、日常的に小さな実験を行います。
例:
– 困っている同僚に声をかけてみる
– 会議で積極的に発言してみる
– 新人との雑談を増やしてみる
– 効率化のアイデアを提案してみる
【ステップ6:フィードバックの収集と調整】
実験の結果を振り返り、周囲の反応や自分の感情を記録します。うまくいった要素は継続し、課題のある部分は調整していきます。
重要なポイント:
– 完璧を目指さず、試行錯誤を繰り返す
– 小さな成功を積み重ねる
– 周囲の反応に一喜一憂しすぎない
– 自分のペースを大切にする
このエクササイズは1〜2ヶ月かけてじっくり取り組むことをお勧めします。焦らず、少しずつ新しい自分の役割を見つけていってください。
現在のHさんは、復職から2年が経過し、完全に職場に定着しています。研修担当としての評価は高く、社内のメンタルヘルス推進委員会のメンバーにも選ばれました。新入社員からは「Hさんに相談すると安心する」と慕われ、同僚からは「経験に基づいたアドバイスをくれる頼れる存在」として認識されています。
「復職当初は『元の自分に戻りたい』とばかり考えていました。でも今思うのは、戻る必要はなかったということ。病気の経験も含めて今の自分があり、それが新しい価値を生み出している」
Hさんの言葉は、復職における根本的な発想転換の重要性を示しています。居場所とは「取り戻すもの」ではなく「つくるもの」。そして、そのプロセスにおいて最も大切なのは、自分自身が能動的に行動することなのです。
復職は確かにゴールではありません。それは新しい職業人生のスタートラインです。そこから先の道のりは、誰かが用意してくれるものではなく、あなた自身が歩きながら作っていくものです。
時には迷い、立ち止まり、方向転換することもあるでしょう。それでも歩き続けることで、必ず新しい居場所は見つかります。いえ、見つかるのではありません。あなたがつくるのです。
もしあなたが今、復職後の居場所探しに悩んでいるなら、Hさんの体験を思い出してください。「以前の自分」に固執するのではなく、「今の自分」ができることから始める。小さな行動を積み重ね、周囲との新しい関係性を築いていく。その先に、きっと新しい居場所が待っています。
明日からまた、一歩ずつ歩いていきませんか?
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-
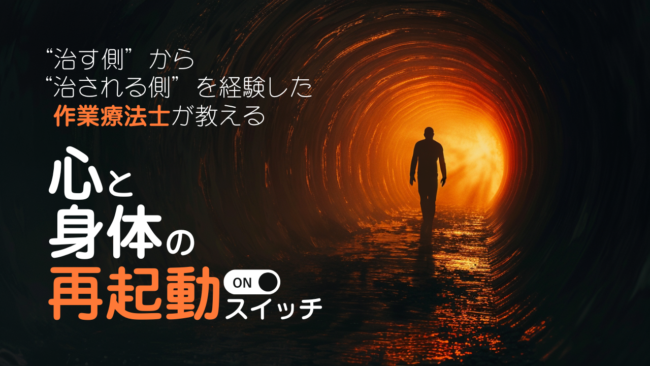
慢性痛に苦しむ女性が”花を活ける”喜びに出会った日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
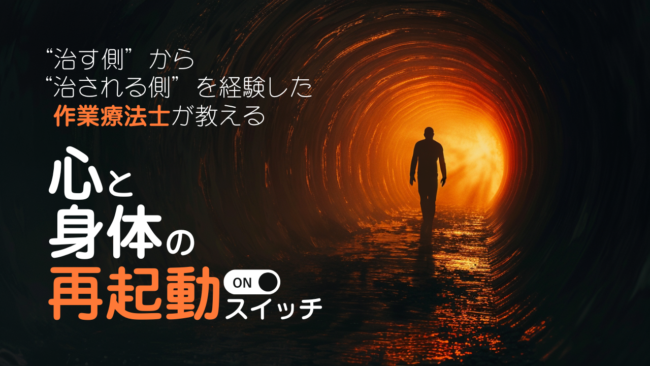
片麻痺の若者が”洗濯バサミで服を干した”午後《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
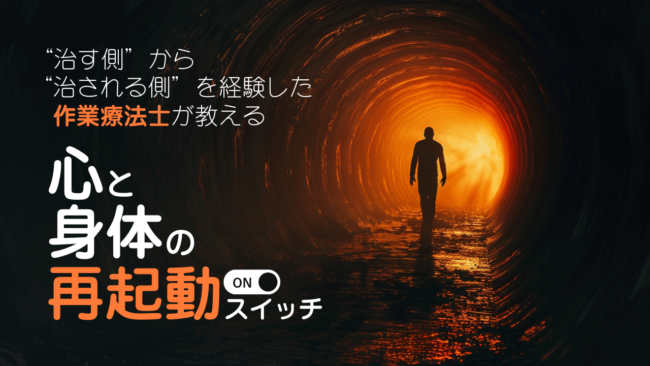
パーキンソン病の男性が”椅子を拭いた”日常動作の意味《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
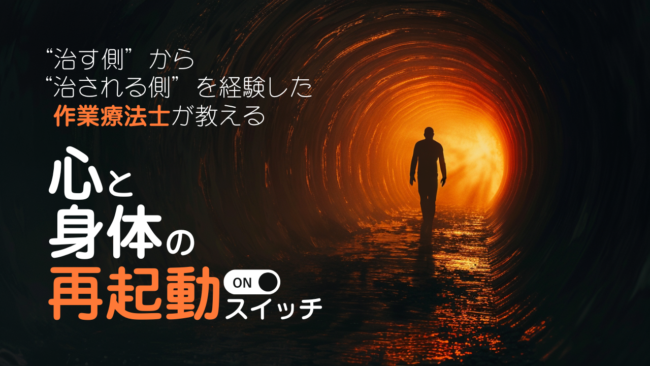
脳卒中で利き手を失った女性が”左手でおにぎり”を握った朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
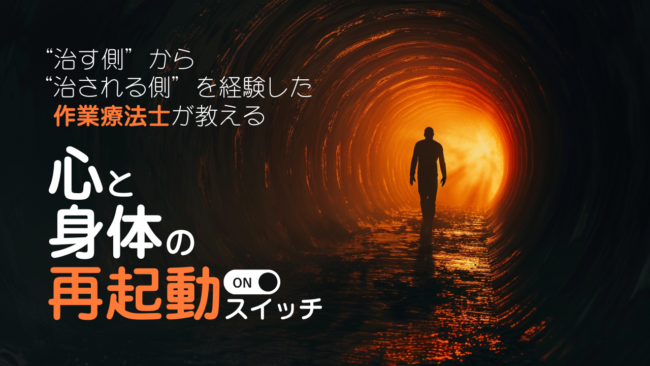
感情表出できなかった男性が”絵”に怒りを描いた日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》



