読書会で気づいた「学び」の本質的な落とし穴 ー映画『宝島』が教えてくれた、知識を資産に変える方法ー
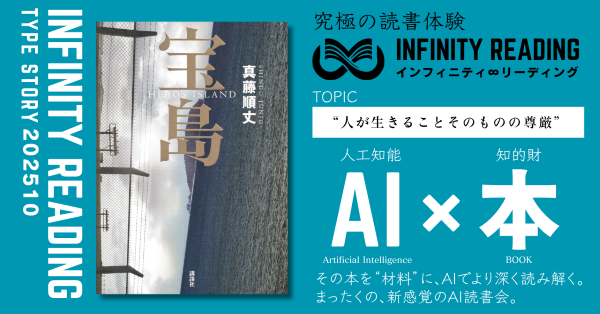
*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
2025/10/23公開
記事 : 山岡達也(ハイパフォーマンス・ライティング)
はじめに:予想の答え合わせから始まった気づき
先週の記事で、10月22日(水)に開催されるインフィニティ∞リーディングに関する予想記事を書いてみました。その記事の終わりに、「実際にどうなるか あなたも確かめてみませんか」と書きましたので、今回はその顛末を書いておきます。
予想記事へのリンクはこちら:https://note.com/tenroin/n/n3b09acbff88b
個人的には、事前にいろいろと「予想」をしたことで、今までになかった気づきを得ることができたのは、大きな収穫でした。一方で、その「予想」は大事な部分がすっぽりと抜け落ちていました。それは、今までのインフィニティ∞リーディングを真剣に学んでいれば、今回もこうなるだろうと予測できたことでした。
この気づきは、私にとって痛烈な反省となりました。しかし同時に、学びを本当の意味で自分のものにするとはどういうことなのか、深く考えるきっかけにもなったのです。
インフィニティ∞リーディング TYPE Sで取り上げられた『宝島』という作品
毎月第4水曜日のインフィニティ∞リーディングは、TYPE Sと銘打って、小説や漫画などのストーリーを作者目線で解析する回として行われています。10月の課題図書は、真藤順丈氏の小説「宝島」が取り上げられました。
『宝島』と聞いて気がついた方もいらっしゃると思いますが、小説を原作とした同名の映画作品が、先月から全国の劇場で公開されています。沖縄の戦後史を舞台にした壮大な物語で、原作は第160回直木賞を受賞した話題作です。
今年の6月には吉田修一氏の小説が原作となっている『国宝』、7月には吾峠呼世晴氏の漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』がそれぞれ公開され、空前のヒットとなっています。どちらの作品も、映画だけでなく原作も非常に優れた作品として評価されています。
9月に公開された映画『宝島』も、原作となった小説が非常に優れた作品なので、ヒット作になることが期待されていました。しかし、この原稿を書いている時点では、興行成績はかなり苦戦をしているようです。『国宝』ならびに『鬼滅の刃』の二作品とは違い、『宝島』はすでに上映が打ち切られた映画館もあるという現実があります。
映画『宝島』から受けた衝撃
幸い、私は「宝島」を旅先で観ることができました。沖縄の戦後史を象徴するような出来事が映画の中でもいくつか出ていましたが、シーンを観るまでは、自分の中では単に名前だけを知っている事件でした。
コザ暴動、軍用機墜落事故、米軍統治下での人々の生活。これらの歴史的事実が、映画の中で生々しく描写されることで、名前だけを知っている事件の裏側には、実はこんなことがあったのかということを、改めて知ることができました。また、映画で出てきたエピソードで、初めて知った歴史上の出来事もありました。
アジア・太平洋戦争を終えて80年が経過した今だからこそ、観るに値する作品であると強く感じました。沖縄の人々が歩んできた道のり、その複雑さと重さを映像化した作品の価値は、計り知れないものがあります。
なぜ『宝島』は苦戦しているのか
インフィニティ∞リーディングでマスターを勤めている三浦崇典氏が、Facebookで興味深い投稿をされています。それによれば、映画『宝島』を高く評価しているのは、出版関係や著者関係の方が多いとのことです。
それならば、映画が興行的に苦戦している理由が余計に見えてきません。優れた原作があり、制作陣も実力派が揃い、批評家からの評価も高い。それなのに、なぜ観客動員が伸びないのでしょうか。
しかし、読書会の後半戦で、言語生成AIはその理由を鮮やかに解き明かしました。AIの分析は、私たちが見落としがちな観客心理の核心を突いていました。
脳に負荷をかける映画の難しさ
主な理由はいくつかあるのですが、私がこれはと感じたことを一つ取り上げて書いてみます。それは、『宝島』という映画が、観る人の脳にかなり負荷をかけることになったため、映画としての面白さが感じられないのではないかということです。
映画でこんなことがあるのかと思われるかもしれませんが、これが読書となるとどうでしょうか。一般的に、映画に比べて読書は知的にしんどい行為です。テキストを読んでイメージや概念、あるいは映像を脳内で思い浮かべるのですから、脳に負荷がかかります。
『宝島』という映画の場合、読書と似ている部分があります。なぜなら、沖縄の戦後史で起こった事故や事件が映画中でのエピソードのモチーフになっているからです。沖縄の戦後史をある程度知っていないと、ストーリーについていけなくなったり、あるいは途中で違和感を感じてしまったりして、映画を十分に楽しめなくなるリスクがあるのです。こういう自分も、映画の設定の中で、こんなことは現実にはありえないと思ったようなことも実はありあました。
観客は、映画を観ながら同時に歴史的文脈を理解し、キャラクターの行動の背景を推測し、時代背景を把握する必要があります。これは、単純にエンターテインメントを楽しみたい観客にとっては、かなり高いハードルになってしまいます。
そういう意味では、私のように比較的年齢がいっていたり、出版関係や著者関係の人たちにとっては、この映画を楽しむハードルが低かったのかもしれません。歴史的知識がある程度あり、複雑な物語構造を読み解く習慣がある人々にとっては、むしろその複雑さが魅力になるのです。
もしも、映画『宝島』を興行として成立させたいならば、言語生成AIによる分析が示したように、モチーフにする歴史上の出来事を絞ったうえで、メインの登場人物の人間ドラマをもっと描いてみるという手もあったと思います。
「しまった」という気づき
今回のインフィニティ∞リーディングでは、映画『宝島』が苦戦している理由を解き明かしてきました。普段の私なら、なんて素晴らしい解き明かしを目の当たりにできたことを、喜んで終わっていたと思います。しかし、今回は少し違いました。
一言で言えば、「しまった」です。
どうしてこのような展開になるのを事前に読めなかったのだろうか。「国宝」と「鬼滅の刃」を取り上げたインフィニティ∞リーディングでは、映画についても時間をかけて取り上げていました。それはまるで、インフィニティ∞シネマといってもいいくらいでした。
だから、今回も映画についても触れるのは、少し考えればわかったはずです。しかし、私にはそんな予想は全く出来ていませんでした。過去のパターンから未来を予測する。これは基本中の基本のはずなのに、それができていなかったのです。
学びが知識になっていなかった現実
どうしてそんなことがわからなかったのだろうか。インフィニティ∞リーディングが終わった後も、しばらく考えていましたが、ある一つの結論にたどり着きました。
「過去の学びが本当に使える知識になっていなかったからだ」
過去の学びと言っても、何年も昔の話ではなく、ほんの数ヶ月のあいだに学んだはずのことでした。それがここぞというときに役に立ちませんでした。いや、学んだというのは間違いで、面白いテレビ番組を観るかのような態度で、インフィニティ∞リーディングに参加していたのだと思います。
本は読まなくてもよいという言葉に惑わされて、事前に本を読んでこない。本を読む時間がなければ、せめてオーディオブックを聞いたり、AIによるリポートに目を通せばよいのに、それすらもしない。
この怠慢が、学びを表面的なものにしていたのです。情報を受け取ることと、それを理解し、活用できる知識として身につけることは、全く別のことだったのです。
自分に課した宿題
そんな自分の態度を反省した結果、この記事を書く前に自分に次のことを課しました。
まず、小説『宝島』を読了すること。映画を観ただけで満足せず、原作の持つ深みと広がりを体験する必要がありました。原作を読むことで、映画では描ききれなかった部分、省略された背景、キャラクターの内面の動きなどが見えてきました。
次に、『国宝』、『鬼滅の刃』を取り上げたインフィニティ∞リーディングを再視聴すること。ただ観るのではなく、AIで作成した作品リポートと合わせながら再視聴してました。
この作業を通じて気づいたことがあります。それは、インフィニティ∞リーディングが単なる読書会ではなく、作品を多角的に分析し、現代社会との接点を見出し、創作の本質に迫る知的冒険の場だということです。
知識を資産に変える方法
こうした作業を通じて、学びを一過性の消費に終わらせることなく、いつでも引き出せる資産にしたいと強く思います。しかも、お金と違い、知識は何度でも使うことができるし、使えば使うほど価値が上がってきます。最終的には、その価値はまさしくインフィニティ(無限)のレベルに到達します。
知識を資産に変えるためには、以下のプロセスが必要だと痛感しました。
第一に、能動的な参加です。受け身で情報を受け取るのではなく、事前に課題図書を読み、自分なりの仮説を持って参加すること。
第二に、振り返りと定着です。読書会が終わった後、すぐに内容を振り返り、得た気づきをノートに書き留めること。
第三に、実践と応用です。学んだことを日常生活や仕事の中で実際に使ってみること。例えば、作品分析の手法を、自分が読む他の本にも適用してみるなど。
第四に、継続的な学習です。一回の参加で満足せず、継続的に参加することで、パターンを見出し、より深い理解に到達すること。
これは単なる自分の反省ではない
これは単に私の反省ではありません。これを読んでいる皆さんにも問われていることです。
あなたは、日々触れる情報を、本当に自分の知識として活用できていますか?セミナーや講座に参加して、その場では「なるほど」と思っても、一週間後にはその内容を忘れていませんか?読んだ本の内容を、人に説明できますか?
現代は情報過多の時代です。SNSやネットニュース、動画コンテンツなど、私たちは膨大な情報のシャワーを浴び続けています。しかし、その情報のほとんどは、私たちの頭を素通りしていきます。まるで、ザルで水をすくうようなものです。
インフィニティ∞リーディングは、このザルを器に変える方法を教えてくれます。情報を知識に変え、知識を知恵に昇華させ、最終的には自分の血肉とする方法論がここにあります。
インフィニティ∞リーディングが提供する価値
インフィニティ∞リーディングの真の価値は、単に本を読むことにあるのではありません。それは、作品を通じて世界を読み解く力を身につけることにあります。
毎回異なるジャンルの本を取り上げることで、多様な視点を獲得できます。ビジネス書、小説、哲学書、科学書など、普段自分では手に取らないような本との出会いが、思考の幅を広げてくれます。
また、三浦崇典氏の鋭い分析と、参加者との議論を通じて、一人では到達できない深い理解に至ることができます。同じ本を読んでも、人によって感じ方や解釈が異なります。その違いを知ることで、自分の思考の偏りに気づき、より柔軟な思考ができるようになります。
さらに、言語生成AIを活用した分析手法は、これからの時代に必須のスキルです。AIをどのように活用すれば、より深い洞察を得られるのか。その実践的な方法を学べるのも、インフィニティ∞リーディングならではの価値です。
この記事を読んで、思うところがありましたら、インフィニティ∞リーディングへの参加を是非ともお薦めします。小説だけでなく、古典、ビジネス、健康など、幅広い分野をカバーしています。毎週水曜の夜が訪れるのが楽しみになること間違いなしです。
リンクはこちらから:https://tenro-in.com/category/infinity_reading/
また、インフィニティ∞リーディングに参加してみた結果、継続して参加されたい場合には、天狼院読書クラブへの参加をご検討ください。
リンクはこちらから:https://tenro-in.com/book-club/
これは単なるサブスクリプションサービスではありません。毎回のインフィニティ∞リーディングへの参加費が無料になるだけでなく、天狼院書店の各種講座やイベントに割引料金で参加できる、学びのパスポートのようなものです。
月額料金を払うことは、継続的な学習の動機づけにもなります。また、様々な講座やイベントに参加することで、読書を起点とした学びのネットワークが広がっていきます。
天狼院読書クラブのメンバーになることは、単に割引を受けることではありません。それは、学び続ける自分への投資であり、知的好奇心を満たし続ける環境を手に入れることです。
おわりに:学びをインフィニティにする
映画『宝島』の興行的苦戦から始まった今回の考察は、私にとって大きな転換点となりました。学びを消費で終わらせていた自分から、学びを資産に変える自分へ。その変化の必要性を痛感しました。
知識は使えば使うほど価値が上がる。組み合わせれば組み合わせるほど、新しい発見がある。そして、共有すれば共有するほど、より深い理解に到達できる。これこそが、インフィニティ∞リーディングが目指す「無限」の意味なのだと思います。
あなたも、この無限の可能性を秘めた学びの世界に足を踏み入れてみませんか?次回のインフィニティ∞リーディングで、お会いできることを楽しみにしています。
そして、もしあなたが本気で学びを資産に変えたいと思うなら、天狼院読書クラブへの参加をお勧めします。継続は力なり。その言葉の真の意味を、インフィニティ∞リーディングを通じて実感してください。
学びは、終わりのない旅です。しかし、その旅を一人で歩く必要はありません。天狼院書店のコミュニティと共に、知の冒険を楽しみましょう。あなたの参加を、心からお待ちしています。
#インフィニティリーディング
#天狼院書店
#読書会
#宝島
#学びを資産に
#読書好きと繋がりたい
#知識をアップデート
#映画と原作
#沖縄戦後史
#天狼院読書クラブ
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00








