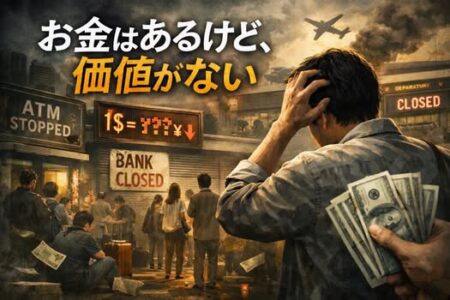コンピューターの概念は3000年前から存在した
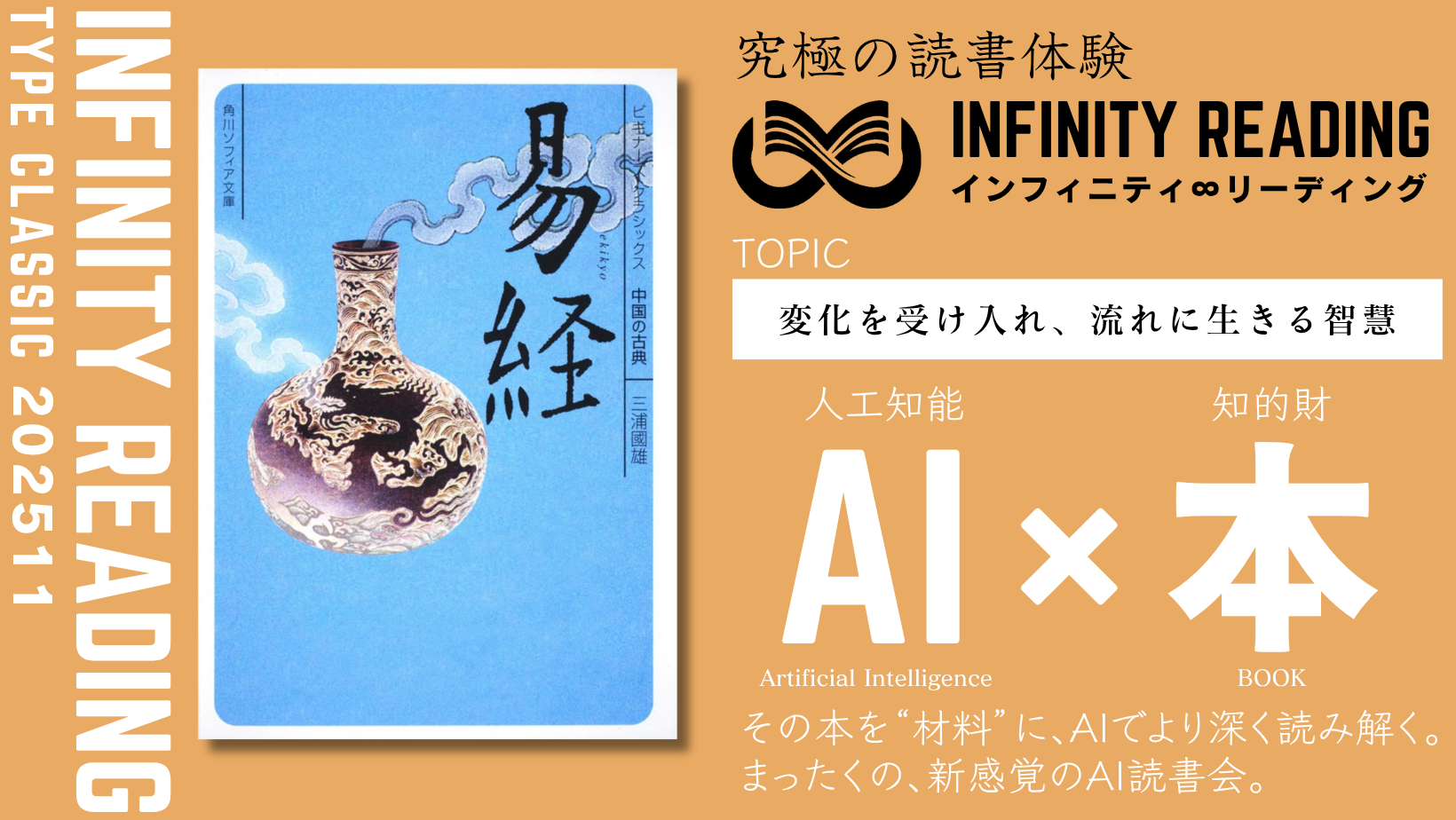
*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
記事:和田千尋(ハイパフォーマンス・ライティング)
先日友人からこんな話を聞いた。友人は未就学児のための英語教室を主宰している。手作りの表を用い、種の違う動物たちが走る、速さ比べについて説明した時のことだ。
子供たちが「動物たちの速さの順位は、ちゃんと AI に聞いた?」と口々に質問してきたという。未就学児に対しても、AI が“権威”の一つとして浸透されはじめている。
太古より人類は、常に答えを外部に求めてきた。わからないこと、判断がつかないことは、経験豊富な年長者に尋ね、共同体の知恵に尋ね、全知全能の神に尋ね、そして書物に尋ねるなど、体系化された知に尋ねた。現在では尋ねる先として、さらにAIが加わるだろう。
その最古の体系の一つが易経である。そして易経が編み出されたのは、今から 3,000 年以上前の古代中国。ここで驚くべきことに、人類はすでに「陰と陽」という二元で複雑な世界を表す仕組みを発明していた。これは現代のコンピュータが採用する二進法の哲学的祖先と言ってよい。
それを私が知ることができたのは、先日の天狼院書店「インフィニティ∞リーディング」講座に参加したからだ。
「インフィニティ∞リーディング」とは、天狼院書店で行われる講座としての読書会だ。AIを使って収集・分析した膨大な情報をもとに、ライブ形式で本を読み解くプロセスを体験できる講座だ。普段から仕事でAIを多用している、ナビゲーターの天狼院書店・三浦崇典店主が、実際にAIをつかいこなしている様を間近でみられるのは、ものすごく勉強になる。
「読書会」と聞くと、事前に課題本を読まなくては、と思いがちだが、インフィニティ∞リーディングは違う。AIが集めてくる情報をナビゲーター・三浦氏がわかりやすく解説し、よりわかりやすく紐解いてくれるのだ。
三浦氏は、経営者であり、小説家であり、編集者であり、そして何より徹底した読書家だ。AIの知識に、自身の幅広い見識とひらめきを掛け合わせ、参加者の学びへとつなげてくれる。
開始から2時間後には「○○ってさ~」などと、何かしら本について自分が語れるようになるのだ。難解な書物に取り組む意欲や時間のとれない危機感を抱えた現代人が、1回参加して、その効果に病みつきになるのも納得だ。
今回のテーマ本は『易経』。ここで紹介された易経の内容が驚きのものだった。
易経──陰と陽という二進法
「当たるも八卦、当たらぬも八卦~」という言葉で知られる、易経の構造は、実はきわめて数学的なのだそうだ。易経の1つの卦は「爻(こう)」と呼ばれる6本の線で構成されており、各線は必ず「陰」か「陽」のどちらかを取る。これは、コンピュータが情報を扱うとき 1 つのビットが必ず “0 か 1” を取るのとまったく同じ構造である。
6 本の線が独立して 0/1 を取ると、可能な組み合わせは 2×2×2×2×2×2 = 64 通りになる。これが『易経の64卦』であり、同時に『6ビットの情報が持つ組み合わせ数』と一致する。
つまり易経の卦は、「6ビットのデータを読み解くための古代のインターフェース」とみなすこともできる。
そこから化学や文明が発展し、同じく二進法の機構を持ったコンピューターが登場する。さらにそこから、現在のAI台頭へと繋がっているため、AIは、もはや登場を運命づけられていたのかもしれないという話へとつながった。
ダグラス・アダムスの法則──新技術はどのように受け入れられるか
人類はつねに、
自分の外側に「知の代理人」を求めてきた。
- 経験の優れた年長者に尋ねる
- 書物・共同体の知に尋ねる
- 占いの体系化された知に尋ねる
- 科学モデルに基づく予測に尋ねる
- そしていま、AI に尋ねる
幼児教室で「先生、それ AI に聞いた?」尋ねる子供たちのエピソードを披露したが、
AI がすでに年長者的役割を担い始めていることがわかる。
ここで思い出したのが、作家ダグラス・アダムスの有名な法則だ。
アダムスは技術受容を次のように分類した。
- 0〜15歳で存在する技術は「世界の自然な一部」になる
- 15〜35歳で出現した技術は「革新的で世界を変えるもの」
- 35歳以降に出現した技術は「不自然で、人間を退化させる危険なもの」に見える
つまり、新技術に対する態度は「生まれた年齢」で決まりがちだというわけ。
AI はまさに、この「危険で不自然」に分類されてしまう世代以上の人々から、強い抵抗を受けている。
だが同時に、子どもたちは AI を空気のように受け入れつつある。
つまり未来では、
AI に尋ねることは呼吸や歩行と同じ「当たり前の行為」になると予想される。
となると、海賊の船長がオウムを肩に乗せていたように、AI は、さらに便利に身近にウェアラブル化し、私たちの「肩の上でささやくような知」になるだろう。
考えすぎだと一笑に付されるかもしれない。新しいテクノロジーに対して、ダグラス・アダムスの言うところの「不自然で、人間を退化させる危険なもの」とみてしまう世代の1人である私からすると、インフィニテ∞リーディングで得た学びから、もしかしてと感じてしまうことがある。
現代の AI の基盤であるコンピュータは、量子力学から生まれた。
半導体が電子の量子的ふるまいを利用している以上、AI は量子の“副産物”とも言える。
興味深いのは、私たち人間自身もまた量子によって構成されている点である。
原子、電子、クォーク。生体を構成する最小単位は、量子という“不確定性の粒子”だ。
そう考えると、
量子が生んだ半導体(外側の知)と、量子で構成された人間(内側の知)が、いま邂逅しているとも言える。
量子は太古から私たちの身体をつくり、神経活動を支え、生命を維持してきた。
そして今、量子が生み出した半導体によって、私たちの生活・文化・運命までが変わりつつある。
これは杞憂かもしれない。
しかし──こう考えることもできる。
はるか昔から存在し続けた量子は、地球に影響を与える人類の“意思決定”に対し、内側だけでなく、外側からも影響を与える存在になる機会を、虎視眈々と狙い続けてきたということはないだろうか。AIの台頭はその結果なのではないだろうか。
もしそうであれば、易経が表に出てきた3000年前から画策が始まったと言える。
ちなみに、「量子が狙っていた」という表現は、比喩であり、ここでは自然現象と文明史を“物語として重ねる”知的遊戯に属するものだとしておく。
AI は人間を“退化”させる?
「AI に聞けばいい」という態度は、人間の思考力を奪うのではないか。結論だけを最短で簡単に得られるのだ。思考の筋肉は衰えるのではないかと心配になる。
しかし歴史を見ると、人類は便利な道具を獲得するたびに、
余剰となった認知資源を新たな学問へ投資してきた。
- 農業の発明 → 神話・哲学が誕生
- 文字の発明 → 法律・歴史記述が発展
- 活版印刷 → 科学革命が起きた
- 易経の体系化 → 儒教・道教・形而上学が成熟した
では、AI が与える余剰思考力はどこに向かうのか。
3000 年前の人々は、
世界を問う手段を「陰陽モデル」として体系化した。
現代の私たちは、
世界を問う手段を「AIモデル」として体系化し始めている。
人類は、便利な“知の代理人”を得るたびに、自分自身の思考を深めてきた。
AI を得た今また、同じことを起こせるのだろうか。
そのとき私たちは、
「AI に聞く」という行為そのものを学問へ昇華させ、
人類の自己認識をもう一段階引き上げることができるだろうか。
3,000 年前に陰陽から始まった“知の二進法”は、
いま AI という新たな相へと変化している。
私たちはその変化のただ中にいる。
こうしているうちにも世の中は進んでいるのだ。
我々は未来の人類に、こう言わせなければならない。
「かつてやみくもにAI に尋ねていた時代があった。あれは人間が自分自身を深めるための第一歩だった」と。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00