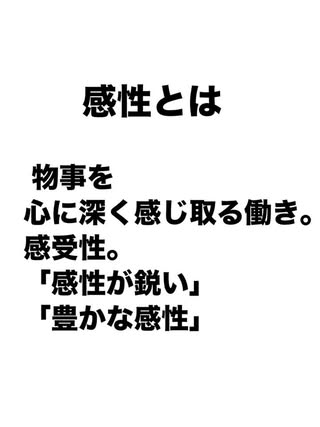小説「ぼくの仕事」《週刊READING LIFE Vol.62 もしも「仕事」が消えたなら》

記事:吉田けい(READING LIFE編集部公認ライター)
「ねえ、何か仕事ないかな?」
ぼくがそう尋ねると、友達のエルカはびっくりしたように目を見開いた。
「仕事、なんてこの世界にあるわけないじゃないか、学校で習っただろ?」
エルカのため息に、ぼくも首を捻るしかなかった。
人間が仕事という労働を自分でやっていたのは、およそ21世紀までのことだそうだ。22世紀にAI技術が飛躍的に向上して、各国の首脳はスーパーAIが務めるようになった。西暦2200年、23世紀になるのを区切りに、各国のスーパーAIが統合、国というものがなくなって、世界は一つになった。
「本当になくなっちゃったのかなあ? 全部の全部?」
「全部の全部だろ。ぼく、仕事してる人なんて見たことないよ」
学校から家までの帰り道、美しく整えられた植木に、夕焼けの光が眩しい。
食べ物、衣服、医療、教育にレジャー、人間が生きていくのに必要なものはすべてAIに制御されたコスモシステムによって、人の手を一切使わずに生産することができる。この植木の手入れだってそうだ。統合されたAIは、貧困問題と戦争問題を解決するために、すべての会社を廃業させ、通貨そのものも廃止した。すべてはAIとコスモシステムから、一人ひとりに必要な分だけ支給されるのだ。人間はコスモシステムの中で、生涯労働の制約を受けることなく、衣食住の心配をすることなく、充実した人生を楽しむことができるようになった。初等学校の社会の時間で習う、十二歳のぼくたちにとってごく当たり前の現実だ。
「でも、ぼく、仕事がしてみたいんだ」
「リク、どうしちゃったの?」
心配そうなエルカに、ぼくはライブラリでみつけた映画や小説の話をした。21世紀以前の古典作品は、どれも人間が労働をすることを前提に物語が作られている。朝起きて、仕事場に行って、同僚と一緒に仕事をする。失敗することもあるけど、成功すると大きな達成感が得られる。家に帰って、家族との和やかなひと時を過ごして、また明日仕事に行く……。その日常の中で事件やロマンスが起こって、それが物語の筋なのだけど、ぼくを虜にしたのはそれではなかった。特に、ニッポンの小さな工場がロケットを作るシリーズが気に入って、何度も何度も繰り返し見た。
「毎日仕事に行くってどんな気持ちなんだろう。学校に行くのとは違うのかな?」
「そんなのぼくに聞かれたって分からないよ……」
「楽しそうに仕事に行く人もいるけど、仕事が辛くてスーサイドしてしまう人もいるんだって。社会問題にもなったらしいよ。そんなにまでしてやらなきゃいけなかったのかな?」
「だって、お金がないとモノが食べられなかったんだろ、当時の人は」
「仕事の資料って、どんなものなんだろう? 物語じゃそんなあたりまでは分からないんだ。学校の宿題やレポートとは違うだろうしなあ」
「……ねえ、リク、その話まだ続く?」
エルカが怒った声を出したので、ぼくは口をつぐんだ。エルカは機嫌を直して、サーカスのチケットに当選したことを自慢し、ぼくも連れて行ってもらえることになった。サーカスも、昔はチケットにお金がかかっていたらしい。人気のチケットはかなりの高額でやりとりされていたとか。今は家からコスモシステムで抽選申し込みをするだけだ。落選しても、リアルタイム配信で見ることが出来るから、あんまり気にする人はいない。エルカと分かれ道になってさよならして、家に着く頃は、あたりはすっかり暗くなっていた。
「ただいま」
「お帰り、リク」
それぞれの家族に、AIが用意した、コスモシステム搭載の家が割り当てられる。僕のうちもそうだ。家に帰ると、ダンスの練習をしているママが声をかけてくれた。僕は玄関先のクリーンルームで全身の埃をクリーンアップされて、手を消毒されて、うがい薬が出てくる。ガラガラぺ、とするころには、メイドロボットが僕の上着を取りに来て、クローゼットにしまってくれる。
「今日の夕飯は?」
「今日はハンバーグにしたよ」
今度はパパの声。どうやら読書をしているみたい。食事は、料理をしてみたいと希望しない限り、コスモシステムが全自動で調理してくれる。家族バラバラのメニューを選ぶこともできるけど、ぼくのうちはみんなで同じものを食べよう、とパパが決めていた。その代わり、誰がメニューを決めるのかが当番制になっている。パパはハンバーグが好きだから、今日のメニューはぼくの予想通りだった。
「ねえ、パパ、仕事ってどこかにないのかな?」
ハンバーグをほおばりながら僕が尋ねると、パパもエルカと同じような困った顔をした。
「仕事はね、辛くて厳しい、前時代の人たちが生きるために仕方なくやっていたものなんだよ。私たちは今満たされていて、働く必要なんかないんだ」
「ほんとに辛くて厳しいだけだったのかな? 映画だと楽しそうな人もいたし、仕事を楽しむような本もたくさん出てたっていうよ」
「研究熱心だな、リクは」
パパが苦笑いする横で、ママがそうだ、と声を上げた。
「そんなに仕事が気になるなら、カケルじいちゃんに電話してみなさい。カケルじいちゃんは若い頃仕事をしていたそうよ」
「わ、カケルじいちゃんが!? 知らなかった!」
ひいひいおじいちゃんのカケルじいちゃんは、もう百歳を過ぎてるけど、怪我も病気もしないで元気に過ごしている。昔の話をたくさんしてくれるので、ぼくはカケルじいちゃんが大好きだ。でも、仕事をしたことがあるなんて知らなかった。もっと早く聞いてみればよかった! 焦ってハンバーグを食べたので喉につまりかけたけど、何とか飲み込んで、カケルじいちゃんに電話をかける。
[おや、誰かと思ったらリクくんか。元気かな]
電話の3Dディスプレイにカケルじいちゃんが投影された。椅子に座って、スポーツ観戦していたらしい。ディスプレイの端っこに、サッカーをしている人たちの様子が映っている。
「カケルじいちゃん、ぼく、仕事がしてみたいんだ! カケルじいちゃんが仕事してた時のこと教えて!」
[仕事かあ。ずいぶん久しぶりに聞いたなあ]
「ねえ、いいでしょ、じいちゃん! 何の仕事してたの、仕事って楽しいの!?」
ぼくがディスプレイに頭を突っ込みそうなほど身を乗り出すと、カケルじいちゃんはうーん、と言いながらしわしわの手を揉みあわせた。
[リクくん、仕事はなあ。楽しいことばっかりじゃないんだぞ。じいちゃんは、コスモシステムの前身みたいな機械の保守点検係をしていたけど、辛い事も多かった]
「楽しいこともあるの?」
[あるにはあるけどなあ。でも、仕事しないで食べていけるなら、それに越したことはない。人間がやるより、AIやコスモシステムがやった方が、ずっと効率がいい。人間でないと出来ない仕事も、ずいぶん減ってしまったからなあ]
「じゃあ、まだどこかに仕事があるの?」
[どうだろうなあ、もうじいちゃんの周りにも仕事はみかけないよ。リクくんも来年は中等部だろう、自分で調べてごらん。それでその結果をじいちゃんに教えてくれ]
わかった、と、カケルじいちゃんと男と男の約束をした。
ぼくはそれから仕事についていろいろ調べた。けれど、現代には何の仕事があるのか、なかなかたどり着くことができなかった。ただ、仕事がだんだんなくなっていく22世紀以降も、経営者や研究者など、頭脳労働の一部の仕事はなかなかAIと交代しにくかったらしい。だからこそAI首脳の登場は衝撃的で、世界中のAI化を加速させた、と書いてあった。それから、音楽家やサーカスのような、エンターテイメントも、なかなかAI化しなかった。機械でもっと素晴らしいことを実現できたとしても、それを敢えて人体で実現することが芸術なんだそうだ。
次の休日、エルカは約束通りぼくをサーカスに連れて行ってくれた。色とりどりの衣装を着た人たちが、とても高いところで宙返りをしたり、信じられないようなポーズをとったりする。ぼくと同じ人間とは思えなかった。敢えて人体で実現するってこういうことか、と分かったような気がした。じゃあ、これが仕事なのかな? 僕にもできるだろうか。エルカのチケットの特典で、出演者の人と握手できた時、ぼくは水色のレオタードを来たお姉さんに尋ねてみた。
「あの、お姉さんのサーカスは、仕事ですか?」
「仕事……?」
お姉さんはぼくの手を優しく握りながら、不思議そうに首を傾げた。
「私は、身体を動かすことが好きだから、サーカスをやっているの。でも、大昔のようにお金をいただくわけではないし、仕事とは違うんじゃないかしら」
「そうですか……」
ぼくががっかりしてしまったのが伝わってしまったのだろうか、お姉さんは、「みんなが私を見てくれたら、それで満足よ」と付け足していた。エルカはその横で、リクまたそんなこと聞いてるのかよ、と笑いを噛み殺していた。ショーは素晴らしかったし、お姉さんは優しかったけど、これもやっぱり仕事じゃなかった。ぼくは少し残念な気持ちだった。
ぼくはめげずに、いろんな人に仕事がないか聞いて回った。インターネットやライブラリでも調べて回った。相変わらずめぼしい情報は見つけられなかったけど、ぼくが仕事を探していることは学校や町中の噂になって、からかわれることもあった。ママは仕事したいなんて言うのはやめろ、と叱ったけど、ぼくはやめられなかった。大人になっても、パパとママみたいに、ずっと勉強してのんびりしているだけなんて嫌だ。あの映画でロケットを作る人たちみたいに、ぼくも仕事をしてみたい。仲間と一緒に困難を乗り越えて、大きな達成感を味わってみたい……。
「……リクくん。仕事を探しているそうだね」
ある日学校で呼び出されると、小さな部屋に大人が数人待っていた。普段は学校には人間の先生はいないから、学校の中で大人の人に会うのは久しぶりだ。緊張して身動きが取れなくなったぼくを見て、大人たちは顔を見合わせて、真ん中の人がぼくに話しかけてきた。
「……はい、そうです」
「どうして仕事がしたいんだ? 今の環境では不満かな?」
「いえ……不満はありません」
ぼくのことをじろじろ見てくる大人たち。こんな風に人に見られるのは初めてだ。喉が渇いて、手がじっとりと湿る。
「それなら、仕事を探すのはやめなさい、そんなものありはしないんだ」
「でも……ぼくは、仕事をしてみたいんです」
ありったけの勇気を振り絞ったぼくの声は、子猫が鳴くみたいな声になってしまった。
「毎日、のんびり幸せに暮らすだけじゃなくて……誰かのために、仕事をしてみたいんです。仕事をして、何かを成し遂げた、って、実感してみたいんです。お金……が、もらえる仕事が、今この世界に存在するのか、分からないですけど……」
「ほう……」
「本当に、どこにも仕事はないんでしょうか? それとも、仕事はあるけど、ぼくには出来ないんでしょうか?」
大人たちはまた顔を見合わせて、何かをひそひそと話した。内緒話がずいぶん長いなと思った頃、今度は左端の人がぼくに声をかけてきた。
「リクくん、君の言う通りだ。仕事はない。そして、君には出来ない」
「……そうですか……」
「正確に言うと、ここに仕事はない。そして、今の君には出来ない」
「……え?」
大人の人──ひげを生やしたおじさんが、ぼくにニッコリと笑いかける。
「コスモシステム内は、すべてAIとシステムが処理してしまうからね。仕事はシステムの外にあるんだよ。もし君がコスモシステムを出て仕事をしたいというのなら、中等部の六年間、首席を取り続けることだ」
「首席って……学科でですか?」
「学科だけではない。実技もだよ。君がそれくらい優秀な人材だとわかったら、中等部を卒業した後、仕事をあげよう」
「…………ほんとですか!?」
飛び上がった僕に、大人たちはみんな微笑みかけてくれた。
「その、その仕事って、とてもやりがいがあるものなんでしょうか」
「もちろんだ」
「一緒に仕事をする同僚もいるんですか?」
「たくさんいるぞ」
「お、お金、も、もらえるんでしょうか」
「コスモシステムの中では使えないけれど、給与も勿論支給されるよ」
すごい、仕事、ぼく仕事ができる! 大人たちは興奮するぼくを落ち着かせると、コスモシステムの外に仕事があることは内緒にするように、と何度も釘を刺した。コスモシステムを出ること、外で仕事を持つことは、本当ならとても優秀な人にだけ知らされる秘密なんだそうだ。ぼくみたいに事前に教えてくれるのは例外中の例外らしい。ぼくはドキドキしながら、誰にも言わないと約束をした。パパにも、ママにも、エルカにも、カケルじいちゃんにも。絶対内緒にする、と誓って、大人が出してきた書類に名前を書いた。
それから六年間、ぼくは中等部でものすごく頑張った。学校の勉強の成績は今までは真ん中くらいだったけど、家に帰ってからもたくさん勉強して、一番を取り続けた。苦労したのが実技だ。体力向上プログラムをAIに組んでもらって毎日実践したから、体育はどうにかなったけど、音楽とか美術とか、感性がものをいう科目は苦労した。結局感性は身に付かなかったけど、その代わりたくさん見て学ぶ方法が身に付いたと思う。とにかく、努力の甲斐あって、ぼくはずっと学年トップだった。
中等部の卒業式の日、約束通りあの大人の人たちがやって来た。パパママに挨拶をして、ぼくが仕事をすることになったことを説明すると、二人ともとても驚いていた。エルカも驚いて、しばらく会えなくなるな、電話しろよ、なんて笑っていた。カケルおじいちゃんも少し寂しそうだったけど、頑張れよ、と応援してくれた。
「さて、行こうか、リクくん」
「はい!」
大人の人たちは、高そうなリニアカーにぼくを乗せ、どこかへと走って行った。ぼくが今まで行った事ないような遠くまで来て、どこかの建物に入ったかと思うと、暗いトンネルのなかをずっとずっと進んでいく。
「仕事は、ずいぶん遠くでやるんですね」
「そうとも、コスモシステムの外だからね」
「あの、コスモシステムって言いますけど、地球のことじゃないんですか? ぼくはてっきり宇宙で仕事をするんだと思っていました」
「まあ、似たようなものだよ、もうすぐ出る」
ぼくの隣に座った、あの髭のおじさんの言う通り、リニアカーはトンネルの外に出た。
真っ黒な雲に覆われた空。
あたり一面、草も生えていない荒野。
時折雲の間を、紫の稲光と、それよりも早い光の点が、轟音と共に駆け抜けていく。
「……ここは……?」
「地球だよ。星間戦争が激化して、焼け野原になってしまったけどね」
光の点が二つぶつかり合って、雲一面が真っ白に光る。遅れてやって来るものすごい音と爆風。リニアカーが何十メートルも吹き飛ばされて、車の中で全員もみくちゃになった。ぼくは悲鳴を上げたけど、おじさんたちは慣れているのか、顔をしかめただけで声一つ洩らさなかった。
「敵のベガ系星人たちは、我々の太陽のエネルギーを根こそぎ狙っているんだ。そんな横暴、許してなるものか。太陽系惑星は連合を組んで迎え撃っているが、戦況は芳しくない。核兵器が効かない敵など、人類は想定していなかったからね。他の星も似たようなものさ」
「かく、へいき……」
22世紀にすべて廃棄されたはずの、最悪の兵器だと習った。人体にも、他の生命にも有害だって……。それがまだ実在していて、戦争している?
「もはや地上は、いや、太陽系の全ての惑星は戦場になった。人類は太陽を守ると同時に、種を守らないといけない。だから地中深くのコスモシステムで、放射能が消える遠い未来まで、人類を培養し続けているのさ」
「培養……」
いつの間にかリニアカーは体勢を立て直して走り出していた。どこまでも荒野だと思っていた景色が、岩ばかりの山に変わりつつある。茫然としているぼくの肩を、髭のおじさんがぽんぽんと叩いた。
「さあ、リクくん、人間がやるべき仕事はもう数える程しか残っていない。戦闘機を操り、核兵器を操り、我々の太陽を守るんだ。AIの計算だけでは敵を出し抜くことはできない、人材は常に不足している」
岩山の隙間に、かすかな光が見えたと思うと、どんどんその数が増えていく。いつか何かのアニメ映画でみたような秘密基地と言えばいいのだろうか、岩山にカモフラージュされた要塞が僕の目の前に現れた。ガラスのような透明な壁の向こうで、たくさんの人たちが手を振っているのが見える。
「ここに入ってしまうと、もう戻ることはできない。最後のチャンスだ」
髭のおじさんが、ぼくの顔をじっと見る。
「コスモシステムに戻るかね? それとも……」
ぼくは震えている手で、おじさんが喋ろうとするのを遮った。
「ぼく、ここで……」
運転している人も、他の人も、もしかするとガラスの向こうの人たちも、じっとぼくを見ている。自分の膝の上に戻した手が、さっきよりも更に酷く震えている。
「……仕事をします」
身体全体が、さっきの爆撃みたいに熱くなった。
◽︎吉田けい(READING LIFE編集部公認ライター)
1982年生まれ、神奈川県在住。早稲田大学第一文学部卒、会社員を経て早稲田大学商学部商学研究科卒。在宅ワークと育児の傍ら、天狼院READING LIFE編集部ライターズ倶楽部に参加。趣味は歌と占いと庭いじり、ものづくり。得意なことはExcel。苦手なことは片付け。天狼院書店にて小説「株式会社ドッペルゲンガー」を連載。
http://tenro-in.com/category/doppelganger-company
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/event/103274