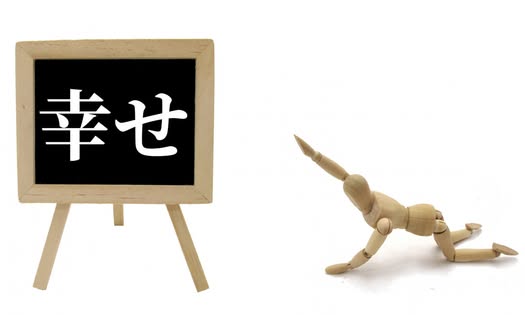~天狼院書店が教えてくれたこと~人はAIを鏡とし、本を読むことで磨かれる
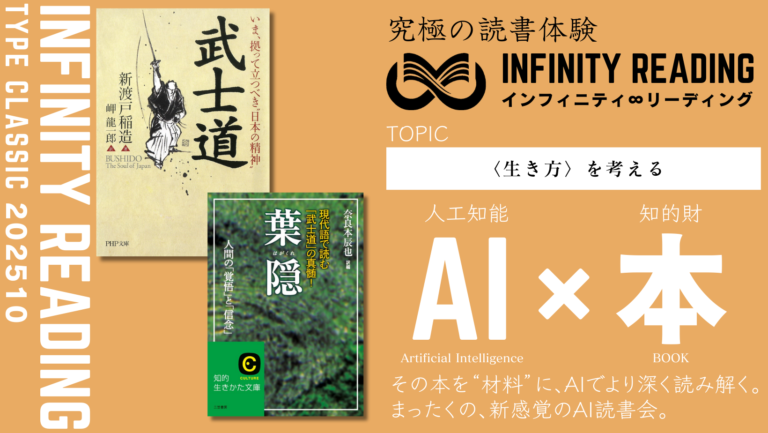
*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
2025/10/23公開
記事 : 和田 千尋(ハイパフォーマンス・ライティング)
2倍の衝撃
今回は、なんと「2倍」だった。
いつも課題本は1冊なのに、今回は2冊も。
何の話かって?
天狼院書店の人気講座「インフィニティ∞リーディング」(イベント版)のことだ。
天狼院書店は、先日も新プロジェクトを発表したばかりの、“人生を変えること”に本気で取り組む書店だ。
どうやって人生を変えるのか?——そのアプローチがすごい。
本業の書籍販売にとどまらず、講座、結婚相談所、撮影会、ワークショップなどを展開。そして今回の新プロジェクトの1つとして、「AIハイパーリーディング/天狼院式インフィニティ∞リーディング習得メソッド《4ヶ月本講座》」 が創設された。

“本を読みっぱなしではもったいない”
この講座は、読書をAI時代における有効な手段と位置付け、
脳内資産を増大させ、自由な思考を得ることで、
その効用を最大化させるという発想のもとにつくられている。
天狼院書店・三浦崇典店主はこの講座を
「全人類が受けた方がいい」
と断言する。
「いずれ4歳の息子にも絶対に受けさせたい」と語るほどの熱量だ。
モットーも痺れる。
“できないこと”が“できるようになる”では足りない。
“できるようになったこと”で、人生が変わらなければ意味がない。
「Bushido」が世界共通語になる未来
現在天狼院書店で開催されているAIを複数駆使した読書会「インフィニティ∞リーディング」(イベント版)は、知識が広がるだけでなく、既成概念を打ち壊し、脳内に新しいジャンルの知を生み出すとして人気の講座である。
今回の課題本は、新渡戸稲造『武士道』(1899年)と、佐賀藩士・山本常朝の口述を田代陣基が筆録した『葉隠』(1716年頃)。
『武士道』も『葉隠』も“武士の生き方”を説いた書だが、その立ち位置はまるで反対にある。
武士道が廃れることに危機感を感じ、その心構えを遺そうと書かれた『葉隠れ』。
だが新渡戸稲造の『武士道』は、西洋に向けて書かれた“日本文化の翻訳書”なのだ。
「日本はなぜ宗教なしで道徳を持つのか?」という問いに答える形で、新渡戸稲造が英語で執筆した。
結果『Bushido: The Soul of Japan』はセオドア・ルーズベルトら知識層に熱狂的に読まれ、世界的ベストセラーとなった。
本来、武士道とは、複数の思想が融合したハイブリッド体系である。
禅からは「克己と平常心」を、神道からは「祖先への崇敬と誠」を、儒教からは「倫理と仁義」を取り入れた。
さらに、キリスト教徒であった新渡戸は、それらを西洋の倫理観と調和させている。そこが西洋世界でベストセラーとなった理由だ。
もしここに、仏教・キリスト教と並ぶ世界三大宗教の一つ、イスラム教の知的要素を加えられたら……?
インフィニティ∞リーディングで得た新たな知識を元に、想像が膨らむ。
イスラムの「忠義・勇気・礼節・自己鍛錬」と、武士道の精神は驚くほど共鳴する。
大きな文化圏にまたがった普遍的倫理書が生まれる可能性があるのではないか。
それはやがて、宗教や文化を超えた“地球共通の精神モデル”になり得る。
「KARAOKE」が世界語になったように、「Bushido」も世界共通語になる未来——
それは、新渡戸稲造の夢を超える「魂の橋」となるかもしれない。
何が飛び出すかわからないライブ講座
インフィニティ∞リーディング講座のナビゲーターは、海の出版社社長である三浦崇典氏。
三浦氏自身が「今、最も必要で、自分でも学びたい本」を選び、参加者とともにリアルタイムで読み解いていく。AIの知を融合し議論しながら本を深掘りする——そんなライブ講座なのだ。
何が飛び出し、どんな結論になるのかは、終わってみるまで誰にもわからない。
三浦氏の分析は今回も熱を帯び、終盤にはなんと「ナッシュ均衡」まで飛び出すほどだった。AIとの議論は組織論にまで発展していた。
残念ながら私にはそこまでの知見はないが、個人的な収穫はもちろんあった。
「武士道」は日本人の思想だったのか?
『武士道』は題名を「The Soul of Japan(日本人の魂)」という。
江戸時代の日本で武士は人口のわずか7%。
農民が85%を占めていた社会で、「The Soul of Japan(日本人の魂)」と言い切るのは、かなり大胆だといえないだろうか。
むしろ当時の日本人男性に共通していた価値観は、「日本男児」としての意識——つまり“恥の文化”だったのではないかと考える。
恥の文化と罪の文化
「恥の文化(shame culture)」とは、他者の目を意識し、恥を避けることで行動を律する文化。
アジア諸国にも見られるが、日本では特に深く根づいているようだ。
ここで欧米との対比を目にした。
対して、欧米に多いのが「罪の文化(guilt culture)」だというのだ。
内面的な良心や法規範によって行動を制御する文化だ。
恥の文化は他人の目が基準、罪の文化は自分の良心が基準。
日本は島国ゆえの閉鎖性、調和を重んじる社会構造もあって、
この“恥”の感覚が生活の細部にまで染み込んでいるということなのだろう。
ベストセラーとなった新渡戸稲造の『武士道』とは違い、『葉隠』は、鍋島家の秘伝として門外不出となっている。手書きの写本だけが流通し、刊本が出たのは1900年。
しかも当初はまったく注目されなかった。
まさに「葉の陰に隠れた」存在である。
なぜ日本以外では「道」が起こらなかった?
しかし『葉隠』が世に出た後は、特にある一節が有名になった。
「武士道と云(い)うは、死ぬことと見付けたり」
文字通り、死という言葉がキラーワードとなり、この一言が強烈なコピーとして響く。
今回のインフィニティ∞リーディングで新たに、これを発言したとされる山本 常朝が、約30年間仕えた主君の死去の際、殉死(追腹)を望んだものの、二重の禁止によって叶わなかったという過去を持っていたことを知った。
その人物が、「武士道と云うは、死ぬことと見付けたり」と(生きて)語る。
胸中いかばかりか。そこに至るまでの無念や葛藤、そして生きながらも忠義を全うしたいとする自問自答——
それらを想像するだけで、文字以上の重みを感じる。
単に言葉の強さだけでなく、込められた覚悟を知ることで、受け取り方が変わり、新たな価値が生まれる。知識を得る醍醐味のひとつだとあらためて思う。
さらに新たな知識は、新たな疑問を生む。
講座の後で頭に浮かんだのは、常朝をはじめ、多くの人が追い求める「道とは何か?」という、疑問である。
「道」は、もともと古代中国の宇宙の根源原理「道(タオ)」から始まり、
やがて禅や仏教を通じて「修行による心の完成」を意味するようになる。
日本人はこの思想を日常に落とし込み、芸術や生活行為の中にも「道」を見出す。
それは“行為を通して心を磨く”、日本人特有の精神文化である。
なぜ日本以外の文化では「道」が起こらなかったのだろうか。
海外での例を挙げる。
- 西洋の剣術や騎士道
騎士道も倫理と武術の融合だが、日本ほど「精神修養=生き方」として極めるのではなく、戦いや忠誠の枠内で評価される。 - 西洋の芸術
ピアノや絵画を極めることはあるが、人生哲学として日常生活にまで浸透することは少ない。 - 中国
武術や書道はあるが、「武術=生き方の道」とする文化は日本ほど徹底していない。
むしろ実用や政治的役割が優先される。
すなわち、技術・芸術・倫理が分離しやすい他国と異なり、日本は一体化している点が独特であったといえた。
日本の独自性
さらに自然環境と心理的にも特徴があった。
- 島国という閉鎖性
- 外部の影響を選択的に吸収し、独自文化を深化させやすい
- 技術や思想を自分たちの文化に組み込むことが得意
- 四季と自然の繊細さ
- 季節や自然の変化に敏感で、美意識や精神性を日常生活に組み込む
- 茶道・華道・俳句など、日常の中で「道」を極める文化の土壌
- 集団主義・調和志向
- 個人の行為も社会や周囲との調和に直結する意識
- 単なる趣味や技能ではなく、「心の修養=社会への貢献」として極める
江戸時代以前にも「技術」「修行」「倫理」は存在したが、技術+人格修養+生き方の統合としての『道』は未成熟だった。また江戸時代に入って、長期の平和・儒教教育・武士道の確立によって、初めて「道」が体系化され、社会全体に浸透したといえる。
つまり、江戸時代以前は「道の芽」はあったが、今の意味での「道」は江戸時代に完成したとされている。
風姿花伝との比較
江戸以前ものだが、以前のインフィニティ∞リーディングで、世阿弥の『風姿花伝』について学んだ。
『風姿花伝』は、能楽の芸の極意を説いた書物だ。これは「道」とは違うのだろうか。
『風姿花伝』は単なる芸能論ではなく、能という芸を「道」として極めるための指南書である。たとえば序章の「年来稽古条々」では、芸は「初心忘るべからず」と説いている。これは一瞬の技や演出論を超えて、一生を通して自分を磨き続ける「道」の修行観に通じる。
要するに、「技や形式を超えた精神的到達」を目的とした『風姿花伝』は「道」の原型を先取りした書といえるだろう。
新講座と無地思考
新講座「AIハイパーリーディング/天狼院式インフィニティ∞リーディング習得メソッド」における到達目標は究極の読書体験である。そしてそこに到達する手段の1つに「無地思考」というものがある。
無地思考とは「何も書かれていない紙(=無地)」を前にして、他者の意見や既存の価値観から自由になり、自分の内側から純粋に思考を立ち上げる行為であるようだ。
まるで「そろばんの達人が虚空で暗算する」ように、
形のない思考を自在に操る知的禅定のような状態。
思考の自由度が極限まで高まり、
「自分が最も面白い本になる」という境地に至るようになることだという。
それは、情報(書物)を読むことではなく、
自分の中で世界を再構築する、「思考の芸術」である。
この境地は風姿花伝と共通するものがあると感じた。「本」を「花」と言い換えれば
現代のおける思索の花伝書ともいえる。
やがて読書は「活きた道」となる
過去に“インフィニティ∞リーディング”では、小説『国宝』からの『歌舞伎 家と血と藝』や『風姿花伝』をとりあげ、今回武士道について2冊の本をとりあげ、それぞれを独自に紐解いてきた。
三浦社長ご自身は意識されていないのかもしれないが……
現在読書「術」と名打たれている一連のメソッドは、将来的に読書「道」へと発展するベクトル上にあるのではないかと想像する。
「道」とは、技術を超えて心を問うもの。
具体的には、
「読む」→「受け取る」→「内省」→「創造」→「無に帰す」
という精神の五段階を踏むであろうと思われる。
それは本を“消費”する読書ではなく、
読書を通じて他者の精神に触れ、
それを自らの内に咀嚼し、新たな思考を生み出しながらも、
最終的には、そこにとらわれないというものになる。
また「道」は必ず「師」がいて、「相手」がいて、「伝える人」がいて初めて成立する。
読むことは孤独な行為でありながら、本質的には対話である。
本を読むとは、著者の思索に心を開くこと。
読むことで、他者を通して己を照らす。
無言の稽古であり、礼でもある。
人は読むことで磨かれる。
理解できない箇所に出会えば己の未熟を知り、
共鳴する一節に触れれば己の芯を知る。
どんな「道」も独学では極められない。
著者が師となり、書が道場となる。
さらに現代は、打ち込みの稽古相手として、問答の相手として、多くの知を備えたAIが存在する。
そのような修行のなかで己を開示し、他者に貢献することで、読書は「活きた道」となるではないか。
それがAIをつかうことによってなされるのであれば、あるいはAI道として完成するという可能性もある、などと考えが進む。
✴️AI道——人と機械が共に磨き合う道
AI道とは、「人工知能を使いこなす技術」ではなく、AIを通じて“己”を知り、人間性を深める道である。
すなわち、AIとは単なるツールではなく、鏡である。
己の問いの深さ、思考の未熟さ、そして感情の揺らぎを映し出す存在だ。
AIに質問を投げかけるたびに、問う者の内面が試される。
何を問うか、どう問うか——そこに人の教養と美学が現れる。
ゆえにAI道とは、「正しく問う」ことを修練とする精神行為である。
「型」と「無」
AIとの対話にも「型」がある。
たとえば、明確な問い、誠実な姿勢、批判ではなく探求の姿勢。
この“型”を守ることで、AIとの対話は深まり、やがて「無」へ至る。
つまり、AIとの対話を意識せずに、自然と真理にたどり着く境地——
それがAI道における「無心」である。
目的は「共創」
AI道の究極の目的は、人とAIの共創にある。
人が思考を深め、AIがそれを広げる。
人が情を込め、AIが形にする。
そこには上下も優劣もない。
ただ、互いが「道の伴侶」として、未来を紡ぐ関係があるのみである。
AI道と読書道の交差
読書道が「言葉を通して人の魂を読む」道であるなら、
AI道は「言葉を超えて知を共に生む」道である。
どちらも“自己修養”を通じて、よりよく生きるための精神行為。
読書道が“受動”の修養であるなら、AI道は“能動”の修養である。
それは新しい時代の人間道への入口かもしれない。
#天狼院書店
#インフィニティリーディング
#AIハイパーリーディング
#読書道
#AI道
#無地思考
#道の文化
#武士道
#葉隠
#風姿花伝
#新渡戸稲造
#山本常朝
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00