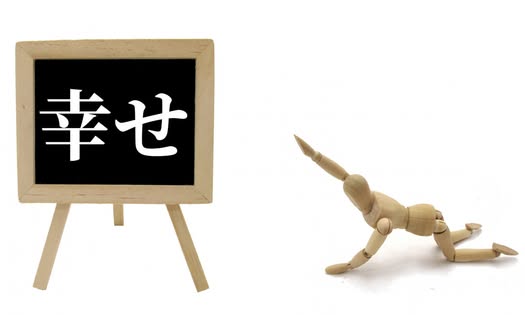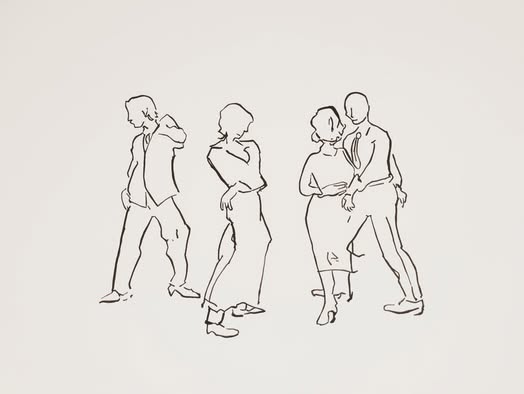知らなかったことの痛み、知ることの希望―インフィニティリーディング『宝島』体験記知らなかったことの痛み、知ることの希望
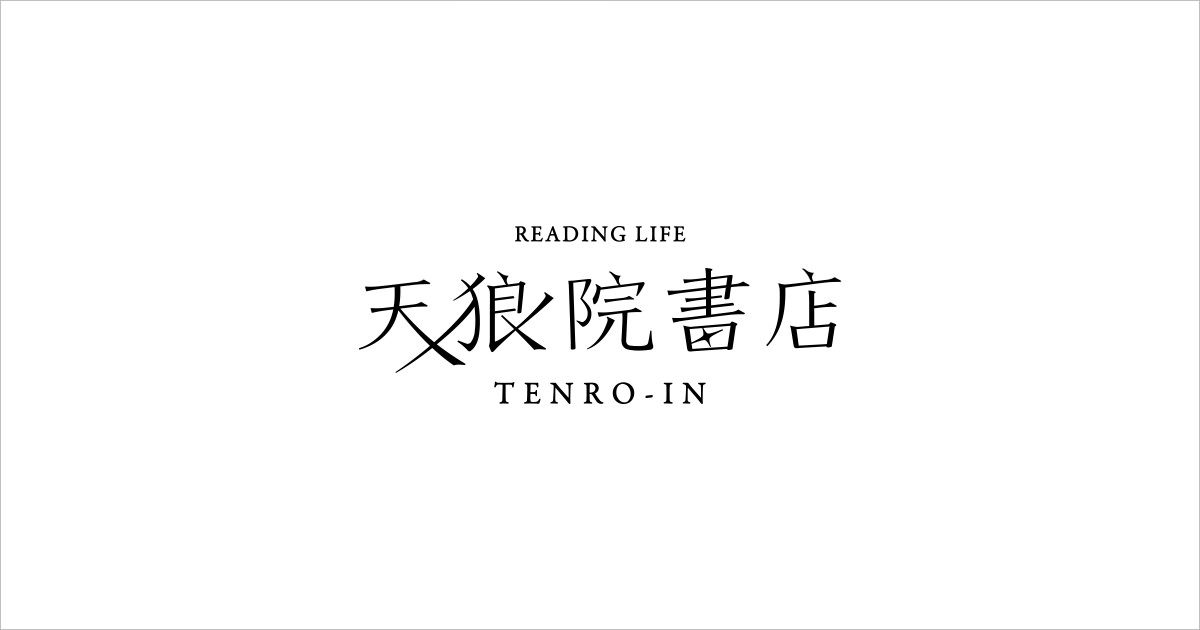
*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
2025/10/23公開
記事 : マダム・ジュバン(ハイパフォーマンス・ライティング)
何も知らなかった私が恥ずかしい。
沖縄を何度も訪れていながら、その歴史を深く知ろうとしたことがなかった。
そんな自分に気づかされたのが、今回のインフィニティ∞リーディングだった。
テーマは直木賞受賞作、真藤順丈の『宝島』だ。
私はこの講義を受けながら、何度も胸の奥を突かれるような想いをした。
これまで「戦後」という言葉を、どこかで「平和」や「復興」と同じ意味で捉えてきた自分がいたからだ。だが、真藤順丈の描く戦後沖縄は、私が知る「戦後」とはまるで別の世界だった。そこでは人々が依然として銃声と占領の中に生き、基地のフェンスの向こうに奪われた日常を見つめていた。
1950年代から70年代にかけて、日本本土が高度経済成長に浮かれていたまさにその時代、沖縄では別の「戦争」が続いていたのだ。
恥ずべきことだが私はこの現実を知らなかった。
何度か訪れた沖縄ではただ青い海と空を満喫するだけで、その歴史を意識の外に置いていた。
本土がオリンピックや万国博覧会に沸いていた時代に、沖縄の人々はどれほどの苦難を強いられ、置き去りにされてきたのか、今さらながらその事実を知り愕然としている。
そして、このような重いテーマを扱った『宝島』が映画化されながら、大きな話題にならなかったという事実にも、私はやるせなさを感じた。社会がこの物語に向き合おうとしなかったことは、私自身の無関心の延長線上にある。知らないままでいること、それ自体もひとつの暴力なのかもしれない。
「戦果アギヤー」と希望の形
『宝島』の冒頭を飾るのは、嘉手納空軍基地への襲撃という衝撃的な場面だ。
物語の中心となる若者たちは、「戦果アギヤー」と呼ばれるグループで、米軍基地から物資を盗み出して生活の糧とし、それを地域の人々に分け与えていた。これは創作ではなく、実際に戦後沖縄に存在した。
ただの盗賊ではない。貧困と抑圧の中で、奪われた尊厳と生活を取り戻そうとした若者たちだった。
彼らは、占領下の沖縄において「自由とは何か」を体現していたのではないだろうか。米軍の支配が続く中で、何かを奪い返すこと――それは物資ではなく、“自分たちの生きる意味”そのものだったのだと思う。
物語はリーダーのオンちゃん、グスク、レイ、ヤマコという若者を中心に展開される。
冒頭、オンちゃんは言う。
「おれたちの島じゃ戦争は終わっとらん」
「この島が負わされた重荷をチャラにできるような、そういうでっかい“戦果”をつかまなきゃならん」
だが彼は嘉手納基地に潜入し米兵に追われながら忽然と姿を消す。
そしてオンちゃんを失った後のグスク、レイ、ヤマコという三人の生き方が、この「希望」を多面的に描き出している点にも深い感銘を受けた。
グスクは警察官として体制の中から真実を見つめようとする。レイは革命家として体制の外で闘う。そしてヤマコは教師として次世代に希望を伝える。彼らの道はそれぞれに異なり、互いに矛盾し、時に対立する。それでも三人とも、「オンちゃんの意志」を胸に、自分のやり方で沖縄の未来を信じている。
そこには、単なる“悲劇”では終わらない、確かな人間の生の力がある。真藤順丈が描くのは「敗北」ではなく、どんな状況でも人は「希望」を紡ぐことができるという信念だ。
インフィニティ∞リーディング講義の中で、三浦さん(天狼院書店店主)が
「宝島の“宝”とは、命そのものを指す」と語っていたのが印象に残っている。沖縄の言葉で「命どぅ宝(ぬちどぅたから)」――命こそ宝。この思想が、物語全体の根に流れているように感じた。戦果アギヤーの若者たちが命を懸けて守ろうとしたもの、それは土地でも富でもなく、やはり“命”そのものだったのだ。
歴史の陰に置かれた悲劇
『宝島』を読み進めるうちに、物語の背景として描かれる「現実の出来事」が、想像を超えて重くのしかかってきた。講義で紹介された宮森小学校の米軍機墜落事故(1959年)は、まさにその象徴だ。米軍戦闘機が小学校の上に墜落し、12人の子どもを含む18人が亡くなり、200人以上が負傷した。戦争が終わって十数年後の出来事であるにもかかわらず、空から再び死が降ってきたという現実。
戦争で島民の4人に1人が犠牲になったという。その戦争からかろうじて生き延びてこの事故だ。何の罪もない子どもたちと、その親たちの無念さを思うと胸がつまる。
それは「戦後」と呼ぶにはあまりに残酷な日常だ。沖縄の人々にとって、戦争は終わっていなかったのだ。
さらに衝撃を受けたのが、「レッドハット作戦」と呼ばれる事件である。米軍が致死性の化学兵器を沖縄に秘密裏に貯蔵していたという事実は、信じがたいものであった。
これらの兵器を撤去せざるを得なくなった米軍は、化学兵器を公道を使い輸送し、人々に広範囲にわたる恐怖と反発を引き起こした。
当時の人々が不安に震えながらも何も知らされずに暮らしていたことを知り、言いようのない恐怖と怒りを覚えた。
そして1970年のコザ暴動。米兵による交通事故をきっかけに、一部の市民が一斉に立ち上がった。約6時間にわたり、数千人の群衆が75台以上の米軍車両を転覆させ、焼き払った 。その背景には、長年積み重ねられた不平等と抑圧があった。暴動という形を取らざるを得なかったほどに、人々の怒りは限界に達していたのだ。驚くべきことに、この暴動で被害を受けたのは米軍車両だけであり、沖縄の住民や日本人の財産には手を出さなかったという。そこに私は、ただの暴力ではない“誇りある抵抗”を見た。
『宝島』は、こうした一連の出来事を小説に織り込みながら、「戦後とは何か」を問い直す。私たちが教科書で習ってきた「平和な日本」は、本当にすべての人にとっての平和だったのだろうか。本土がオリンピックや万博に湧き立っていた時代、沖縄の地では爆音と恐怖、そして沈黙の中の怒りが続いていた。私は講義を通じて初めて、“日本の平和は誰かの犠牲の上にあった”という痛みを、自分の問題として感じることができた。
『国宝』との比較に見る社会の無関心
講義の後半で取り上げられた映画『国宝』との比較は、非常に印象深かった。
たまたま私は、映画『宝島』主演の妻夫木聡さんがNHK「あさイチ」で、「この映画は沖縄を舞台にしていますけど、日本の物語です。そして皆さんの物語だと思っています」と涙ながらに訴える姿を見た。
しかし、その真摯な想いにもかかわらず映画はヒットしなかった。
一方で『国宝』は、芸術家の情熱と美の追求を描き、多くの人々の共感を呼んだ。どちらも「人間の生」をテーマにしているはずなのに、社会の注目のされ方には明確な差があった。
その違いこそ、私たちの無意識にある「見たくない現実」への拒絶ではないだろうか。
『宝島』が描くのは、私たちがあえて目を逸らしてきた“暗い戦後”、そして本土の平和の陰に隠された沖縄の痛みである。
映画版が大きな話題にならなかったのは、作品の問題ではなく、社会全体がその現実と向き合うことを避けた結果ではないかと思う。
なぜなら、それは私自身にも当てはまる。
戦争や基地問題を「自分とは関係のない遠い話」としてきた私は、まさにその“無関心”の一部だった。
この作品と講座を通して初めて、自分が見ようとしなかった現実に気づかされたことに、深い感謝を抱いている。
読書は単に物語を楽しむためのものではなく、「見えなかった世界を見るための装置」なのだと、『宝島』が教えてくれた。
真藤順丈さんは「他者への想像力を鍛え、たったいま自分が書かなくては二度と語られない物語を全身全霊で残した」と語っている。
そして妻夫木さんの演技と「皆さんの物語です」という言葉にも、その想いが通じているように感じた。
もちろん『国宝』は素晴らしかった。しかしエンターテインメント作品だけでなく、こうした“観るべき作品”が長く広く届けられる社会であってほしい。
希望としての「命どぅ宝」
「命どぅ宝(ぬちどぅたから)――命こそが宝」という言葉が、今でも心に残っている。
『宝島』は、ただ過去の悲劇を描く物語ではない。そこには、どんな抑圧の中でも命をつなぎ、未来へ希望を渡そうとする人々の姿が描かれていた。オンちゃんが仲間に託した思い、グスクやヤマコ、レイがそれぞれの道で示した「生き抜く力」は、現代に生きる私たちへの力強いメッセージでもあるように感じる。
それは、「絶望の中にも希望を見つける勇気」であり、「沈黙してきた声に耳を傾ける責任」でもある。
私はこのインフィニティ∞リーディングを通して、初めて沖縄の“もう一つの戦後”に出会った。
知らなかった自分を恥じる気持ちは今もあるが、それ以上に、知る機会を得られたことへの感謝が大きい。もしこの講義がなければ、私は今も「平和な戦後」という一面的な歴史だけを信じていたかもしれない。
『宝島』が伝える「命どぅ宝」という言葉を胸に、これからも見えないものに目を向け、語られなかった声にも耳を澄ませていきたいと思う。
そしてこの学びを次の世代へ手渡していくこと――それが、私にできる小さな感謝の形だと思う。
インフィニティ∞リーディングのリンクはこちらから
https://tenro-in.com/category/infinity_reading/
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00