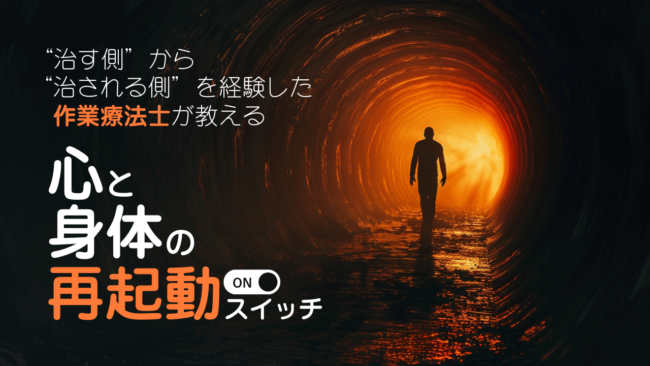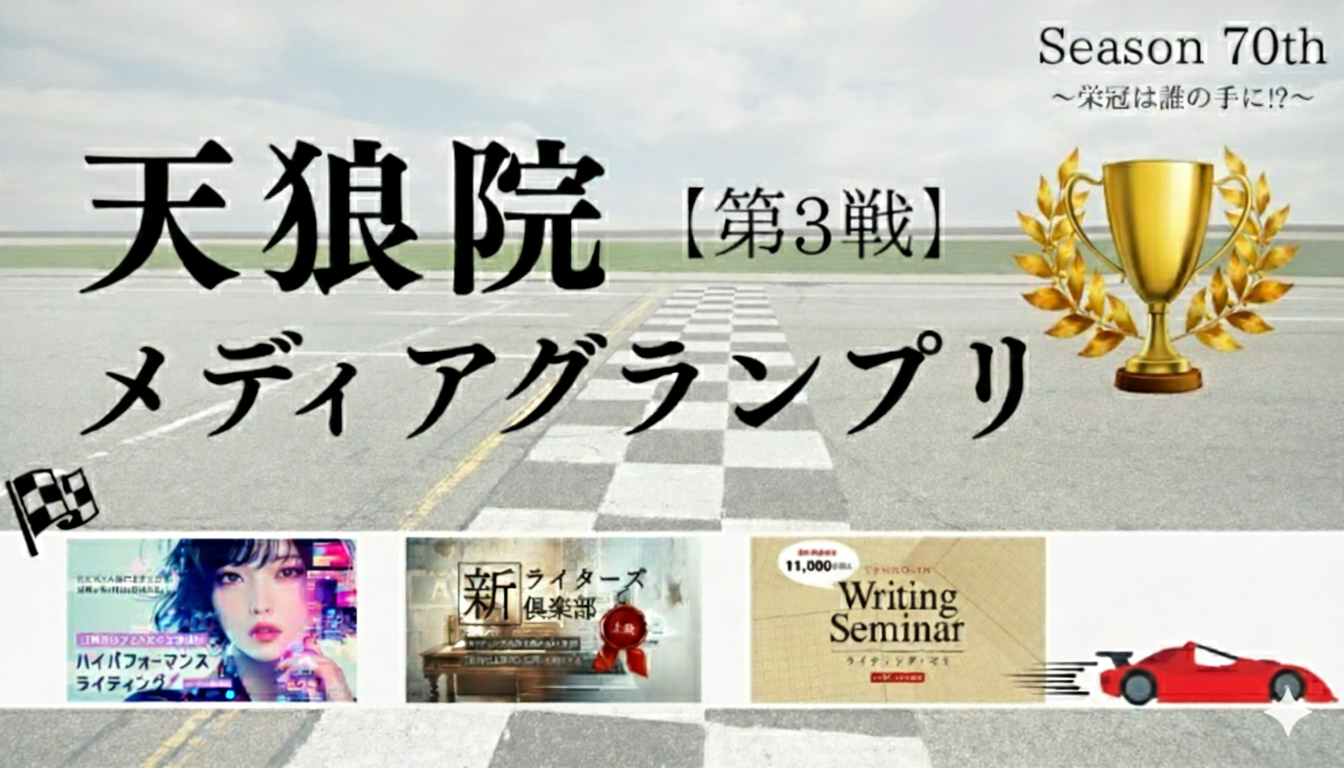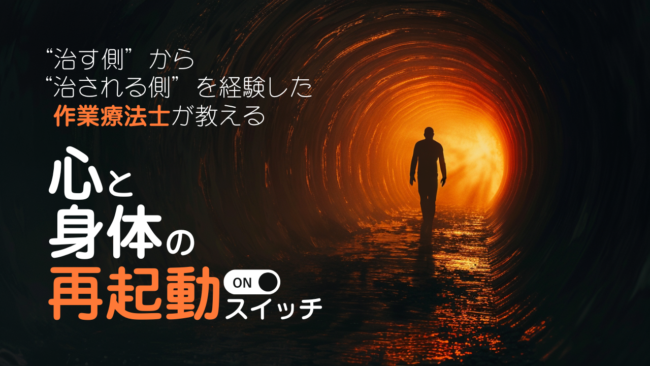葉隠が語りかけてくるもの──佐賀藩の歴史から見えてくる静かな力
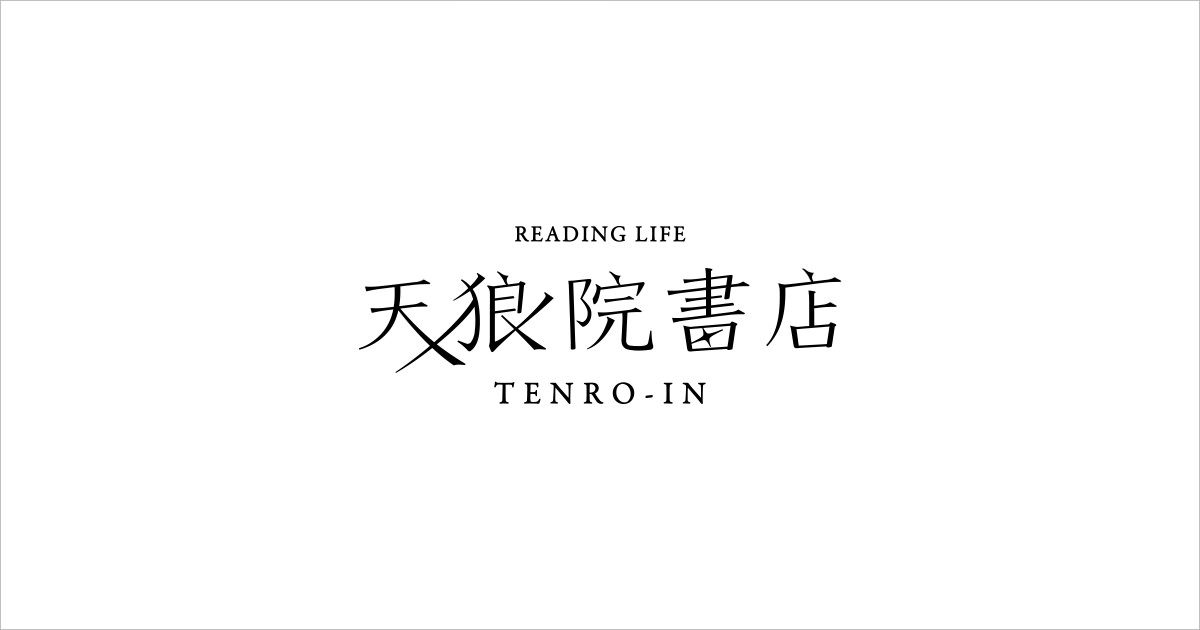
*この記事は、「ハイパフォーマンス・ライティング」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
記事:山岡達也(ハイパフォーマンス・ライティング)
『葉隠』という古典を、手に取ってみたことはあるでしょうか。
「武士道の本」「死ぬことと見つけたり」というフレーズで知られるこの書物は、実は三百年前の佐賀で、一人の元武士が語った「迷いとの向き合い方」を記録したものでした。この古い言葉は、現代の私たちの心にも響いてくるのですが、普通に読むのは難しいです。
そこで、『葉隠』を読み解くのに、一本の補助線を引いてみました。
佐賀藩の歴史を縦糸に、『葉隠』という思想を横糸にしながら、生まれた背景、忘れられた時間、再び光を浴びた瞬間、そして今日の私たちへの問いかけを、ゆるやかにたどってみたいと思います。
■ 葉隠とは何か──「迷わない心の整え方」
『葉隠』は、江戸時代の佐賀藩で、元武士・山本常朝が語った言葉をまとめた書物です。常朝は若い頃から藩主・鍋島光茂に仕え、主君の死後、武士としての生き方を語り継ぐことに残りの人生を捧げました。
難しく考える必要はありません。この本が伝えようとしていることは、ひと言でいえば──
「迷わずに、自分の役目に向き合う心の整え方」
有名な「死ぬことと見つけたり」という一句も、実は”死ね”という話ではなく、「最終的にどうあっても覚悟する気持ちを持つことで、迷いが減る」という意思決定の比喩です。現代風に言えば、「最悪の事態も想定した上で、いま自分がすべきことに集中する」という、ある種の腹の据え方を示しています。
当時の佐賀藩の武士たちは、日々の仕事の中で迷い、揺れ、時に怠け、時に踏ん張る。その等身大の姿が、葉隠の背景にあります。常朝が語った言葉は、完璧な人間の理想論ではなく、弱さや迷いを抱えた人間が、それでも前に進むための「心の支え」だったのです。
■ 生まれたときから「危機の書」だった
葉隠が生まれた十八世紀初頭、佐賀藩はまだ安定しているように見えました。しかし常朝の目には、武士たちの心が少しずつゆるみ始めているように映っていました。
平和が続き、武士が戦場に立つことはほとんどなくなり、仕事は行政へと変わります。日々の細かな事務、年貢の管理、奉行所の業務……。そうした日常の中で、戦うために鍛え上げられてきた心は、どこか曖昧になっていきます。
「このままでは、武士が武士でなくなってしまう」──常朝はそんな危機感を抱いていました。しかし、彼が語った言葉は、単なる昔への郷愁ではありません。変化する時代の中で、それでも「自分の役割に誠実に向き合う」という姿勢の大切さを説いたものでした。
常朝は『葉隠』を生み出しましたが、内容があまりに厳格だったため、藩校で正面から扱われることはありませんでした。読む人は読んでいるけれど、多くの人には広まらない──そんな不思議な立ち位置のまま、長い時間を過ごすことになります。
■ 形だけ残り、心からは遠ざかった日々
十八世紀後半から十九世紀前半、佐賀藩は”冬の時代”でした。藩政の弛緩、財政難、贅沢、怠慢──葉隠が警告する行為が、むしろ日常の風景になっていきます。
葉隠は「昔の立派な武士の教え」と尊ばれます。実際、150年余りにわたって、藩のなかで途切れることなく読み継がれてきました。しかし、その内容の厳しさ、禁欲さ、自己鍛錬の精神は、現実の藩政にとって”扱いづらいもの”になり、心からの理解は遠のいていきました。
こうして葉隠は、「あるけれど、活かされない」長い年月を過ごします。まるで、本棚の奥にしまわれた古い手紙のように。
さらに問題なのは、トップがだめになることです。
葉隠の根幹は、武士は主君のために誠心誠意尽くすことです。たとえダメな主君であっても、誠心誠意尽くすのが武士の勤めです。しかし、主君のダメさ加減が限度を超えてしまうと、葉隠の精神の根幹が崩れてしまいます。
政治の手腕がない、不正を働く、えこひいきする、側近任せの政治、こんな主君では部下もついて行けません。
こうした状況は、佐賀藩だけでなく、全国の多くの藩が同じような状況にありました。平和の中で、かつての精神は徐々に形骸化していく。それは避けがたい時代の流れでもあったのです。
■ 再び光が当たる──鍋島直正という実践者
転機は幕末に訪れます。十代藩主・鍋島直正の登場です。
直正は、幼い頃から藩の腐敗や財政の破綻を目の当たりにし、自分自身を厳しく律する生活を送っていました。藩主となったとき、佐賀藩は崩壊寸前。借金は膨れ上がり、藩士の士気は低下し、どこかで大きく舵を切らなければ、沈むしかない状況でした。
そこで直正は、葉隠の「迷わぬ決断」「私心を捨てる」「倹約」「日々の鍛錬」「奉公の心」といった核の部分を、近代的な行政改革に翻訳して使ったのです。
注目すべきは、直正が葉隠を”そのまま”使ったわけではないという点です。彼は葉隠の精神を、時代に合わせて読み替え、実務的な改革に落とし込みました。これは単なる復古主義ではなく、古い知恵を新しい時代に活かす、創造的な応用だったのです。
直正の改革は精神論ではなく、制度と組織そのものを作り替える実務改革でした。
江戸屋敷の浪費を徹底的に見直し、接待費・贈答費を大幅削減。名ばかり役職や仕事のない家臣を整理し、適材適所の配置へ。役所の仕組みそのものを再編し、決裁のスピードを大幅に上げる。これらは”痛み”を伴う改革でしたが、直正は自らも質素な生活を貫き、まずは自分自身から変わることで藩士の不満を抑え込みました。
同時に、直正は化学・物理・数学・砲術・冶金・医学といった近代科学の導入に積極的でした。弘道館を拡充し、専門教育を進めたことで、佐賀藩は「科学の藩」に変わっていきます。のちに明治の官僚となる逸才たちを数多く輩出する背景には、直正の教育改革がありました。
■ アームストロング砲という「奇跡」
さらに驚くべきは、アームストロング砲の国産化です。
アームストロング砲は、イギリスで開発された当時最先端の大砲で、高度な製造技術が必要とされました。金属の精度、材料の純度、火薬の安定性、鋳造技術、測量と計算──すべてが高い水準で揃っていなければならない。他の藩は輸入するしかなかったこの大砲を、佐賀は「自分たちの手でつくる」と決めます。
普通の藩であれば、挑戦しようとすら思わない難題でした。しかし、佐賀藩には挑戦しないといけない理由がありました。
海外からの脅威に対抗するには、自分たちで強力な武器をつくらないといけない。
失敗したら、藩どころか国全体が危なくなる。
この危機感をてこに、地道に技術改良を積み重ねて、国産のアームストロング砲の完成につながったのです。
こうして完成した佐賀藩のアームストロング砲は、見事に目標を撃ち抜きました。その威力と精度は他藩の武士を震え上がらせ、「佐賀藩兵40人は、他藩の1000人に匹敵する」とまで言わしめました。
これは単なる武器の開発ではなく、日本の近代技術史を切り開く象徴的な瞬間であり、戦争のあり方を変えるゲームチェンジャーの誕生でもありました。
葉隠は「昔話」ではなく、藩改革のなかで再び息を吹き返したのです。そして、その精神は具体的な成果として、目に見える形で結実しました。
■ いま、私たちに葉隠が問うこと
三百年前の武士に向けられた言葉が、現代の私たちに何を問うのでしょうか。
私たちは刀も差さないし、主君もいません。もちろん、戦争もありません。では、葉隠は私たちに何を語りかけてくれるのでしょう。
今回は強い言葉ではなく、葉隠が私たちにそっと語りかけてくるものという視点でまとめました。
「迷うときほど、自分の軸を見つけること」
仕事、人間関係、人生の選択──私たちは日々、小さな迷いと大きな迷いの中で生きています。そんなとき、「自分は何を大切にしているのか」「どう在りたいのか」を問いなおすことが、前に進む力になります。葉隠は、その問いを静かに投げかけてくれます。
「自分をすこし律することの大切さ」
大げさな修行ではなく、日々の生活の中で少しだけ”芯”を持つ。朝、少し早く起きる。約束を守る。人の話を最後まで聞く。そんな小さなことでも、それを続けることで、不思議と自分の軸が定まってきます。葉隠が語る「鍛錬」とは、そういう日常の積み重ねのことかもしれません。
「役割に向き合うことで、自分が整うこと」
武士には武士の役割があったように、私たちにも各々の役割があります。家庭、職場、地域、友人関係……。その一つひとつに丁寧に向き合うことで、不思議と心が落ち着くことがあります。役割を果たすことは、義務ではなく、自分を支える柱になるのです。
「過去に学びつつ、未来をつくる視点」
葉隠は過去の精神論ですが、鍋島直正が示したように、”未来をつくるための材料”としても使えます。古い知恵を、そのまま真似るのではなく、今の時代に合わせて読み替える。そうすることで、過去の知恵は現代に生きる力になります。
■ 「インフィニティ∞リーディング」が開いた扉
このテキストを書いたきっかけは、天狼院書店の「インフィニティ∞リーディング」という読書会で『葉隠』が取りあげられたことでした。
この読書会の特徴は、店主である三浦崇典氏が、豊富な経験と知識に加え、言語生成AIを駆使しながら課題本を読み解いていくこと。千年単位の歴史をもつ読書と、最近登場したAIとが織りなすコラボレーションは、私たちに新たな気づきを提供してくれます。
読書会の中で、AIは膨大な知識を瞬時に引き出し、歴史的背景や関連する文献を示してくれます。それを三浦氏が的確に解釈し、参加者に投げかける。そのやりとりの中で、一冊の本が立体的に浮かび上がってくるのです。
実際、この読書会に参加して、私はずいぶんと変わりました。
今回の記事を書くにあたり、四国の片隅から佐賀へ出かけました。史跡として残されている葉隠発祥の地や、佐賀城本丸資料館を訪ね、山本常朝や佐賀藩士について理解を深めることができました。資料館で見た直正の改革の記録、アームストロング砲の実物──それらは、読書会で学んだ知識に、確かな手触りを与えてくれました。
これをきっかけとして、葉隠と佐賀藩の歴史を結びつけるという、読書会でも出てこなかった発想を得ることができたのです。こんなことは、1年前の自分では考えられないことでした。本を読むだけでなく、その舞台を訪ね、自分の足で歩き、自分の目で確かめる。読書会がきっかけとなって、そんな行動が自然と生まれてきたのです。
毎週水曜日に開催される「インフィニティ∞リーディング」を中核に据えて、事前に課題本を読んでみたり、事後に自分なりに行動してみる。読書会を通じて、本の中の世界と現実とを何度でも行き来できるようになる。それが出来るようになれば、読書の世界がきっと拡がります。
人生を変えるようなきっかけの扉を、あなたもそっと開いてみませんか。
【インフィニティ∞リーディングのお申し込み・詳細はこちらから】
https://tenro-in.com/category/infinity_reading/
ご参加を心よりお待ちしております。
《おわり》
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00