降りられない高座に上がり続けて《週刊READING LIFE Vol.294 もう止められない》
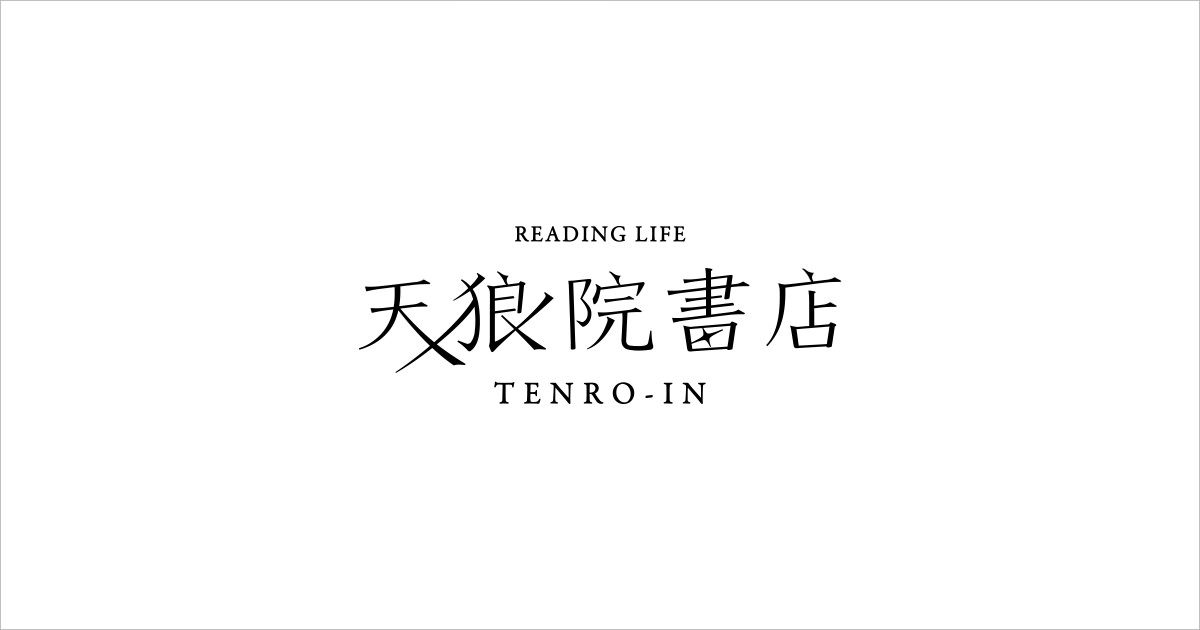
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「新・ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/2/3/公開
記事:大塚久(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
2023年の夏。地元のショッピングモールで買い物中、ふと目に留まった一枚のチラシ。「新しい趣味を見つけてみませんか」という文字が、どこか心に響いた。その日は理由もなく足を止め、そのままカルチャーセンターのカウンターに向かった。
カルチャーセンターの小さな教室には、机を並べて座布団を敷き、簡易の講座が出来上がっていた。師匠の話を聞き、簡単そうに見えた所作を真似してみるが、言葉の抑揚や間の取り方ひとつで全く異なる印象になることに驚かされた。思ったより難しい。しかし、それ以上に、舞台に立つ稽古の時間は、仕事とは異なる解放感を与えてくれた。
半年後、発表会の日がやってきた。出囃子が流れると、足元の板が急に重く感じられた。高座に上がると、ライトの熱が肌を刺すようで、声が遠ざかる。台詞は霧の中に隠れ、言葉を掴む手が空を切るようだった。それでも、視界の中に動く観客の影がかすかな音を返してくれた。自分が何をしたのかも覚えていない。それでも、拍手の音が背中に降り注ぐと、さっきまでの重さが霧のように消えていった。それは稽古では得られなかった、不思議な温もりだった。「いや〜、本物の落語家さんみたいな雰囲気でしたよ」と師匠の言葉に背を押され、また舞台に立ちたいと思った。
しかし、順調だった道が途切れる日が訪れる。次の発表会。今回の発表会はいつものカルチャーセンターではなく、プロの落語家も使うようなホールで、実際に入場料も取って行うものだった。何度も練習を重ね、自信を持って臨んだ「厩火事」という演目だった。最後のオチを言い違えた瞬間、会場の空気が音を失った。笑いの余韻が引いていくのを追うように、視線が床へと落ちる。ライトの光は冷たく、肩にのしかかるようだった。「なぜだ?」その問いが足元の座布団にしみ込んでいく。拍手も聞こえず、袖に戻ると手元の扇子がやけに軽く感じられた。
悔しさが薄れることはなかった。それでも、「もう一度、高座に上がりたい」という思いは消えなかった。稽古場の畳に座ると、以前よりも深い集中力が自分を包み込むのを感じた。次は、もっと良い高座にした。その思いが、再び僕を落語に引き寄せた。
初めての落語会
落語を始めて1年余りが過ぎた2024年、僕は初めて落語会を主催することを決意した。きっかけは、2024年5月の発表会での大失敗だった。観客を笑わせるはずのオチで噛んでしまい、会場の空気が凍りつくあの瞬間が忘れられなかった。「次こそ成功させたい」そんな思いが、僕を突き動かした。
2024年12月23日、小規模ながらもいつも通っているブックカフェのスペースを借り、初の落語会を開くことに決めた。当初は軽い気持ちで始めた計画だったが、準備を進めるほど、その重さに気づかされる。会場の手配、出演者との連絡、チラシの作成、観客の集客。さらに、当日の進行や音響、など、やるべきことが次々と浮かび上がってきた。
最初にぶつかった壁は集客だった。自分の知り合いだけでは観客が足りないことは明らかで、地元の商店街や公民館にチラシを置きに行ったり、SNSで情報を発信したりとあらゆる方法を試した。数日間は反応がなく、不安で眠れない夜もあった。しかし、少しずつ「行ってみたい」と言ってくれる人が現れ、ようやく光が見え始めた。
予期せぬトラブルが起きた。音響機器が突然動かなくなり、出囃子が上手くならない。スタッフの方が起点を聞かせてくれてことなきを得たが、出囃子がないと落語会の雰囲気が半減してしまう。
そして迎えた当日。開演前、席が埋まっていく会場には、親しい顔もあれば、どこか遠慮がちな初めての来場者もいた。ざわめきが徐々に薄れ、静寂が押し寄せると、舞台袖で手の震えが止まらなくなった。足元の床板が冷たく感じられる。視線は自然と下に落ち、袖の中で手を握り直す。笑いが起こる景色を想像する余裕は、今はまだない。その瞬間、袖に響いた出囃子の音が、震える背を押した。
いよいよ自分の番が来た。高座に上がると、最初は緊張で声が震えた。しかし、客席の一角から漏れた笑い声が、波紋のように広がっていく。その音が、自分の背をそっと押してくれるのを感じた。特に、小学生たちが楽しそうに笑顔を見せる姿に、心の中の不安がすっと消えていくのを感じた。自分の演目を無事に終えると、会場には拍手が湧き起こり、その音が深く心に染み渡った。
終演後、多くの人が感想を伝えに来てくれた。「また友達を連れてきたいです」「落語なんて初めて観ましたが、とても楽しかったです」という言葉に胸が熱くなった。特に、「昔の日本の暮らしが垣間見えて面白かった」と話してくれた方の笑顔は忘れられない。この日、僕は落語を通じて人と心がつながる喜びを初めて実感した。
初めての落語会は、運営の苦労や緊張の連続だったが、それ以上に得られるものが大きかった。この経験があったからこそ、僕は次の舞台に向けて一歩踏み出せたのだ。
広がる影響
初めての落語会を終えると、想像以上の反響があった。終演後、観客から寄せられる感想の中で特に印象的だったのは、「落語ってもっと敷居が高いものだと思っていたけど、意外と親しみやすいんですね」という言葉だった。初心者の僕が主催した会でも楽しんでもらえたという事実は、達成感を超える感動を与えてくれた。そして何より、「次もまたやってほしい」という声が、僕を次の高座へと導いた。
その後すぐ、2025年1月にコミュニティカフェでの出演依頼が舞い込んだ。地域の人たちが集うアットホームなカフェで落語を披露してほしいという話だった。大きなホールではなく、観客との距離が近い空間は初めてだったが、少人数だからこそ反応がダイレクトに伝わり、新しいやりがいを感じる場になるだろう。
さらに3月には、地元の地域集まりでの出演が決まった。この集まりは地域活性化を目的としたイベントの一環で、今回、落語がプログラムに加えられた。主催者から「落語を通じて地域の皆さんを元気づけてほしい」と頼まれたとき、その言葉に大きな責任を感じた。
広がる影響は、僕自身の心境にも変化をもたらした。最初は「ちゃんとできるだろうか」「失敗したらどうしよう」という不安ばかりだった。しかし、経験を重ねる中で「次はどうやってお客様に楽しんでもらおうか」という前向きな思考が芽生えるようになった。高座に上がるたびに感じる充実感と観客の反応は、苦労を忘れさせるほどのエネルギーを与えてくれる。
このように、初めての落語会をきっかけに活動の幅が少しずつ広がっている。落語を通じて笑顔を届けるという役割にやりがいを感じながら、次の舞台に向けて一歩ずつ進んでいく自分がいる。それは、降りられない高座が「降りたくない高座」に変わりつつある瞬間だった。
降りられない高座
2024年12月23日の初めての落語会は、僕にとって大きな転機となった。それまで、落語はあくまで趣味であり、自己満足で完結していた。しかし、この会をきっかけに「高座に上がる」という行為の持つ力を知り、自分自身が変わり始めていることを実感した。
最初は、高座に上がるたびに強いプレッシャーを感じていた。「ちゃんと演じられるだろうか」「お客様は楽しんでくれるだろうか」。そんな不安が頭を離れず、緊張で手が震えることもしばしばだった。そこで僕は、高座の隅でジャンプをしたり、深呼吸を繰り返したりと、自分なりのルーティンを取り入れていった。それは、少しずつ身体と心を整える作業でもあった。
プレッシャーの正体を探る中で見つけたのは、「完璧に演じなければならない」という思い込みだった。しかし、何度も高座を経験するうちに気づいたのは、お客様は「完璧さ」だけを求めているわけではないということ。むしろ、話し手の感情や誠実さ、演技を通して伝わる温かみこそが、彼らにとっての「楽しさ」の核であることを理解した。その瞬間から、高座に上がる心構えが変わった。「お客様と一緒に楽しむ」という姿勢が、自分の緊張を自然に和らげていった。
初めての落語会の成功を経て、僕の中に新たな目標が生まれた。それは、「より多くの人に落語を楽しんでもらう」ということだ。これまでの高座は地元の小規模な会が中心だったが、次はもっと広い範囲で活動したいと考えている。特に若い世代や落語に馴染みのない人たちにも、その魅力を伝えたいという思いが強まっている。
また、自分自身のスキルを磨くことも欠かせない。落語はシンプルに見えて奥が深い。言葉選びや間の取り方、声の抑揚ひとつで観客の反応が変わる。その技術を磨くために、日々の稽古に加え、プロの落語家の高座を見に行ったり、仲間と意見を交わしたりする時間を大切にしている。
次回の舞台は2025年1月30日に予定されているコミュニティカフェでの落語会だ。アットホームな雰囲気の中、どのような演目が観客に響くのかを考えながら準備を進めている。そして、その次の3月20日には地域の集まりでの出演が控えている。それぞれの観客に合わせた内容を練り上げ、新たな挑戦の場としたい。
振り返れば、「降りられない高座」という感覚は、最初は責任感や周囲の期待から来るものだった。だが今では、高座に上がること自体が楽しみであり、自分にとっての喜びへと変わった。そしてその高座は、自己成長の場であり、新たな出会いを生む場所でもあると感じている。
「降りられない」と思っていた高座が、気づけば「降りたくない」と感じる場所になっていた。高座の上で目の前のお客様と呼吸を合わせる時間が、自分を満たしていくのを感じる。高座に上がり、座布団が足元から静かに支える。観客の呼吸が自分の呼吸と溶け合い、言葉が自然と流れ出す。挑戦の場ではなく、心を通わせる場所。それが、今の高座だった。
□ライターズプロフィール
大塚久(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
神奈川県藤沢市出身。理学療法士。2002年に理学療法士免許を取得後、一般病院に3年、整形外科クリニックに7年勤務する。その傍ら、介護保険施設、デイサービス、訪問看護ステーションなどのリハビリに従事。下は3歳から上は107歳まで、のべ40,000人のリハビリを担当する。その後2015年に起業し、整体、パーソナルトレーニング、ワークショップ、ウォーキングレッスンを提供。1日平均10,000歩以上歩くことを継続し、リハビリで得た知識と、実際に自分が歩いて得た実践を融合して、「100歳まで歩けるカラダ習慣」をコンセプトに「歩くことで人生が変わるクリエイティブウォーキング」を提供している。
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00






