激しいトレーニング vs 穏やかなトレーニング 〜理学療法士が教える自分に最適な健康法の見つけ方〜《週刊READING LIFE Vol.296 あなたはどっち派?》
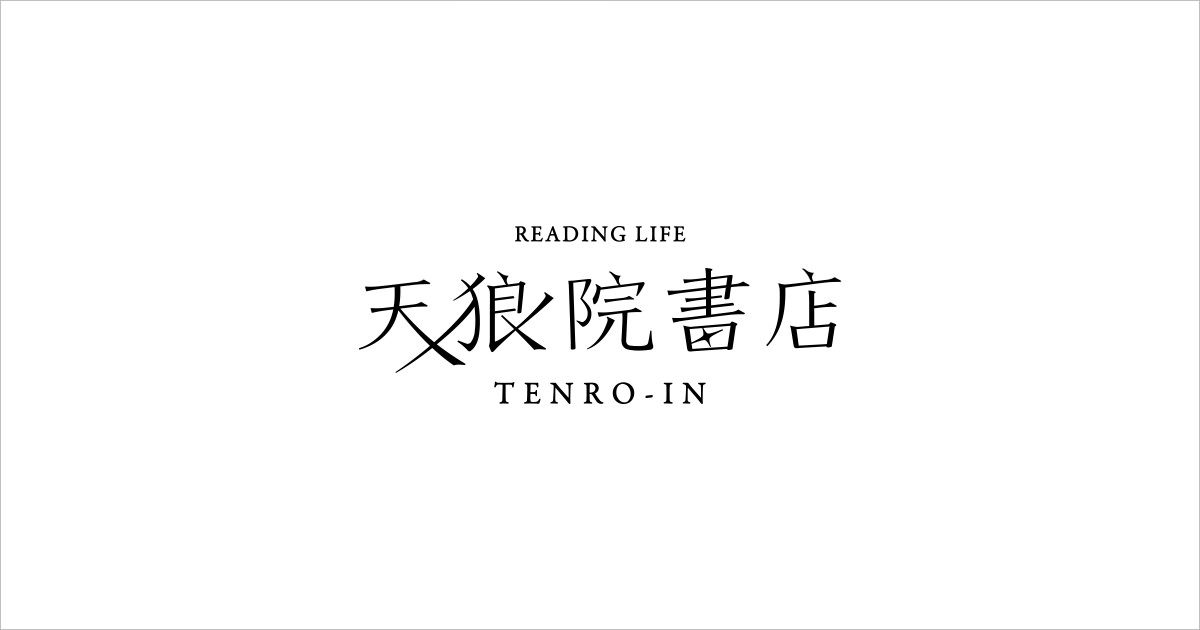
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/2/20/公開
記事:大塚久(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
僕は25年間、理学療法士として多くの患者さんの健康維持や機能回復をサポートしてきた。ここ5年は特にウォーキングの指導に力を入れ、自分自身も毎日1万歩を目標に歩く生活を続けている。すると体重が落ちただけでなく、仕事のパフォーマンスも上がり、店舗の売上まで向上するという思わぬ効果を実感した。さらに昨年、RYT200のヨガインストラクター資格を取得し、ヨガの視点からも健康や心身のバランスについて伝えられるようになった。
現代の健康法は、「激しい運動派」か「穏やかな運動派」かという二択ではなく、「自分に合った運動」を見つけることが重要だ。ライフステージや体調、目標に応じてウォーキングやヨガといった低負荷の運動と、筋トレやHIIT(高強度インターバルトレーニング)のような高負荷の運動をバランスよく組み合わせる。いわば、パーソナライズド・フィットネスだ。僕自身の実体験と最新の研究をもとに、低負荷運動と高負荷運動の相乗効果、そしてその最適なバランスについて詳しく話していきたい。
低負荷運動:ウォーキングとヨガ
1万歩ウォーキングの効果
毎日1万歩を歩くことを習慣にしてから、体重が減ったのはもちろん、血流が改善され、運動の効率も上がった。ウォーキングは有酸素運動として心血管系の健康に寄与し、長く続けやすい点が最大のメリットだ。また、歩くことで自律神経が整い、睡眠の質も向上するという研究結果もある。
ウォーキングの際には、ただ歩くだけでなく、歩き方にも注意を払うことが重要だ。姿勢を正し、足の裏全体を使って踏み出すことで、より効率的にエネルギーを消費し、関節への負担を減らすことができる。また、適度なスピードで歩くことも大切で、早歩きを取り入れることで脂肪燃焼効果が高まるとされている。
ヨガの柔軟性とリラクゼーション効果
ヨガを取り入れることで、身体の柔軟性が向上し、深い呼吸や瞑想的な動きによって精神的なリラクゼーションも得られた。ヨガは自律神経を整え、ストレスを軽減する効果があるとされている。また、特定のポーズは内臓の働きを活性化し、消化機能の改善にもつながる。
ヨガにはさまざまな流派があり、それぞれに特徴がある。例えば、ハタヨガは基本的なポーズと呼吸法を中心に行い、初心者にも取り入れやすい。一方、アシュタンガヨガやヴィンヤサヨガは動きが多く、筋力向上にも役立つ。自分に合ったヨガのスタイルを見つけることで、無理なく続けることができる。ちなみに僕が個人的に一番おすすめするのは基本のハタヨガだ。
実生活へのポジティブな影響
ウォーキングやヨガを取り入れたお客様の健康意識が高まり、その結果として仕事にもいい影響がでている。身体の調子が良くなると、活力や集中力が上がり、仕事の成果にもつながるのだ。特に朝のウォーキングは一日の生産性を高め、気分をリフレッシュするのに効果的だ。
また、運動を習慣化することで、生活の質も向上する。例えば、通勤時に一駅分歩く、エレベーターではなく階段を使うといった小さな工夫が積み重なることで、運動量が自然と増え、健康維持につながる。
科学的根拠
ウォーキングは軽度の有酸素運動として、American Heart Association(AHA)をはじめとする主要な健康機関から推奨されている。適度なウォーキングは、心拍数を上げることで血液循環を促進し、心臓病や高血圧のリスクを低減することが科学的に確認されている。また、定期的なウォーキングは動脈の弾力性を向上させ、コレステロール値の管理にも役立つとされる。
さらに、最近の研究では、1日30分以上のウォーキングが心血管疾患の予防に大きな効果をもたらし、糖尿病や脳卒中のリスクも低減することが示されている。ウォーキングのペースを少し速めることで、酸素消費量が増え、より効果的なカロリー消費が期待できる。
また、ヨガは単なる柔軟性向上のための運動ではなく、ストレスホルモンであるコルチゾールの低下を促すことで、自律神経のバランスを整える働きがあることが、PubMedに掲載された複数の研究で報告されている。これにより、心身のリラクゼーションが促進され、精神的な健康維持にも寄与する。
特に、深い呼吸を伴うヨガのポーズは、副交感神経を優位にし、ストレスや不安の軽減に効果を発揮する。さらに、定期的なヨガの実践は、睡眠の質を向上させ、血圧を安定させることが明らかになっている。特定のポーズや瞑想を取り入れることで、不眠症の改善やうつ症状の軽減も期待できる。
このように、ウォーキングとヨガはそれぞれ異なるメカニズムで健康に良い影響を与えるが、両者を組み合わせることで、より高い相乗効果を得ることができる。
高負荷運動:筋トレとHIITの重要性
中等度以上の運動の必要性
最新の研究では、軽度の運動だけではなく、中等度以上の運動も取り入れることで代謝の向上や筋力増加が促されることが分かっている。特に筋トレやHIITは、短期間で効果が出やすい。高負荷運動は骨密度を上げ、加齢に伴う骨折リスクを低減する役割もある。
筋トレを行う際には、正しいフォームを意識することが重要だ。例えば、スクワットでは膝をつま先より前に出さないようにし、背筋を伸ばして行うことで腰への負担を軽減できる。また、筋トレ後には適度なストレッチを行い、筋肉の回復を促すことも大切だ。
高負荷運動の科学的根拠
高負荷運動を行うと、体内のグルコース利用が促進され、インスリン感受性が改善される。さらに筋トレは、脳内の神経成長因子(BDNF)の分泌を促し、認知機能や記憶力の向上にも寄与する。また、筋力をつけることで姿勢の改善や腰痛の予防にもつながる。
高負荷運動にはHIIT(高強度インターバルトレーニング)も効果的だ。短時間で心拍数を上げることで、短時間でも大きな運動効果を得ることができる。特に忙しい人にとっては、短時間で効率的に運動ができる点がメリットとなる。
両者のバランスの重要性
現代の健康維持においては、単に「激しい運動派」か「穏やかな運動派」かという二者択一ではなく、自分自身の体調やライフスタイル、目標に合わせた「パーソナライズド・フィットネス」が求められている。低負荷運動と高負荷運動、それぞれが持つメリットを上手に組み合わせることで、体全体の健康はもちろん、脳機能の向上や実生活でのパフォーマンスアップ、さらには経済的な成果にも繋がっていく。
低負荷運動の役割
ウォーキングやヨガは、基礎体力を底上げし、柔軟性を高めるだけでなく、日々のストレスを軽減する効果もある。どちらも激しい動きがない分、継続しやすく、無理なく習慣にしやすいのが特徴だ。体に過度な負担をかけずに続けられるため、長期的に見ても健康維持の土台を作るには最適な方法だ。
高負荷運動の役割
一方で、高強度トレーニング(HIITや筋トレ)は、短時間で効率よく代謝を上げ、筋力をつけるのに役立つ。筋肉が増えれば基礎代謝が上がり、結果的に脂肪が燃えやすくなる。さらに、強い刺激を体に与えることで、骨密度を高め、加齢による衰えを防ぐ役割も果たす。低負荷運動だけでは補えない、ダイナミックな身体機能の向上を支えてくれるのが高負荷運動の強みだ。
低負荷運動の脳への影響
ウォーキングやヨガは、脳にも穏やかな刺激を与え、精神的な安定をもたらす。リラックスすることでストレスホルモンのコルチゾールが減少し、脳内の血流が改善される。これにより、集中力が増し、気持ちの浮き沈みが少なくなる。さらに、ヨガの深い呼吸は副交感神経を刺激し、不安を和らげる効果もある。
高負荷運動の脳への影響
それに対して、高負荷運動は脳の成長を直接促す。運動によって分泌される神経成長因子(BDNF)は、記憶力や学習能力を向上させる働きがある。つまり、高負荷運動を取り入れることで、単に身体が鍛えられるだけでなく、思考のクリアさや認知機能の向上も期待できる。
低負荷と高負荷の運動をバランスよく組み合わせることが、身体と脳の両方にとって最適なアプローチとなる。どちらかに偏るのではなく、目的に応じて上手に取り入れていくことが、長く健康を維持する秘訣だ。
また、運動時間帯も重要であり、朝の軽い運動は代謝を活性化し、夜のヨガはリラックス効果を高めるとされている。
高強度運動とBDNFの増加
最近の研究によると、短時間の高強度運動(例えばHIITや筋トレ)は、脳内でBDNF(Brain-Derived Neurotrophic Factor)と呼ばれる神経成長因子の分泌を促すことが明らかになっている。BDNFは神経細胞の成長をサポートし、シナプスの可塑性(神経回路の柔軟な適応)を高めることで、認知機能や記憶力の向上に寄与する。
たとえば、Rojas Vega et al.(2006)の研究では、高強度運動を行った被験者の血中BDNFレベルが有意に増加し、これが脳の神経機能改善と関連していることが報告されている。つまり、高負荷運動は、筋力向上だけでなく、脳のパフォーマンスを高めるためにも有効であると言える。
低負荷運動と脳内血流・ストレスホルモンの調整
一方で、ウォーキングやヨガなどの軽度の有酸素運動も、脳にとって重要な役割を果たす。これらの運動は、脳内の血流を改善し、ストレスホルモン(コルチゾールなど)のバランスを整える効果があることが、複数の研究で示されている。
たとえば、定期的なウォーキングが脳血流を増加させ、精神的なリラクゼーションや安定感をもたらすことが報告されている。ウォーキングによって脳へ酸素と栄養がより効率的に供給されることで、注意力や集中力が高まり、ストレス耐性の向上にもつながる。
さらに、ヨガの深い呼吸法や瞑想は副交感神経を活性化させ、心身のリラックスを促進する。これにより、不安の軽減や睡眠の質の向上が期待できる。
高負荷運動と低負荷運動は、脳機能の向上においても相互に補完し合う関係にある。高負荷運動はBDNFの分泌を促し、認知機能を高めるのに対し、低負荷運動はストレスホルモンを調整し、心の安定に貢献する。どちらもバランスよく取り入れることで、身体だけでなく、脳の健康も維持することができる。
運動は、単なる体力づくりではなく、脳の健康にも深く関わる。科学的根拠に基づいた運動法と、実際に効果が実証されている成功事例を参考にしながら、自分に最適なパーソナライズド・フィットネスプランを実践することが、これからの健康維持の鍵となる。
毎日の生活の中で、ほんの少しの工夫で運動を取り入れることができる。通勤の際に一駅分歩く、エレベーターではなく階段を使う、朝のストレッチを習慣にするなど、小さな積み重ねが大きな変化を生む。こうした行動の積み重ねが、脳機能の向上、ストレス耐性の強化、さらには仕事のパフォーマンス向上へとつながる。
運動の効果を最大限に引き出すためには、継続が何よりも重要だ。無理なく続けられる方法を見つけ、自分のペースで取り組むことが大切だ。行動を起こすのに「遅すぎる」ということはない。未来の自分のために、今日から一歩ずつ、自分に合った運動法を見つけ、実践していこう。
□ライターズプロフィール
大塚久(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
神奈川県藤沢市出身。理学療法士。RYT200ヨガインストラクター。2002年に理学療法士免許を取得後、一般病院に3年、整形外科クリニックに7年勤務する。その傍ら、介護保険施設、デイサービス、訪問看護ステーションなどのリハビリに従事。下は3歳から上は107歳まで、のべ40,000人のリハビリを担当する。その後2015年に起業し、整体、パーソナルトレーニング、ワークショップ、ウォーキングレッスンを提供。1日平均10,000歩以上歩くことを継続し、リハビリで得た知識と、実際に自分が歩いて得た実践を融合して、「100歳まで歩けるカラダ習慣」をコンセプトに「歩くことで人生が変わるクリエイティブウォーキング」を提供している。
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00







