対話できない国、日本?《週刊READING LIFE Vol.296 あなたはどっち派?》
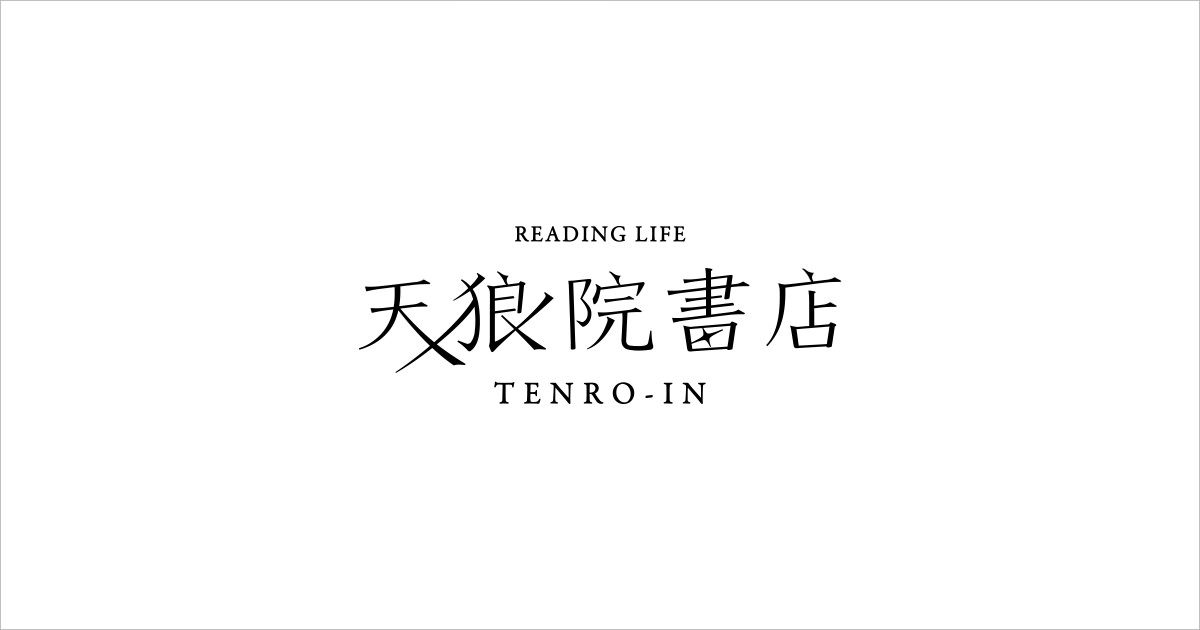
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/2/20/公開
記事:片山勢津子(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
「あなたは何派ですか?」
例えば、「アウトドア派vsインドア派」と尋ねられたら、あなたはどちらを選ぶだろう? そんな話なら気軽にできるかもしれない。しかし、話題が「戦争」「政治」になると、一気に言葉を選びづらくなる。今、世界は分断の時代だ。ウクライナ戦争、アメリカの政治対立、日本の政権交代……。対立ゆえに対話が求められている。
そんなことを考えていると、息子たちの授業参観を思い出した。それは、討論の授業だ。長男の場合は、次の内容だったと思う。
「病気の母のために子供がパンを盗んだ。この行為は許されるだろうか?」
それは、フランス小説『罪と罰』の主人公、ジャン・ギャバンの罪を思わせるような設定だった。授業が始まると、教室は重苦しい雰囲気に包まれた。子供たちが、その状況を自分のこととして把握し始めたからである。ある生徒は「それでも盗みは絶対に悪い」と主張し、別の生徒は「お母さんを救うためなら仕方がない」と訴えた。
息子は、「母親が死んだらその子も死んでしまうよ」と、一生懸命に話したらしい。そう。私は行けなくて、後からママ友に聞いた内容だ。長男は真面目な性格だったので、私はそれを知って驚いた。でも、彼の実体験から出た言葉だ。極度のアレルギー体質だった息子は、私が作ったものしか食べられなかったからだ。給食も食べていなかったので、彼の事情はクラスの皆が知っていた。彼の実感から出た言葉の気迫が伝わったのか、議論は加熱していったらしい。どちらの意見も甲乙つけ難く、勢力伯仲となった。
その時、「では、どうすればよいのだろう?」と先生の問いが始まった。子供達は、解決策を考え始めた。どんな発言があったか定かではないが、おそらく公的支援や情状酌量という概念を、先生は引き出していったのだろう。暗かったクラスにようやく光が差し込んで授業は終わったという。
先生は、「家庭でも話し合いの場を持ってください」と、保護者に伝えた。このエピソードを聞いて、子供に考えさせる授業は大切だと痛感した。つい、日頃の忙しさにかまけて、子供の本音をじっくりと聞いたことがなかったからだ。子供との会話は自分で考えさせる能力を養うためにも大切だと、日常生活を振り返った。
その2年後のことだ。同じように次男の参観日で討論の授業があった。楽しみに出かけた教室の黒板には、こう書かれていた。
「ソース派 vs 醤油派」
正直、唖然としてしまった。けれども、子供達は授業が始まる前から授業の内容を知って、嬉しそうだった。この問題がどのように進むのか、じっと見ていた。
授業が始まると、子供たちは次々に発言して、教室はすぐに元気一杯の空気で満ち溢れた。でも、身近な例を自由に話していたので、これが討論なのかどうなのかを疑問に思った。自分の好き嫌いの主張合戦のようだったのだ。そのうち、「卵焼きにはソースか醤油か」「お好み焼きには何をかけるべきか」など、まるでテレビのバラエティー番組のようになった。面白いことを言ったら笑いが起こるという状況だ。私はがっかりした。
「病気の母のためにパンを盗んだ子供は許されるのか?」と言う授業では、みんなが葛藤しながら考え、答えを出そうとしていた。では、「ソース派 vs 醤油派」はどうか? みんなが笑いながら、自分の好みを語るだけだ。ここには「対話」も「交渉」もない。ただ主張しあっただけだ。「山 vs 海」「都市 vs 田舎」など、もう少し考えさせるテーマにすれば、議論する意義が深まっただろう。ディベートなら、深い洞察や新たな解決策がなければ意味がないと思う。
このように、私が子供たちの討論の授業を思い出したのには、訳がある。分断の時代、日本人は対立した時の収拾が下手だと聞いていたからだ。海外を相手に、これからやっていけるのだろうかと、不安になったのだ。
でも、「仲介役になれるのは日本だ」と、いとも簡単にテレビや新聞では語られる。記者会見やインタビューに応じる時、日本の政治家は原稿を読んでいる。咄嗟に判断が必要な時に、そのような状態で大丈夫だろうか。対立すれば、解決策を考えるのが当たり前だけれども、我々日本人にそんな能力があるのだろうか。その能力をすぐにでもつけなければならない時代だ。
息子達の討論は、いわゆる「ゆとり教育」の一環として、始まった。ディベートの授業は、今もあると思うが、私は日本の教育には不安を感じている一人だ。よく指摘されるように、日本の教育は詰め込みが中心で、自主的に考える力を育む点が欠ける。人目を気にしたり、人に頼る傾向があり、まともな発言を避けていると感じるからだ。
これは、最近の経験に基づいた気持ちである。例えば、若者に何か新しいことを言うと、「その方法を教えてほしい」とすぐに聞かれる。「子供じゃあるまいし自分で考えてよ」と、呆れてしまうのだ。恐らく、子供の時に、回答を導く方法を手取り足取り丁寧に教わったのだろう。考えるプロセスが大事なのだけれども、よく理解しないで答えや公式だけを覚えてきたのだろう。
外国人に指摘されて、日本の教育の欠点を知らされたことがある。それは、こう聞かれた時だ。
「日本の学校では、どうして作文をしっかり見ないの?」
確かに、日本の宿題に作文はあるが、先生はサラッと読むだけで細やかな指摘はしない。欧米では、幼少期から自分の考えを発表させ、中学生くらいから文章の構造を学び、それに沿って練習をする。だから、作文には細かなチェックが入るらしい。日本では、文の構成を学校では細かくは教えないと思う。
学力の多くは、○×式や選択問題のテストを中心に図られる。そして、大きな試験ほどこの傾向が強くなる。間違いを減らすためなのだろうが、マークシート形式のテストが普及して、記述式問題はほとんどない。面接の試験があるじゃないかと言われそうだが、日本ではそもそも、自説を理論づけて話すトレーニングをしていない。ディベートの練習程度で、ほとんどしていないといって良いのではないかと思う。むしろ、当たり障りのない受け答えを学んで、無難に済まそうとする。
外国人の中に入ると、日本人は大人しい。他人の発言に圧倒されて、上手く喋れなくて困った経験がある人もいるだろう。日本人同士ならそれでも問題はないが、世界では、話さなければ興味がない。あるいは、意見がない人だと判断される。気配を察するのは、日本人だけだと言ってもいいかもしれない。論理的に話の筋道を通して説明しないと、説得力は発揮できない。それが、グローバルな世界なのだ。
実は、私は海外でアンケート調査をして失敗したことがある。日仏で同じアンケート調査をしたときのことだ。日本語のアンケートの仏訳で、フランス人はまともに答えてくれなかった。それは、調査会社のモニター相手の大掛かりな調査だったので、念を入れて準備した。それにも関わらず、失敗した。
幸い、事前に気づいた。知人にアンケート用紙を見せて、顔をしかめられたからである。そして、マーケット専門の知人から、道筋が大切だと言うことを教えられた。日本人は、聞けば素直に答えてくれるが、海外ではそうはいかないことを学んだのだ。論理的に話の筋道が通っていないと、アンケートにさえ、真面目に答えてくれない。慌てて修正したので、大失敗とまではいかなかったが、予想通り、自由記述には真面目に答えてくれなかった。以後、まず筋道を考えて、フランス語で設問を作り、それから日本語に訳す方法に変えた。
実は、アンケート調査をする前に、しばらくパリに住んでいた。だから、フランス人の考え方を凡そ知っていたはずなのに、身についていなかったことを恥じた。しかも、通訳の知人から、日本人がいかに交渉下手かを聞かされていたのに。
企業の通訳をしていた彼女は、日系企業がプロジェクトで失敗した事例、交渉下手で不利を被っているのを見て、何度も歯軋りした。彼女によると、「私が誘導しますから」と言っても、結局、日本人は相手の理路整然とした主張を前に、降伏してしまうというのだ。世界で戦うには、かなりのトレーニングが必要だと言うことが、アンケート調査で失敗してよく分かった。
彼女によると、日本人の会話での欠点の一つは、相手の話を聞くのが下手なことだという。トラブルへの対処が、その時に明確になるという。グローバルな場では、うまくいかないことを前提に、交渉する力が必要だと力説した。「日本の交渉力は、まるでサッカーでボールを回すのが得意でも、ゴール前でシュートを打てないようなもの」と、例えた。確かにそうだ。日本サッカーも日本式コミュニケーションも、いいところまで行くが、最後の詰めができていない。準備をしたとしても、それでは意味がない。
日本では「空気を読む」文化が強いので、細かい言葉にしなくても伝わる。だが、それは国内での話。海外では、明確に言葉にしなければ伝わらない。実際、私はフランスでのアンケート調査で失敗した。日本語のアンケートをそのまま翻訳しても、フランス人には質問の意図が不明確で伝わらないので、自由記述にまともに答えてもらえなかった。
「察してほしい」は、日本の外では通用しない。言葉にしなければ、相手には伝わらない。だからこそ、「言葉にする力」「論理的に話す力」を、日本人はもっと鍛えるべきだ。それが、対話の第一歩なのだから。
討論とは、自分の主張を通すためのものだけではなく、相手と話し合い、新たな解決策を決めていくことだ。
最近、危険に思っているのは、力を頼りに自分の意見を押し通すと言う風潮になっていることだ。自分の主張だけを強めても対立は解消しない。この方法では分断を引き起こす。私たちが気をつけないといけないのは、人の話を聞いて論理的に話を進める方法である。だから、教育の場では、それを教えた上で、どのように考えていくのか、話し方、物事の進め方について、ぜひ教えてほしい。
日本人は寛容である。これは優れた文化だと思う。ただ、人目を気にし、規則や固定概念に縛られて、自分の考えを新たにまとめる訓練が、ともすればできていない。未来のために、学校教育では作文の書き方を、詳しく指導してほしい。企業の会議では、根回しを必要としない自由な意見が言える場を設け、新しい方策を考えるようにしなければならないだろう。家族でも、いろんな話題を大切に語り合おう。
相互の話し合いとは、意見をぶつけることではなく、解決策を探す場だ。交渉とは、勝ち負けではない。そして、話し合いは、戦いではなく未来をつくることだ。これからの時代、日本人に必要なのは、「聞く力」と「伝える力」。
対話は、政治だけの話ではない。ビジネスでも、教育でも、家庭でも、誰にでも必要なスキルである。「考えをまとめて話し、相手の話を聞き、互いに解決策を探る」力を、日本人はもっと養わなければいけない。同調せずに、身近なコミュニケーションから、まずは始めてみたい。
□ライターズプロフィール
片山勢津子(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-

あなたはこし餡派?それとも粒餡派? 「どっちもいいよね」と言えるようになったら、世界が広がった《週刊READING LIFE Vol.296 あなたはどっち派?》
-

激しいトレーニング vs 穏やかなトレーニング 〜理学療法士が教える自分に最適な健康法の見つけ方〜《週刊READING LIFE Vol.296 あなたはどっち派?》
-

家事ヤロウのレシピ帳《週刊READING LIFE Vol.296 あなたはどっち派?》
-

ナミコはホントにかわいいな《週刊READING LIFE Vol.296》
-

春フェス vs. 冬フェス あなたはどっち派? それぞれの魅力を徹底解説!《週刊READING LIFE Vol.296 あなたはどっち派?》



