新しい弔いのスタイル 常識知らずの夫に呆れるどころか尊敬してしまった話《週刊READING LIFE Vol.297》
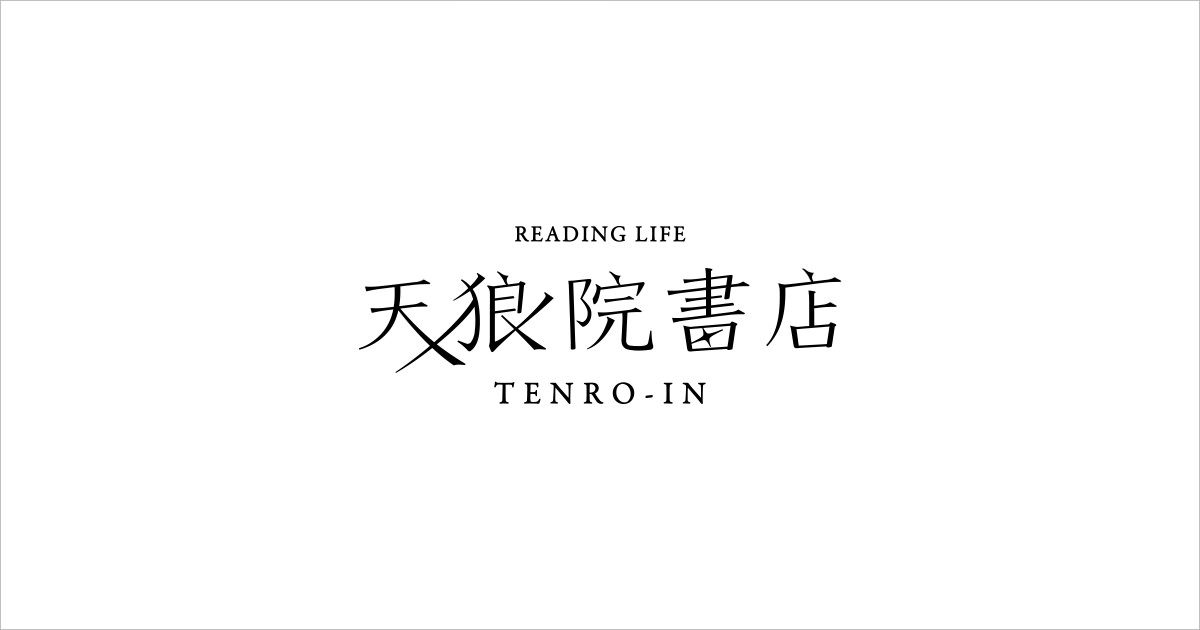
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/2/24/公開
記事:かたせひとみ(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
遅い。
時計を見ると20時を回っていた。
と、その時、玄関のチャイムが鳴った。
やっと夫が帰って来た。
昼過ぎにふらっと出て行って、この時間だ。
どこに行ってたんだろう。自分の鍵で開ければいいのに……。
私は軽く舌打ちしながら、玄関ドアへ向かう。
玄関を開けると、暗闇の中、夫が台車を押したまま立っていた。
なんで台車?
台車の上には大きな箱がある。何だろう、この箱は……。
え、もしかして……プレゼント?
こっそり用意していたんだ!
私たちは数日後に結婚記念日を控えていた。
夫は気を利かせて、プレゼントを用意してくれていたらしい。
何も考えていないように見えて、ちゃんと考えていたんだ。
私は、夫の心遣いに少し目頭が熱くなった。
しかし、よーく見ると、プレゼントの箱にしては違和感がある。
どっしりとした木の箱だ。深い茶色が、高級感を漂わせている。
こんなギフトボックス、見たことがない。
かなり大きい箱で、60センチ四方はあるだろうか。
大きさから考えると中身は……オーブンレンジ? でも、木の箱に入れるとは考えにくい。
あ! もしかして、バラの花束100本?
色々プレゼントの中身を想像してみるが、どうもこの重厚感のある箱と中身がマッチしない。
目が暗闇に慣れてきた頃、箱に彫り物や細工が施されているのに気づいた。
数秒後、その箱の正体に気づき、ショックで息が止まりそうになった。
まさか! こんなことって!
夫が運んできた箱、それは仏壇だった……。
開いた口が塞がらないとはまさにこのこと。
なぜここに仏壇? 台車の上に仏壇? え? え?
仏壇は、夫の実家に置いてあったもので、いずれ我が家に持ってくることになっていた。
しかし、こちらの準備は何ひとつできていない。まして、今日持ってくるなんてひと言も聞いていない。
ついさっきまで結婚記念日のプレゼントだと思って、軽く喜びの涙まで流しそうになったのが実は仏壇。
別の種類の涙が出てきそうだ。
「な、何で今日なの?」
「うん。実家に寄ったついでに」
何のついで? 仏壇って、そんな軽いノリで持って帰れるもの?
そもそも、仏壇を素人が勝手に動かしていいの?
「魂入れ」や「魂抜き」が必要なんじゃないの?
何より、こんなふうに雑に運んでいいの?
普通、緩衝材で何重にも包んで、傷をつけないように慎重に丁寧に運ぶでしょ?
緩衝材も敷物もなく、むき出しのまま台車に載せられている仏壇……。
言いたいことは山ほどあったが、驚きすぎたせいで、言葉が出てこなかった。
夫にどこに置くつもりか尋ねると「俺の部屋でいいでしょ」という。
俺の部屋? 物であふれているあの部屋に?
私は、リビングに置くことを提案した。
しかし、夫は、運ぶのが大変だから、玄関に近い自分の部屋でいいという。置き場所の決め方までもが、雑だった。
まあいい。一旦は夫の部屋に置こう。
そうだ、仏壇と言えば遺影だ。遺影はどこに飾るつもりか、夫に尋ねた。
「あー、遺影ね。捨てて来た」
す、す、捨てた? 遺影を? 言っておくけど「あなたの」ご両親の遺影ですよ!
私じゃなくて、あ・な・た・の! それを捨てたって!
驚きのあまり、体が勝手に名画ムンクの『叫び』と同じポーズを取っていた。
『北斗の拳』のコミック全27巻は捨てられないのに、親の遺影はこうもあっさり捨てられるのか……。
しかし、私は思い直した。
いや、いくらなんでも写真は捨てないだろう。きっと額だけ捨てたんだ。
そう思い、改めて尋ねると、「両方捨てたよー」と、あっけらかんとした答えが返ってきた。
とても短くシンプルな言葉だったが、その破壊力は強烈だった。
私は言葉を失ってしまった。比喩ではなく、本当に。
「……」
しかも、写真は個人情報の心配もあるからと、わざわざ、ビリビリに破って捨ててきたという。
ここ、個人情報の心配をするところですか?
遺影を破くなんて信じられない。お義父さん、お義母さんがあの世で泣いてるよ!
夫は、驚く私に気づく様子もなく、言葉を続ける。
「遺影なんてなくたっていいよ。親父とおふくろはここにいるから」と、グーにした右手を左胸に当て、ゆっくりと瞳を閉じた。
そうね、お義父さん、お義母さんは、いつもあなたのそばにいるわね……。
いや、そういう話じゃない!
仏壇の衝撃に続く更なる衝撃に、私はノックアウト寸前だった。神経が細やかな人だったら呼吸困難に陥るだろう。
しかし、幸か不幸か、私の神経は案外太かった。
だからなのか、夫は私を全く気にすることなく、さっさと自分の部屋に仏壇を運び始めた。
そして、部屋の一角に仏壇を置いた。
設置を終えた夫は、何かをやり遂げたような清々しい表情で「うん、完璧だ」とご満悦だった。
義両親は、非常に信心深い人達だった。仏壇には季節の花と菓子を欠かさず供え、毎日手を合わせていた。もちろん仏壇の掃除も欠かすことはなかった。
この仏壇の購入も、一大イベントだった。
義両親は、暦で日取りの良い日を選び、わざわざその日に運んでもらうほどの念の入れようだった。
当日、何重もの緩衝材で丁寧に包まれた仏壇は、白い手袋をはめた葬儀屋によって恭しく家の中に運び込まれた。当然のように、僧侶による魂入れの法要も執り行われた。
その仏壇が、今、こんなにもぞんざいな扱いを受けている。仏壇は、どんな思いで私達を見つめているのだろうか?
今まで大切に扱われてきた分、ショックを受けているだろう。
なにより、義両親がどれほど驚いていることだろうか。
私は心の中で「ごめん……。化けて出ないでね」とつぶやきながら、仏壇に手を合わせた。
常識をぶっ壊せ、とは言うけれど、ここまで大胆に壊すか?
結婚記念のプレゼントはとんでもないプレゼントになってしまった。そして、それは思いがけなく過去一番のサプライズにもなった……。
しかし、夫の弔いに関する非常識は今に始まったわけではない。
仏壇セルフ移動事件に遺影ビリビリ事件。
どちらもかなり非常識な話だが、既にそれ以上のことをやってのけていた。
なんと、夫は、義母の一周忌をすっ飛ばしたのだ。
こんな人、私の周りには一人もいない……。
義母は9月の初めに亡くなった。通常であれば、翌年の8月半ばに新盆供養を行い、9月に一周忌を行う。
しかし、夫はなぜか、新盆供養に一周忌も含まれると思い込んでいた。その理由は、「2つの法要の間隔が短いから」というものだった。
お寺から一周忌について連絡がなかったのも良くなかった。夫は、短期間で二度も法要を行うのは大変だろうと、お寺が気を利かせてくれたと解釈していた。
なんだ、その勝手な解釈は。そんなことあるわけない。
私は、夫に何度も説明した。
新盆と一周忌は別物だ。こちらからお寺にお伺いを立てて、日取りを決めて執り行うものだ。
新盆と一周忌をセットにしたら、お寺にとっては稼ぐ機会の損失だ。お寺の駐車場に並ぶ住職ファミリーの高級外車の数々を見ろ。
1回ン万円を稼げるチャンスをみすみす捨てるか?
お寺だって慈善事業じゃない。「今回はセットでいいよ」なんて、考えられない。
うちはセット扱いにしてもらえるほど常連でもないし、そもそも「セット」などという制度自体存在しない。
しかし、いくら説明しても、夫の解釈はビクともしなかった。
「せっかくセットでいいって言ってくれてるのに、何言ってんの?」
「おかしなこと言う人だなぁ」という目で私を見ていた。
夫に言っても、話にならない。
まあいい。一周忌が近づいてきたら、親戚から連絡があるだろう。
親戚の中に、一人二人は法事にうるさい人がいるものだ。「一周忌をやらない」と言ったら驚くはずだ。その人から夫を諭してもらおう。
私は大船に乗ったつもりで、親戚からの連絡を待った。
しかし。
誰一人連絡を寄こさなかった……。
みんな自分のことで忙しいのだ。本音を言えば、法事なんてそんなに行きたいものではない。呼ばれるから行くのであって、自ら進んで行く人の方が珍しいだろう。
こうして、親戚に説得してもらう戦略もあっけなく頓挫した。
結局、次の手を打つこともできず、一周忌は行わずに終わった。
私は、一周忌をスキップした世にも珍しい夫婦の片割れになった。
あれだけ信心深かった義両親を思うと、少し胸が痛んだ。自分達も、みんなに手厚く悼んで欲しかったのではないだろうか。
「お義父さん、お義母さん、ごめん。化けて出ないでね」と墓前に手を合わせた。
息子のところに化けて出てくることはないだろうと思いつつ、心の中で詫びた。
対する夫は、まったくお気楽なものだった。
本人は新盆も一周忌もきちんと終えたつもりでいるのだから、当然と言えば当然だった。
しばらく経ってから「そういえば一周忌は?」と聞いてきた親戚もいた。
夫は、「お寺が気を利かせてくれてさ。新盆のときに一緒に済ませたよ。コロナも収束してないから、接触を減らしたかったんだろうね」と、答えていた。
この頃は「コロナ」を出せば、皆納得するという風潮があった。
世の中の流れにうまく乗った夫の回答に、親戚は何の疑いも持たなかった。
一周忌をスキップしたのは夫の勘違いだ。
勘違いは誰にでもある。私もしょっちゅうだ。
しかし、仏壇の引っ越しとなれば、話は違ってくる。
ちゃんとした手順を踏んで引っ越しをしよう。私は、いずれ仏壇を購入した仏具屋さんに話を聞きに行こうと考えていた。
それなのに、ああ、それなのに。
突然、仏壇はやってきた。
よく「夫の親の仏壇を家に置きたくない」という妻側の意見を耳にする。
「見られているようで落ち着かない」
「インテリアに合わない」
そんな声も少なくない。
確かに、仏壇は家に馴染みにくい存在だ。私も妻側の意見に共感するところはあった。
それほど大きくない仏壇でも、やはり存在感はある。
この仏壇をきっかけに夫婦の諍いが増えないといいのだけれど。
そう思いながら仏壇との生活が始まった。
しかし、生活はほとんど変わらなかった。
仏壇は夫の部屋にあり、遺影もない。
代わりに、義両親が二人で写っているスナップ写真を飾っている。
これは夫の案だった。
「遺影って、好きじゃないんだよなぁ。俺たちが拝むんだから、俺たちが好きな写真にしようよ。親父達が二人で写っている写真でいいんじゃない」と、この写真を選んだ。
写真が小さいからだろうか。義両親に見られているような感覚はまったくない。
そして私は、思いがけない発見をした。
仏壇はよく見ると、素晴らしい工芸品だった。繊細な彫刻、上品に輝く螺鈿細工、金色の飾り。それはまるで小さな精巧に作られたミニチュアハウスのようだった。
その美しさに惹かれた私は、次第に仏壇に愛着を感じるようになった。
さらに、常識外れと思っていた夫の行動にも共感するようになった。
なぜ、私はあれほど「常識」や「慣習」に従わなければならないと考えていたのだろう。
実際、法事に積極的に参加したい人がどれだけいるだろうか。
気慣れない喪服で窮屈な思いをしながら、意味がよくわからないお経を聞く。
「早く終わらないかな」と私が思うように、他の人も同じように思っているかもしれない。お経をあげている僧侶だって、もしかしたら……。
けれども、「慣習だから」「そういうものだから」と誰もがそれに合わせて我慢している。
一周忌をしなくても、何の不都合もなかった。
仏壇を自分で運んだことも、遺影がないことも、今のところ何も問題はない。
幸い、義両親が化けて出ることもなく、不幸な出来事が起きることもなかった。(ホッ)
仏壇を運んだあの夜、夫は胸に手を当てて「親父とおふくろはここにいる」と言った。
「調子いいこと言ってー」と、半ばあきれた思いで見ていたが、今は違う。
義両親が夫のそばにいてくれて良かったと思える。
夫は毎日仏壇の水を変え、小さなスナップ写真を見つめながら手を合わせている。これが、夫の弔いのスタイルなのだ。
それぞれが思う形の弔いをすればいい。
仏壇を雑に運んでも、遺影がなくても、一周忌をスキップしても、故人を想う気持ちがあるなら、それで十分なのかもしれない。
常識を派手にぶっ壊した夫を尊敬する。
常識に囚われない人になりたいとずっと思ってきた。そのお手本が、まさかこんな身近にいたとは。
大抵の人は、疑問に思うこともなく、淡々と粛々と前例や慣習に従って生きている。私だってそうだ。でも、夫はその逆を選んだ。
まるでチルチルとミチルが探した「幸せの青い鳥」だ。
私が探していたもの、お手本にしたい人は、思っていたよりずっと近くにいたようだ。
□ライターズプロフィール
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00






