心の深呼吸がしたくなったら、本をひらこう《週刊READING LIFE Vol.305 アナログならではの魅力》
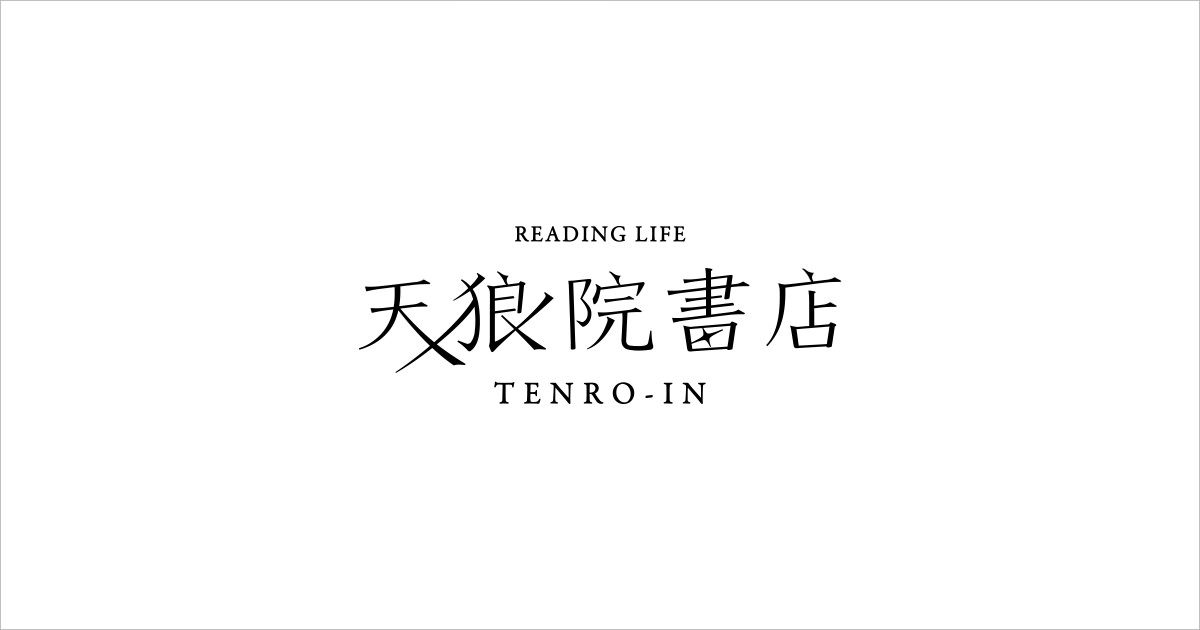
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/4/21/公開
記事:山岡達也(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
なぜ、あの一冊だけは捨てられずに、本棚の奥に眠り続けているのだろう。
スマートフォンをはじめとするデジタル機器があれば、世界中の情報にたちどころにアクセスできる。大量の本を持ち歩かなくても、電子書籍アプリ一つあればいつでも読書ができるし、新刊も発売と同時に入手できる。ニュースやSNS、動画配信サービスも手軽に楽しめて、移動中やちょっとした空き時間でさえ隙なく情報を得られるのが現代の当たり前の光景である。しかし、そんな便利さに囲まれながらも、ふと「立ち止まりたい」と感じる瞬間があるのではないだろうか。
実は、その「立ち止まりたい気持ち」は、紙の本に触れたときにこそ生まれることが多い。触れた瞬間に指先が感じるざらりとした紙質、ページをめくるときにかすかに聞こえる音、そしてページとページのあいだに挟まっている余白。それらは、デジタル端末のスワイプやタップでは味わいにくい、五感に訴えかける体験をもたらしてくれる。例えるなら、紙の本は焚き火のような存在である。夜の静けさのなか、ぱちぱちと薪が爆ぜる音に耳を澄ませ、ゆらめく炎をぼんやり眺めていると、心がじんわりとほどけていく。紙の本にもそんなぬくもりがあり、ページを開くたびに静かで穏やかな時間が立ち上がるのである。
デジタルが悪いわけではない。電子書籍は場所を取らず、文字の大きさやフォントを自由に変えられるし、検索機能やハイライト機能など、デジタルならではの魅力が満載である。忙しい現代人にとって、それらの便利さは心強い味方となる。むしろ、デジタル書籍の快適さを知っているからこそ、紙の本を開いたときに「やはりこれが好きだ」と気づく人も多いのではないだろうか。デジタルの時代にアナログの魅力が際立つのは、両者を比べる機会が増えたからとも言えよう。
体を巻き込む読書体験
紙の本をめくる行為は、読む人の体を自然に巻き込んでいく。右手でページを押さえ、左手でそっとめくり、少し進んだところで「もう一度最初の文章を振り返ってみたい」と思ったときには、指先で数枚前のページに戻る。この動作はわずかに手間がかかり、電子書籍リーダーのスワイプやタップよりもスムーズさには欠けるが、その「一手間」こそが読書をゆっくりと味わうための余裕になっているのである。ページの角度がわずかに変わり、手が紙を支える感覚や、インクのにおいをかすかに感じる瞬間も、読書体験に奥行きを与えてくれる。
さらに、紙の本には「余白」という大きな魅力がある。文章の行間やページの隅、章と章の切り替わる白いスペースなど、一見無意味に見える空白の部分が、読者の思考をゆったりと広げる場になっているのだ。読み進めていて「あれ、これは自分にとってどういう意味だろう」と疑問を抱くときや、「この言葉はちょっと心に引っかかるな」と感じるとき、自然と視線は行間やページの外側へと移る。そこにはデジタル端末のように広告や通知が割り込んでくることはない。物理的に何も書かれていない空間が、感情や記憶を受け止める「余白」として機能し、自分だけの思いや解釈がゆっくりと膨らんでいくのである。
実際に余白を使って、ちょっとしたメモを書き込む楽しみも紙の本ならではである。鉛筆やペンで自由に思ったことを綴り、後から読み返したときに当時の感情を呼び戻すことができる。電子書籍にもハイライト機能やしおり機能はあるが、それらは画面の上に「記号」として表示されるだけで、手書きの筆圧や紙をこすった痕跡まで残るわけではない。紙の本に書き込んだ文字は、下手をすれば消しゴムでこすっても跡が残るほど物理的に深く刻まれる。そうした「生身の記憶」は、ややアナログ的ではあるが、それゆえの温かみが読書体験をいっそう豊かにしてくれる。
過去の自分との対話
読み終えた本を、もう一度手に取る喜びも大きい。一度読んだ本を再読するとき、人は無意識に「当時の自分」と「いまの自分」を重ね合わせる。ページの角が折れていたり、飲み物の染みがついていたりするのを見つけると、「そういえば、あのときはこんな気持ちで読んでいた」と当時の情景がよみがえる。あるページに線を引いたり書き込みをした部分を見つければ、「こんな一文に感動していたのか」と、過去の自分の感性と対話できる。情報だけを求めるなら、デジタルで十分かもしれない。しかし、このように紙の本が育む「時間の連なり」や「記憶の重なり」は、まさにアナログ特有の財産である。
一方で、現代はスマートフォンを手に取れば、SNSや動画、ニュースサイトなどから無尽蔵に情報が流れ込んでくる時代でもある。通知が鳴るたびに意識をそちらへと向けさせられ、次から次へと情報をチェックしているうちに、気づくと何をしていたのか分からなくなることもあるだろう。こうした情報の洪水からそっと離れたいときこそ、紙の本を開いてみる価値がある。電源を入れなくても、待ち受け画面を解除しなくても、本を開けば目の前に文章が現れる。そこには広告も通知もなく、ただ紙とインクだけの世界が広がる。読書が「自分と向き合う時間」であると実感できるのは、こうした静かな環境に身を置いたときである。
デジタルとアナログの調和
デジタルとアナログは対立する存在ではない。普段は電子書籍での読書が多い人が、寝る前や休日など、ゆっくり読めるときだけ紙の本を開くのも素敵な使い方だろう。あるいは、気になった新刊はまず電子書籍で試し読みし、これは紙でも手元に置きたいと思ったら書店で購入する、というハイブリッドな方法をとる人もいる。デジタルの便利さを最大限に活かしながら、アナログのぬくもりも享受する暮らし方が、現代には合っているのかもしれない。
焚き火のようにじんわりと心をあたためてくれる読書時間は、実を言えばそれほど特別な準備を必要としない。いつものバッグに文庫本を一冊入れておくだけでも、ちょっとした待ち時間が静かな読書タイムに早変わりする。喫茶店や電車の中でスマートフォンを覗き込む代わりに、紙のページをめくってみれば、そこには一瞬の「余白」が生まれる。行間の空白に目を留めれば、自然と自分の中に言葉や記憶が湧き上がってくる。こうしたちょっとした立ち止まりこそが、心を深呼吸させてくれるきっかけになり得る。
たとえば、レコードやカセットテープを手間をかけて楽しむ人がいるように、紙の本という「非効率なツール」をあえて使う行為は、現代人にとってむしろ贅沢な選択なのかもしれない。フィルムカメラで写真を撮るときも、撮影後すぐに確認できないもどかしさがある反面、「本当にこの瞬間を撮りたいのか」を丁寧に考えるという大事なプロセスが生まれる。アナログには、結果を急がずゆったりと過程を味わえる余裕がある。紙の本でも同じように、ページをめくる一動作ごとに「自分はいま何を読んでいるのだろう」と立ち止まるきっかけが眠っている。
ハイブリッドな読書スタイルを求めて
アナログを礼賛するだけではなく、そこにデジタルを組み合わせる暮らし方も考えてみたい。新刊や専門書、あるいは語学学習用の本は電子書籍で用意し、いつでも検索やハイライトができるようにしておく。一方、愛着を深めたい作品や大切な思い出の詰まった本は紙で手元に残し、本棚に並べておく。「両方使い分けるのが自分にぴったりだ」と感じる人もいるだろう。ハイブリッドな読書ライフを選択することで、効率も味わいも両立できるはずである。
たとえデジタル全盛の時代であっても、紙の本には焚き火のような役割があると感じる。目まぐるしく流れる時間の中で、あえて紙を開き、文字を追いかけるうちに、不思議と心が落ち着きを取り戻していく。ベッドサイドのランプの下で本を開けば、ページをめくる音が静かな子守唄のように聞こえることもある。なかなか寝つけない夜こそ、スマートフォンを眺めるより、紙の本に身を委ねるほうが心を穏やかにしてくれるかもしれない。
捨てられない一冊の意味
では、なぜ私たちは、古びた一冊をなかなか捨てられないのだろう。そこには単なる情報を超えた「温度」や「香り」、そして「過去の自分との対話」が宿っているからではないだろうか。使い込まれた背表紙の汚れや、挟まったまま忘れられていた栞は、どれも「この本と過ごした時間」を形にして残している。紙の本がずっとそばにあり続けることは、人生のある時期を象徴する記念品をずっと手元に置いているのと同じでもある。だからこそ捨てられないし、ふと思い出したときに開いてみると、少しだけあたたかな気持ちになれるのである。
現代はあらゆることが効率化されており、何かをじっくり「味わう」ための余白が徐々に減っているように感じられる。しかし、紙の本を開く行為には、効率とは別の次元にある大切な豊かさが潜んでいる。情報をたんに消費するのではなく、言葉と自分をゆっくりと重ね合わせ、五感で味わうという行為は、慌ただしい日常に埋もれていた自分の感受性や好奇心を呼び覚ますきっかけになる。紙をめくるたびに、ページの向こうから焚き火の炎がちらちらと揺れているように感じることがある。忙しさのなかでは忘れがちな「自分に向き合う時間」を思い出させてくれるからかもしれない。
再発見の喜び
最後に、もし自宅の本棚を眺めていて「この一冊はもういいかな」と思う本があったら、あえて捨てる前にもう一度開いてみるのはいかがだろうか。そこには当時の書き込みや折り目が残っていて、そのときの自分が何に心を動かされていたのかを再発見できるかもしれない。あるいは、全然興味を持てないと思っていた本が、いま開いてみると違った光を放つこともある。そうしたちょっとした再会は、デジタルを眺めるだけでは得られない小さな驚きとして日常を彩ってくれる。スマートフォンを閉じ、静かな部屋で紙の本をめくるとき、焚き火の前で手をあたためるように、心がじんわりと温かくなるかもしれないのだ。
この記事を読み終えたあと、ほんの少しでも「本を開いてみようかな」と思ってもらえたらうれしい。デジタル全盛の時代だからこそ、アナログとデジタルを柔軟に使い分けながら、紙の本ならではの静かな喜びを味わってほしい。余白にペンを走らせる書き込みの感触や、何年か後に再び手に取ったときにこみ上げる懐かしさは、きっと電子機器の画面では味わえない特別な贈り物である。焚き火のようにそっと寄り添ってくれる一冊が、あなたの心にも小さな灯りをともしてくれるかもしれない。文字と向き合うその時間は、きっと自分自身を少しやさしく、ゆるやかな気持ちで見つめ直すための、大切なきっかけになるはずである。
□ライターズプロフィール
山岡達也(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
四国在住。職業は生物化学系の技術者である。天狼院書店との関わりは、2019年にライティング・ゼミに参加したことに始まる。ライターズ倶楽部には2025年1月より参加。
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00





