デジタル時代に、あえてアナログを選ぶ《週刊READING LIFE Vol.305 アナログならではの魅力》
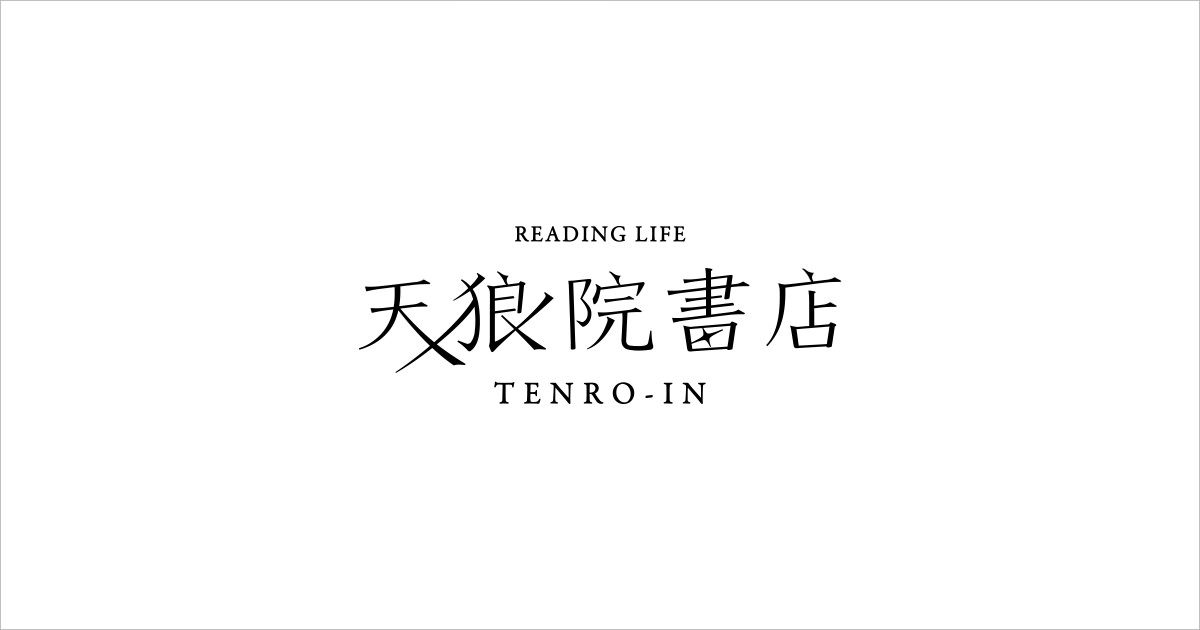
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/4/21/公開
記事:マダム・ジュバン(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
「ねえ、見てよこれ!」
久しぶりに会った妹が自分のスマホを私に見せた。
「やだ、何これ~!!」
そこには“優しそうな初老のおじさん”風の犬の画像があった。
そうこれは最近SNSで話題の「AIによるペットの擬人化加工」。
妹が溺愛するペットのミニチュアダックスはとても可愛いが、今10歳だから人間ならおよそ60歳。
しっかり白髪まじりの眉毛に、垂れ目の人生を語れそうな瞳。
まさかの画像に妹と二人、しばらく笑いが止まらなかった。
それにしても、AIでこんなこともできるなんて驚きだ。
そう言えば最近、私は6歳の孫のくもんのお迎えをした。
「もうすぐ終わります」「いま終わりました」と先生からLINEが届き、私は教室へと向かった。タイミングはバッチリ。まったく時間の無駄が無い。
家に帰れば孫は「ディズニープラス」チャンネルで器用に番組を切り替えて、お気に入りのアニメを見始めた。
1本ずつVHSビデオを買ったりレンタルしていたのが嘘のように、定額料金さえ払えばこれでもかとコンテンツは選び放題。
孫はきっとこれを「当たり前」として育つのだろう。
入学式の写真もスマホのアプリで共有され気に入ったものだけプリントをすればいいのだ。
子育てひとつ取っても何もかもが便利で効率的。
10年前には想像もしなかった事が今では当たり前になり、デジタルにかなり助けられている毎日。
でもふと、どこかに忘れ物をしてしまったように心がざわつくのは何故なんだろう。
そんな風に感じていたある日、私はFacebookに懐かしいひとの名を発見した。
それは私の初めてのボーイフレンド。
ラブレターをくれた相手だった。
今の子どもたちならきっとLINEでやり取りするのだろうが、あの頃誰かに想いを伝えるといえば「手紙」だった。
中学1年の春のこと。
ある日登校すると下駄箱の中に、白い封筒を見つけた。
もうそれだけでドキドキだ。
友だちに見られないよう、こっそり片隅で封筒を開ける。
便せんにはお世辞にも上手いとは言えない、筆圧強めの字が踊っていた。
文面はさすがに覚えてはいないが「君のことが好きになりました。つきあってください」とか何とかだったと思う。急いでカバンにしまった。
相手は同じクラスのY君だった。ハッキリ言ってタイプでは無い。
それに私の顔を見れば悪態ばかりつくY君がどうして?
(からかわれているのかも……)そう思ったけれど何だかワクワクした。
だってそれは私が生まれて初めてもらった「ラブレター」だったのだ。
たとえ下手な字であっても、ひと文字ひと文字の温もりを感じる。
私のために頭をひねって手紙を書いてくれたのだと思うと、やはり嬉しかった。
クラスの中でそれほど目立つ存在でもない私を「好き」と言ってくれた。
その事実に舞い上がり、相手のことを好きかどうかもよくわからないまま交際を始めた。
交際と言っても図書館や卓球場に行ったり、互いの家を行き来したりと可愛いものだ。
だが、ほどなくY君は父親の仕事の都合で千葉県に引っ越してしまった。
当時私が住んでいたのが武蔵野市だったから子どもにとっては、まあまあの遠距離となる。
それからも私はY君と文通を続けた。そしてある日Y君が久しぶりに私に会いに来てくれることになった。
武蔵境駅で待ち合わせ、そこからどこかへ行こうと手紙には書いてあった。
私は新しく買ってもらったギンガムチェックのブラウスを着て、約束の10分前から改札口で待った。
しかし約束の時間を過ぎてもY君は現れない。
10分、20分、30分……。私は改札口から出てくる人を見逃さないよう必死に目をこらしていたが見つけることはできなかった。
もしかしたら待ち合わせ場所は反対側の出口なのかもしれない。
私は伝言板に伝言を残そうと思った。
念のため記すと「伝言板」は昭和の時代、ほとんどの駅にあった誰でも利用できるメッセージボードである。
(誰か同級生に見られたら恥ずかしいな……)と思ったが私は思いきって「Y君へ 駅の反対側へ行きます」と書いては移動。そして戻る、そんなことを繰り返した。
しかし1時間経っても彼は姿を見せない。
Y君に何かあったんじゃないだろうか? 事故?
今度は伝言板を「Y君へ、電話ボックスへ行くね」と書き変え、思いきって彼の家に電話したが誰も出ない。
2時間が過ぎた。
心配は次第に哀しみへと変わった。
(私、すっぽかされたんだ……)
(こんなブラウス着てくるんじゃなかった……)
Y君から誘ったのに、なんなんだ。張り切っていた自分が情けない。
私はまた伝言板に向かった。
「Y君へ、2時間待ったけど帰ります」
その夜、やっとY君から「約束の日を1週間間違えていた、ごめん」と電話があった。
「私2時間も待ったんだからね……」
「ほんとうにごめん」
「……」
その後、彼からの手紙はもう届かなかった。
私たちの幼い交際は終わった。
あれから私はさまざまな人たちと数多くの手紙を交わしてきた。
好きなひと、友人、家族、恩師……。
「手紙」というツールはただの伝達手段のひとつではない。
書くために相手のことを想い、言葉を選び、したためる。
何度も書いては破り書き直す。そして投函してから相手に届くまでの時間にまた想う。
あのひとはこの手紙を読んでどんな顔をするのだろう?迷惑じゃなかったろうか……。
返事をくれるだろうか?
アナログな「手紙」は手間も時間もかかるが、例えば恋人であるならその手間暇をかけることで相手への想いを熟成し、時にはその予感や余韻に酔うこともできる特別なツールなのではないだろうか。
だからこそ、私は大切なひとには今でも「手紙」を送る。
LINEやメールには入りきらない感謝や伝えきれなかった想いを、手書きの文字に込める。
たとえ「アナログ人間」と笑われようとも。
そして今ではもう見かけなくなった伝言板。
スマホひとつで連絡がつく今の時代には、「すれ違い」が生まれない。
けれどこの便利さと引き換えに、私たちは「伝言板」というアナログなツールがくれた、相手を待つという時間やトキメキを失ったのかもしれない。
とは言え、すべてが便利になった今でもアナログにこだわりたいものがある。
私にとってそれは、本。
本を読むことが何より好きな私はKindleも使うし、Audibleも利用する。
Kindleの軽さや手軽さや、家事をしながら歩きながら聴くことのできるAudibleの便利さ。
こんな時代が来るなんて!
始めた当初は本当にワクワクした。
でも、なんだろう。私だけの悪い癖なのかもしれないが、デジタルものを最後まで読み(聞き)切れない。
たくさんコンテンツがあることに目を奪われ、じっくりとひとつの作品に集中して読了できないのだ。
そして書店好きの私としては悲しいことに今は書店の数がどんどん減少している。
統計によるとここ20年でその数は約半分になってしまったという。
この原因は書籍のデジタル化だけではない。
とくに若年層を中心に「本を読まない人」が増えているせいだ。
電車の中を見渡せば、本を読んでいる人などほとんどいない。
スマホで動画を見たりゲームをする人ばかりだ。
昭和生まれの私が嘆いたところで現状は変わらないが、読書する楽しさ、そしてアナログの「紙の本」にはデジタルでは味わうことのできない奥行きがあることを知って欲しい。
とにかく書店好きの私は、暇さえあれば書店をうろつく。
たとえ旅先の小さな店でも、入らずにいられない。
そしてこれはと思う1冊、時には数冊を選び、いそいそと持ち帰る。
コーヒーを淹れてソファに深く躰を沈め、新しいページを開く時の喜び。
ページをめくる手触り、文字を目で追いながら頭の中で“自分の声”で読む感覚、気になるところに付箋を貼り、栞を挟んで閉じるまで。
その静かで満ち足りた時間は何よりも贅沢なひとときに感じる。
デジタルでは味わえない「読んだ」という実感が、そこにはあるように思う。
私にとって読書とは、ただの娯楽ではない。
幼い頃、読書家の父は私に本だけは豊富に与えてくれた。
両親とも「本」とは呼ばず「御本(ごほん)」と呼び、うっかり畳の上にある本をまたいだりしたら叱られた。
本は尊いものとして教えられたのだ。
決して裕福な家ではなかったが私のために父が毎月1冊ずつ買ってきてくれた「少年少女世界名作文学全集」。
「小公女」「ひみつの花園」「ああ無情」「若草物語」「あしながおじさん」……。
綺麗な箱に入ったその分厚い本を父の手から受け取る時がとても嬉しかったのを覚えている。
本の中には私のおよそ知らない世界が広がっていた。
屋根裏部屋で暮らす小公女セーラ、秘密の花園を見つけたメアリー、一切れのパンを盗んだことから人生の荒波にのまれるジャン・バルジャン、4人姉妹の次女で男勝りのジョー、孤児院で暮らすジュディ……。物語の主人公は私の頭の中で泣き、笑い、街を駆け抜けた。
私も一緒になって泣いたり笑ったりドキドキした。
それらの名作は後にアニメや映画になって楽しむことはできたが、本から想像する世界は私だけのもので、もっと自由でわくわくした気がする。
小学校から帰ると夢中で本にかじりついている私を、父は嬉しそうに眺めていたっけ。
紙の本は幼い私にとって、きっともうひとりの友だちだったに違いない。
ところで、いま小学校ではすでに1年生のうちから1人1台iPadなどのタブレットが配られるという。
動画教材やデジタルドリル、宿題もオンラインで提出することもあるらしい。
そして授業もコロナ渦をきっかけに「オンライン授業」が広まった。
調べものも辞書ではなく、検索ボックス。
はあ……。
時代はここまで進んだのか。
孫から「ばあば、これはねこうするの」と教えられる日もそう遠くない気がする。
それでもアナログの良さを充分知っている私としては、その尊さを伝えたくなる。
だからできるだけ、絵本を読んで聞かせている。
先日は逆に、ひらがなを覚えたばかりの孫がたどたどしく私に「つるのおんがえし」を読んでくれた。
ついこの間までオムツをしていたのに……とその成長にまた目を細める。
そんな時間はアナログならではの宝物の時間だ。
タブレットで問題を解き、検索で答えを見つけ、動画で知識を得る。
それはそれで効率的だし、これからの時代に必要なスキルなのだろう。
けれど、ひとつの問いに時間をかけて悩んだり、辞書のページをめくってようやく探し当てた言葉に「やった」と小さくガッツポーズしたり、
私たち世代にはそんな“まわり道”の中で育まれてきたものが、確かにあったように思う。
アナログは、決して古いだけのものではない。
手で書くこと、手でめくること、誰かを思い浮かべて手紙やカードをしたためること。
そのすべてに、私たちの「心の速度」が宿っている。
便利になった世の中に助けられながらも、私はこれからも、紙の本を読み、手紙をしたため自分なりの「アナログな日々」を大切に生きていきたいと思っている。
□ライターズプロフィール
マダム・ジュバン(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
本と書店が好きすぎて、とあるブックカフェで働く。
マダム・ジュバンの由来は夫からの「肉襦袢着てるから寒くないよね」というディスリから命名。春になってもジュバンが脱げない60代。
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00





