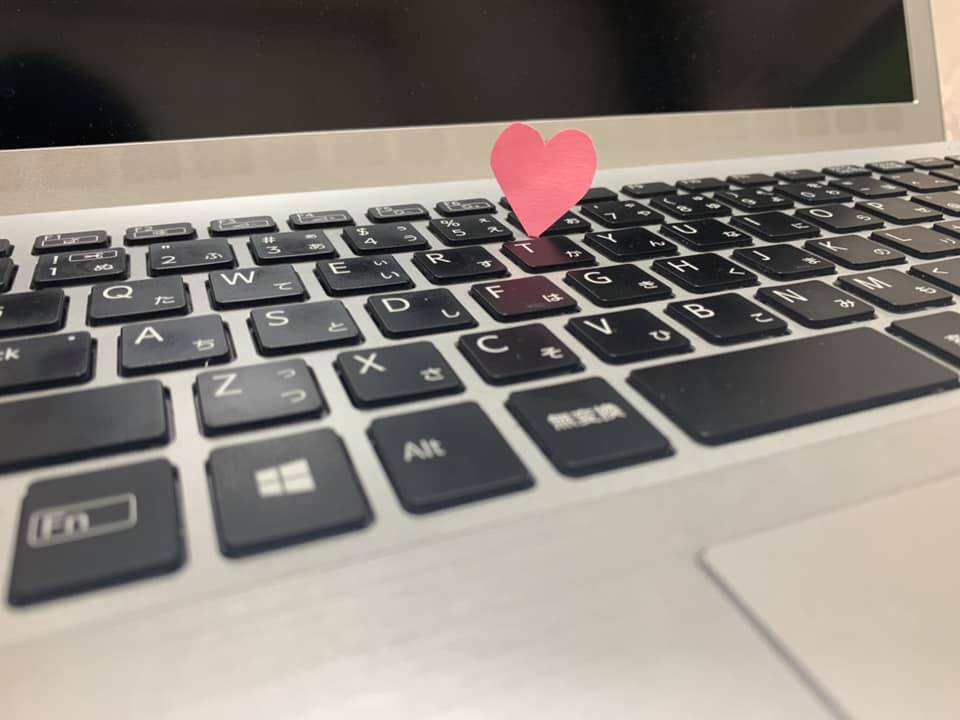ダイアン・キートンに似た乙女《週刊READING LIFE Vol.31「恋がしたい、恋がしたい、恋がしたい」》

記事:高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
お世話になった方に勧められて百貨店に就職した。
右を向いても左を向いても、20代前後の女性ばかりだった。社員だけでなく、お手伝いの派遣社員の大半も女性だった。
仕事中だけでなく、休憩時間で彼女たちとコミュニケーションが取れないと途端に仲間はずれにされた。
オン、オフとも女性との関係性が重視されていた。
中学高校と男子校だった。大学の学部は商学部で1クラスに女性は4人だけだった。
体育会の陸上競技部では、部員は男性だけだった。
男性中心の社会で育ってきた私にとって、女性の集団は初体験だった。
そんな自分でも大学時代、恋い焦がれていた女性はいた。
ひとつ年上の陸上競技選手だった。走る姿がまるでカモシカのようだった。高校時代にアジア大会で3位になった彼女は陸上競技界のヒロインだった。
無名の自分は彼女にアプローチして何回かデートもした。
しかし、大学2年のときに思いっきりフラれたことで、自分は恋愛には不向きだと思っていた。
女性に話しかけることすら、緊張感からなかなかカンタンではなかった。
故 城山三郎先生はエッセイの中で、「社会人になるということは、選べない人間関係のなかに入ること」書かれている。
私としては選べない以前の問題だった。
仕事を覚える以上に大切なことは、日々の女性との人間関係だった。
開店前の準備をはじめ、仕事中、さらには休憩時間のなかで、ひとりひとりに「どうやってリアクションしたらいいんだろう」とばかり考えていた。
恋愛に偏差値があるとしたら、限りなく低く測定不可能なレベルだった。
そんな人間が百貨店に就職するということで、OB、同期、後輩から声を揃えて「よせばいいのに」と言われた。
学生時代の恩師からは、「おまえは不器用だから、女性には気をつけろ」とだけ言われていた。
身体も心も硬いままだった私に比べて、同期の何人かは入社と同時に狙いを定めて社内恋愛を始めていた。
先輩社員の大半は、社内恋愛で結ばれた方たちだった。
当然のことながら、既婚、未婚を問わず、職場内の恋愛も活発で、カップルは次から次へと誕生していた。
職場内の男女の関係は、フランクさ以上だった。
ボディタッチについては、許される相手となら公然とまかり通っていた。
店舗の開店前、平気で女性社員の肩に手をかけて会話する先輩がいた。
ある先輩から「おまえなぁ、あいつ(同僚女性)の肩くらい抱いてやれよ」と忠告されたことがあった。
今だったら、間違いなくセクハラで訴えられるアドバイスだ。
百貨店で勤務する人間にとって、休みが土日でない以上、自ずと交友範囲は限られている。
社長をはじめ、大半の取締役や会社の上層部も社内恋愛した末の結婚だった。
20代後半になっても女性に縁のないことから、「おまえ彼女いないのか?」と不思議がられた。
そんな私でも、29歳のときに結婚することになった。知人の紹介だった。
社外の相手ということで、周りから話題になった。
「やっぱりな。あいつって社内では(相手を)見つけられないからな」といううわさも耳に入った。
どんな形であれ、30歳を前に縁があってホッとした。
職場では、ロマンスグレーの50代の上司が30歳の女性社員と不倫をしていた。
そんな姿を見ながら、自分のような器用ではない人間ではあり得ないと思い始めていた。
38歳のとき、1月15日に母を膵臓がんで亡くした。
2ヶ月経っても自分の中でポッカリと穴が空いたような感じが続いていた。
家庭生活では、長男は幼稚園の年長、次男は年少となっていた。
仕事では平凡な百貨店マンとしての毎日が続いていた。
職場は支店のなかで一番の赤字店で、仕事はお客さまサービス部門だった。
店舗の環境から努力が報われにくい環境だった。
周りの女性は40代以上の中高年ばかりになっていた。
ベテランの女性たちは、キャピキャピしない分、落ち着いていた。
ファーストコンタクトさえ誤らなければ。これほど心強い相棒たちはいなかった。
その年の4月だった。
何の気なしにオフィスのあった8階フロアを歩いていたとき、視界のなかで何かがピンときた。
それは紳士用品のバーゲン会場だった。
20代前半の女性社員がワゴンケースの脇でたたずんでいた。
ベテランの販売員だったら、お客さまの姿を求めてキョロキョロするところだが、彼女はボーッとしていた。
ひと目見て新入社員だと分かった。
そして自分のなかで1つの妄想が広がっていた。
(ダイアン・キートンの20代の頃ってこんな感じだったのかなぁ)
なぜだったかわからない。
彼女をオスカー女優にたとえていた。
しかも新入社員である。無意識が感じていたとしか言いようがない。
その翌日だった。
元部下の女性が私のもとに来た。
「今年の新人で体育会の陸上競技部出身者が1人いるんです。それも女性なんです」
体育会陸上競技部出身の私に対して、わざわざ情報を持ってきてくれた。
高校時代に全国ベスト2になった逸材で、出身大学は中央大学という。
中央大学の女子陸上競技部といえば、かつてオリンピック選手を輩出した名門中の名門である。
そのなかのアスリートである。
(だれだろう?)
陸上競技がとりもつ縁(えにし)である。無性に会ってみたくなった。
「彼女ですよ」
指さした10メートルほど先を見てハッとした。
前日見た、あの”ダイアン・キートン”だった!!
同じ社内である。開店中であったが彼女に向って歩き始めていた。
挨拶するのに躊躇しなかった。
「(部門は異なるけど)よろしく」と言った。
陸上競技の専門は私と同じ(彼女は七種競技、自分は十種競技)だった。
考えてみれば入社以来、女性に対して自分から積極的に声をかけた経験はなかった。
「何かあったらいつでも言ってね。同じ競技者どおしなんだから」
(オレって、こんなセリフ言っちゃって良かったかな?)
自分でも信じられなかった。
彼女のニックネームは「ウッシー」だった。
別にネス湖の恐竜にちなんでのものではない。
牛山(仮名)の頭文字のウシを取って、ウッシーと呼ばれていた。
その日からだった。
入社17年目で初めて会社に行くのがこんなにワクワクし始めた。
15歳年下で、しかも所属は同じ部門でもないのに、「彼女が会社にいる」というだけで気持ちがウキウキしていた。
心が解放され、喜びを感じ始めていた。
今までは自分のセクションだけを巡回するだけだったが、いつしか彼女がいる5階フロアに行くようになった。特に担当する紳士肌着コーナーを回るのが1日のルーティーンになっていた。
言葉は交わさなくても彼女の姿を見るだけで満足だった。
挨拶だけで、その日が輝きを増していた。
接客をしている彼女が慣れない品物のラッピングをしているときだった。
部外者でありながら衝動的にカウンターのなかに入った私は、「ちょっと貸してみな」と言うやいなや品物を包み始めていた。
そのセクションの上司がムッとしながら、
「なんで、おまえがここにいるんだよ?」と言ってきた。
「お客さまがいらっしゃるから当然でしょ」
と笑いながら返していた。
自分にもこんなサービス精神があったなんて信じられなかった。
すべては、ウッシーがいたからこそだった。
ほどなくウッシーを食事に誘った。
彼女の同期も一緒にということにした。
もとより、人見知りな私である。
3人なら会話も途切れないだろうと思ったからだった。
最初の会食は横浜中華街の北京飯店だった。
社会人なりたての2人を見ながら、自分にもこんな時代があったんだなぁと思った。
そんな経験は初めてだった。
いつしかウッシーの存在が仕事のやりがいになっていた。
彼女たいるだけで白黒だった毎日の仕事に、彩りが加わった
毎日の服装に気を使うようになった。いつしか男性向けのファッション雑誌も読むようになった。
会食用に、会社付近の飲食の施設を歩き始めていた。
彼女たちの同期全員を集めての食事会も実施した。あくまでも先輩風を吹かしているようで、お目当てはウッシーだった。
その反面、冷静に考えてみた。
相手にとってみれば私は単なる会社の先輩にしか過ぎない。
彼女にとっても自分にとっても、ほんとうに良い関係性ってなんだろう?と思い始めていた。
「好きだからこそ、その関係を大事にしたい」
うまく説明ができないがウッシーの幸せを考え始めていた。
ある夏の休日の午後だった。
昼寝から起きた直後のぼーっとしているとき、突然、「彼女が幸せになるには?」という感情が降りてきた。
なぜだったかはわからない。
ほぼ同時に銀座支店の総務部で働いている陸上競技部の後輩、青島(仮名)の顔が浮かんだ。
「そうだ、あいつって今⁉」
と思うやいなや、無意識に銀座店の大代表に電話をしていた。
2時間後、私は銀座店別館地階のカフェで青島と相対していた。
別にこちらから質問したわけではなかったが、青島はいきなり話しだした。
「最近、友人たちの結婚式に出ることばかりでねぇ」
「じゃ、心がけさせてもらうな」
2ヶ月後、自由が丘のイタリアンレストラン『キャンティ』で、青島とウッシー、私と3人で食事をした。
食後、青島とウッシーは日吉に行った。
彼女の実家は日吉だった。
駅前には青島にとって学生時代に汗を流したグラウンドがあった。
「これでいいのだ」
なぜか納得している自分がいた。
3年後、2人は結ばれた。
私にとって自分の結婚以上に嬉しいできごとだった。
現在浜松で写真館を経営している2人には、大学3年生を頭に3人の子どもがいる。
「結婚して35年、あなたは外に女も作らずに尽くしてくれましたねぇ」
数日前、家内から言われた。
そんなつもりはなかった。
いや、私だって派手な恋愛に憧れたことがあった。
縁というか、自分の持って生まれたものだったのかもしれない。
ただし、あのときは間違いなく感情が解放される時間だった。
とんち物語で有名な一休禅師は最晩年、自分より40歳以上も若い尼僧と恋に落ちた。
余命幾ばくもないなか、弟子からの「末期の言葉を」という問いに対して、たったひとこと
「死にとうない」
と答えたという。
年齢を問わず恋愛は、人に限りない希望とエネルギーをもたらしてくれるのかもしれない。
❏ライタープロフィール
高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
ベストメモリーコンシェルジュ。
慶應義塾大学商学部を卒業後、三越に入社。
販売、仕入をはじめ、24年間で14の職務を担当後、社内公募で
法人外商を志望。ノベルティ(おまけ)の企画提案営業により、
その後の4年間で3度の社内MVPを受賞。新入社員時代、
三百年の伝統に培われた「変わらざるもの=まごころの精神」と、
「変わるべきもの=時代の変化に合わせて自らを変革すること」が職業観の根幹となる。一方で、10年間のブランクの後に店頭の販売に復帰した40代、
「人は言えないことが9割」という認識の下、お客様の観察に活路を見いだす。
現在は、三越の先人から引き継がれる原理原則を基に、接遇を含めた問題解決に当たっている。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/82065