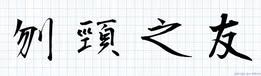“普通”を取り戻すことは、なぜこんなにも尊いのか――お箸と仕事と化粧が教えてくれたこと《週刊READING LIFE Vol.315 『普通』って何だろう?》

*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/7/17/公開
記事:内山遼太(READING LIFE編集部 ライターズ倶楽部)
「先生、”普通”になりたいんです」
その日、リハビリテーション室で六十代の男性患者さんが、私にそう言った。脳卒中を患って三ヶ月。右半身に麻痺が残り、これまで当たり前にできていたことの多くが、今はできなくなってしまった。
私は作業療法士として、彼の言葉に応えようと口を開きかけて、しかし言葉に詰まった。
“普通”って、何だろう?
誰が決めるのだろう、”普通”を?
作業療法士という職業を知らない人は多い。簡単に言えば、病気や事故、生まれつきの障害によって「できなくなったこと」を「できるようにする」ことを支援する仕事だ。手足の動きを改善したり、日常生活の動作を練習したり、時には職場復帰に向けた訓練も行う。
私たちが日々向き合うのは、「昨日まで当たり前にできていたことが、今日はできない」という現実と格闘する人々だ。歯を磨く、シャツのボタンを留める、コーヒーカップを持つ。健常者にとっては意識することすらない、これらの動作が、突然「特別なこと」になってしまう。
そんな患者さんたちが口にするのが、「普通の生活に戻りたい」という言葉だ。初めてこの仕事に就いた頃は、その言葉の重みを理解していなかった。「普通」なんて、誰にでも共通する基準があるものだと思っていた。
しかし、十年以上この仕事を続けてきて分かったのは、”普通”は千差万別だということだった。ある人にとっての”普通”は、別の人にとっては”特別”で、またある人にとっては”物足りない”ものかもしれない。
田中さん(仮名)は、私が忘れられない患者さんの一人だ。五十八歳の会社員で、脳梗塞により左半身に麻痺が残った。利き手である右手は使えるものの、両手を使う動作が困難になってしまった。
初回面談で田中さんが最初に口にしたのは、「お箸で食事がしたい」という願いだった。
「スプーンやフォークでも食べられるんですけどね」と田中さんは苦笑いを浮かべた。「でも、やっぱりお箸で食べたいんです。家族と同じように」
田中さんの奥様は、「スプーンでも十分よ」と言ってくれる。お子さんたちも「お父さんが元気でいてくれるのが一番」と言ってくれる。周囲の人々は皆、田中さんを受け入れてくれていた。
それでも田中さんは、お箸にこだわった。
「これまで五十八年間、お箸で食事をしてきたんです。それが僕の”普通”なんです」
リハビリは困難を極めた。左手で茶碗を支えながら、右手でお箸を操作する。健常者なら無意識に行っている動作を、田中さんは一つ一つ意識的に学び直さなければならなかった。
お箸の持ち方から始まって、豆をつまむ練習、麺をすくう練習。何度も何度も繰り返した。お箸を落とし、ため息をつき、それでも翌日にはまた練習台に向かった。
三ヶ月目のある日、田中さんがついに一人でお箸を使って完食できた日があった。練習用の小さな豆腐を最後の一片まで、きれいに食べ終えた時、田中さんの目に涙が浮かんでいた。
「先生、”普通”って、こんなに嬉しいものだったんですね」
その時私は気づいた。”普通”とは、決して「当たり前」ではないのだと。むしろ、とても特別で、尊いものなのだと。
山田さん(仮名)は、交通事故で脊髄を損傷し、車椅子での生活を余儀なくされた三十二歳の男性だった。事故前は建設現場で働く職人で、体を使う仕事に誇りを持っていた。
「俺の”普通”は働くことなんです」
山田さんの”普通”への道のりは、田中さんとはまた違った困難さがあった。体の機能を元に戻すことはできない。だからこそ、新しい”普通”を見つけなければならなかった。
パソコンの操作から始まり、事務作業のスキルを身につけ、最終的には建設会社の現場管理という新しい職種に就くことができた。現場には出られないが、図面を読み、工程を管理し、職人たちと連絡を取り合う。
「体の使い方は変わったけど、建設の仕事に関わり続けることができた。これが僕の新しい”普通”です」
山田さんの笑顔を見た時、私は”普通”というものの柔軟性を知った。”普通”は固定されたものではなく、その人の人生に合わせて変化していくものなのだと。
佐藤さん(仮名)は、パーキンソン病を患う七十歳の女性だった。手の震えが強く、細かい動作が困難になっていた。佐藤さんにとっての”普通”は、毎朝の化粧だった。
「若い頃から六十年間、毎日欠かさず化粧をしてきたの。人に会う時は、きちんとした姿でいたいのよ」
佐藤さんにとって化粧は、単なる身だしなみではなかった。それは社会とのつながりであり、女性としての誇りであり、他者への敬意の表現でもあった。しかし、手の震えでアイラインは引けない。口紅もうまく塗れない。
「鏡を見るたびに、『この人は誰?』と思ってしまうの」
私たちは一緒に、佐藤さんに合った化粧法を探した。震えても使いやすい化粧品を選び、短時間でできる手順を考えた。完璧ではないけれど、佐藤さんが「これなら外に出られる」と思える方法を見つけることができた。
「先生、ありがとう。またお友達に会いに行けるわ」
佐藤さんの言葉から、”普通”とは個人的な満足を超えた、社会的・文化的な営みでもあるのだと気づかされた。
これらの経験を通して、私は”普通”というものの本質を考えるようになった。健常者の私たちが何気なく過ごしている日常は、実はとても恵まれた、特別な状態なのかもしれない。
朝起きて、歯を磨いて、服を着て、朝食を食べて、仕事に向かう。帰宅して、夕食を作って、お風呂に入って、眠りにつく。これらの一連の動作を、何の困難もなく行えるということは、実は奇跡的なことなのではないだろうか。
患者さんたちと向き合う中で、私は自分自身の”普通”も見つめ直すようになった。毎朝コーヒーを飲めることの幸せ。家族と同じ食卓を囲めることの喜び。好きな服を自分で選んで着られることの自由。
これまで当たり前だと思っていたことが、実はどれほど貴重なものだったのかを、患者さんたちが教えてくれた。
作業療法士としての経験を重ねる中で、私の仕事の本質が見えてきた。それは、単に身体機能を回復させることではない。医学的な目標を達成することでもない。「その人が大切にしてきた生活を、可能な限り取り戻す手伝いをする」ことなのだと思う。
田中さんにとってのお箸は、家族との食卓を共にするための道具だった。山田さんにとっての仕事は、社会とのつながりを保つ手段だった。佐藤さんにとっての化粧は、他者との関係性を築くための文化的な営みだった。
一人一人が大切にしてきた「生活の核」は違う。それぞれに深い意味があり、それぞれに物語がある。私たちの役割は、その人だけの「生活の核」を理解し、それを実現するための道筋を一緒に歩むことなのだ。
この仕事を始めてから、私は「普通とは何か」という問いを常に胸に抱いている。街を歩いていても、電車に乗っていても、ふと思う。今、何の困難もなく歩いている自分の足。当たり前に握っている吊り革。これらはすべて、失って初めてその価値に気づくものなのかもしれない。
健常者である私たちの”普通”は、実は非常に恵まれた状態なのだ。しかし、だからといって「感謝しなさい」と言いたいわけではない。むしろ、”普通”であることの意味を、もう少し深く考えてみてもいいのではないかと思うのだ。
私たちが何気なく過ごしている日常が、誰かにとっては憧れの的であり、目標であり、夢である。そのことを知ることで、私たちの日常はより豊かな意味を持つのではないだろうか。
「普通になりたい」と願う人たちと向き合う仕事を続けて十年以上。時々、なぜこの仕事を選んだのだろうと考えることがある。
答えは、”普通”が生まれる瞬間に立ち会えることの感動にあると思う。
田中さんがお箸で最後の一片を口に運んだ瞬間。山田さんが新しい職場で初めて「お疲れさま」と声をかけられた瞬間。佐藤さんが化粧を終えて「今日はお友達に会いに行くの」と微笑んだ瞬間。
これらの瞬間は、決して劇的なものではない。しかし、そこには確かに人生が輝く光がある。失われたと思った”普通”が戻ってくる瞬間、あるいは新しい”普通”が生まれる瞬間。そこに立ち会えることが、この仕事の最大の喜びなのだ。
「普通って何だろう?」という問いに、明確な答えはないのかもしれない。しかし、この仕事を通して一つ確信を持って言えることがある。
“普通”とは、その人が自分らしくいられる状態のことなのだ。
そして、”普通”とは決して当たり前ではない。それは特別で、尊く、時には奇跡的なものなのだ。なぜなら、それを取り戻すために、新しく見つけるために、懸命に戦っている人たちがいるからだ。
今日も私は、”普通”になりたいと願う人たちと向き合っている。その人だけの”普通”を一緒に探しながら、私自身も自分の”普通”を見つめ直し続けている。
きっと明日も、新しい”普通”との出会いが待っているのだろう。
□ライターズプロフィール
内山遼太(READING LIFE ライターズ倶楽部)
千葉県香取市出身。現在は東京都八王子市在住。
小学生の頃、鹿島アントラーズの選手たちの不屈のプレーに心を打たれ、「自分もこんなふうに誰かの力になれる人になりたい」と思うように。高校時代には、表舞台を支える仕事に魅力を感じ、作業療法士の道を志す。
大学卒業後は、終末期医療の現場で神経難病の方々のリハビリに携わり、現在はデイサービスにて、生活期高齢者への予防的リハビリを提供。作業療法士としての実践に加え、終末期上級ケア専門士・認知症ケア専門士としての知識も活かしながら、「その人らしい生き方」を支える支援に取り組んでいる。
また、新人療法士向けのセミナー講師としての活動や、日々の現場で出会う「もう一度◯◯したい」という願いを形にするための執筆活動にも力を注いでいる。
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00