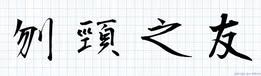普通という名の架け橋 〜違いを超えて通じ合う瞬間〜《週刊READING LIFE Vol.315 『普通』って何だろう?》
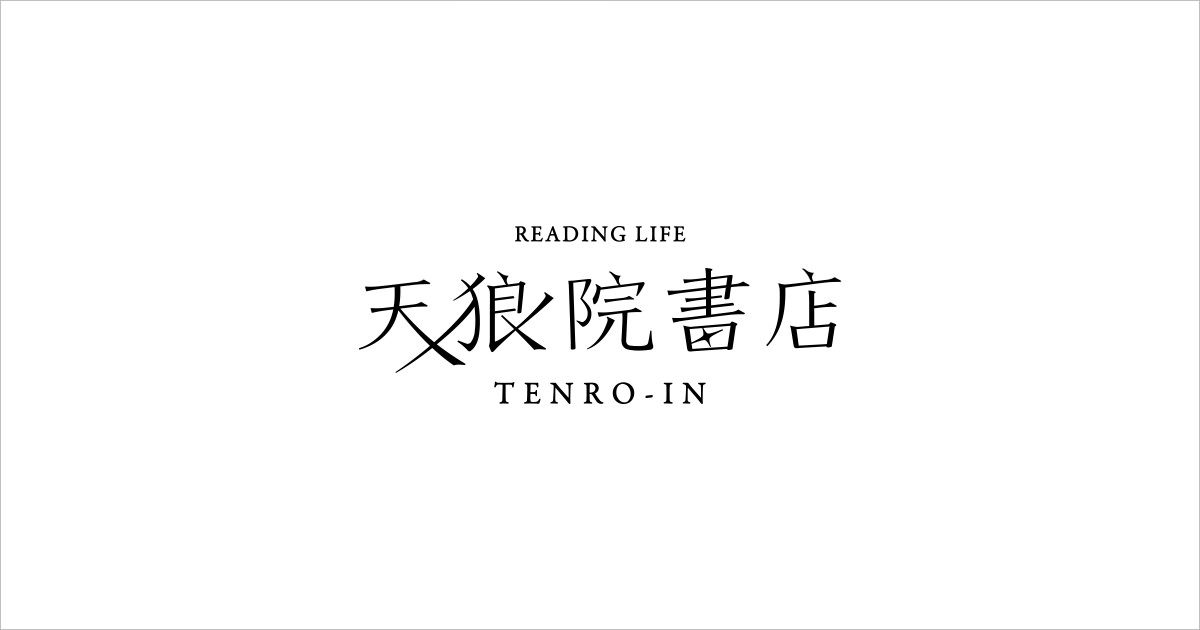
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/7/17/公開
記事:大塚久(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
「大塚さんって、ちょっと“普通じゃない”ですよね」
病院のリハビリ室で、後輩の理学療法士にそう笑われた。
高齢の患者さんに片脚スクワットを教えていた最中だ。僕は膝を深く曲げさせず、重心をほんの少し右斜め前へ移すよう指示していた。
「なぜその角度なんですか?」と尋ねられ、僕は玄関の上り框の高さ、室内階段の段差、手すりの位置、家具の並び……その患者さんの家の間取りを一気に説明した。
「家へ戻った瞬間、真っ先に越えなきゃいけないハードルがそこなんだ。脳には“特異性の原則”があって、本番に近い動きをくり返したほうが神経回路は効率よく書き換わる。だから筋力だけでなく“角度”も実際の場面に寄せたいんだよ」
後輩は目を丸くしたまま肩をすくめた。
「そこまでこだわるなんて……普通じゃないですね」
僕にとっては、研究論文でも裏づけられた“当たり前”——つまり普通のつもりだった。けれど同じ職場でも、誰かの普通は別の誰かの普通じゃないらしい。胸の奥に、ひやりと小さな水滴が落ちた。
「普通じゃない」
この五文字は、ときに勲章、ときに烙印になる。
学生時代の僕はスクールバックを持つ皆と異なり、肩掛けの綿のバックを使い、髪型はまだ今ほど普通じゃなかったおしゃれ坊主頭にしていた、部活を終えた友人たちと帰り道が一緒になるたび「渋いね」と揶揄まじりに笑われた。照れくささもあったが、普通じゃないことが誇らしくもあった。ところが理学療法士として働き始めると、事情は逆転する。“普通”に寄り添えなければ、同僚や患者さんとの信頼関係を築きにくい。それなのに僕は、家の段差や猫の動線まで想像しながらリハプログラムを練る。結果「こだわりが強すぎる人」と思われやすい。勲章と烙印が首のうしろで交差し、しばしば自分の足どりをもつれさせる。
そんな葛藤がピークに達するのが、若手療法士向けに開く研修会だ。
受講生は免許取得1〜3年目が多く、僕とは世代も教育課程も職場規模も違う。開講初日の教室には、エアコンの送風音ばかりがやけに大きく反響する。僕が「一人ずつ自己紹介を」と促しても、声は箸より細い。空気は、静まり返るというより“縮こまる”という質感を帯びる。
そこで僕はひたすら問いを投げる。
「休みの日、何をしてる?」
「地元は?」
最初は誰もが遠慮がちだ。それでも続けると、ふと神奈川のローカル線の名を挙げた受講生がいた。「あ、僕もその沿線です」と別の受講生が応じる。二人の声が半音上がり、肩がふっと下がった。僕はすかさず「その駅前の古い喫茶店、まだあります?」と被せた。すると下を向いていた青年が顔を上げ、「あそこでナポリタン食べました」と笑う。教室の温度が数度上がったように感じられた。おそらくエアコンは同じ設定のままだ。それでも空気はやわらかくなる。共通項という“安心できる一点”に足をかけた瞬間、人は違いをこわがらずに済むのだ。
僕は20年以上リハビリに携わり、つくづく思う。違いを認め合うには、まず小さな共通点が必要だ。
だから患者さんにも、まず家族構成や愛犬の名前を尋ねる。そこに「分かる!」が芽生えたとき、機能訓練の説明がすっと体に入る。僕が角度にこだわる理由も、ただの“変わり者の執念”ではなくなる。
それにしても「普通」という語感は、どうしてこんなに角ばって聞こえるのだろう。少し歴史をさかのぼると、鍵は“定規化”の大波が押し寄せた明治期にある。
近代国家を築こうとした政府は、徴兵制・義務教育・鉄道・郵便、人とモノを一斉に動かす仕組みを整える必要に迫られた。そこでは「標準語」「普通教育」「普通列車」「普通郵便」など、“誰もが同じとみなせる枠”を示すラベルが不可欠となる。漢籍にあった〈普く(あまねく)通じる〉という二文字が、翻訳語として量産され、社会インフラの隅々へ染み込んでいった。
けれど、それ以前の暮らしはどうだったか。江戸の町人も京の公家も、共通の“硬い定規”ではなく、「常(つね)」「例(ためし)」といったゆるやかな経験の積み重ねで物事を測っていた。川の水位を目で追い、「だいたい膝下まで減ったら田植え時分だな」と見当をつける。言葉も方言が主で、隣の藩に越えれば挨拶すら変わる。“空気を読む”文化は、一枚の定規よりも無数の気配を頼りに場を整えてきたとも言える。
背景には、仏教が運んだ「諸行無常」――すべてはうつろうという感性がある。桜は散り、蝉は七日で鳴きやむ。季節も人の命もとどまらない。ならば、永遠に当てはまる“正解”を外からはめ込むより、その瞬間ごとの「だいたい」「ほどほど」で折り合いをつけるほうが肌になじむ。
だからこそ、明治の定規語〈普通〉は便利である一方、どこか異質な硬さを残したのだろう。流れる川に竹尺を差し込み、「水位は何尺何寸」と刻むような――必要だけれど、少しだけ水の自由を奪う手つき。その微かな違和感が、現代の僕らにもまだ響いているのかもしれない。
たとえば季節の俳句は、五七五の器に一瞬の揺らぎを掬い取る。
花びらが散るのも、蝉が鳴きやむのも「常」。だがその「常」は刻一刻と相を変える。日本語はもともと“変わりゆくもの”を抱きしめる柔らかさを持っていたのだと思う。だからこそ、明治以降に押し寄せた「普通」という硬質な定規には、どこかしら文化的軋みが残る。
現代はさらに複雑だ。
学校や会社では服装や髪型など「周りと同じ」が安心のルールだが、スマホを開けば「目立ってナンボ」の世界が広がる。SNSで“映える”ためには、日常を切り取り、彩りを増幅しなければならない。けれど撮影後、冷めたパスタをつつきながら画面を見返すと、空虚な風が胃の底へ吹き込む。高校生の「私、これ、味で選んでないから」という言葉が耳に残る。リモートワークの会議ではジャケットを着込んだ上半身と、スウェットの下半身がカメラの境界で共存する。二つの定規を同時に握らされ、どちらにも合わせきれず漂うのが、いまを生きる僕たちの“デフォルト姿勢”かもしれない。
医療現場にも、定規の衝突がある。
手術後の患者さんは「痛いから動きたくない」と言う。それが患者さんにとっての普通=常識だ。一方、理学療法士の教科書には「早期離床が回復を早める」とある。こちらの普通=エビデンスは、ステージが安定したらなるべく早く動くことだ。二つの普通がぶつかりあい、ベッドサイドの空気が張りつめる。
僕はそんなとき、必ずすり合わせから入る。「痛みがこわいのは分かります。でも、今この腫れ具合なら歩いても悪化しません。歩かない方が筋力低下と肺炎のリスクが上がります」——医学データを示しながら、患者さんの日常目標(自宅トイレまで一人で歩きたい等)を言葉にし直す。互いの定規をゆっくりと重ね合わせ、新しい“暫定の普通”を編み直す瞬間、患者さんの肩がゆるみ、表情がほころぶ。普通は立場によって変わる。だからこそ、編み直す対話そのものがケアになる。
人類史を引いてみれば、集団に合わせる模倣能力は生存の鍵だった。同じ言語を話し、同じ火を囲み、同じ毒キノコを避ける。ところが環境が激変したとき、群れを救ったのは“普通じゃない”挑戦者でもあった。洞窟を出て草原へ踏み出した誰か、海を渡った誰か——協調と逸脱、二つの役割があってこそ種は続く。
ならばいま僕らに必要なのは、「普通」に合わせるか「普通じゃない」を貫くかの二択ではない。出会うたびに暫定的な“架け橋”を編み直し続ける柔らかさだろう。共通点で安心を得たら、違いへ歩み寄る。違いに触れて揺れたら、再び共通項を探す。その往復運動こそが、生きづらさを和らげるかもしれない。
研修会の最終日、受講生たちは小さなグループ発表を終え、互いの成果を拍手で讃え合った。初日の硬直を思い出すと、別の世界のようだ。教室に漂うコーヒーの香り、ホワイトボードのペン先が走る乾いた擦過音、拍手が重ね合わさる弾力……そのすべてが「あ、僕ら少し分かり合えたんだ」と身体感覚で告げてくる。
“普通”は、固定された基準ではない。人と人が出会うたびに生まれる、柔らかい通じ合いの可能性だ。僕が玄関の上り框を思い浮かべてスクワットの角度を設定するのも、その可能性を脳と身体に刻むため。後輩に「こだわりすぎ」と笑われても構わない。だって、それが患者さんにとっての“新しい普通”の橋脚になるかもしれないのだから。
あなたが最近「分かり合えた」と感じた瞬間は、どんな瞬間だっただろう。
肩がふっと下りたときのぬくもり。声が半音上がったときの軽さ。心に浮かぶその感覚こそ、たしかに立ち上がった“あなたと誰かの普通”なのかもしれない。
□ライターズプロフィール
大塚久(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
神奈川県藤沢市出身。理学療法士。RYT200ヨガインストラクター。2002年に理学療法士免許を取得後、一般病院に3年、整形外科クリニックに7年勤務する。その傍ら、介護保険施設、デイサービス、訪問看護ステーションなどのリハビリに従事。下は3歳から上は107歳まで、のべ40,000人のリハビリを担当する。その後2015年に起業し、整体、パーソナルトレーニング、ワークショップ、ウォーキングレッスンを提供。1日平均10,000歩以上歩くことを継続し、リハビリで得た知識と、実際に自分が歩いて得た実践を融合して、「100歳まで歩けるカラダ習慣」をコンセプトに「歩くことで人生が変わるクリエイティブウォーキング」を提供している。
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00