墓場まで持っていくつもりだった話 — 作業療法士として語れなかった五年間《週刊READING LIFE Vol.322「本当は墓場まで持っていきたい話」》
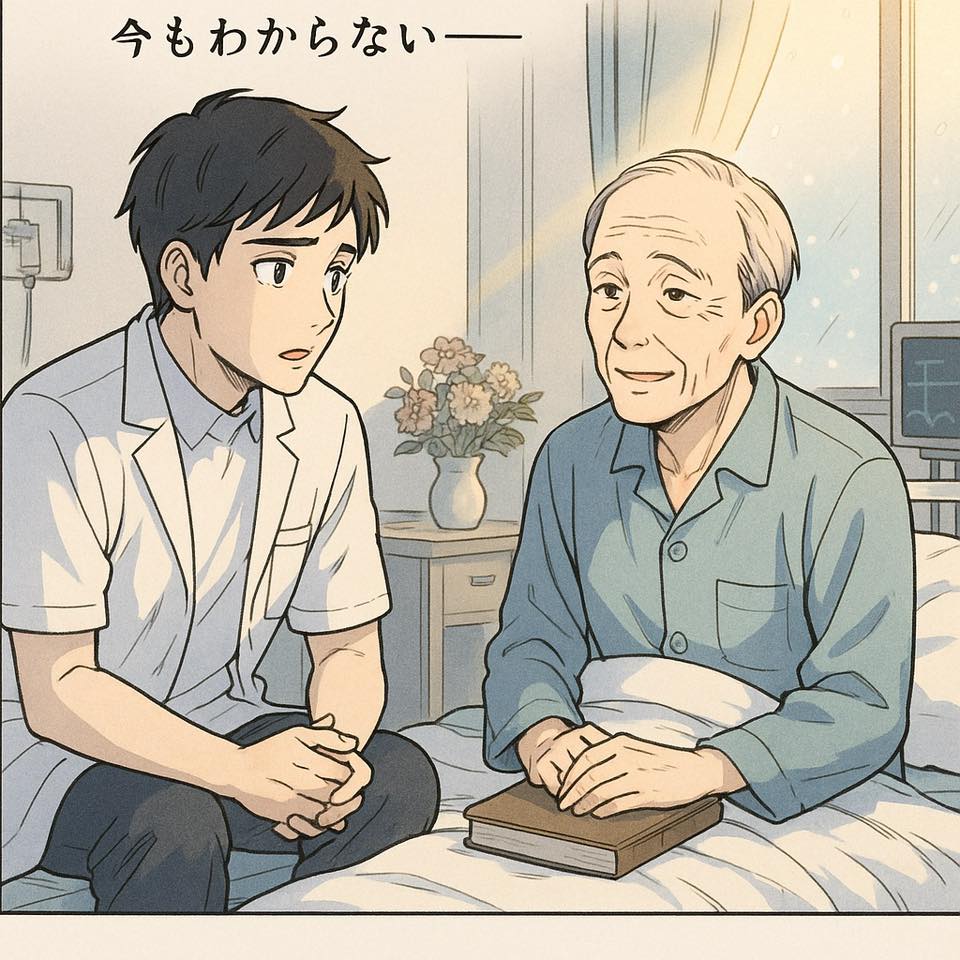
*この記事は、「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
2025/9/4/公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
五年以上、誰にも語ってこなかった。語ることが許されない気がしていた。だが、今も彼の顔が時々、夢に出てくる。
医療者でなくても、誰にでも”語られなかった出来事”があると思う。これは、私にとってのそれだ。
作業療法士として働き始めて七年になる。新人だった頃を振り返ると、まだ手探りで患者さんと向き合っていた自分がいる。教科書で学んだ知識と現実のギャップに戸惑い、先輩の背中を追いかけながら必死にもがいていた。その中で、ひとりだけ、どうしても心の奥に引っかかり続けている人がいる。
彼のことを考えるたび、胸の奥に埋まった感情の地雷が疼く。それは善意と無力感の境界で立ち往生した、ある冬の日の記憶だ。
職場の同僚にも、家族にも、この話をしたことがない。話すべきではないと思っていた。患者の秘密を守ることは、医療従事者の基本的な倫理だから。だが、それだけが理由ではない。この話をすることで、自分の中の何かが壊れてしまうような気がしていた。
墓場まで持っていくつもりだった。けれど最近、この重い記憶が私の中でゆっくりと形を変え始めている。もしかしたら、語ることにこそ意味があるのかもしれない。
あれは作業療法士になって三ヶ月目の、二月の寒い朝だった。私が配属されたのは、終末期医療を専門とする病院だった。ここでは「回復」ではなく、「最期まで自分らしく過ごすこと」が治療の目標とされていた。
新人の私には、まだその意味が十分に理解できていなかった。山田太郎さん(仮名)、六十二歳。膵臓癌の末期で、痛みのコントロールと残された時間を少しでも有意義に過ごすための支援を目的として入院されていた。余命は数ヶ月と告知されていた。
カルテを見ながら、私は緊張していた。終末期の患者さんを担当するのは初めてだった。大学では学んだが、実際にどう接すればいいのか、何を目標にリハビリを進めればいいのか、まったく見当がつかなかった。
初回評価のため病室を訪れたとき、山田さんは窓の外をじっと見つめていた。雪がちらつく灰色の空を、表情を変えることなく眺め続けている。声をかけると、ゆっくりと振り返った。
「作業療法士の内山です。今日からリハビリを担当させていただきます」
私の声は、緊張で少し震えていた。
「ああ、よろしく」
淡々とした返事だった。特別愛想が悪いわけでもないし、反抗的でもない。ただ、どこか遠いところにいるような印象を受けた。まるで、この病室の中に身体だけがあって、心は別の場所にあるような。
評価を進めていくうちに、山田さんの状態が少しずつ見えてきた。身体機能的には大きな問題はなかった。ただ、化学療法の影響で体力は落ちており、疲れやすさを訴えていた。痛みも時々あるようだった。
しかし、何より私を戸惑わせたのは、山田さんの表情だった。怒っているわけでも、悲しんでいるわけでもない。ただ、すべてを受け入れてしまったような、深い諦めのようなものが感じられた。
「リハビリの目標を一緒に決めませんか?」新人らしく教科書通りの質問をする私に、山田さんは苦笑いを浮かべた。
「目標って、何のための目標ですか?」
私は答えに詰まった。終末期の患者さんにとって、目標とは何なのだろう。回復期病棟なら「歩けるようになること」「家事ができるようになること」といった明確な目標があった。しかし、ここでは——。
最初は、癌告知を受けた患者さんによく見られる反応なのかもしれないと考えた。受容の段階に入っているのかもしれない。でも、どう関わっていいかわからなかった。教科書には「患者の意思を尊重する」と書いてあったが、具体的にどうすればいいのか。
先輩の佐藤さんに相談すると、「焦らなくていいよ。まずは山田さんという人を知ることから始めてみて」とアドバイスをもらった。でも、新人の私には、それすらも難しく感じられた。
リハビリを始めて三週間が経った頃、山田さんとの関係は少しずつ変化していた。最初は事務的だった会話に、時々個人的な話題が混じるようになった。
「内山さんは、まだ若いですね」
「はい、新人です。至らないところばかりで申し訳ありません」
「そんなことないですよ。一生懸命やってくれているのがわかります」
そんな会話を交わしながら、私は山田さんの人となりを少しずつ知っていった。元は会社員で、趣味は読書と園芸だったこと。奥様と二人暮らしで、子どもはいないこと。癌が見つかったのは半年前で、それまでは健康そのものだったこと。
ところが、山田さんの表情は相変わらず重いままだった。身体的な痛みは薬でコントロールできているはずなのに、別の種類の苦しみを抱えているように見えた。
ある日のリハビリ中、私は勇気を出して尋ねてみた。
「山田さん、何か心配事がおありですか?」
新人の私が踏み込んでいい領域なのかわからなかったが、このままでは何も変わらない気がした。
彼は長い間黙っていた。そして、ぽつりと呟いた。
「妻のことが心配なんです」
「奥様が?」
「私が先に逝くことになって……妻は一人になってしまう。家のこと、お金のこと、何もわからない人なんです」
その時の山田さんの表情を、私は今でも鮮明に覚えている。愛する人を残していく辛さと、責任感の重さが混じった、複雑な苦悩が宿っていた。
私は慌てて言った。「きっと奥様も、山田さんの心配はわかってらっしゃいますよ。一緒に準備していけば——」
「内山さんは知らないんです」
山田さんは私の言葉を遮った。
「妻は、まだ私の病気の本当のことを知らないんです」
それ以上は何も話してくれなかった。その日のリハビリは、気まずい沈黙の中で終わった。
それ以上は何も話してくれなかった。その日のリハビリは、重い空気の中で終わった。
翌日、私は先輩の佐藤さんに相談した。山田さんの家族状況について、もう少し詳しく知りたいと伝えた。すると、佐藤さんは深刻な表情を見せた。
「実は、山田さんのケースはとても難しいの」
山田さんは、奥様に病名を告知していなかった。「胃の調子が悪いので検査入院している」とだけ伝えているという。奥様は山田さんの帰りを待ちながら、毎日お見舞いに来ていた。
「どうして本当のことを言わないんですか?」新人の私には理解できなかった。
「奥様が心臓に持病を抱えていらっしゃるの。ショックで倒れてしまうかもしれないって、山田さんは心配してるのよ」
私の胸に、重いものが沈んだ。山田さんの苦悩の正体が、少しずつ見えてきた。
愛する人を残していく辛さに加えて、その事実すら伝えられない孤独感。自分だけが真実を抱えて、一人で死に向き合わなければならない現実。
「回復すること」だけを考えてきた新人の私には、あまりにも重すぎる現実だった。
山田さんとの関わりは、一ヶ月を過ぎようとしていた。終末期病院では、患者さんの在院期間に明確な区切りはない。その人のペースに合わせて、最期まで支援を続けるのが基本方針だった。
でも、新人の私には、何をもって「支援」と言えるのかがわからなくなっていた。
チームカンファレンスでは、山田さんの今後について議論が続いていた。医師からは、病状が安定している間に奥様への告知を検討すべきだという意見が出ていた。
「ご本人の心理的負担を考えると、一人で抱え込み続けるのは限界があるでしょう」
看護師長も、ソーシャルワーカーも、みな山田さんのことを心配していた。しかし、最終的な判断は山田さん自身に委ねられていた。
そんな中、私は一つの決断をした。
山田さんと正面から向き合って、本音で話してみようと思ったのだ。新人で経験も浅い私が何かできるとは思えなかったが、せめて山田さんの気持ちを理解しようと努めてみたかった。作業療法士としてではなく、一人の人間として。
ある午後、いつものようにリハビリ室で山田さんと二人きりになったとき、私は切り出した。
「山田さん、奥様への告知のこと、とても悩んでいらっしゃいますね」
山田さんの手が止まった。
「一人で抱え込むのは、本当に辛いと思います」
「内山さんに何がわかるんですか」
山田さんの声は震えていた。でも、今度は怒りではなく、深い悲しみが込められていた。
「私は、わからないんです」私は正直に答えた。「でも、わからないなりに、山田さんの気持ちを理解したいと思っています」
長い沈黙があった。
そして、山田さんは堰を切ったように話し始めた。
奥様との出会いから結婚まで、四十年近い夫婦生活のこと。奥様の心臓の持病がわかったときの心配。そして、自分が癌だと診断されたときの絶望。
「妻には、本当に幸せな人生を送ってもらいたかった。でも、私が先に逝くことで、全部台無しになってしまう」
「台無しって……そんなことないですよ」
「内山さんは若いから、わからないんです。四十年一緒にいた人を失うということが、どれほど辛いか」
私は、その時に無力感を覚えた。確かに私は若くて、結婚もしていない。夫婦の絆や、愛する人を失う痛みについて、実感として理解することはできなかった。
でも、だからといって黙っているわけにはいかなかった。
「でも、山田さん、奥様も山田さんと一緒に残された時間を過ごしたいと思っているかもしれません」
「そんな綺麗事……」
山田さんの言葉に、私の胸が詰まった。新人の私が言えることなど、確かに綺麗事なのかもしれない。でも、ここで黙ってしまったら、山田さんはまた一人で抱え込むことになってしまう。
「綺麗事かもしれません。でも、本当のことを知らないまま別れるのと、真実を共有して最後の時間を過ごすのと、どちらが奥様にとって良いのでしょうか」
私は、新人らしい真っ直ぐな思いを込めて話し続けた。奥様と一緒に告知を受けることの可能性、お二人で残された時間を過ごすことの意味、真実を共有することで得られる絆について。
山田さんは、その時初めて笑った。苦しそうな、でも少し温かい笑顔だった。
「内山さんは、本当に真面目ですね」
その瞬間、私は確信した。山田さんの心に、小さな光が灯ったのだと。
しかし——
三日後、山田さんは急変した。夜中に激しい腹痛を訴え、緊急手術が必要になった。廊下に響く緊急コールの音、慌ただしく走り回るスタッフの足音、手術室へと運ばれていく山田さんの顔——すべてが頭の中でぐるぐると回り続けた。
癌の転移による腸閉塞だった。
手術は成功したが、山田さんの体力は大幅に消耗した。意識も朦朧とした状態が続いた。人工呼吸器の機械音が、静まり返った病室に響いていた。
そして、奥様がついに真実を知ることになった。医師から病状の説明を受けざるを得なくなったのだ。
私の「希望」の言葉が、皮肉にも山田さんを急かしてしまったのかもしれない。告知について考え始めた矢先に、病状が急激に悪化したのだ。
山田さんは手術後、二週間で息を引き取った。最期は奥様に看取られながら、安らかな顔で旅立った。
奥様は、山田さんの本当の病気を知った後も、毎日病室に通い続けていた。ショックは大きかったが、心臓の発作を起こすこともなく、最後まで山田さんを支え続けた。
しかし、私にはどうしても許せない気持ちがあった。
私の未熟な関わり方が、山田さんに余計なプレッシャーを与えてしまったのではないか。告知について悩ませてしまったことが、ストレスとなって病状悪化を早めたのではないか。
その後のリハビリは、先輩の佐藤さんが引き継いだ。私には、もう終末期の患者さんと向き合う自信がなくなっていた。
この出来事を、誰にも話せなかった理由がいくつかある。
まず、患者の秘密を守るという職業倫理。山田さんの個人的な事情や、あの日の出来事を他人に話すことは許されない。
しかし、それ以上に、自分自身を守りたかったのだと思う。
私の関わり方が正しかったのか、間違っていたのか。あの時、希望を語らずにいたほうがよかったのか。それとも、もっと違うアプローチがあったのか。
答えは出ない。そして、答えが出ないことが、何よりも辛かった。
作業療法士として、患者さんの「生活の質の向上」を目指すことが私たちの使命だ。しかし、その「生活」自体に意味を見出せない人に対して、私たちは何ができるのだろうか。
山田さんのケースは、私にとって大きな転換点となった。それまで信じてきた「回復すれば幸せになれる」という単純な図式が、崩れ去った瞬間だった。
五年以上が経った今、私なりの答えが少しずつ見えてきている。
あの時の私の言葉が、山田さんを追い詰めたのかもしれない。しかし、同時に、あの瞬間に山田さんが見せてくれた笑顔も本物だったと思う。
人間の心は複雑で、矛盾に満ちている。希望と絶望、生きる意味と無意味感、愛と孤独——これらは常に隣り合わせに存在している。
私がしたことは、山田さんの複雑な感情のうち、「希望」の部分だけを見ようとしたことだった。それは確かに一面的だったかもしれない。
しかし、だからといって、希望を語ることを諦めるべきではないとも思う。ただ、その希望は、相手の絶望や虚無感を十分に理解した上で、慎重に、謙虚に伝えられるべきものなのだ。
山田さんとの出来事があってから、私の患者さんとの向き合い方は変わった。
以前のように、単純に「回復」を目指すだけではなくなった。その人がどんな人生を歩んできて、何を大切にしていて、何に苦しんでいるのか——そうした背景を、できる限り理解しようと努めるようになった。
そして、「答えを出すこと」よりも、「一緒に考えること」を大切にするようになった。
患者さんの問題を解決することが、必ずしも私たちの役割ではない。時には、解決できない問題を抱えながらも、その人なりの方法で生きていくことを支えることが、私たちにできることなのだ。
山田さんのケースは、私にとって失敗体験だった。しかし、その失敗から学んだことは計り知れない。
完璧な関わり方など存在しない。私たち医療従事者も、不完全な人間だ。間違いを犯すし、傷つくし、迷うことも多い。
大切なのは、その不完全さを受け入れながらも、目の前の人のために最善を尽くそうとする姿勢を持ち続けることなのだと思う。
先日、新人の後輩から「終末期の患者さんとどう関わればいいかわからない」という相談を受けた。その時、山田さんのことを思い出した。
山田さんは二年前に亡くなったと、当時の看護師長から聞いていた。最期まで奥様に支えられて、自宅で過ごしたという。その話を聞いて、少しだけ救われた気持ちになった。
山田さんは、私に大切なことを教えてくれた。希望を語ることの重さと責任。人間の複雑さと向き合うことの大切さ。そして、答えの出ない問題を抱えながらも生きていくことの意味。
今でも、あの時の私の判断が正しかったのかわからない。もう一度あの場面に戻ったとしても、たぶん似たような判断をしてしまうかもしれない。
でも、それでもいいのだと思う。完璧でなくても、迷いながらでも、目の前の人と真摯に向き合うことに意味があるのだ。
私の手帳の奥には、今でも山田さんの名前が書かれたメモがある。そこには、彼から学んだことも一緒に記されている。
「人は答えのない問題を抱えながらも生きていく。私たちの役割は、その人の歩みに少しでも寄り添うこと」
墓場まで持っていくつもりだったこの話を、今ここに記すのは、同じような経験をしている医療従事者がいるかもしれないと思うからだ。
完璧な関わり方を求めすぎて苦しんでいる人、患者さんとの関係で悩んでいる人、自分の判断に確信を持てずにいる人——そんな人たちに、少しでも伝わればいいと思う。
私たちは不完全で、それでも懸命に生きている。それは、患者さんも同じだ。
だからこそ、お互いの不完全さを受け入れながら、それでも諦めずに歩き続けることに意味があるのだ。
山田さん、ありがとうございました。あなたから学んだことを胸に、私は今日も作業療法士として歩き続けます。
❏ライタープロフィール
内山遼太(READING LIFE公認ライター)
千葉県香取市出身。現在は東京都八王子市在住。
作業療法士。終末期ケア病院・デイサービス・訪問リハビリで「その人らしい生き方」に
寄り添う支援を続けている。
終末期上級ケア専門士・認知症ケア専門士。新人療法士向けのセミナー講師としても活動中。
現場で出会う「もう一度◯◯したい」という声を言葉にするライター。
2025年8月より『週刊READING LIFE』にて《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》連載開始。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/8/28/公開
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00





