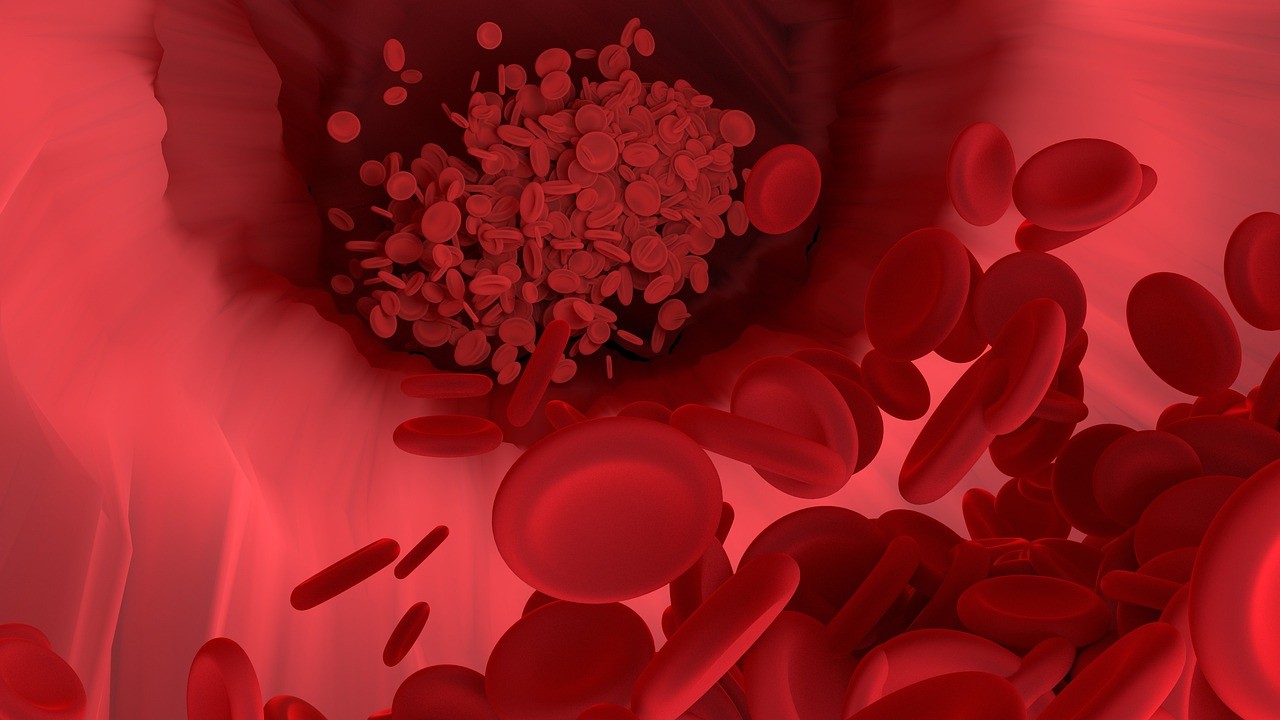自分が作り出していた孤独《週刊READING LIFE Vol.57 「孤独」》
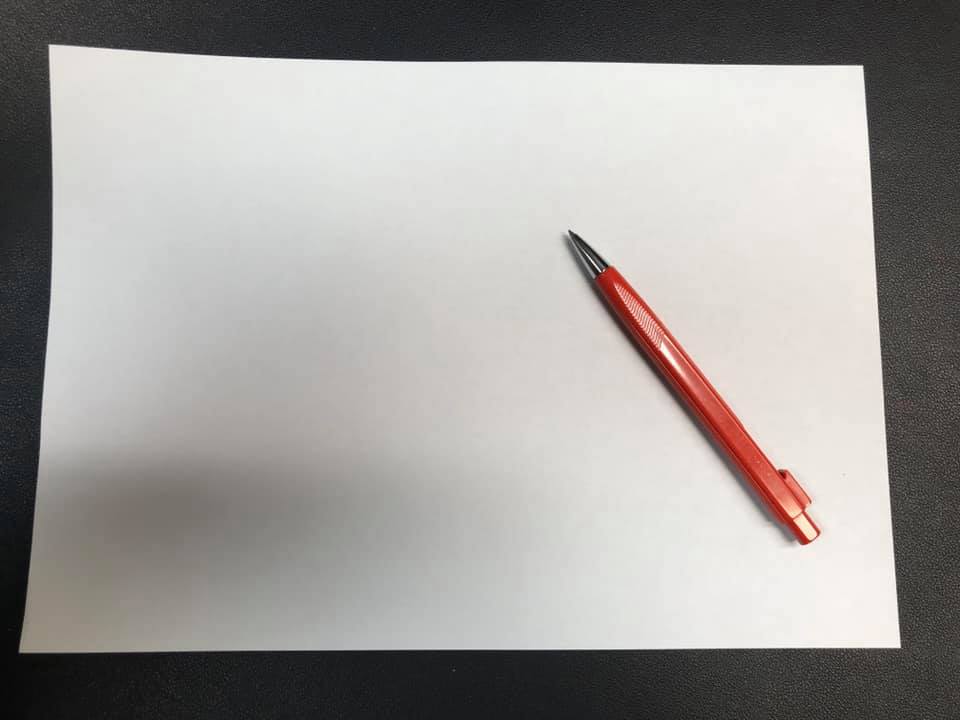
記事:高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
薄暗い地下道を歩いていた。
極力これから始まる日々を考えようとしないでいた。
手には人事異動の辞令を持っていた。
これからの毎日を少しでもイメージしようものなら、不安で押しつぶされそうだった。
それでも微かな言葉が浮かんできてしまった。
「オレには、……」
そのひとことが出るともう止められない。
「オレには、……、オレにはできるわけないよ。だって、……」
堰(せき)を切ったように言葉とシーンと人の声がこだましてきた。
新たな任地への挨拶は、視野狭窄(しやきょうさく)、金縛り状態から始まった。
百貨店に入社したものの、もともと人と接するのは得意ではなかった。
「おまえ、そもそも入る会社間違えたんじゃない?」と上司から言われたこともあった。
そうはいっても、入社した以上、安易に転職に踏み切れるわかではなかった。
ただただ辛抱した。
辛抱して店頭に立ち続けることで、少しずつ慣れがを感じ始めていた。
入社して13年が経とうとしていたときに内勤の辞令をもらった。
販売促進だった。お客さまとの接客の機会はほとんどないセクションである。
異動が決まったときは、一抹のさびしさがあったが、内心で「これでお客さまに気を遣わないで済む」とホッとした記憶がある。
販売促進、スポーツ用品の仕入、計数管理……。気がつくと内勤生活は10年目に入ろうとしていた。このままずっと内勤生活を続けられたらいいよなと思い始めていた。
百貨店である以上、店頭での販売こそが主流である。
しかし、人には向き不向きがあるもの。
このまま、得意ではない接客をしないで、デスクワークで働いていけたらいいんだと勝手に解釈していた。
そんな矢先である。上司から人事異動を告げられた。
所定の時間の10分前に総務の会議室に出向くと、辞令を受ける社員であふれていた。
しばらくすると人事の担当者に整列を促された。
立ち位置は、辞令の呼ばれる順番である。
私は会議室の演台に向かって一番左側の列の中程になった。
定刻と同時に社長が入ってきた。
社長の後ろには、辞令を持った人事部長が、まるで芸能人の付き人のように付いている。
自分の運命が決まってしまうような絶望感にさいなまれはじめた。
「では、始めます」
演台に立った社長は辞令を読み上げ始めた。
名前と異動先の部署名を言って、辞令を手渡すだけ。
そこには、こちらの感情への配慮もなにもない、極めてシンプルな儀式である。
「来るな来るな」と思いながらも、私の番は来た。
「本店食品部セールスマネージャーを命ず」
社長の声は機械的だった。それ以上でもそれ以下でもない。終わりだった。
辞令を受け取った以上、それに従うしかない。
行きたくない仕事であり部署だった。
理由は未経験だったからである。
アパレルや、スポーツ用品なら販売したことはある。
ただし今度は、口に入るものを扱うのである。
衛生面の業務知識が必要なことは容易に想像がつく。
販売する以前に、品物の知識、衛生面の知識、そして慣習などゼロから学ばなければならないことばかりである。
一番は自分が行う仕事がまるで想像できないことだった。
辞令を持って食品の販売の事務所にあいさつに行ったところ、担当は輸入食品の販売の責任者と知らされた。
扱い商品は多岐にわたっていた。英国ハロッズから直輸入された紅茶、ジャム、フランスのダロワイヨの国内でライセンス生産された菓子、パン、惣菜、そして30席ほどのティーサロンが2ヶ所である。
仕事を聞かされながら、自分のなかでは、言い訳モードが高まるばかりだった。
「経験していないんだ」
「販売ブランク10年なんだ」
「人間関係だって、誰一人知らないんだ」
3日後には、このセクションで働き始めるのである。
「できる」前提で始めようなんて気持ちは微塵もないのである。
しかし、時間は待ってくれない。
事務所のあとは、自分が担当する輸入食品コーナーにあいさつにいった。
営業時間中である。お客さまが次から次へとひっきりなしにご来店されている。
ご用命もご自宅使いから、ギフトのラッピング、景品としてのご注文などさまざまである。
「現場の仕事って、いったい何だろう?」
そして、自分はどんな働きをすればいいのか?不透明感は高まるばかりである。
しかし聞こうにも、私にとって前任者となる責任者は不在だった。
仕事の流れも知らないままで不安いっぱいだが、ひとまず社員一人一人へのあいさつをすることにした。
「やけに女性社員が多いんだな」
それもそのはずだった。
責任者の私を除いて、63名の販売員はすべて女性だった。
「マネージャー」
背後からだった。
ボーっとしていたのだろうか、自分が呼ばれたなんて気づかなかった。
「マネージャー!!」
2度目の声で驚いて振り向いた。
そこには女性社員2人がいた。
ベテランの清水(仮名)と小野(仮名)だった。
「お聞きしたことがあります」
清水からにらみつけられるような視線で言われた。
私は奥のバックヤードに連れて行かれた。
壁一面の棚にハロッズのコーポレートカラー、モスグリーンのボックスに入ったギフトセットが置かれた一角のわずかのスペース。
輸入食品コーナーのユニフォームであるトラッドウェア姿の女性2人と相対することになった。
「マネージャーの方針を聞かせてください」
方針だなんて、ほんの1時間ほど前に辞令を受け取ったばかりである。
接客ブランク10年の私としてはなにを話してよいか分かるわけがなかった。
まして、方針だなんて……
しかし、回答をしなければ「絶対に帰さないぞ」という2人の視線にさらされていた。
「……」
恥ずかしいことに、なにかを言おうにも言葉が出なかった。
想定しない辞令を受けただけでなく、いきなりアウェイの洗礼である。
沈黙の時間が流れた。
(ここはなにか言うしかない)
このセクションの現状と抱えている問題について何一つ聞いていない私である。
「今までのマネージャーのやり方をまずは引き継ぐよ」
無意識のうちに自然に口をついて出た言葉だった。
2人の表情に微かな笑いがこぼれた、いやこぼれたように感じた。
その笑いになぜか不自然さ感じた。
「だから、いいんだよ」
「……?」
左隣にいた小野が清水に向かって言ったひとことに意味深以上のものを感じ始めることになった。
なんとかクリアしたかと思った私だったが、それは最初の第一関門ではなかった。
百貨店生活のなかで最もチャレンジングなシチュエーションの序章だった。
この人間関係の中でこれから過ごしていくのである。
責任者になったのに、なにをしたら良いかをアドバイスはない。
それは闇雲なマネジメントの始まりだった。
3日後の午前9時45分、食品の販売1日目、地下の食品フロア全員の前であいさつすることになった。担当する輸入食品売場だけではない。生鮮もお菓子も、お酒売場の社員も全員が集まっての場である。
その数約200数十名だっただろうか。
名前を言ったことまでは覚えている。
自己紹介をしている一方で、心の声は「ヘルプ!」と叫んでいた。
自分はこれからいったい、なにをどうすればいいか不透明なままの初日。気づくと朝礼は終わっていた。
午前9時57分、ご来店されるお客さまをお迎えする待機のポジションに着いた。
「あとは何とかなりますから」
前任のマネージャーから掛けられた言葉を思い出していた。
前日の引き継ぎの時間は10分。仕事の流れが分かるわけがなかった。
「どうしたらいいんだ……」
もう待ったなしだった。食品の業務知識もなければ、販売の現場での金銭授受の基本も踏襲していない。
さらにレジスターはすべてオンライン化されていた。
伝票はあるものの、まったく一新している。
販売の責任者でありながら、知識も運営方法の知恵も持ち合わせていない状態。
人事異動を恨めしく思っても今となっては仕方がない。
午前10時、開店のベルと同時に店舗の扉が開けられた。
ヨハン・シュトラウスの『美しき青きドナウ』のBGMが流れ始めた。
ご来店されたお客さまが次から次へと入り口からの通路を私に向かって一直線に進んでくるのが見えた。
先頭は40〜50代のご婦人方である。顔がはっきりとわかる距離になった。
その数は数十人だろうか。いや、あとからあとから続いてきた。
「パテックフィリップのイベント会場はどちらですか?」
先頭のご婦人からだった。
「……?」
”いらっしゃいませ”とも言えず、身体が金縛りにあったかのように動けないのである。
なにを言ったらいいんだろう?
パテックフィリップって、時計だったよな。
瞬時に思っても言葉も出ないし、身体も動かないのである。
「1階でございます。こちらのエスカレーターをご利用ください」
同じセクションの販売チーフだった。
63人いる女性販売員のなかで役職上で一番上である。
お客さまは私には目もくれずに、上りエスカレーターを駆け上がっていった。
(オレって、なんで知らないんだ)
お客さまが視界から見えなくなってはじめて言われた。
「マネージャー、しっかりしてくださいよ」
カウンターの電話が鳴った。外線だった。
率先垂範しなくてはとばかりに、受話器を取った。
「おまたせいたしました。日本橋本店食品部、高林でございます」
と言いかけたそのときだった。
「あんたのとこのジャムって、何なのさ!!」
(ジャムって?!)ジャムがいったいどうしたのだろう。
「ジャムがどうかなさいましたか?」
火に油を注ぐ結果となったのかもしれない。
「変なものが入っているのよ。オレンジマーマレードジャムの中に黒い石みたいなものが入ってるのよ」
(ジャムに石?)
信じられなかった。ジャムの中にへんなものが入っているなんて、自分の人生にまったくなかったことだった。
私は背広に着替えて、お客さまのもとにお詫びに向かった。
商品に関する異物混入のクレームの電話だった。
帰社すると、こんどは受付から、「お客さまが怒っていらっしゃいます。いますぐにこちらへ
来てくれませんか?」
受付まで行くと、脇では60代後半の女性が怒り心頭の表情をされていた。
初日からこんな調子だった。
しかも、自分で自分をコントロールできない状態であるだけでなく、自ら接客をするとクレームをしでかしてしまうのである。
上司からは、「おまえもっとしっかりしろよ」と言われ、同僚からは、「自信持てよ」と言われた。しかし、どうやって、もっとしっかりするか?そして、どうやって自信を持てるようになれるかが皆目検討がつかないのである。
部下からも「うちの今度来たマネージャーってさ」
と陰口を叩かれてしまう状態だった。
じつは、半年以上にわたって、この「どうにもうまくいかない」という状態は継続することになったのである。
しかも責任者でありながら、売上高も上がらないとあっては、全社的にも「ダメなやつ」という烙印が押されつつあった。
相談しようにも誰に、どう聞いたらいいんだろう?
悶々としたまま時間だけが過ぎつつあった。
そんな私にとって、総務にいた同期生から、よかったらということで紹介された人が、一人の心理カウンセラーだった。
年齢は50代後半の女性である。所在地は会社の近くだった。
とにかく、わらにもすがる思いだった。
1週間に2回、昼休みに彼女のもとに通った。
最初の2週間は私が話すだけだった。
3週間目からかの女によるワークが始まった。
それは、「紙に書く」というもの。
書く対象はなんでも良いので、とにかく「紙に書いてみない?」
私は会社から支給された手帳に書き始めた。
お客さまとのお約束、お客さまがおっしゃった言葉、上司からの指示の内容、部下の言ったひとこと……
など
最初の1、2週間は何の変化もなかった。
3週間目に入ったころから、紙に書いていると、なぜか不思議に心が落ち着くような感じがした。
1ヶ月を過ぎると、書きながら自分の活動を俯瞰しているもうひとりの人間がいた。
すると、部門の売上高はどんな活動をすればよいか? 新しい研修プロガムは?
など、対応が自分のなかで映像として見えてくるのである。
紙に書くようになって、この食品の辞令を受けたときに、そもそも自分に問題があったことに気づき始めた。
しかも、なにか問題があると頭のなかで極力解決しようとしていた。
頭のなかのワーキングメモリーが、いっぱいいっぱい状態を自分で作っていたともいえる。
紙に書いていると不思議に気持ちが落ち着くのである。
書くとは、自分の感情をいったんペンとインクを使って紙の上に文字として置く。
それは身体から自分の感情、解釈、偏見、知識をはじめ、いったん身体から離すことにつながった。
書きはじめて1ヶ月が過ぎたとき、周りが良いも悪いもない。
すべての責任は自分にあったのではないか?
と思い始めていた。
未経験、人間関係ゼロ、ブランク10年、マネジメント経験ゼロ……。
「だからできるわけがない」と自分で自分にカベを作っていたのに気づき始めていた。
「自分は孤独だ」と感じていながら、その元凶を作っていたのは、他ならぬ自分だったのではないかと。
希望した異動でなかったせいもある。
それを他人のせいにして、「だれか、なんとかしてよ」自分以外に求めていたのである。
クレームもうまくいかないのも、「自分のせいなんかじゃないよ」
というエクスキューズの世界である。
それが、紙に書くようになって少しずつ変わりはじめていたのである。
半年後、私は人事異動で2階級ダウンの平社員になり、部署も法人外商(営業)に変わることになった。
私には紙に書くという習慣が始まっていたことから、なんら恐れることはなくなった。
まずは紙に書く。
すると新たな世界が紙の上に創り出されるのである。
すべての責任は自分にあった。うまくいかなくて孤独感満載だった私を救ってくれたのは、「紙に書く」という行動だった。
◻︎ライタープロフィール
高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
ベストメモリーコンシェルジュ。
慶應義塾大学商学部を卒業後、三越に入社。
販売、仕入をはじめ、24年間で14の職務を担当後、社内公募で
法人外商を志望。ノベルティ(おまけ)の企画提案営業により、
その後の4年間で3度の社内MVPを受賞。新入社員時代、
三百年の伝統に培われた「変わらざるもの=まごころの精神」と、
「変わるべきもの=時代の変化に合わせて自らを変革すること」が職業観の根幹となる。一方で、10年間のブランクの後に店頭の販売に復帰した40代、
「人は言えないことが9割」という認識の下、お客様の観察に活路を見いだす。
現在は、三越の先人から引き継がれる原理原則を基に、接遇を含めた問題解決に当たっている。
http://tenro-in.com/zemi/102023