私が私であることを認められるように《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》

記事:今村真緒(天狼院書店ライターズ倶楽部)
「あなたは、橋の下で拾った子だから」
幼い頃に、母から発せられた言葉を今でも覚えている。
腹立ちまぎれに言った言葉とは分かっている。
だが、そう言った母の顔つきは、私にひょっとして本当かも知れないと思わせるほど冷たかった。
「ぐず。のろま」
母のタイミングに合わせることができないときは、そんな言葉が浴びせられた。
小学校高学年のとき、ほぼオール5の通知表を持ち帰ったときも、私が望んだ反応は帰ってこなかった。
「当たり前でしょ。このくらい」
常に完璧を目指しスパルタだった母には、自分の理想の結果でないと受け入れてもらえなかった。
母の思惑と一致しないとき、私は決まって責められた。
「どうしてそんなことを言うの? 信じられない。Sさんが聞いたらびっくりするよ」
話とは関係がないのに、私が懐いていたSさんまで持ち出して拒否された。
多分Sさんは、そんなことで私を否定しない。
それなのに、このことを知ったらSさんが私を嫌うかもしれないという脅しだった。
今思えば、母はそうやって巧みに自分の理想、いや都合の良い娘に、私を誘導しようとしていたのだと思う。
弁が立つ母には、子どもだった私が適うはずもない。
私の家では、全てが、母の機嫌に左右されていた。
母の逆鱗に触れると、容赦なく家から追い出された。
母は、玄関や1階の窓の鍵を全て閉め、私が家に入れないようにした。
寒空の下、私は帰りの遅い父に入れてもらうか、お隣のおばさんが見かねて母に進言してくれるかを待つしかなかった。
しばらくすると、私は庭にある小屋をつたって、屋根から2階の自分の部屋に入ることを思いついた。
いつ家から閉め出されるか分からないので、学校から家に帰ると2階の窓の鍵を開けておくようにした。
できるだけ、息を潜めて、余計なことは言わないように気を遣う日々に沈んでいた。
私が間違っているから。私が悪いから。
だから怒られるのは、仕方がないのだ。
どんなに頑張っても、褒められることなどめったにない。
けれど、母がそう言うのなら、私はもっと頑張らなければならない。
私の中で、母は絶対的存在だった。
母にどう扱われようとも、私は自分を責めることしかできなかった。
だって、私は母に気に入られたかったから。笑顔で話したかったから。
もう、蔑んだ目つきで一瞥されるのに耐えられなかったから。
おまけに私は、真面目でバカ正直だった。
いつしか先回りして、母の望む方向へと答えを探す癖が身に付いていた。
そうしなければ、いつも暗い闇に心が蝕まれてしまう。
中学生になると、私は理不尽なことに対して違和感を持つようになっていた。
反抗期ということもあり、納得できないことがあると母と言い争いになった。
私が正論を言うと、母流のロジックで容赦なく否定された。
母の思い通りの答えでないからだ。
母は、常に勝者でなければならないようだった。
いよいよ私が譲らないと、今度は泣き落としで迫られた。
最終手段は、いつも親子の情というものに訴えられた。
本質とは違うところで、いつも母は私を屈服させた。
心配しているのに。愛情から厳しくしているのに。あなたのためなのに。
どうして、あなたは分からないの?
そう言う圧力で、私を支配した。
理論的にではなく、感情的に言いくるめられる。
親子だから。子どもだから親に従うのは当たり前。
そういう前提で、私がどう思っているか、何を求めているかは無視された。
母の思う通りに振る舞うことを求められ続け、何かが違うと思いながらも、いたたまれない思いをしたくないばかりに、自分の心を押し殺すことだけは上手になっていった。
母がいつも言っていた「親子」である筈なのに、上辺を取り繕った「あるべき姿」はとてもいびつに思えた。
そのせいか、私は子どもの頃の満ち足りた記憶というものがあまりない。
何を言っても、私をまるごと受け入れてくれる存在。
母親とは、そういうものではなかったのか。
私もまた、理想の母親像を追い求めていた。
友だちの母親を見ては、羨ましさが募っていた。
「どうして、そんなことをお母さんに言えるの?」
私が驚くと、友達は私のその発言にびっくりしていた。
「真緒ちゃん、どうしてお母さんに言えないの? 思ったことを言えばいいのに」
無理だ。
私の家では、そんなこと通用しない。あり得ないことだった。
自分の理想と現実とのギャップが苦しかった。
ますます、母に対して底なしの溝が深まるばかりだった。
結婚が決まった頃、夫に言われた一言が胸に刺さった。
「実の親に話すのに、そんなに考えなくてもいいんじゃない」
前に友だちが言ったことと同じだ。
けれども考えずに話せば、私が悪者になるのはいつものことだ。
細心の注意を払わなければ、倍返しどころではない。
私は、これまでの母との経緯を夫に語った。
「怖がって避けてばかりじゃ駄目じゃないの? 喧嘩をしようとは言わないけれど、本音を言わないから、お義母さんはそれでいいと思っているんじゃないの? 伝えないと、いつまでも分かってもらえるわけがないよ」
私だって、ずっと本音を言いたかった。
でも、それはすぐに却下される。
気まずくなるのが耐えられない。
言っても無駄ということは、これまでで経験済みだ。
「それでも、言い続けたら良いよ。真緒はお母さんの所有物ではないし、自分の想いを言うのに遠慮することはない。真緒は、真緒。ありのまま、そのままでいいんだよ」
泣きそうになった。
母が認めなければ、駄目な自分。
私の価値は、母の一言で左右されていた。
母が提示する条件を満たさなければ、認めてもらえないと思っていた。
無条件で受け入れてもらうことに渇望していた自分を、まざまざと思い知った。
心の奥底にある暗くて湿った感情に、気づかない振りをして生きていた。
母という絶対的な存在を、未だに自分自身から切り離すことができていないこと。
自分の物差しでなく、母の物差しで今まで生きてきたこと。
いつまでも、母の愛を乞う怯えた幼子が私の中にいること。
母は、私を自分の思い描く理想の娘にしたいだけなのだ。
そして、それが私にとっても正しいと信じている。
確かに、私のことを愛していないわけではないかも知れない。
でも、それは従順で、母にとって都合の良い娘であることが必須なのだ。
条件付きの愛情か。
どこか冷めた気持ちで、母を見ることが多くなった。
結婚後、母は私の夫のことを悪く言うようになった。
私が実家に寄り付かなくなり、言うことを聞かなくなったのは、私の夫のせいに違いないというのだ。
結婚してから、私は初めて開放感を味わっていた。
夫は、私が何を言おうとも一旦受け入れてくれる。
夫の意見とは違っていても、私の意見として冷静に聞いてくれる。
自由に息をして、思ったことを妙にオブラートに包むこともなく、相手の機嫌を伺いながらおどおどしなくても良いことに、居心地の良さを感じた。
自然と、夫との生活で自分らしさを見いだしていった。
娘を授かったとき、子ども好きな私はとても嬉しかった。
しかし、同時に不安に陥った。
親子の関係について、自分が悩んできたことを思い出すからだ。
生まれてくる子どもに、私はちゃんと愛情を持って育てることができるだろうか?
自分の理想を押し付ける親になってしまいはしないだろうか?
ありのままの子どもを、受け止めることができるだろうか?
私みたいに、鬱々とした感情を持て余す子供を増やすことになりはしないだろうか?
常に、娘を育てるにあたり自問自答してきた。
もちろん、子どもが親の思い通りになることはない。
腹が立ち、どうしようもない感情に襲われることもあった。
子育ては、試行錯誤の毎日だ。
親といっても、私にできることといえば、折に触れ、娘にいつも味方であることを伝えること。
娘が、ありのままに振る舞える環境を作ること。
頭ごなしに否定するのではなく、娘の意見を尊重すること。
娘を叱りすぎてしまったとき、冷静になれば言い過ぎたと反省した。
思っていても、伝えなければ私の気持ちは娘には分からない。
だから、言い過ぎたと思ったら次の日に謝るようにした。
私が母に求めていたことを、私の娘として生まれてきてくれた娘にすることが、私の不安に対する免罪符のような気がしていた。
夫は、今では母のお気に入りだ。
母の性格を分かった上で、夫は母に誠意を尽くしてくれる。
「良い人と結婚したね」
そう母が言ったときには、以前の夫に対する母の言動を思い出して苦笑いした。
夫は、媚びるわけでもなく、絶妙に母の自尊心をくすぐるようだ。
やっぱり、母は自分を尊重してくれる人に相変わらず弱いのだ。
考えてみれば、母も強烈に自分を認めてもらいたい人なのかもしれない。
私が母に対して自分で折り合いをつけるようになったからか、母が少し丸くなったのか、以前よりは心に波風が立たなくなった。
ありのままでいい。そのままでいい。
その言葉は、私を癒してくれた。
構えずに、さらっと力まずに、あるがままでいること。
自然に受け入れること。
それを支えに日常を過ごしてみれば、いかに余計なものに自分が捕われていたかが分かる。
おかげ様で、私は夫をはじめ、人に恵まれている。
その人たちとの縁を大切に、様々な想いを分かち合いたい。
条件など付けずに認め合い、個々を大切にしたい。
心で繋がる人達は、ありのままの私を見てくれる。
その存在が、私の心を潤してくれる。
私の曇っていた眼を開き、自分の心と向き合う力を与えてくれる。
そして、背中を押してくれるのだ。
ちゃんと、自分の軸を持って歩いていけるように。
私が、私であることを認められるように。
□ライターズプロフィール
今村真緒(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
福岡県出身。
自分の想いを表現できるようになりたいと思ったことがきっかけで、2020年5月から天狼院書店のライティング・ゼミ受講。更にライティング力向上を目指すため、2020年9月よりREADING LIFE編集部ライターズ倶楽部参加。
興味のあることは、人間観察、ドキュメンタリー番組やクイズ番組を観ること。
人の心に寄り添えるような文章を書けるようになることが目標。
この記事は、人生を変える天狼院「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」をご受講の方が書きました。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325
■天狼院書店「シアターカフェ天狼院」
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-1 WACCA池袋 4F
営業時間:
平日 11:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
電話:03−6812−1984
関連記事
-

「息子が死んでも責任を取らせないから校庭で遊ばせてほしい」先生へ母が告げたあの一言が私を今でも支えている《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-

アランからもらって、Kちゃんに贈る言葉《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-

私もこの境地に達したいものだ《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-
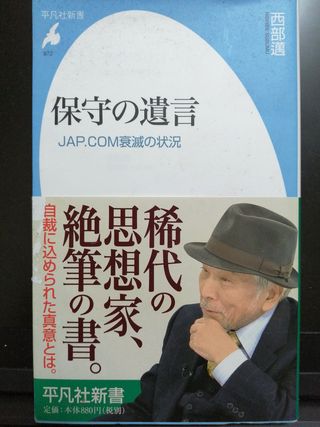
師匠がくれた忘れられない一言が僕の支えになった《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-

あの時、諦めていたらこの未来はなかっただろう《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》



