僕のセルフケアが、ここから始まった ― 作業療法士の停電と再起動《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
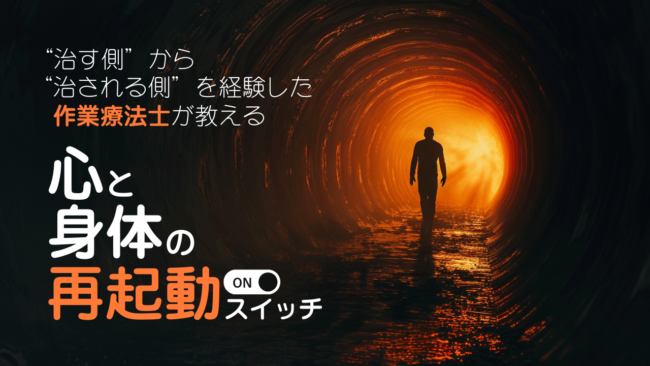
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
*この記事は、天狼院書店のライティング・ゼミを卒業され、現在、天狼院書店の公認ライターであるお客様に書いていただいた記事です。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
2025/8/11公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
作業療法士として終末期病棟で働く25歳の筆者(2021年当時)に、ある日突然、右腕のしびれが襲った。「胸郭出口症候群」と診断され、治す側から動けない側へと立場が逆転。完璧でなければ患者に寄り添えないという思い込みが、心を静かに蝕んでいく。朝、制服を着ながら涙が出る日々。しかし、自主リハビリで右腕がほんの数センチ上がった瞬間、涙とともに希望が戻ってきた。心と身体が”自分”とつながらなくなる「停電」状態から、どう「再起動」したのか。医療現場で働く専門職の実体験から、誰にでも起こりうる心身の不調との向き合い方を考える。
—–
午後2時、終末期病棟の廊下に響く静かな足音。その日はいつもより空気が重く感じられた。消毒液の匂いが漂う中、僕は作業療法士として、この場所で3年間働いていた。25歳の僕にとって、命の終わりに寄り添う現場は重く、同時に深い意味を感じさせてくれる場所だった。病室から聞こえる小さな咳、看護師の靴音、そして時折響く家族の泣き声——そのすべてが、ここが特別な場所であることを物語っていた。
「Tさん、今日は少し座ってみましょうか」
ベッドサイドで、末期がんのTさんに声をかけた。彼女の身体を支えようと両手を差し出した瞬間、右腕に電気が走るようなしびれが襲った。冷たいベッドレールが手の甲に触れる感触と同時に、思わず手を引っ込める。その時の自分の手の震えを、今でもはっきりと覚えている。
「先生、大丈夫ですか?」
Tさんの心配そうな声に、僕は慌てて笑顔を作った。「ちょっと肩が凝っただけです。大丈夫ですよ」
しかし、その後も右上肢の違和感は続いた。歩行中にもふらつきを感じる。翌週の診察で「胸郭出口症候群」と診断された時、診察室の白い壁が急に遠く見えた。僕の中で何かが音を立てて崩れた。
治す側の僕が、動けない側になった。
リハビリテーションの専門家として、患者さんの「できない」に寄り添ってきたはずなのに、自分が当事者になると、その現実を受け入れることができなかった。
右腕の可動域制限は、仕事のあらゆる場面に影響した。患者さんの移乗介助に時間がかかる。リハビリ動作の見本を示せない。何より、自分の身体が思うように動かないことで、患者さんへの対応が遅れることに深い罪悪感を感じた。
終末期病棟という場所の特殊性が、その罪悪感を増幅させた。ここでは時間が限られている。今日が最後のリハビリになるかもしれない。そんな貴重な時間を、僕の不調で無駄にしてしまうのではないか。
「この一回の関わりが、その人の人生最後のリハビリかもしれない」
そう思うと、自分の不完全さが許せなくなった。完璧でなければ、この場所にいる資格がないのではないか。患者さんたちは人生の最終章を歩んでいるのに、僕は自分の小さな不調に気を取られている。
朝、制服を着ながら涙が出た。鏡に映る自分が、まるで知らない人のように見えた。着慣れたユニフォームの重さが、その日はやけに肩に食い込んだ。
「もう2度とこの仕事はできないんじゃないか」
心療内科で「軽度のうつ状態」と診断された時、僕は妙に納得していた。心が静かに崩れていくのを、どこか他人事のように眺めている自分がいた。
【POINT】停電とは何か?
この体験を通して、僕は一つのことを理解した。
停電とは、心と身体が”自分”とつながらなくなる状態だということを。
日々の行動はこなしている。病院に行き、患者さんと話し、記録を書く。でも、そこに「気持ち」や「意味」が乗ってこない。やりたいことがあっても、手が伸びない。身体が止まったような、感情が麻痺したような――静かなシャットダウン。
作業療法士として出会ってきた多くの患者さんたちの言葉が、急に重みを持って僕の胸に響いた。「身体が自分のものじゃないみたい」「やる気が起きない」「自分が分からなくなった」——これらの言葉の本当の意味を、僕は理解していなかった。
今、僕自身もまた、“停電したひとり”だった。
停電は突然やってくる。電球が切れるように、コンセントが抜けるように。そして多くの場合、それは静かに始まる。大きな音も、劇的な変化もない。ただ、いつものように動いているつもりなのに、何かが違う。そんな違和感から始まる。
診断から1ヶ月が過ぎた頃、僕は恐る恐る自分の身体と向き合い始めた。完全に壊れたと思っていた自分を、試すように。まるで壊れた機械の動作確認をするように。
最初は簡単なストレッチから始めた。首を左右に回す。肩を上下に動かす。朝の冷たい空気の中で、一人でそれを続けた。右腕の痛みとしびれは相変わらずだったが、それでも少しずつ、毎日続けた。
自主リハビリという言葉に、皮肉を感じていた。患者さんに「継続が大切ですよ」と言い続けてきた僕が、今度は自分にその言葉を向けている。
3週間後のある朝、いつものようにストレッチをしていた時だった。右腕が、ほんの少しだけ、いつもより高く上がった。ほんの2センチ、3センチの違い。指先に感じる空気の温度、肩の筋肉がゆっくりと伸びる感覚——その瞬間、涙が溢れた。それは悔しさでも悲しさでもない、何か温かい涙だった。
「僕の身体、まだ戻れるんだ」
その小さな変化が、消えかけていた希望に火を灯した。身体の反応が、“できる自分”の存在を思い出させてくれた。心の中にも、少しずつ光が戻り始めた。
鏡を見る時間が、少し長くなった。制服を着る時の涙は、いつの間にか止まっていた。
振り返ってみると、あの涙の理由がよく分かる。
腕が少し上がったという身体の小さな変化が、心を大きく動かした。「あ、僕の身体はまだ生きてる」「まだ変われるんだ」——そんな実感が、一気に湧き上がってきたのだ。
自分で自分をケアして、それがうまくいった。この小さな成功体験が、「自分にはまだできることがある」という感覚を取り戻させてくれた。誰かに治してもらうのではなく、自分の手で少しずつ変えていく。その実感こそが、希望だった。
そして何より、完璧でない自分も受け入れることができた。完璧な支援者でなくても、この場所で価値のある存在でいられる。不調を抱えた自分も、また違った形で患者さんと向き合えるかもしれない。
再起動とは、“元に戻る”ことではない。“もう一度つながる”ことだ。身体と心、そして自分自身の価値と。
あの時、僕が毎日続けていたセルフケアを紹介したい。特別な道具も、特別な技術も必要ない。誰でも今日から始められるものばかりだ。
- 首の横のストレッチ(朝・夜の2回)
症状のある側の肩に反対の手を置き、首を反対側にゆっくり倒す。首の前側と横側が伸びているのを感じながら15秒キープ。朝起きた時と寝る前に必ず行った。最初は痛みで首を動かすのも怖かったが、少しずつ動かせる範囲が広がっていった。
- 胸の前のストレッチ(仕事の合間に)
壁に腕をかけ、腕を固定したまま体を反対に捻る。胸の前が伸びる感覚を30秒間味わう。デスクワークの合間、お昼休みの時間などに行った。胸が開く感覚が、なんだか心も開くような気分にさせてくれた。
- 鎖骨周りのセルフマッサージ(お風呂上がりに)
テニスボールを使って、鎖骨の下から肩にかけて圧迫しながらマッサージ。筋肉がほぐれる実感が得られ、血行も良くなった気がした。何より、「自分で自分をケアしている」という感覚が、心の支えになった。
これらを続けて3週間。腕が数センチ上がった朝、「続けてきてよかった」と心から思えた。完璧にできなくても、忘れる日があっても、また次の日から始めればいい。そんな小さな積み重ねが、僕の「再起動スイッチ」だったのだ。
停電した時、僕たちは暗闇の中で動けなくなる。でも、完全に電気が失われたわけではない。どこかにブレーカーがあり、どこかにスイッチがある。それを見つけて、そっと押すこと。時には他者の手を借りながら、時には自分の手で。
僕の場合、そのスイッチは体の小さな変化だった。でも、人によってスイッチの場所は違う。音楽かもしれない、人との出会いかもしれない、新しい環境かもしれない。
停電は誰にでも起こる。仕事で、人間関係で、健康面で、人生の様々な場面で。それは恥ずかしいことでも、弱いことでもない。人間らしいことだ。
あなたにも、こんな”停電の兆し”はありませんか?
・朝起きるのが辛くなった
・好きだったことに興味が湧かない
・身体がなんとなく重い
・いつものことをしているのに、なぜか満足感がない
そんな小さなサインから、停電は静かに始まる。
重要なのは、気づくこと。「あれ、なんか変だな」という違和感を無視しないこと。立ち止まること。そして、“静かに再起動すること”。
この連載では、様々な「停電」と「再起動」の瞬間を紡いでいきたい。医療現場で出会った方々の体験、僕自身のその後の歩み、そして読者の皆さんと一緒に考えたい「つながり直す」方法について。
次回からは、他者のストーリーに耳を傾けていく。あなたにもきっと、自分だけの再起動スイッチが見つかるはず。停電の暗闇は怖いけれど、必ず明かりは戻ってくる。その時まで、一緒に歩いてみませんか。
❏ライタープロフィール
内山遼太(READING LIFE公認ライター)
千葉県香取市出身。現在は東京都八王子市在住。
作業療法士。終末期ケア病院・デイサービス・訪問リハビリで「その人らしい生き方」に
寄り添う支援を続けている。
終末期上級ケア専門士・認知症ケア専門士。新人療法士向けのセミナー講師としても活動中。
現場で出会う「もう一度◯◯したい」という声を言葉にするライター。
2025年8月より『週刊READING LIFE』にて《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》連載開始。
***
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-
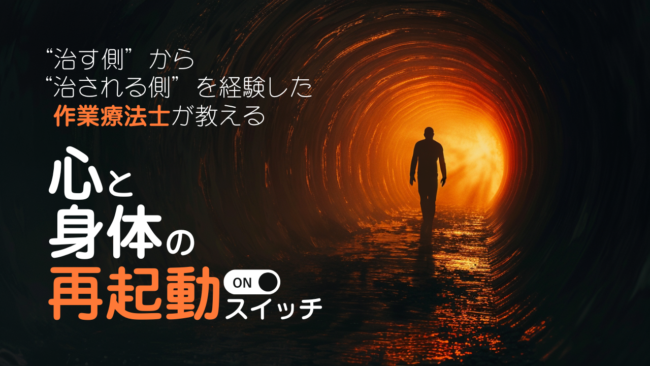
慢性痛に苦しむ女性が”花を活ける”喜びに出会った日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
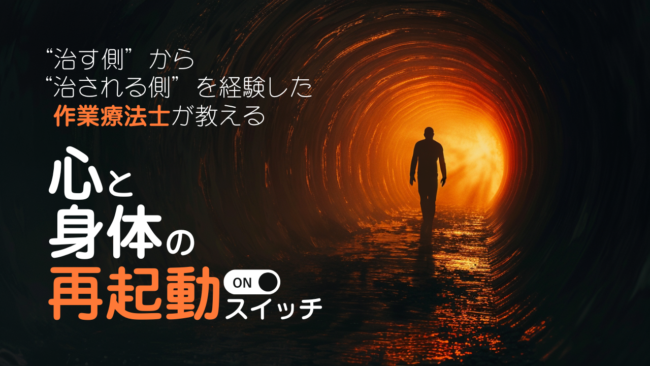
片麻痺の若者が”洗濯バサミで服を干した”午後《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
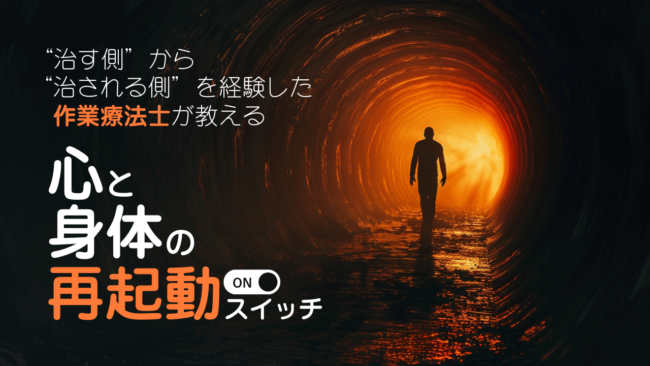
パーキンソン病の男性が”椅子を拭いた”日常動作の意味《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
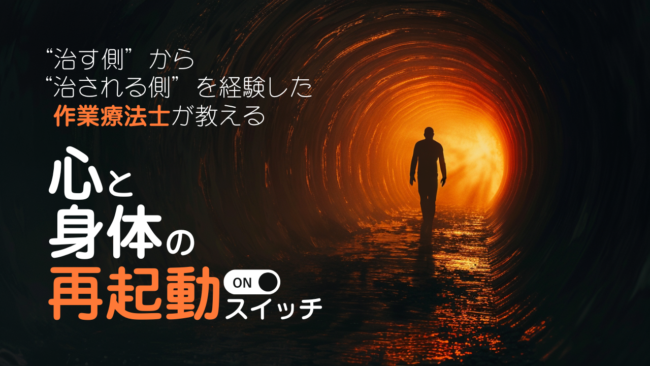
脳卒中で利き手を失った女性が”左手でおにぎり”を握った朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
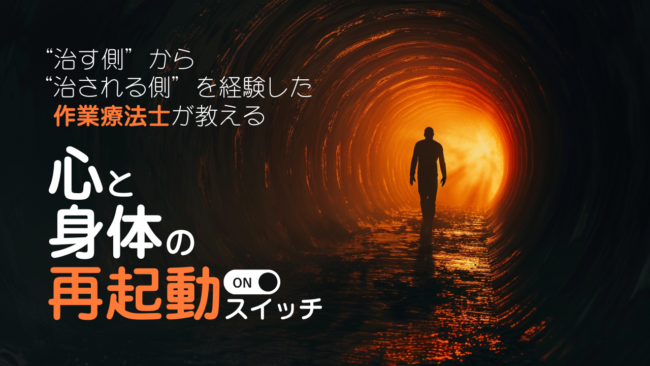
感情表出できなかった男性が”絵”に怒りを描いた日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》



