「すべてを奪われたその日から ― 災害で止まった時間を再起動する」《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
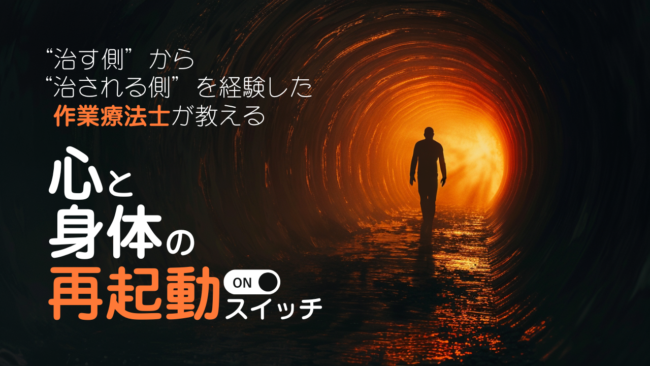
2025/10/15/公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
※一部フィクションを含みます。
突然の災害で家も仕事も家族も失ったら――人はどうやって立ち上がれるのでしょうか。喪失の大きさに押し潰され、時間が止まったままの男性。彼が見出したのは「再建」ではなく「再起動」という視点でした。失ったものに目を向けるのではなく、残っているものを手がかりにして、もう一度生き直す。そのプロセスが未来への扉を開きます。
——
2021年3月11日午後2時46分――その瞬間、Sさん(54歳)の人生は完全に変わりました。東日本大震災から10年後、今度はSさんが住む地域を大地震が襲ったのです。妻と大学生の娘を津波で失い、経営していた漁業関連の小さな会社も港と共に流され、家も跡形もなく消えました。
「病院で目を覚ました時、最初は夢だと思いました。でも現実だった。妻と娘がいない。会社もない。家もない。50年以上生きてきて築いてきたものが、すべて2時間で消えてしまった」
Sさんの声には、深い絶望と虚無感が滲んでいました。避難所生活が始まっても、彼は壁を見つめたまま何日も過ごしました。食事も取ろうとせず、支援者が話しかけても反応しない状態が続いたのです。
災害による喪失は、他の人生の困難とは質的に異なる特徴があります。突然性、包括性、不可逆性——これらの要素が組み合わさることで、被災者は「意味の喪失」とも呼べる深刻な心理状態に陥ることがあります。
心理学者のヴィクトール・フランクルは、強制収容所での体験を基に「人間は意味を求める存在」だと述べました。Sさんの場合、家族、仕事、住居という人生の意味を支えていた三本柱がすべて失われたことで、生きる意味そのものが見えなくなってしまったのです。
「朝起きても何をすればいいかわからない。家族のために働く必要もない。帰る家もない。なぜ私だけが生き残ったのか、その理由がわからなくて、毎日が苦痛でした」
Sさんに転機が訪れたのは、災害から4ヶ月後のことでした。同じく被災した近所の高齢者、Tおばあちゃん(82歳)との会話がきっかけでした。
「Sさん、私たちは『元通り』にはならないよ。でも『新しく始める』ことはできる。私は戦争で家族を失った時も、そうやって生きてきた」
Tさんの静かな言葉は、Sさんの心に深く響きました。「再建」という言葉に縛られていた彼にとって、「再起動」という新しい視点との出会いでした。
「再建」とは、失ったものを元通りに戻そうとする試みです。しかし、家族の命は戻りませんし、津波で変わった地形に同じ町を再現することも現実的ではありません。一方「再起動」とは、現在残っているリソースを使って、新しい人生を始めることを意味します。
「Tさんの言葉で、目から鱗が落ちました。私は妻と娘を『取り戻そう』として苦しんでいた。でも二人はもういない。それなら、二人の分まで生きる新しい人生を始めようと思えたんです」
この発想転換は、心理学でいう「意味の再構築(Meaning Reconstruction)」のプロセスです。災害などの重大な喪失体験の後、人は失ったものに意味を見出すのではなく、現在と未来に新しい意味を創造することで立ち直っていきます。
Sさんの場合、妻と娘の死を「意味ある出来事」にしようとするのではなく、「二人が生きた証として自分が新しい人生を歩む」という意味づけに転換したのです。これにより、過去への執着から解放され、未来に向かう力を取り戻すことができました。
しかし、再起動の意志を持ったSさんを待っていたのは、さらなる困難でした。善意の支援者や友人たちからの言葉が、時として重い負担となったのです。
「『頑張って』『きっと良くなる』『前向きに考えよう』——みんな励ましてくれるのはありがたかったけれど、そんな簡単な問題じゃない。家族を失った痛みは、頑張ったからといって消えるものじゃないんです」
これは災害被災者や重大な喪失を経験した人が共通して感じる苦しみです。周囲の善意は理解できるが、その言葉が現実と乖離していて心に響かない。むしろ「理解されていない」という孤立感を深めてしまうことがあります。
特に「時間が解決してくれる」「いつかは立ち直れる」といった未来志向の励ましは、今この瞬間の苦しみを軽視しているように感じられ、被災者をさらに孤独にしてしまう場合があります。
「支援物資の配布で『お元気ですか』と声をかけられても、『元気です』としか答えられない。本当のことを言ったら相手が困ってしまう。でも嘘をついている自分も嫌になる」
この「感情の不一致」は、被災者の心理的負担を増大させます。社会は「復興」や「立ち直り」を求めますが、個人の心の回復はそのペースに合わせることはできません。この齟齬が、被災者を二重の孤立に追い込むのです。
Sさんが最も辛かったのは、「生存者の罪悪感」でした。なぜ自分だけが生き残ったのか。妻や娘の代わりに自分が死ねばよかったのではないか。このような感情は災害被災者に共通して見られる反応ですが、周囲には理解されにくく、一人で抱え込まざるを得ません。
「夜中に目が覚めると、妻と娘の顔が浮かんでくる。『お父さん、なんで私たちを助けてくれなかったの』と責められているような気がして、眠れなくなる。誰にも話せないから、一人で泣いていました」
Sさんの真の再起動は、「失ったもの」ではなく「残っているもの」に焦点を移すことから始まりました。きっかけは、避難所で出会った臨床心理士の助言でした。
「失ったものを数えるのではなく、今あるものを見つけてみませんか。どんなに小さなことでも構いません」
最初、Sさんは「何も残っていない」と答えました。しかし心理士と一緒に丁寧に振り返ってみると、確かに「残っているもの」がありました。
まず、身体的な健康。津波に流されながらも奇跡的に重傷を負うことなく生き延びました。次に、40年近い漁業の経験と知識。そして、同じ被災者仲間とのつながり。妻と娘との思い出。さらには、これまで培ってきた人との関わり方や価値観。
「リストを作ってみたら、意外にたくさん『残っているもの』があることに気づきました。体も動くし、漁のことはよく知っている。何より、妻と娘が教えてくれた『人を大切にする』という気持ちは失われていない」
この「資源の棚卸し」は、心理学的支援において「ストレングス・アプローチ」と呼ばれる手法です。問題や欠陥に焦点を当てるのではなく、個人が持つ強みや資源を発見し、それを活用して問題解決を図る方法です。
Sさんの場合、漁業経験という専門知識が最も大きな資源でした。港は破壊されましたが、海は残っています。漁船は流されましたが、漁の技術は頭の中にあります。そして何より、同じく漁業で生計を立てていた仲間たちが、同じ避難所に何人もいました。
「一人では何もできないけれど、みんなで力を合わせれば何かできるかもしれない。そう思えた時、初めて『未来』という言葉が頭に浮かびました」
セルフケアエクササイズ「残っているものを書き出す」
大きな喪失を経験したあなたへ。Sさんが実践した「資源の棚卸し」エクササイズを紹介します。失ったものの大きさに押し潰されそうな時こそ、残っているものの価値を再発見してください。
【ステップ1:安全な空間の確保】
このエクササイズは感情的に負荷がかかる場合があります。一人で行う場合は、信頼できる人にサポートを求められる環境を整えてください。可能であれば、カウンセラーや心理士と一緒に行うことをお勧めします。
【ステップ2:身体的資源の確認】
まず、あなたの身体で機能している部分をリストアップしてください。
例:
– 歩くことができる
– 手を使える
– 目が見える
– 声を出せる
– 呼吸ができる
些細に思えることでも、すべて重要な資源です。
【ステップ3:知識・技術・経験の棚卸し】
これまでの人生で身につけた知識、技術、経験を書き出してください。
例:
– 仕事で培った専門知識
– 料理や手工芸のスキル
– 子育ての経験
– 人との関わり方
– 困難を乗り越えた過去の経験
【ステップ4:人間関係の資源】
現在も関わりがある人、支援を求められる人をリストアップします。
例:
– 家族や親戚
– 友人・知人
– 職場の同僚
– 専門家(医師、カウンセラーなど)
– 地域のコミュニティ
【ステップ5:内面的資源の発見】
あなたの価値観、信念、性格の強みを考えてみてください。
例:
– 人への思いやり
– 困難に立ち向かう意志
– ユーモアのセンス
– 学ぶ意欲
– 希望を持ち続ける力
【ステップ6:環境・制度的資源】
利用可能な社会制度、サービス、環境を確認します。
例:
– 社会保障制度
– 支援団体
– 医療機関
– 教育機関
– 自然環境(海、山、公園など)
【ステップ7:統合と活用計画】
これらの資源をどのように組み合わせて、新しい人生を築けるか考えてみてください。完璧な計画である必要はありません。小さな第一歩を考えるだけで十分です。
重要なポイント:
– 「こんなもの資源じゃない」と否定しない
– 他人と比較しない
– 今すぐすべてを活用する必要はない
– 定期的に見直し、追加・修正する
このエクササイズを通じて、あなたの中にも必ず「残っているもの」があることに気づくはずです。それが新しい人生のfoundation になります。
災害から3年が経過した現在、Sさんは新しい人生を歩んでいます。小さな観光船「希望丸」を運航し、地元の海で漁業体験ツアーを行っています。参加者には災害の体験を語り、命の大切さと自然の脅威について伝えています。
「妻と娘がいた頃の生活には戻れません。でも、二人が教えてくれた『人を大切にする』という気持ちを活かした新しい生活を築くことができました。二人も、きっと今の私を見守ってくれていると思います」
Sさんの船には、彼の体験に心を打たれた多くの人が訪れます。中には人生の困難に直面している人もいて、Sさんの話を聞いて新しい hope を見つけて帰っていきます。
「私の体験が誰かの role に立てるなら、すべての喪失にも意味があったと思えます。妻と娘の命も、無駄ではなかった」
Sさんの言葉は、災害からの回復の本質を表しています。それは「元に戻る」ことではなく、「新しい意味を創造する」ことなのです。
私たちは人生の中で、様々な喪失を経験します。それは disaster のように突然のものかもしれませんし、病気や失業、離別のように徐々に訪れるものかもしれません。その喪失の大きさに圧倒され、「もう終わりだ」と感じることもあるでしょう。
しかし、Sさんの体験が教えてくれるのは、どんなに大きな喪失があっても、必ず「残っているもの」があるということです。その資源を丁寧に見つけ出し、創造的に組み合わせることで、新しい人生を築くことは可能なのです。
過去を取り戻すことはできません。しかし、明日をつくることはできます。失ったものの記憶を大切にしながらも、残ったもので新しい価値を創造していく——それが真の意味での再起動なのです。
もしあなたが今、大きな喪失の中にいるとしたら、Sさんの体験を思い出してください。「過去に戻れなくても、明日はつくれる」「失ったものではなく、残ったものに目を向ける」「再建ではなく、再起動を目指す」
今日から、小さな一歩を踏み出してみませんか?
あなたの中にも、必ず新しい明日につながる資源が残っています。
❏ライタープロフィール
内山遼太(READING LIFE公認ライター)
千葉県香取市出身。現在は東京都八王子市在住。
作業療法士。終末期ケア病院・デイサービス・訪問リハビリで「その人らしい生き方」に寄り添う支援を続けている。
終末期上級ケア専門士・認知症ケア専門士。新人療法士向けのセミナー講師としても活動中。
現場で出会う「もう一度◯◯したい」という声を言葉にするライター。
2025年8月より『週刊READING LIFE』にて《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》連載開始。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-
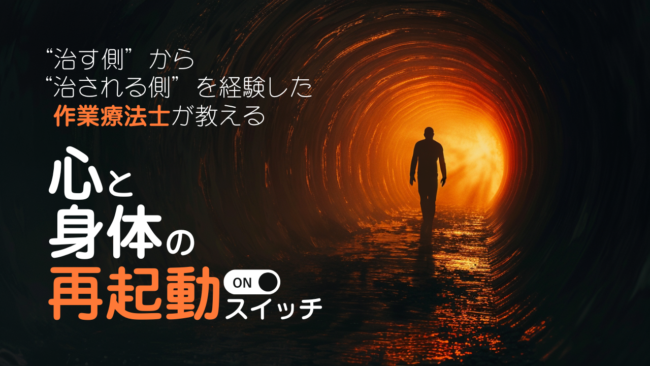
慢性痛に苦しむ女性が”花を活ける”喜びに出会った日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
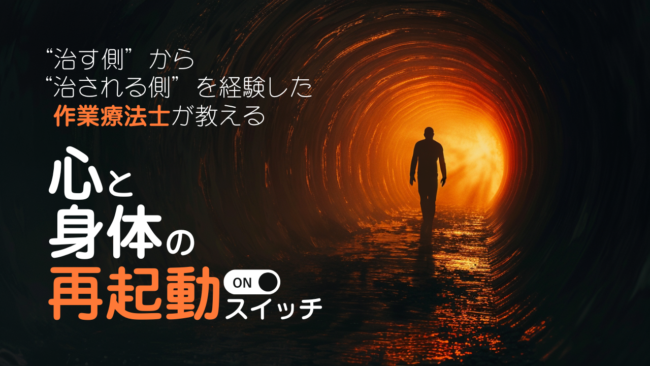
片麻痺の若者が”洗濯バサミで服を干した”午後《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
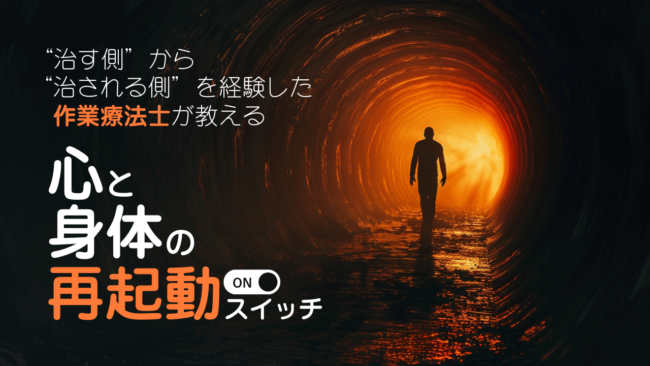
パーキンソン病の男性が”椅子を拭いた”日常動作の意味《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
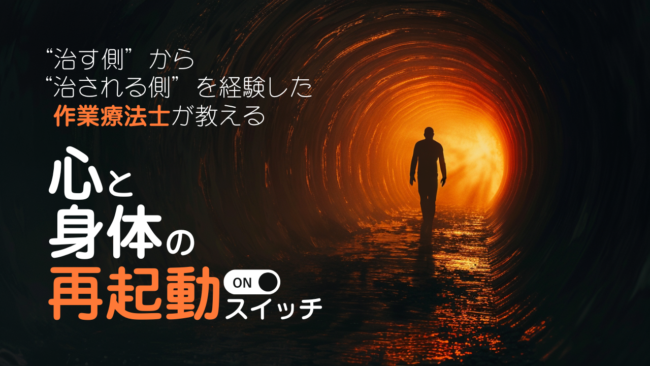
脳卒中で利き手を失った女性が”左手でおにぎり”を握った朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
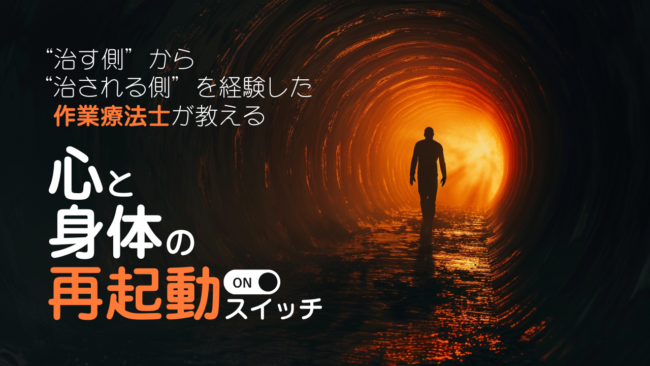
感情表出できなかった男性が”絵”に怒りを描いた日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》



