「おいしい」が戻ってきた——拒食症の少女と人参の一口《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
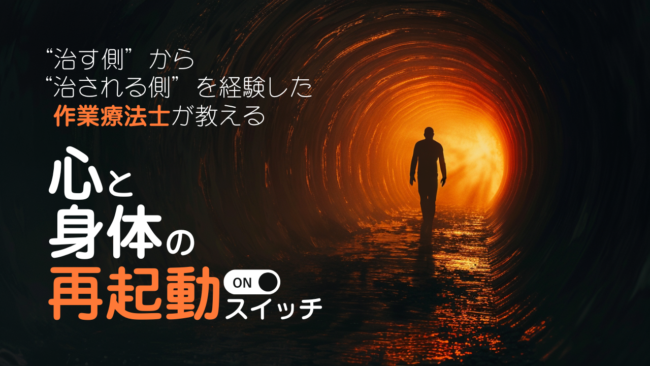
2025/11/3/公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
※一部フィクションを含みます。
食卓の上の人参を、彼女は長い間見つめていた。食べたら太る、また後悔する——その恐怖が心を支配していた。けれど、ふと湯気に乗って届いた甘い香りに、手が動いた。ほんのひと口、口にした瞬間、舌が思い出した。「おいしい」——その言葉が、彼女の中の”生きる感覚”を呼び戻した。
——
彼女は十七歳だった。細い腕、浮き出た鎖骨、頬がこけた顔。体重は標準の七割ほどしかなかった。けれど彼女の目には、鏡に映る自分が「まだ太っている」ように見えていた。
拒食症——正式には神経性やせ症と呼ばれるこの疾患は、単なる「食べたくない」という問題ではない。食べることそのものが、恐怖の対象になる。「食べる=失敗」「太る=価値を失う」という思い込みが、心を支配する。
彼女もまた、その恐怖の中にいた。
初めて彼女と会った日、母親がこう言った。「この子、昔は食べることが大好きだったんです。料理も手伝ってくれて、いつも『おいしい』って笑っていたのに」その言葉に、彼女は俯いたまま何も答えなかった。
拒食症の背景には、しばしば完璧主義や自己評価の低さがある。彼女の場合、中学三年生の時の友人関係のトラブルがきっかけだった。
「あの頃、クラスで仲の良かった友達のグループがあったんです」と、後に彼女は私に話してくれた。「でも、ある日、私だけ仲間はずれにされて。理由もわからないまま、誰も話しかけてくれなくなった」
孤立した彼女は、自分の何が悪かったのかと考え続けた。そんなある日、別のクラスメイトがこう言った。「痩せればもっと可愛くなるのにね」
何気ない一言だったかもしれない。けれど、傷ついていた彼女の心に、その言葉は深く刺さった。
「そうか、私は太っているから嫌われたんだ」
実際には、彼女は標準的な体型だった。けれど、彼女の目には自分が太って見えた。そして、「痩せれば認められる」と信じ込んだ。
最初はダイエットのつもりだった。食事の量を少し減らす。お菓子を控える。それだけのはずだった。
けれど、いつの間にかそれは止められなくなった。食べる量を減らし、カロリーを計算し、体重計の数字に一喜一憂する。一キロ減れば安心し、百グラム増えれば絶望する。
そして気づいたときには、食べることそのものが「敵」になっていた。
食卓は彼女にとって、常に緊張の場だった。家族が「少しでいいから食べて」と声をかける。その優しさが、かえって彼女を追い詰めた。食べなければ心配される。食べれば罪悪感に苛まれる。どちらを選んでも、心は休まらない。
これもまた、心の「停電」の一つの形だった。停電とは、心身の機能が一時的に失われ、感じる・考える・動くといった活動が停止している状態を指す。彼女の場合、特に「おいしい」という感覚——生きることの喜びに直結する感覚が、完全に遮断されていた。
味わう力が失われ、食べることが単なる「カロリー摂取」という数字の問題になる。食事は敵であり、恐怖であり、戦いの場になる。
作業療法の導入当初、私が「食」に関する話題を出すと、彼女は明らかに拒否反応を示した。視線をそらし、口を閉ざし、時には涙を流した。
「食べることについて話すのは、まだ早いかもしれませんね」と私は言った。彼女は小さく頷いた。
心が停電している時、無理に電源を入れようとしても逆効果になる。まずは安全な場所で、少しずつ心の準備を整える必要がある。
私たちは、食べることから離れた活動から始めた。絵を描く、粘土をこねる、布を縫う。手を使い、何かを作り上げる時間。
最初のセッションで、私は色とりどりの折り紙を用意した。「今日は、好きな色で何か作ってみましょう」
彼女は戸惑いながらも、淡いピンクの紙を手に取った。「何を作ればいいですか」
「何でもいいですよ。花でも、鳥でも。あなたが作りたいものを」
彼女は小さな花を折り始めた。最初は手つきがぎこちなかったが、徐々に慣れていく。一つ、二つ、三つ——小さな花が増えていった。
「私、不器用だから」と彼女は言ったが、作品は丁寧で繊細だった。
次の週、彼女は自分から提案した。「この花を、カードにしてもいいですか」
「もちろんです」
彼女は画用紙に、折った花を一つずつ貼り付けていった。黄色、ピンク、水色——色とりどりの花が、カードを彩っていく。その集中した表情を見ながら、私は少しずつ彼女の心が開いていくのを感じた。
三週間ほど経った頃、彼女が珍しく自分から話しかけてきた。「先生、これ、母の日に母にあげてもいいですか」手には、色とりどりの花で埋め尽くされた小さなカードがあった。
「素敵ですね。お母さん、きっと喜びますよ」
彼女は少し照れくさそうに微笑んだ。それは、私が初めて見た彼女の笑顔だった。
その笑顔を見て、私は思った。彼女の心は、少しずつ温まり始めている。
手を動かすことは、心を癒す。特に創作活動は、「自分にもできる」という自己効力感を育てる。拒食症の人は、しばしば「自分には価値がない」と感じている。けれど、美しいものを作り出せるという体験は、その思い込みを少しずつ溶かしていく。
数週間後、私は彼女に別のアプローチを試みた。「今日は、調理のプログラムに参加してみませんか」
彼女の顔色が変わった。「調理、ですか」声が震えている。
「ええ。でも、食べなくてもいいんです。ただ、作るだけ。手を動かすことは、他の活動と同じです」
彼女は不安そうに私を見つめた。「でも、食べ物を作るって……」
「そうですね。食べ物を作ります。でも、作ることと食べることは別です。まずは作る過程を楽しんでみませんか。色、香り、手触り——そういうものを感じてみましょう」
その言葉に、少しだけ緊張が和らいだ。「……やってみます」
その日のメニューは、人参のグラッセだった。
キッチンに並んだオレンジ色の人参を見て、彼女は一瞬立ち止まった。その視線には、恐怖と興味が入り混じっていた。
「皮を剥くところから始めましょう」と私が声をかけると、彼女はゆっくりとピーラーを手に取った。
手を動かすこと。それだけに集中する時間。
人参の皮が剥かれ、鮮やかなオレンジ色の断面が現れる。「きれいな色ですね」と私が言うと、彼女も小さく頷いた。「本当に、きれいです」
人参を薄く輪切りにしていく。包丁を握る手は少し震えていたが、彼女は丁寧に、慎重に切っていった。
「上手ですね。お料理、以前はしていたんですか」
「……小学生の頃は、母と一緒によく作ってました」
彼女の声には、懐かしさが滲んでいた。
切った人参を鍋に入れる。水を注ぎ、バターを加え、砂糖を振りかける。火にかけると、じわじわと甘い香りが立ち上った。
彼女の表情が、わずかに変わった。
「……いい匂い」
その声は、驚きに満ちていた。まるで、長い間忘れていた何かを思い出したような。
鍋の中で人参が柔らかくなり、照りが出てくる。バターと砂糖が絡み、艶やかな琥珀色に変わっていく。その様子を、彼女はじっと見つめていた。
「こんなに綺麗な色になるんですね」と彼女が呟いた。
「ええ。人参は、火を通すと甘みが増して、とても美しい色になります」
彼女は鍋を覗き込み、湯気の向こうの人参を見つめた。そして、ふと私を見た。
「少しだけ、味見してみてもいいですか」
その言葉に、私は驚いた。彼女から「食べたい」という言葉が出るとは思っていなかったからだ。
「もちろんです。でも、無理はしないでくださいね」
彼女は深く息を吸った。フォークで人参を一切れ取り、自分の皿に置く。それを見つめること数秒。やがて彼女は、フォークを持ち上げた。
手が震えている。呼吸が少し速くなっている。
ほんのひと口。
口に入れた瞬間、彼女の目が大きく見開かれた。
「……あまい」
その声は、か細かったけれど、確かに届いた。そして彼女は、もう一度口を開いた。
「おいしい」
それは、彼女が他者の前で「おいしい」と言えた、初めての瞬間だった。
彼女の目から涙がこぼれた。けれど、それは悲しみの涙ではなかった。
「忘れてました。人参って、こんなに甘いんですね。昔、母が作ってくれたグラッセも、こんな味だった」
彼女は静かに泣きながら、もう一口、人参を口に運んだ。
これが「再起動」だった。再起動とは、停電していた心身の機能が、少しずつ回復し始める過程を指す。完全に恐怖が消えたわけではない。けれど、「食べる=恐怖」だけではなく、「食べる=感じる」という感覚が、ほんの一瞬だけ蘇った。
止まっていた何かが、ほんの少しだけ動き始めた。
食べることは、生きることの根源的な行為だ。けれど拒食症の人にとって、それは恐怖であり、罰であり、戦いになる。
なぜか。
それは、食べることが「感じること」と深く結びついているからだ。
味を感じる。香りを感じる。温かさを感じる。そして「おいしい」と感じる。それは単なる味覚の問題ではなく、「自分が生きている」ことを実感する行為だ。
拒食症の人は、その「感じる力」を失っている。正確には、感じることを恐れている。感じることは、感情を動かすことだ。喜びも、悲しみも、苦しみも。それらすべてを避けるために、彼女たちは「食べない」ことを選ぶ。
けれど、人参の甘さを感じた瞬間、彼女の中で何かが繋がった。
味覚の回復は、「身体と心の再統合」を意味する。長い間切り離されていた感覚と感情が、再び結びつく。それは小さな、けれど確かな変化だった。
その後のセッションで、彼女はこう話してくれた。
「あの日から、少し変わったんです。食べることが、前ほど怖くなくなった。まだ怖いときもあるけど、『おいしい』って感じられることもある」
彼女は少しずつ食べられるものを増やしていった。最初はほんの一口。次は二口。やがて、一食分。
完全に恐怖が消えたわけではない。今でも、食べることに不安を感じる日はある。体重計の数字に怯える日もある。
けれど彼女は、もう「食べる=悪」とは思っていない。
ある日、彼女が嬉しそうに報告してくれた。
「昨日、母と一緒に夕飯を作ったんです。母の日のお返しに、私がご飯を作りたいって」
「素敵ですね。何を作ったんですか」
「人参のグラッセと、チキンのソテーと、サラダ。母が『おいしい』って言ってくれました」
彼女の顔には、誇らしげな笑顔があった。
「食べることは、生きることなんだと思えるようになりました」
そう彼女が言った時、私は深く頷いた。
半年後、彼女の体重は少しずつ増えていった。まだ標準には届いていなかったが、健康的な範囲に近づいていた。
そして一年後、彼女は高校を卒業し、調理の専門学校に進学することを決めた。
「料理を作ることが、楽しいんです。人に『おいしい』って言ってもらえるのが、嬉しい。将来は、誰かを笑顔にできる料理人になりたい」
彼女のその言葉を聞いて、私は深く感動した。
かつて食べることを恐れていた少女が、今度は誰かのために料理を作りたいと願っている。それは、完全な再起動だった。
作業療法士として、私が大切にしているのは「五感の再接続」だ。
停電している心は、感じる力を失っている。見る、聞く、触れる、嗅ぐ、味わう——それらの感覚が鈍り、時には完全に遮断される。
再起動のためには、その感覚を少しずつ取り戻す必要がある。
彼女の場合、それが「味覚」だった。人参の甘さという、ほんの小さな感覚が、彼女を「生きる方」へ導いた。
作業療法では、こうした「感じる体験」を安全な環境で提供する。無理に食べさせるのではなく、調理という行為を通して、香りや色、温かさに触れる。手を動かし、五感を使う。その過程で、少しずつ心が開いていく。
食べることは、単なる栄養摂取ではない。それは「生きる実感」そのものだ。
一口の人参が、彼女の「生き直す」始まりになった。その瞬間を、私は忘れない。
—
※本文における用語の定義
停電: 心身の機能が一時的に失われ、感じる・考える・動くといった活動が停止している状態。感覚が鈍り、感情が動かなくなった状態を指す。拒食症においては、特に「おいしい」という感覚や、食べることの喜びが完全に遮断され、食事が恐怖の対象となった状態を意味する。
再起動: 停電していた心身の機能が、少しずつ回復し始める過程。感覚や感情が再び動き始める、段階的な変化を意味する。完全な回復ではなく、微細な感覚——味わう、感じる、楽しむ——が少しずつ戻ってくる過程を指す。
❏ライタープロフィール
内山遼太(READING LIFE公認ライター)
千葉県香取市出身。現在は東京都八王子市在住。
作業療法士。終末期ケア病院・デイサービス・訪問リハビリで「その人らしい生き方」に寄り添う支援を続けている。
終末期上級ケア専門士・認知症ケア専門士。新人療法士向けのセミナー講師としても活動中。
現場で出会う「もう一度◯◯したい」という声を言葉にするライター。
2025年8月より『週刊READING LIFE』にて《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》連載開始。
❏ライタープロフィール
内山遼太(READING LIFE公認ライター)
千葉県香取市出身。現在は東京都八王子市在住。
作業療法士。終末期ケア病院・デイサービス・訪問リハビリで「その人らしい生き方」に寄り添う支援を続けている。
終末期上級ケア専門士・認知症ケア専門士。新人療法士向けのセミナー講師としても活動中。
現場で出会う「もう一度◯◯したい」という声を言葉にするライター。
2025年8月より『週刊READING LIFE』にて《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》連載開始。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-
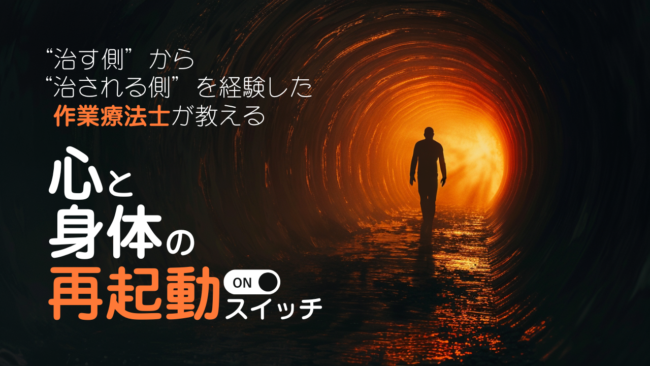
片麻痺の若者が”洗濯バサミで服を干した”午後《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
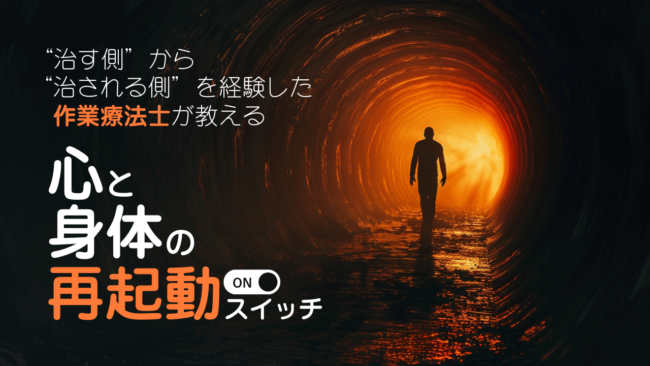
パーキンソン病の男性が”椅子を拭いた”日常動作の意味《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
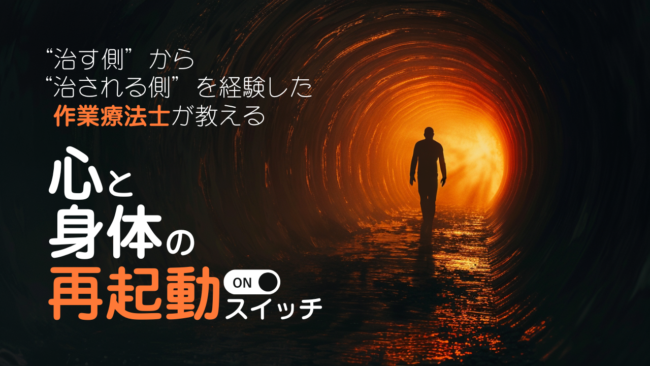
脳卒中で利き手を失った女性が”左手でおにぎり”を握った朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
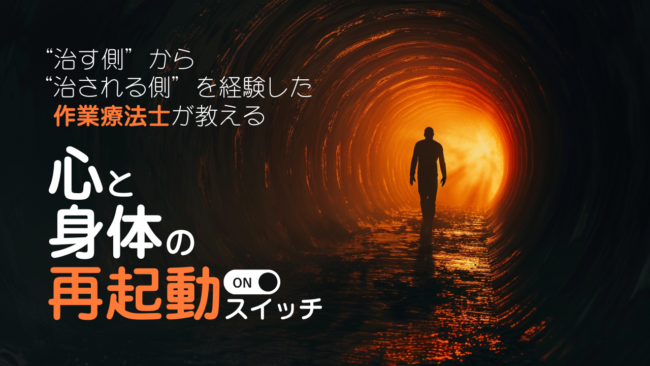
感情表出できなかった男性が”絵”に怒りを描いた日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
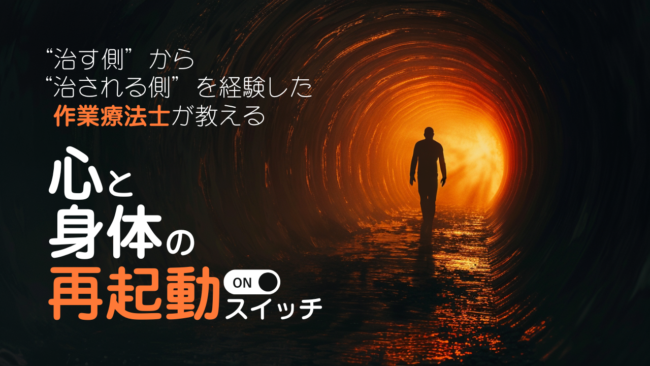
心的外傷を抱える母が”折り紙を子どもに渡せた”瞬間《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》



