ひきこもり5年の青年が、初めて「今日」を刻んだ朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
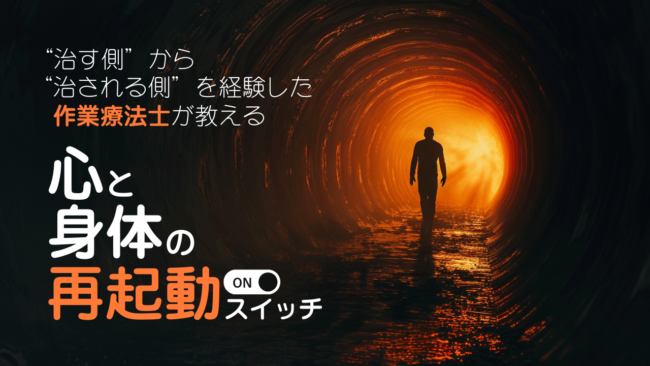
2025/11/10/公開
記事:内山遼太(READING LIFE公認ライター)
※一部フィクションを含みます。
彼の部屋には、時間がなかった。カーテンは閉ざされ、昼夜の区別もなく、曜日も関係がない。そんな彼が、ある朝、静かにカレンダーを壁に貼った。誰に言われたわけでもない。その一枚の紙が、止まっていた時間を、少しずつ動かしはじめた。
——
彼と初めて会ったのは、訪問作業療法の依頼を受けてからだった。二十代半ば、ひきこもり生活は五年に及んでいた。外出はゼロ。昼夜は完全に逆転し、家族とも顔を合わせることはほとんどない。
部屋のドアをノックすると、長い沈黙の後、小さな声が聞こえた。「……どうぞ」
中に入ると、そこは薄暗かった。カーテンは固く閉ざされ、窓からの光は一切入ってこない。部屋の隅には布団が敷かれ、その周りには空のペットボトルやカップ麺の容器が散乱していた。パソコンのモニターだけが、青白い光を放っていた。
彼はベッドの端に座り、視線を床に落としたまま、私の方を見ようとしなかった。
「こんにちは。作業療法士の者です」と私は声をかけた。彼は小さく頷いただけだった。
会話は続かなかった。私が何を尋ねても、返ってくるのは「はい」「いいえ」「わかりません」だけ。それでも私は、週に一度、彼の部屋を訪れ続けた。
初回の訪問を終えて、母親が廊下で私にこう話した。
「息子は、高校を卒業してすぐ、ひきこもるようになったんです。大学に落ちて、それから部屋から出なくなって。最初は少しの間だと思っていたのに、もう五年です」
母親の目には、疲労と諦めが混じっていた。
「食事は部屋の前に置いておくと、夜中に取りに来ます。でも、私たちとは話しません。このまま、ずっとこうなんでしょうか」
その声には、深い絶望があった。
ある日、私は部屋の様子を観察しながら、ふと気づいた。
時計がない。カレンダーもない。この部屋には、「時間」を示すものが何もなかった。
「今日が何曜日か、わかりますか」と尋ねると、彼は首を横に振った。「何日かも、わかりません」
「今、季節は何だと思いますか」
彼は少し考えてから、「……春、ですか」と答えた。けれど、その日は十月の秋だった。
彼の部屋には、時間が存在しなかった。
ひきこもり生活が長期化すると、「昨日」と「今日」と「明日」の区別がなくなる。曜日も、日付も、季節さえも意味を失う。それは単なる「時間感覚の喪失」ではなく、「停電」の一つの形だった。
停電とは、心身の機能が一時的に失われ、感じる・考える・動くといった活動が停止している状態を指す。彼の場合、時間が止まることで、生活のリズムも、役割も、目的も、すべてが途切れていた。社会との接点が失われ、自分がどこにいるのか、いつなのかもわからなくなる。
彼は、そんな「時間のない世界」に、五年間閉じ込められていた。
最初の数週間、私たちはほとんど会話をしなかった。私が部屋に入ると、彼は小さく会釈をする。そして沈黙。私は無理に話しかけず、ただそこに座っていた。
「今日はいい天気ですよ」と窓の外のことを話す。彼は頷くだけ。「最近、何か気になることはありますか」と尋ねる。「特にないです」と短く答える。
けれど、私は諦めなかった。
作業療法士としての訪問の目的は、必ずしも「すぐに変化を起こすこと」ではない。まずは「安全な人間関係」を築くこと。この部屋が、少しでも安心できる場所になること。それが最初の一歩だった。
三週目の訪問で、彼が少しだけ話してくれた。
「先生は、なぜここに来るんですか」
「あなたと話すためです」
「でも、僕、何も話せません」
「話せなくても大丈夫です。ただ、ここにいるだけでいい」
彼は不思議そうな顔をした。「それで、いいんですか」
「ええ。あなたがここにいて、私がここにいる。それだけで十分です」
彼は少し考え込むような表情を見せた。そして、小さく頷いた。
四週目の訪問で、小さな変化があった。
部屋に入ると、彼が珍しく自分から口を開いた。
「あの、聞いてもいいですか」
「はい、何でしょう」
「先生は、毎週同じ曜日に来てるんですか」
「ええ、そうですよ。毎週水曜日の午後二時です」
彼は少し考え込むような表情を見せた。「そうなんですね。曜日、わからなくなってて」
その言葉に、私は希望を感じた。「曜日を知りたい」と思うこと。それは、時間に関心を持ち始めた証拠だった。
「外の世界には、曜日があるんですよね」と彼が言った。
「ええ。月曜日から日曜日まで、一週間が繰り返されています」
「僕には、それがない。毎日が同じで、どこからどこまでが一日なのかもわからない」
彼の声には、微かな寂しさが滲んでいた。
「時間を取り戻したいですか」と私は尋ねた。
彼は長い沈黙の後、小さく頷いた。
ある日、私は彼の部屋の壁に古いポスターが貼られているのに気づいた。色褪せたアニメのキャラクターが描かれたそれは、何年も前のものだった。端が剥がれかけていて、ところどころ黄ばんでいた。
「このポスター、お好きなんですか」と尋ねると、彼は少しだけ顔を上げた。
「……昔は。高校生の頃、好きだったアニメです」
「そうですか。大切な思い出なんですね」
「でも、もう古いから。このアニメ、もう終わったし」
彼は壁を見つめながら、ぽつりと言った。「これ、もう使えないんですよね」
「新しく何か貼りたいものはありますか」
彼は少し考えてから、こう言った。「……カレンダー、あったらいいかもしれません」
その言葉は、私にとって小さな驚きだった。ひきこもりの人にとって、カレンダーは時に苦痛の象徴になる。過ぎていく日々、何もしていない自分、変わらない毎日——それらを突きつけられるからだ。
けれど彼は、カレンダーを求めた。
「どうして、カレンダーが欲しいんですか」と私は尋ねた。
彼は少し考えてから、答えた。「今が、いつなのか知りたい。先生が来る日も、ちゃんと覚えておきたいから」
その言葉に、私は深く感動した。彼の中で、何かが動き始めていた。
「わかりました。次回、お持ちしますね」
彼は小さく頷いた。
翌週、私は一冊のカレンダーを持って彼の部屋を訪れた。シンプルな紙製のもので、月ごとにめくれるタイプだった。大きな数字と曜日が書かれていて、余白にはちょっとしたメモも書き込める。
「これ、使ってみますか」と差し出すと、彼はそれを受け取り、しばらく見つめていた。
「……貼ってもいいですか」
「もちろんです。どこに貼りましょうか」
彼は立ち上がり、壁に向かった。古いポスターを、ゆっくりと剥がす。長年貼られていた跡が、壁に四角く残っていた。彼はその跡を指でなぞった。
「五年間、ここにあったんですね」と彼が呟いた。
「新しいものを貼る時が来たんですね」
彼は頷いた。そして、その場所に新しいカレンダーを貼る。手は少し震えていたけれど、彼は丁寧に、まっすぐに貼った。
カレンダーが壁に収まった。白い紙に黒い数字。今月の日付が並んでいる。
彼は一歩下がって、それを眺めた。そして、カレンダーの「今日」の日付を指でなぞった。
「……今日は、水曜日なんですね」
その声には、どこか安堵のような響きがあった。
「そうです。十月の第一水曜日です」
彼はもう一度カレンダーを見つめた。「十月、か。もう秋なんですね」
「ええ。外の木々も、少しずつ色づいてきていますよ」
彼は窓の方を見た。カーテンは閉まったままだったけれど、その向こうに世界があることを、彼は思い出したようだった。
「いつか、カーテンを開けてみたいです」と彼が言った。
「その日は、きっと来ますよ」
これが「再起動」だった。再起動とは、停電していた心身の機能が、少しずつ回復し始める過程を指す。止まっていた時間が、ほんの少しだけ動き始める。完全に元通りになるわけではない。けれど、「今」という瞬間を知ることが、世界との繋がりを取り戻す第一歩になる。
カレンダーを貼る——それは、一見すると何でもない行為だ。けれど、ひきこもりの人にとって、それは大きな意味を持つ。
カレンダーは「社会時間」との接続を象徴する。
曜日があるということは、月曜日があり、週末があり、人々が働き、休む——そんな社会のリズムが存在するということだ。それを知ることは、自分が「社会の外」にいることを認識することでもある。
けれど同時に、それは「戻れる場所がある」ことを示している。
彼がカレンダーを貼ったことで、彼の部屋に「今日」が生まれた。そして「今日」があるということは、「明日」もあるということだ。
翌週、彼は自分からカレンダーの話をした。
「先生、今日は水曜日ですよね」
「そうですよ。よく覚えていましたね」
「毎日、見てます」と彼は言った。「朝起きたら、今日が何日か確認するようになって」
「それは素晴らしいですね」
彼は少し照れくさそうに笑った。「まだ、昼夜逆転は治ってないんですけど。でも、今日が何曜日かわかるだけで、少し違うんです」
「どう違いますか」
「なんていうか、自分が生きてるって感じがします。時間が流れてるって」
その言葉を聞いて、私は深く頷いた。
その後、彼は少しずつ変わっていった。
カレンダーを見る習慣がつき、日付を意識するようになった。「今日は金曜日だから、明日は土曜日か」と呟くようになった。やがて、「来週の水曜日に、また来てもらえますか」と、未来の予定を口にするようになった。
それは小さな、けれど確かな変化だった。
ある日、彼はカレンダーに丸印をつけていた。
「これは何ですか」と尋ねると、彼は答えた。「先生が来る日です。水曜日に印をつけておくと、忘れないから」
彼は、時間を「管理」し始めていた。予定を立て、それを覚えておく。それは社会生活の基本的なスキルだ。
数週間後、カレンダーには他の印も増えていた。
「これは?」と私が尋ねると、彼は少し恥ずかしそうに答えた。
「ゴミの日です。母が、いつも大変そうだから。僕も少しは手伝おうと思って」
「実際に、手伝ったんですか」
「いえ、まだ。でも、いつか」
その「いつか」という言葉に、未来への希望が込められていた。
数ヶ月後、彼のカレンダーにはさらに多くのメモが書き込まれていた。「母の誕生日」「年末」「初日の出」——小さな予定が増えていた。
「少しずつ、やることを書き込むようにしてます」と彼は言った。「そうすると、一日が少し意味を持つような気がして」
そして、ある日のこと。
彼が「来週、カーテンを開けてみようと思います」と言った。
「本当ですか」
「はい。五年ぶりに、外の光を見てみたい」
翌週、訪問すると、彼の部屋に細い光の筋が入っていた。カーテンが、ほんの少しだけ開いていた。
「開けたんですね」
「少しだけ。まだ全部は無理だけど、少しずつ」
彼の顔に、柔らかな光が当たっていた。
作業療法士として、私がこの過程で学んだことがある。それは、リハビリテーションの本質は「他者とつながること」だけではなく、「時間と再会すること」でもあるということだ。
時間が動き始めることで、人は再び「生きている」ことを実感する。過去があり、現在があり、未来がある。その連続性の中に、自分の居場所を見つける。
彼にとって、カレンダーはその入り口だった。
半年後、彼は大きな決断をした。「外に出てみようと思います」
最初は玄関まで。母親が驚きの表情で見守る中、彼は玄関のドアを開けた。そして、一歩だけ外に足を出した。
「空気が、冷たいですね」と彼は言った。
次は家の前まで。その次は、郵便ポストまで。そして、近所のコンビニまで。少しずつ、少しずつ、彼の世界は広がっていった。
一年後、彼は私にこう話してくれた。
「あのカレンダーを貼った日のこと、覚えてます。あの日から、何かが変わった気がします。時間が、また動き始めたような」
「今は、どんな気持ちですか」と私は尋ねた。
「まだ怖いです。社会に戻れるかどうかもわからない。でも、少しずつ前に進んでる気がします。カレンダーを見るたびに、『今日』があって、『明日』があるって思えるんです」
彼は今、週に数回、外に出るようになった。まだアルバイトや仕事には至っていないけれど、図書館に行ったり、公園を散歩したりする。
新しいカレンダーには、「図書館」「散歩」という予定が書き込まれている。そして、未来の日付には「ハローワーク」という文字もあった。
ある日、彼が母親と一緒に私のところに来た。母親は涙を浮かべながら、こう言った。
「息子が、自分から外に出たいと言ったんです。五年間、ずっと部屋にいたのに。ありがとうございます」
彼は少し照れくさそうに笑った。「まだ、ちゃんと社会復帰できたわけじゃないですけど。でも、もう時間は止まってない。前に進んでる気がします」
停電していた時間が、再起動する。それは突然の変化ではなく、静かで、ゆっくりとした変化だ。けれどその変化は、確実に人生を前に進める。
一枚の紙——カレンダーという、ありふれた日用品が、彼の人生の針を再び動かした。
作業療法では、こうした「日常的な道具」を使って、心の再起動を支える。カレンダー、時計、ノート、ペン。それらは特別なものではない。けれど、使い方次第で、人生を変える力を持つ。
彼がカレンダーを壁に貼った朝。その瞬間を、私は忘れない。
それは、止まっていた時間が再び動き始めた朝だった。そして、一人の青年が、再び世界とつながり始めた朝だった。
—
※本文における用語の定義
停電: 心身の機能が一時的に失われ、感じる・考える・動くといった活動が停止している状態。時間感覚や生活リズムが途切れ、社会との接続が断たれた状態を含む。ひきこもりにおいては、「昨日」「今日」「明日」の区別がなくなり、時間が存在しない世界に閉じ込められた状態を指す。
再起動: 停電していた心身の機能が、少しずつ回復し始める過程。完全な回復ではなく、微細な感覚や行為から徐々に心が動き始める段階的な変化を意味する。時間との再会や、生活リズムの回復を通じて、心が再び動き始める過程を指す。一瞬で完了するものではなく、ゆっくりと、確実に前進していく変化である。
❏ライタープロフィール
内山遼太(READING LIFE公認ライター)
千葉県香取市出身。現在は東京都八王子市在住。
作業療法士。終末期ケア病院・デイサービス・訪問リハビリで「その人らしい生き方」に寄り添う支援を続けている。
終末期上級ケア専門士・認知症ケア専門士。新人療法士向けのセミナー講師としても活動中。
現場で出会う「もう一度◯◯したい」という声を言葉にするライター。
2025年8月より『週刊READING LIFE』にて《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》連載開始。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院カフェSHIBUYA
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号
MIYASHITA PARK South 3階 30000
TEL:03-6450-6261/FAX:03-6450-6262
営業時間:11:00〜21:00
■天狼院書店「湘南天狼院」
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目18-17
ENOTOKI 2F
TEL:04-6652-7387
営業時間:平日10:00~18:00(LO17:30)/土日祝10:00~19:00(LO18:30)
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「名古屋天狼院」
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-14先
Hisaya-odori Park ZONE1
TEL:052-211-9791
営業時間:10:00〜20:00
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
関連記事
-
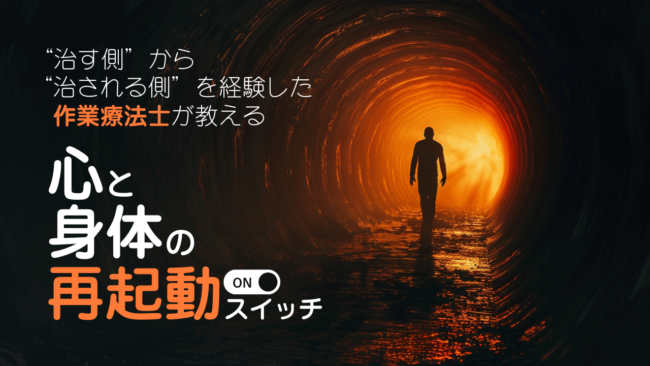
パーキンソン病の男性が”椅子を拭いた”日常動作の意味《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
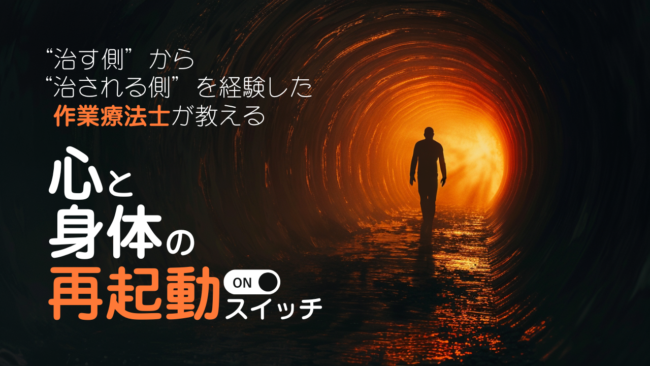
脳卒中で利き手を失った女性が”左手でおにぎり”を握った朝《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-

第3回 《週間READING LIFE「けっこん、します」》
-
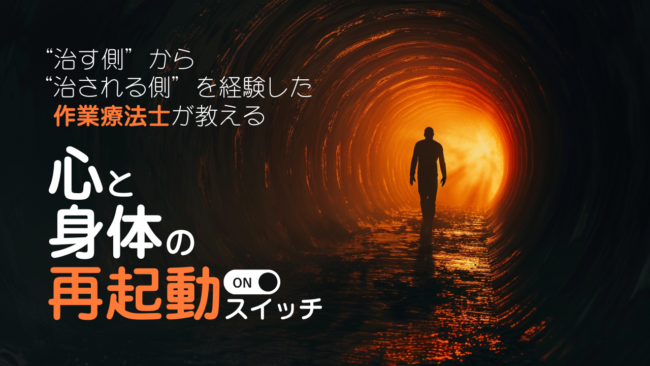
感情表出できなかった男性が”絵”に怒りを描いた日《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》
-
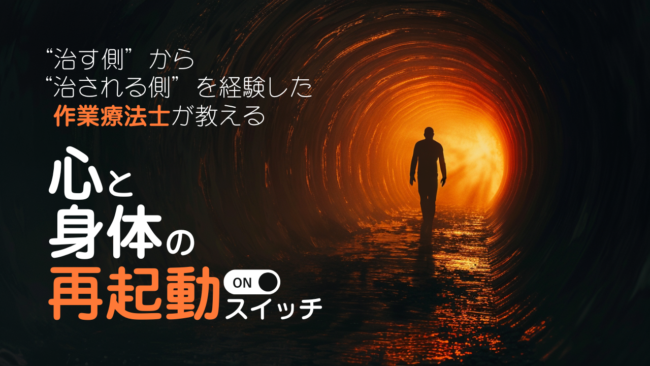
心的外傷を抱える母が”折り紙を子どもに渡せた”瞬間《“治す側”から”治される側”を経験した作業療法士が教える『心と身体の再起動スイッチ』》



