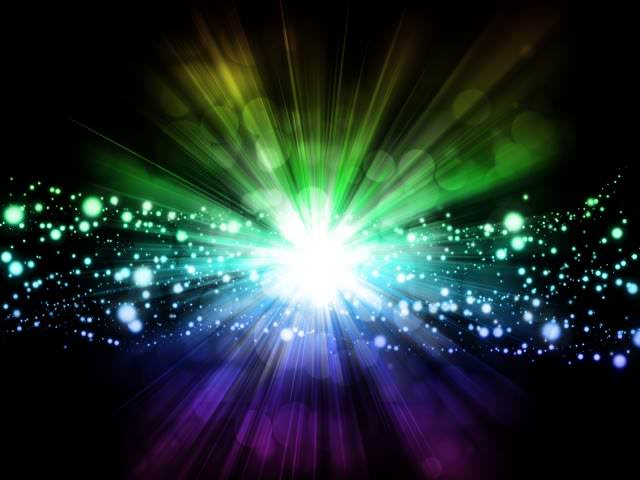こんな田舎、絶対に戻るもんかと思っていたのに《週刊READING LIFE vol.6「ふるさと自慢大会!」》

記事:大國 沙織(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
「どこ出身?」
このセリフは、初対面の人によく聞かれる質問ベスト3に入るだろう。
でもどうかお願いだから、私には聞かないでほしい。
出身地を聞かれると、いつも困ってしまう。
何と答えるのがベストなのか、未だに正解がわからない。
私の生まれは、東京都文京区だ。
でも、3歳までしか住んでいなかったので、記憶はないに等しい。
その後は父の仕事の関係で渡米し、小学校1年生まで、ネブラスカ州のオマハという田舎町で過ごした。
3年間住んだので、思い出もそれなりにできたけれど、帰国したら英語はきれいさっぱり忘れてしまった。
今も、英語はほとんど話せない。
しばらくは群馬や東京などを転々とし、根なし草生活を続けてきた私達家族は、ようやく新天地にたどり着いた。
それが、千葉県の鴨川市だった。
海と山に囲まれた、よく言えばのどかな、悪く言えば何もない場所である。
都内からは、特急か高速バスを使っても、2時間半。
電車は、1時間に1本しかない。
それどころか、たまにイノシシが衝突して電車が止まる。
どこからどう見ても、立派な田舎である。
転校初日の自己紹介には慣れっこになっていた私も、ここにはなかなか馴染むことができなかった。
というか、この地を去るその日まで、ついに馴染めなかったのだけれど……。
日本の田舎は、アメリカのそれとは全く勝手が違った。
小学生にしてすでにコミュニティができあがっていて、私は完全によそ者扱いを受けた。
仲間はずれは辛かったけれど、それでも構わなかった。
どうせまた、「引っ越すことになったよ」と親に言われるだろうから。
これまでだって、いつもそうだった。
やっと友達ができたと思っても、すぐに別れの時はやってくる。
それならばいっそ、友達なんて作らない方がラクかもしれない。
ところが今度は、一向に引っ越しの気配はなかった。
両親はこの新しい場所を気に入って、すっかり腰を落ち着けてしまったように見えた。
私だけがいつも、自分の居場所はどこにもないと感じていた。
そのうちさすがの私も、ここでうまくやっていくしか道はないのだと悟った。
ようやく一緒に遊ぶ友達もできて、学校に行くのが苦痛ではなくなってきた、ある日のこと。
「やっぱり、私は仲間に入れてもらえないんだ」と、痛感させられる出来事が起こった。
地元のお祭に、私だけ参加させてもらえなかったのだ。
理由は単純だった。
「さおりちゃんは、よそ者だからダメ」
友達だと思っていた数人に言われたに過ぎないので、ちゃんと大人に頼んだら、もしかすると参加させてもらえたかもしれない。
でも、それ以上拒否されるのがこわくて、早々に諦めてしまったのだ。
なんとなくそれがトラウマになってしまい、なにかにつけ、自分がよそ者であるという実感がずっとつきまとった。
中学〜高校時代は、「高校を卒業したら、絶対に家を出るんだ」と思っていた。
それだけが、希望だった。
立地的にも、都内の大学に進学する者が多かった。
毎日家から通学するのには、さすがに無理がある距離だ。
しかも海辺なので、風が強いとすぐに電車が止まってしまう。
私にとって、地元に残るという選択肢は皆無だった。
もっとも、ここを「地元」だと認識したことはなかったのだけれど。
ところが、根拠のない自信だけはあった私は、すべり止めの受験を全くせず、浪人を余儀なくされてしまった。
今振り返ると、自分の実力さえ正確に把握できていないのには呆れるしかないが、この事態は全くの想定外だった。
でも、どうにかして家を(というかこの田舎を)抜け出したい。
あれこれ考えた末、私は両親にある提案をした。
大阪によさそうな個人指導塾があるから、そこで浪人生活を送りたいと。
両親は、拍子抜けするほどあっさりと認めてくれた。
それが、「あなたは家にいてもだらけそうだから、逆にいいかもね」という理由だったのはちょっと悔しいけれど、そんなことはもはやどうでもいい。
やっと、この場所を離れられるのだから。
窮屈で、つまらなくて、どこにも居場所を見出せないこの田舎から、ようやく逃げ出せるのだから。
初めて訪れた大阪は、はたしてこれが同じ国か、と思うほどカルチャーショックの連続だった。
言葉も、食べ物の味付けも、エスカレーターで立つ位置でさえも。
でも、塾の先生達は皆面倒見がよく、いつも感じよく接してくれ、「よそ者」の私を温かく受け容れてくれた。
塾の雰囲気もオープンで、閉鎖的な要素はまったくなかった。
私は、やっと自分の居場所を見つけられた気分だった。
そのうち、都内の大学をまた受験しようという私の決意は、徐々に揺らぎはじめる。
関西人の気さくな雰囲気はなんとも居心地がよく、私の性に合ったのだ。
結局、関西の大学ばかり受験し、京都の大学に進学が決まった。
古典文学が好きだった私は、京都という場所に、ある種の特別な憧れを抱いていた。
けれど、住むには不安もあった。
生粋の京都人の中には、「いけず」な人もいると、聞いたからである。
でも実際にフタを開けてみると、全然そんなことはなかった。
京都の人達も、学生の私には総じて親切にしてくれたし、そもそも京都には外から来た「よそ者」も多かった。
県外から移住してくる人も意外と多く、海外の人も少なくない。
そうなるともはや、自分が「よそ者」だとは思わなくなる。
京都はあまりに居心地がよく、結局7年も住んだ。
その魅力はとても語り尽くせないが、一つだけ取り上げるなら、やっぱり「鴨川」の存在は無視できないだろう。
京都の人(特に学生)は、どうしてあんなにも鴨川が好きなんだろう。
よっぽどの悪天候でもない限り、鴨川に人がいないのを見たことがない。
ただ河原に座っておしゃべりに興じる人(これが一番多い)、ピクニックする人、ヨガや太極拳をする人、楽器の練習をする人……。
何をしても許されるような懐の広さが、鴨川にはあるのだろう。
ちなみに私の地元の地名も、同じ漢字で同じ読みの「鴨川市」。
なんとも皮肉なことである。
「鴨川がどうのこうの」と言う話になると、「どっちの鴨川?」と誰かが確認するのは、もう我が家あるあるだ。
そんなにも大好きな京都を泣く泣く離れることにしたのは、やはり就職のためだった。
就職希望の出版社は、都内にあったのだ。
就職先を取るか、居住地を取るか。
かなり迷ったが、最終的には仕事の内容で選んだ方が後悔しないと思った。
けれど、東京に住むのは私にとって想像以上にハードで、試練の連続だった。
東京で生まれ、しばらく住んでいたはずなのに、私の身体と心は、そこで暮らすことを明らかに拒否していた。
空気が淀んでいて、呼吸がしづらい。
人混みを歩くだけで酔ってしまい、気分が悪くなる。
夜中まで鳴り止まない騒音。
それまでなんともなかった食べ物で起こる、アレルギー症状の数々。
昼も夜もないような、生活リズムの毎日。
いつか慣れることを期待しつつ、仕事のため、と思い無視し続けていたが、半年で限界がきた。
心身ともにボロボロになっていた私には、田舎の実家で静養する以外に選択肢はなかった。
ところが、8年ぶりに(千葉の)鴨川に戻ってきて、驚いた。
空気が、こんなにも澄んでいて美味しいとは。
これなら、思いっきり深呼吸できる。
聞こえてくるのは、鳥のさえずり、虫やカエルの声、田んぼの水の流れる音だけ……。
少し車を走らせれば、世界中からサーファーが集まる、美しいビーチが広がる。
夕方には、連なる山間に沈んでいくドラマチックな夕日。
毎日表情が違うので、見ていて全く飽きない。
夜になれば、まるで降るような満天の星空。
鴨川には、何もないと思っていた。
こんなに自然が豊かだなんて、全然気づかなかった。
私はいつも、この場所の悪いところしか見ていなかったのだ。
でも思い返せば、当時から色々な恩恵に預かっていた。
私が、ちっとも自覚できていなかっただけで……。
そういえば小学生の頃は、つまみ食いしながら家に帰るのが楽しかった。
野の花を摘んで蜜を吸うと、うっとりと甘くて幸せな気持ちになった。
花の種類によって少しずつ味が違うので、その変化も面白かった。
田舎育ちで私よりも草花に詳しい友人は、「こっちの方が美味しいよ!」と私にすすめてくれたりもした。
木いちごはジューシーで甘酸っぱくて、たまにハズレもあるのが、また盛り上がった。
みかんや柿も、実質食べ放題だった。
本当は人の家のものだが、田舎の人にとってはあまりにありふれているので、わざわざ収穫する人もおらず、朽ちるまで放ったらかしなのだ。
初めてそれを知ったときは、「なんてもったいない!」と驚いたものだが、毎年食べきれないほど沢山実るとなると、珍しくもなくなるのだろう。
田舎とは、実に豊かである。
中学時代には、いつも部活帰りに、体操着のまま海に飛び込んでいた。
友人達と波に身を任せて泳いでいると、自然と練習の疲れも取れ、先輩や顧問に怒られたことも忘れられた。
泳ぎ疲れたら浜辺に座り、髪が乾くまでひとしきりおしゃべりした。
体操着が塩まみれになるので、母にはやめてくれと言われたものだけれど、気持ちがいいのでなかなかやめられなかった。
中学と高校は自転車通学だったが、誰もいない田んぼのあぜ道を、よく大声で歌いながら帰った。
今振り返ると、これ以上ない最高の環境でのびのびと過ごせた、贅沢な青春時代だったと思う。
そして、都会に疲れて弱っていた私には、自然は何よりの薬だった。
散歩をしているだけで、田園風景の美しさに癒され、涙が出そうになった。
Uターンして、改めて地元の良さに気づくという話はたまに聞くけれど、まさか自分がそうなるとは、誰が予想しただろう。
そもそも体調なんて崩さなかったら、一生帰る気はなかったのだ。
すっかり元気になった今、どこに住んでもいいのだけれど、やっぱり田舎に暮らしたい。
景色はどこを見渡しても美しいし、何を食べても新鮮で美味しい。
そして、生活に余白がある。
余計な情報が入って来過ぎないから、自分の感覚を研ぎ澄ませられる。
いや、畑仕事や薪割りなど、やることは無限にあるのだけれど、それさえも豊かなのだ。
暮らしを自分でクリエイトする楽しさがある。
高校までは、面倒だと見向きもしなかった労働を、面白いと感じている自分がいる。
田舎の人にとっては当たり前な生活の全てが、一周回って私には新鮮なのだ。
あれだけ疎外感を感じていた田舎特有の人間関係も、今は全く気にならない。
きっと関係性が濃密な組織に私が属していないから、ということもあるだろう。
でもそれ以上に、隣近所にどんな人が住んでいるかがわかっていて、日々挨拶を交わしたり、野菜をおすそ分けし合ったりするような関係が心地よい。
お互いに踏み込み過ぎないけれど、なんともいえない安心感がある。
近過ぎず、遠過ぎずな感じでちょうどいいのだ。
今だから断言できるけれど、私の地元・鴨川は、本当にいいところだと思う。
高校時代の私が聞いたら、卒倒してしまうかもしれないけれど。
そして、心からそう思えるようになったことが、この上なく嬉しい。
未だに「出身は?」と聞かれたら困ってしまうけれど、でもそろそろ、「千葉の鴨川です!」って胸を張って答えてもいいのかもしれない。
厳密には出身地とは言えないかもしれないけれど、私にとっては、やっぱり「ふるさと」と呼べるような場所は、ここ以外にはないのだから。
❏ライタープロフィール
大國 沙織(Saori Ohkuni)
1989年東京都生まれ、千葉県鴨川市在住。
4〜7歳までアメリカで過ごすも英語が話せない、なんちゃって帰国子女。高校時代に自律神経失調を患ったことをきっかけに、ベジタリアンと裸族になり、健康を取り戻す。
同志社大学文学部国文学科卒業。同大学院総合政策科学研究科ソーシャル・イノベーションコース修士課程修了。
正食クッキングスクール師範科修了。インナービューティープランナー®。
出版社で雑誌編集を経て、フリーライター、料理家として活動。毎日何冊も読まないと満足できない本の虫で、好きな作家はミヒャエル・エンデ。
【メディア掲載】マクロビオティック月刊誌『むすび』に一年間連載。イタリアのヴィーガンマガジン『Vegan Italy』にインタビュー掲載。webマガジン『Vegewel Style』に執筆中。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/62637