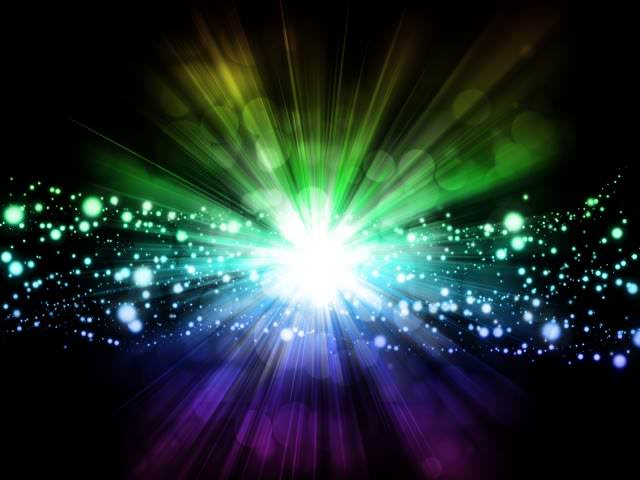望郷は国境を越えて《週刊READING LIFE vol.6「ふるさと自慢大会!」》

記事:江島 ぴりか(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
赴任先が〝ウラジオストク〟と知らされたとき、それがどこの町なのか全く見当がつかなかった。
ロシアへの派遣プログラムなのだから、ロシア国内であることは間違いない。
しかし、待遇の手厚さだけで選んだプログラムだったので、当時の私はロシアといえばモスクワぐらいしか思いつかなかった。
地図を広げ、モスクワから出発して、順にシベリア鉄道の沿線をたどってみた。
モスクワ……、エカテリンブルグ……、ノボシビルスク……、イルクーツク……、ハバロフスク……、ウラジオストク……。
あ、あった、ウラジオストク!
場所を確認して、ひどくがっかりしたのを覚えている。
あんなに広大なロシアの中で、一番東の端っこ、新潟空港から2時間もかからずに着いてしまう町だった。
ようやくあこがれの海外生活がかなうと思ったのに、よりによって日本のすぐ近くだ。
これじゃあ、なんだか海外に行く気がしない。
生まれ故郷の北海道から東京に行くのと大して変わらないじゃないか。
違うのはパスポートとビザが必要なことくらいだ。
そんな失望から始まったロシアとの関わりだったが、その後何年も続くことになる。
そして私にとって、まさしく第2の故郷となった。いや、運命の場所だったのだ。

その年の6月、ウラジオストクの空港に到着したとたん、そこには全くの異世界が広がっていた。
空港なのにやけに薄暗く、理解できない早口のロシア語が怒号のように飛び交う。
あれはたぶん、白タクの客引きだったのだろう。事前に手配した送迎車がなければ、あの人込みをくぐり抜ける勇気はなかなか出ないだろう。
ロシアのドライバーはたいてい荒っぽく、夜間でも、土砂降りでも猛スピードで走る。
おかげで、空港から大学の宿舎に着くまでに、体がコチコチになってしまった。
翌日から始まった私のロシア生活は、ハプニングと驚きの連続だった。
ロシア人はサービスという単語を知らないとよく聞かされていたが(今はかなり変わったと思うが)、お店でコーラを買おうとしたら、「値段がわからないから売れない」と言われ、レジに商品を持って行っても、化粧直しに熱心な金髪美女の店員に無視され、郵便局から小包を日本へ送ろうとしたら、「担当者がいないから明日来て」と言われる。ちなみに次の日に行っても、「明日来て」と言われる。〝明日〟は永遠に来ない(かもしれない)、というオチだ。
でも、誤解しないでほしい。彼らは意地悪で冷たい人たちなのではない。
実に正直で、金儲け主義ではない、素朴な人たちなのだ。
市場で、かなりふくよかなおばちゃんたちが、おしゃべりに夢中になっていた。
足元に置かれた、バケツ一杯のじゃがいもを買おうとしたが、彼女は首を横に振る。
「そのじゃがいも、あまり良くないから」
じゃあ、なぜ市場に売りに来ているんだ? というツッコミはゲスである。
ロシア語もへたくそな、外国人の若い娘に、品質の悪いものを売りつけてまで金は欲しくないのだ。決して、おしゃべりを中断したくないからではない(と思いたい)。
総菜を選んでいても、わざわざ「こっちの方が新しいよ」と教えてくれる(たぶん、嘘ではない)。
運賃のための小銭を持ち合わせておらず、バスの中で困っていると、後方に座っていた若い男性がさらりとお金を払ってくれ、びっくりしたこともある。確かに、日本円で数十円程度の金額だが、見知らぬ他人の運賃を払ったりするだろうか? お礼を言っても、その男性はまるでよくあることかのような涼しい顔で、それ以上、私に関心があるという素振りもなかった。
知人でも、他人でも、本当に困っている人がいたら、手を差しのべる。
やれやれ、と言いながらも、放っておけない。結局、面倒を見てしまう。
そんな温かさとやさしさを、たびたび感じることがあった。
ロシア生活で、日本人が最も困難を感じるのは停電と断水だろう。
世界初の有人宇宙飛行を成功させ、今も国際宇宙ステーションへ宇宙船を送り出している国なのに、ライフラインの脆弱さにはあきれてしまう。
停電も断水も事前に告知なく起こるので、電気があるうちに仕事をし、水が出るうちに炊事とシャワーを済ませ、電池やロウソク、水と食料を常に確保するクセが身に付いた。今、災害時に電気や水道に障害が起きても、過度に慌てずにいられるのは、きっとこの経験のおかげだ。さすがに、エレベーターに閉じ込められて、見知らぬ男性と暗闇に取り残されたときは生きた心地がしなかったが、「人生には待つしかないこともある」ということを、ここから学んだ。
ちなみに映画などでは、常に〝修理中〟の張り紙があるエレベーターが、ソビエト時代を皮肉る場面として出てきたりするが、実のところ、ロシアになってもその「慣習」は続いている。何年経っても〝工事中〟で穴が開いたままの歩道や、階段が途中まで建設されて空中で止まったままの、不思議な光景も目にする。ロシア人の大らかでのんびりした気質が、そんなところに表れていて楽しい。美しい自然や歴史的な建造物もいいが、こんな風景もユニークで、意外にインスタ映えするように思う。
ロシアの素晴らしい教会や大聖堂、美術館やバレエ、日本人の口にも合うスープ料理など、ガイドブックによくある情報も興味深いが、それ以上に、ロシア人の考え方や生活に、私は妙な親近感と懐かしさを覚え、ロシアが大好きになった。うまく言えないけど、そこでの生活は、自分にしっくりくるような気がしていた。
父が、樺太(カラフト)生まれだったと知ったのは、ロシア生活が1年過ぎて、一時帰国したときだったと思う。樺太は、現在のロシアのサハリンである。
偶然、古い戸籍謄本を見つけ、父の出生地が「樺太」と記載されていたのだ。
長い間隠されていた真実に、心が震えた。
父方の祖父母は、おそらく戦後、樺太から引き揚げてきた人たちだったのだ。
父が小さい頃に引き揚げてきたと思われるが、父からも祖父母からも樺太の話を聞いた覚えがない。母も知らなかったと驚いていた。あるいは、父も詳細な記憶はなかったかもしれない。
父も祖父母もすでに他界している。樺太が、当時どんなところだったのか、今ならいろいろ聞いてみたいが、生きていたとしても、何も語らなかったかもしれない。命からがら引き揚げてきた人たちは、当時の壮絶な体験をあまり話したがらない、と聞いたことがある。
でも、彼らにとって、樺太は間違いなく故郷だったのだ。
後年、私もサハリンを訪れた。
歴史に翻弄されてその地に生まれた父と、意図せずしてロシアを愛するようになり、その地に降り立った私。
もしかしたら、何も語らなかった祖父母の、「私たちがそこに住んでいたという歴史を忘れないで」という想いが、私をここに連れてきたのだろうか。
何か、大きな運命のめぐり合わせを感じずにはいられなかった。
約6年間にわたるロシアでの生活は、もちろん楽しいことばかりではなかった。
ロシア人の考え方が理解できなかったり、治安に不安を覚えたり、あらゆる手続きに時間がかかったり、イライラすることも多かったし、泣きたくなる夜もたくさんあった。
それでも、私にとって、ロシアは私という人間を成長させてくれた大切な場所であり、私の一部であり、時には私そのもののような気がしてくる。
私のアイデンティティについて考えるとき、もはやロシアを抜きには語れない。
ロシアは、私たち日本人の固定観念を覆し、常識という壁を打ち破ってくれるワンダーランドだ。だから、一度足を踏み入れると、おもしろくてやめられなくなる。
そして、歴史的にも地理的にも、本当はとても近くて、少なくない日本人にとって、心の中に生き続けるふるさとでもある。
またロシアがむしょうに懐かしくなってきた。
きっといつか再び訪れたい。むしろ来世はロシア人かもしれない。
そんなことを妄想しながら、今夜はウォッカとイクラ入りクレープで乾杯しよう。
❏ライタープロフィール
江島 ぴりか(Etou Pirika)
北海道生まれ、北海道育ち、ロシア帰り。
大学は理系だったが、某局で放送されていた『海の向こうで暮らしてみれば』に憧れ、日本語教師を目指して上京。その後、主にロシアと東京を行ったり来たりの10年間を過ごす。現在は、国際交流等に関する仕事に従事している。2018年7月から天狼院書店「ライティング・ゼミ」を受講、同年9月からREADING LIFE編集部ライターズ倶楽部に参加。
趣味は映画館での映画鑑賞とタロット占い。ゾンビとオカルト好き。中途半端なベジタリアン。
夢はベトナムかキューバに移住することと、バチカンにあるエクソシスト養成講座への潜入取材。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/62637