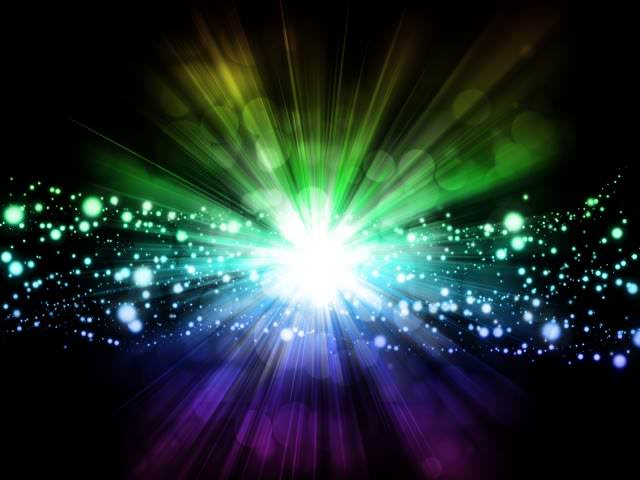いつかまた訪れたい、大好きな第二のふるさと《週刊READING LIFE vol.6「ふるさと自慢大会!」》

記事:相澤綾子(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
彼女は、両手を広げ、最初に私の応対をした店員と顔を見合わせ、思い切り肩をすくめた。そして私には理解できない言葉で何かを口にした。
「この日本人、英語さえできない」
とでも、言ったのだろうか。
確かに、英語も自信がない。でも彼女の方もたどたどしかったし、発音もフランス語みたいだった。もし英語がネイティブの人と話すことになったら、私の方が通じるんじゃないか。そんな風に思うくらいだった。けれど、今の状況は私が不利だった。「英語を話せるか?」と訊いたら「話せる」と答えたので、英語を話せる店員を連れてきた。けれど通じなかった。悔しいけれど、今の私は、「英語さえできない人」ということになっている。
覚えたばかりの「結構です」というジェスチャーをして、笑顔で「さよなら」を言った後、その場を立ち去った。この時何を店員から訊こうとしていたのか、今はもう思い出せない。ただ、絶対にフランス語を話せるようになろう、と強く決意したことだけは覚えている。
夫の仕事の関係で、パリ郊外の都市ブローニュ=ビヤンクールに着いたのは、その2週間ほど前だった。友人たちに渡仏のことを話したときには、「いいなあ」と羨ましそうな顔で言われた。けれど、旅行に行くわけじゃない。そこで生活をしなければいけない。しかも1歳10カ月と4カ月の子どもを連れて。フランス語もろくに話せない私は不安でたまらなかった。
着いた日は1月8日、冬至から2週間しか過ぎていなくて、夜が長く、寒かった。外を歩くと、靴底から冷気が伝わってきた。フランスは天井から明かりを吊り下げる習慣がなく、スタンドのライトで下から天井を照らすのが一般的だった。圧倒的に光が足りなくて、暗さと寒さで気が滅入った。
夫が選んだ住む場所は、前任者もその前も、代々住んでいたところだった。近くに日本人幼稚園があり、徒歩30分のところに日本語を話せる小児科医もいる。公園に行けば、ちらほら日本人に会うこともあった。子どもたちを遊ばせつつ、母親同士盛り上がっているのを見かけたけれど、私は横目で見ながら、あの仲間に入るのは、もう少しフランス語が話せるようになってからにしようと考えた。その中に入れば、安心してしまい、2年半、ここの地に足をつけて、生きていくという決意がにぶってしまう。
近所には日本人にフランス語を教えてくれるバザンという女性がいた。夫の前任者たちの妻もマダムバザンからフランス語を習っていたそうで、私も予約をとった。流暢な日本語で対応してくれて、翌週の火曜日の午後に最初の授業をすることになった。
到着時は、ボンジュール、ボンソワール、メルスィ、数字の1から20しか言えなかったけれど、1週間で曜日を覚えた。どの店が何曜日に開いているかを把握しなければならなかったからだ。個人商店は日曜日は休みだし、それ以外にも休みがある。大きなスーパーでさえ、日曜日の午後は閉店した。だから店の前に掲示されている曜日で休みを確認するのは、とても重要だった。
夫が仕事に行くために家を出てから、家に帰ってくるまで、一日中、会話らしい会話はない。子どもたちに話しかけたって、ろくに言葉は返って来ない。朝夕の家事をしながらフランス語教材を聞き、子どもたちが寝入ってから1時間は必ずフランス語の勉強をすることにした。午前中と夕方子どもたちを公園に連れていくと、教材を広げつつ、横目で子どもたちを見守った。時には、フランス人の子どもたちの会話に、聞き取れる言葉はないかと探した。あとは店で簡単な挨拶をする程度だ。
そんな毎日だったから、毎週火曜日のマダムバザンの講義は楽しみでたまらなかった。唯一人、夫以外で日本語を話す相手だった。そして、言い換えも上手なので、フランス語で話してくれても理解できることも増えてきて、どんどん楽しくなっていった。
個人商店のパン屋でバゲット、日本ではフランスパンと呼ぶ長いシンプルなパンを買う時にも、フランス語を使ってみた。フランス語には男性名詞と女性名詞がある。バゲットは女性名詞なのだけれど、間違えても通じるだろうと考えて、覚えるつもりはなかった。分からないまま男性名詞の時と同じ表現で「バゲット1本ください」というと、店員はにっこりして、女性名詞の時の表現に言い換えてくれた。次に訪れた時に、言われた通りに表現すると、店員は嬉しそうな顔をした。
マダムバザンから、好みのバゲットを買う時の表現を教えてもらった。例えば、よく焼けたパリパリのバゲットが好きなら「よく焼いたものを」という。焼きたてが好きなら「熱いものを」という。私はホカホカの柔らかいバゲットが好きだったので、必ず「熱いバゲットを1本ください」というようにした。包まれた紙を通してバゲットの温かさが伝わってくる。フランス人がよく歩きながらバゲットの端を食べるのを真似して、店を出るとすぐにちぎって食べた。焼きたてのバゲットは指で軽くちぎれる。口に含むと小麦の焼けた香りと甘みが広がった。ベビーカーに乗っている上の子にもちぎって渡した。子どもは食べ終えると、すぐに後ろを振り返って催促した。
こんな時どんな風に表現するのだろうと思ったことはメモで書き留めておいて、マダムバザンのレッスンの時にまとめて質問した。少しずつ使える言葉が増えていくにしたがって、ぐんぐん暮らしやすくなっていった。
マダムバザンは私の母親と同い年だった。私より少し若い娘と息子がいるとのことだった。本当に日本のことが好きなようで、日本のことをよく知っていた。日本人をたくさん教えていたから、日本人の生活や好みもよく理解していた。私が小さな子どもたちを育てながら新しい生活に慣れようとしていることを、大変だけどよく頑張っている、といつも励ましてくれた。
ふと思いついて、マダムバザンに質問した。
「マダムバザンはなぜ日本語を話せるのですか?」
彼女は少しいたずらっぽい顔で笑いながら、答えてくれた。
「大学に入る時にボーイフレンドがいた大学に行きたくて。そこは遠かったのだけれど、日本語学科があったから、日本語が勉強したい、と親にお願いしたの。これは夫と会う前の話よ」
マダムバザンのこういうところも私は好きになった。
最初の夏を迎える頃には、色んなことに慣れてきた。フランス人はバカンスを大切にするので、パン屋も2週間くらいお休みになる。互いに相談しているのか、バカンスがかぶることはなく、こっちが休みならあちらに行けばいい、という具合だった。来たばかりの頃は、日曜日が休みであることさえ不便に感じていたのだけれど、そもそも日本は働きすぎなんじゃないだろうか、と考えるまでになった。
さらに、1年が経つ頃には、電話で病院の予約が取れるくらいにまでなっていた。わざわざ30分かけて日本語の話せる小児科医のところに具合の悪い子どもを連れていくのは大変なので、近所の小児科医に行くようにした。その小児科医はとても親切で、メールで質問してもすぐに返してくれた。お勧めの耳鼻科や眼科についても、彼に訊いて、教えてもらったところに通った。
その頃には、日本人の友達も少しずつ増え、情報交換しつつ、一緒に遠出したりということもするようになった。一人ではできなかったこともチャレンジできたりして、世界が広がった。一度経験すると、自分だけの時も、ベビーカーにおんぶで子どもたちを連れてどんどん出かけるようになった。
フランス語もできるだけ使った。一度通じなくてもめげずに、言い換えしたり頑張った。相手も根気良く聞いてくれた。たまにイラっとしたかなと思って、
「フランス語が下手でごめんなさい」
と言うと、
「いえいえ、そんなことないわよ」
と慌てたように、笑顔で返してくれたりした。本当はイライラしていたのかもしれないけれど、そんな風に接したかったわけじゃないという気持ちを示してくれた。フランス語を覚えたおかげで、物理的にも精神的にも世界が広がった感じがした。名刺を男性と女性に分ける考え方も風流だと思えるくらいになった。そして何より、行きつけの店や公園があるブローニュ=ビヤンクールが好きになった。家族でどこかに旅行に出かけたとしても、ブローニュ=ビヤンクールの街並みが見えてくると、ほっとした気持ちになった。私はここが好きなのだ。
2回目の秋を迎えたとある火曜日、マダムバザンが授業に来なかった。15分を過ぎても連絡がないので、電話してみることにした。
いつもと声の感じが違った。私とはフランス語で話すようになっていたのに、日本語で返してきた。
「留守番電話、聞いてませんか? 実は夫が亡くなったのです。今週はお休みさせてください。来週は授業をできます」
私は驚いた。ムッシューバザンは数回しか見たことが無かったが、元気そうだったので、急に亡くなったことが信じられなかった。留守番電話を聞き直したけれど、間違って消してしまっていたのか、入っていなかった。
私は何か自分にできることはないだろうかと考えた。マダムバザンと私は、基本的にはフランス語の先生と生徒という関係だった。ランチに招いたことはあったけれど、それくらいだった。フランス人同士が、こういう時にどんな風に接するのかもよく分からなかった。
日本だったら、お悔やみの言葉とともに、香典を渡したりするのだろう。フランスにはそういう慣習はないようだった。でも思いつくのはそれくらいしかなかった。私は白い小さな封筒に50ユーロを折って入れて、次の授業の時に準備しておいた。
授業の日、マダムバザンは見るからにやつれていた。ご主人が亡くなった日のことを話してくれた。先に休んでいて、バタンという大きな音が聞こえてきたので急いで行ってみると、もう息をしていなかったという。一瞬で遠くに行ってしまったのだ。マダムバザンは「でも彼が苦しまなかったのは良かった」と付け加えた。
授業の最後に私は、小さい封筒を取り出し、手渡しながら、説明した。言葉は事前にフランス語で考えておいた。
「日本では親戚や友達などの大事な人が亡くなった時には、お金を渡す習慣があります。あなたは、私にとって、フランスのお母さんです。だから、元気になって欲しいです」
マダムバザンは目にいっぱい涙をためて、
「とっても優しいのね、ありがとう、私も娘のように思っている」
と答えてくれた。私も泣いてしまった。ブローニュ=ビヤンクールの生活に慣れるために私も頑張ったけれど、それができたのはマダムバザンのおかげだった。彼女なしには、ここでの生活を楽しむことなんてできなかっただろう。
そして2年半の滞在を終え、帰国する時がやってきた。帰国するのは嬉しかったけれど、それと同じくらいブローニュ=ビヤンクールを離れることが寂しかった。私が好きになったのは、この街だった。あそこのパン屋さん、公園、スーパーの店員、顔見知りのご近所さん。何度か話したことのある人みんなに、私は帰国することを伝えた。
使わないとどんどん、フランス語を忘れていく。この前、ついに「木曜日」を忘れていることに気付いて、辞書で確認した。マダムバザンの誕生日にもメールを送っていたけれど、今年は忙しくてうっかり過ぎてしまった。それでも、帰国後4年経っても、私の第二のふるさとはブローニュ=ビヤンクールなのだ。私はあの場所で必死に生きた。
実は、生まれ育った場所のことを、そんな風に思えていない。そこにいるのが当たり前のことで、むしろ、就職したら東京に出たいと思っていたくらいだった。遠く離れて暮らしたのは渡仏した時だけで、戻ってくることは分かっていた。ここにいるのが当たり前だから、その大切さに気付けていないのかもしれない。
でもそれだけではない。本当にここで生きることに必死になっていただろうか。だから私はもう一度、生まれ育った場所ともっとじっくり向き合いたい。全力で暮らして、いつかこの場所を大好きな本当のふるさとにしたい。
❏ライタープロフィール
相澤綾子(Ayako Aizawa)
1976年千葉県市原市生まれ。地方公務員。3児の母。
2017年8月に受講を開始した天狼院ライティングゼミをきっかけにライターを目指す。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/62637