自分の足で、自分の目で《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》

記事:青木文子(天狼院公認ライター)
「なんでそんなこと、話さなきゃいかんのや!」
いきなり怒鳴られた。
人から怒鳴られることには慣れていなかった。大学3年生のゼミ。初めてフィールドワークに出たときのことだ。人の話を聞くのが得意だと思っていた私はいきなり出鼻をくじかれた。
怒鳴る側にも理由はある。いきなり若い大学生がやってきて、家族構成や仕事の内容をあれこれ聞いてくる。しかも答えるのは義務ではなく、あくまでボランティア。もちろん、事前に回覧板で、大学のゼミ生たちが聞き取り調査をして回るということは自治会長の名前で伝えられている。でも、それを知っていることと、目の前でプライベートなことを聞かれてついイライラしてしまうのは別の話だ。
フィールドワークとは、研究をする際に、そのテーマに関係する現地に行って、直接観察したり、人から聞き取り調査やアンケート調査したりする方法のことをいう。
医学部に進むはずだったのに、高校3年生の夏に「理系と文系を両方やりたい」と思いついてしまった。結局進んだのは当時日本に2つしかない「理系と文系の両方が学べる」学部のひとつだった。
その学部で意図せずして出会ったのがフィールドワークだった。
いきなり怒鳴られた私のフィールドワークデビューは農村社会学の実習。群馬の山奥。ある集落に泊まり込んでのフィールドワーク。最初の泊まり込みは約10日間だったろうか。集落の公民館を借りて寝泊まりする。集落の仕出し屋でお弁当を頼んで、お風呂は先生の車に便乗して近くの銭湯に行った。
初めてのフィールドワークは、最初目も当てられなかった。いきなり怒鳴られるとか、話をしてもらえないとかが、ざらにあった。あまりに話の聞き取りがうまくできなくて、帰り道田んぼの畦を歩きながら涙がこぼれる事もあった。
何事も続けていくとみえてくるものがある。
何日もするうちに、いきなり質問をしない方がいいことに気がついた。まずその人の何気ない話を聞く。こちらの身の上話をする。そうするうちに、お互いの間に挟まっていた空気の塊が溶けてくる。そこから聞き取りの質問をすると、不思議なほどに相手が話してくれるようになるのだった。
聞き取りはそれこそ朝から夕方までだった。暗くなる頃には宿舎である公民館に帰ってくるのが約束だった。ところが、何日かするうちに、学生の中で私だけ宿舎に帰る時間が遅くなっていった。
行った先の農家の方から
「宿舎の弁当は冷たいやろうから、ご飯食べていきなさい」
「遠くまで銭湯に行くよりうちでお風呂入っていきなさい」
と声をかけてもらえるようになったからだ。そのたびに、その方のお家の電話を借りて、先生に「遅くなりますがこれこれこういう事情です」と説明するのだった(当時はまだ携帯電話なんてなかったから)
あるお宅に行ったときのことだった。
「せっかくだから夕食を食べいきなさい、宿には車で送ってあげるから」と言われ、言葉に甘えることにした。同居しているお孫さんたちと一緒に夕食を食べながら話すうちに仲良くなった。
「ぶんちゃん(私はぶんちゃんと呼んでもらっていた)、いいもの見せてあげる」
小学生のお孫さんが夕食後、大事そうに自分の部屋からお菓子の箱に何かをいれて運んできた。
「今ね、暖めているの。もうすぐ生えてくるから」
生えてくる? なにが生えるの?
蓋を開けてみると、卵があった。おじいちゃんがとってきた、鴨の卵だという。
「このあたりじゃあ、卵から鳥が孵化するのを、生えるっていうのよ」
じっと見ていると、箱の中の卵は動き出しそうだった。
私の中でも何かが孵化しそうだった。人に向かい合う、話を聞かせてもらう。その扉の向こうにこんなに豊かな世界がある。そこには本に書いてないことが沢山あった。私はフィールドワークに心が震えていた。
農村社会学の実習は年1回きりだった。私はどうしても、もっともっとフィールドワークがしたくなっていた。そこで、隣の学科の先生に直談判をしに行った。隣の学科には私の学科にはいない、民俗学の先生がいて、民俗学のフィールドワークのゼミがあった。
「どうしてもフィールドワークを学びたいのです。先生のゼミに潜らせてもらってもいいですか?」
ゼミに潜ることを先生に頼むのも今思うと変だった。そこはおおらかな学風ゆえか、先生は面白がってOKをしてくれた。
そのゼミのフィールドワークは佐渡島の民俗学調査だった。私はそこで農村の農事暦をテーマに選んだ。種をまく、作物を刈り取る。どのタイミングですればいいかの言い伝えを調べる。例えば銀杏の葉っぱの大きさが、大豆を3つ包めるようになったらこの農作業を始めればいい、とか、田んぼに稲を植えた後には今年の豊作を祈ってこんなまじないをするとかだった。
そのゼミも、佐渡ヶ島現地の宿に2週間ほど泊まり込んでのフィールドワークだった。夢中になった。一日聞き取りに回ったあと、宿に帰ってきてカードに聞き取ってきた内容をまとめた。
何がそんなに私を夢中にさせたのだろうか。私があまりにも民俗学に熱を上げているのをみて、そのゼミの先生がこう提案してくれた。
「バイト代は出せないが、足代飯代宿代は全部出すから、鞄持ちで調査の手伝いをしないか?」
私にとって、願ってもない話だった。もちろん答えはYESだった。そこからゼミの先生の鞄持ちをして、2ヶ月に1度は佐渡島の調査に行ったり、伊豆七島の調査に行ったりするようになった。
先生はお酒が好きだった。特に日本酒が好きだった。佐渡島だと、日本酒がおいしい。フェリー乗り場で降りると、先生はいつも1万円を私に渡して、にやりと笑ってこういうのだった。
「これで、今から3日間分の日本酒買ってきて。純米吟醸以上じゃないとだめだよ」
私のほかにも鞄持ちで声をかけられた学生がいた。調査が終わると宿に帰る。夜になると、宿で先生を囲んで談話が始まる。フェリー乗り場で買った日本酒の登場だ。酔っ払うと、いつも先生は繰り返しこういった。
「本を一生懸命読むなんてことは、もっと年をとってからすればいいさ」
「今はまず自分の身体をそこに持って行きなさい。とにかくあちこちに行くんだ。自分の足でその場に行って、自分の目でそれを観てくる。それ以上のことはないから。それがフィールドワークだから」
大学4年生になった。季節は秋だったろうか。ある日、先生からゼミ室に呼ばれた。なんだろう。ほかに学生は居なかった。ゼミ室に行ってドアをノックすると先生の声がした。いつもだと、誰か大学院生とかゼミ生がいるのだけれど、この日は先生がひとりでデスクに座っていた。
おずおずと部屋に入って、いつもの定位置に座った。先生が口を開いた
「大学院にいったらどうだ?」
びっくりした。そんなことは考えていなかったから。
「推薦状は書くから。君は、人の話を聞く才能があるよ」
先生は褒めてくれたのは嬉しかった。でも、私は傍目にみても決して優秀な学生でなかった。人並みにはできないことが沢山ある。たとえばデータの処理や聞き取りのまとめは決して得意ではない。それでも先生は、フィールドワークに出ているときの私のイキイキした顔や、嬉しそうに「こんな話を聞いてきたんです!」と報告する姿をよく見ていてくれたのだろう。
一晩考えた。このまま大学院に進んで民俗学の研究者になる道もあった。でも、そのときの私には、イメージがもてなかった。研究者界隈の煩わしさが気になったし、研究者になった先の道もあまり現実的に思えなかった。もう地元での会社の内定ももらっていた。小さな文具メーカーだった。
数日してゼミ室に行った。意を決して先生に伝えた。
「先生、フィールドワークをやりたい気持ちはあります。でも、やっぱり就職します。世の中を観てみたいんです」
「そうか」
先生はそれだけ言った。
ゼミ室に沈黙が流れた。先生になにか申し訳ないような気持ちになって思わず私は目を伏せた。ゼミ室の床が見えた。床のあちこちには所狭しと本が積まれてあった。
突然、先生が言った。
「自分の足で行って、自分の目で見てきなさい」
私は顔を上げて先生をみた。何度も聞いたあの言葉だ。
「それさえ忘れなければ、世界のどこに居ても、どんな仕事をしていてもそれはフィールドワークになるから」
ハッとした。
先生の目をみた。
その言葉が慰めでもなく、とりあえずの接ぎ穂で言っている言葉でないことが伝わってきた。先生の目は本気だった。
そうか。学問でなくてもフィールドワークってできるのだ。
人の言葉を聞くこと、その風景をみること。私の心が震えフィールドワークはどこでもいつでも自分の足でいって自分の目でみればいいだけなのだ。
目の前にあった、大学院か就職かの2つに分かれた道でない風景が見えた。それは広い草原だった。この先にどの道を選んでも、それはすべてこの草原の中に通っていく道なんだ。
それならできる。それならやってみたい。一生、フィールドワーカーでいたい。
「中小企業の社員から観たフィールドワークとか面白いかもしれないぞ」
今度はちょっと冗談めかして先生が言った。
私は今、司法書士をしたり、セミナー講師をしたり、教育委員をしたりしている。他の人からはいろいろな仕事をしているように見えるかもしれない。でもどんな時も、どんな仕事をしていても、やっていることは同じだ。いつも自分の足で行って、自分の目でみること。
「自分の足で行って、自分の目で見てきなさい」
その言葉が胸の中にある限り、私は生涯一フィールドワーカーでいられるはずだから。
□ライターズプロフィール
青木文子(あおきあやこ)
愛知県生まれ、岐阜県在住。早稲田大学人間科学部卒業。大学時代は民俗学を専攻。民俗学の学びの中でフィールドワークの基礎を身に付ける。子どもを二人出産してから司法書士試験に挑戦。法学部出身でなく、下の子が0歳の時から4年の受験勉強を経て2008年司法書士試験合格。
人前で話すこと、伝えることが身上。「人が物語を語ること」の可能性を信じている。貫くテーマは「あなたの物語」。
天狼院書店ライティングゼミの受講をきっかけにライターになる。天狼院メディアグランプリ23rd season、28th season及び30th season総合優勝。雑誌『READING LIFE』公認ライター、天狼院公認ライター。
この記事は、人生を変える天狼院「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」をご受講の方が書きました。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325
■天狼院書店「シアターカフェ天狼院」
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-1 WACCA池袋 4F
営業時間:
平日 11:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
電話:03−6812−1984
関連記事
-

「息子が死んでも責任を取らせないから校庭で遊ばせてほしい」先生へ母が告げたあの一言が私を今でも支えている《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-

アランからもらって、Kちゃんに贈る言葉《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-

私もこの境地に達したいものだ《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-
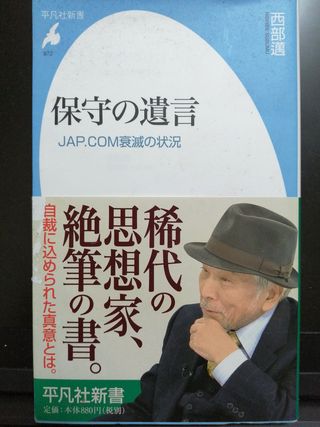
師匠がくれた忘れられない一言が僕の支えになった《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》
-

あの時、諦めていたらこの未来はなかっただろう《週刊READING LIFE vol,104 私を支える1フレーズ》



