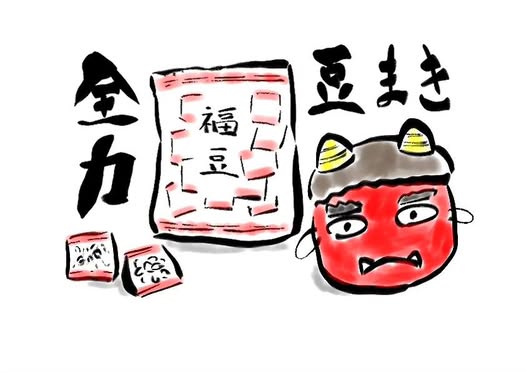40代最後の一年が、人生の助走だった理由

*この記事は、「ライティング・ゼミ」にご参加のお客様に書いていただいたものです。
記事: 小島 香奈子(ライティング・ゼミ25年11月開講コース)
一月、誕生日を迎え、私は四十代最後の一年に入った。
新しい年の始まりというよりも、「いよいよここまで来た」という感覚のほうが強かった。
特別な決意があったわけではない。ただ、この一年は、これまでとは少し違う時間になる気がしていた。
何かに挑戦したい。
大きなことでなくてもいい。ただ、今までやってこなかった何かを始めたいと思っていた。
通勤時、車の窓から見えるギター教室が目に入る。
もう七年も続けている英語は、いつになったら話せるようになるのだろう。
ダイエットも、半年で六キロ太ったまま、何も変わっていない。
やりたいことは、いくつもあった。
でも、どれもできなかった。
仕事が最優先だった。
早出残業は当たり前。休日出勤も、たいして気にならなかった。
「今は仕方ない」「落ち着いたら」
そう言いながら、目の前の仕事をこなす日々が続いていた。
気づけば、この会社で働いて二十年が過ぎていた。
会長は、私が独身時代に勤めていた会社の“おじさん”のような存在だった。
見た目は少し怖いが、話すととても親身になってくれる人だった。
父には相談しにくいことも、会長には自然と話せた。
仕事のことだけでなく、将来のことや迷いについても、いつも耳を傾けてくれた。
私が結婚を機に退職したあとも、会長は連絡をくれた。
食事に行ったり、年賀状を交換したり。
仕事を離れても、その関係は続いていた。
あるとき、会長から電話があった。
息子さんが会社を立ち上げることになり、事務員を探しているという話だった。
その頃の私は、ちょうど働きたいと思っていた時期だった。
子どもはまだ小さかったが、家の中だけで過ごす日々から、少し外に出たい気持ちが強くなっていた。
「子ども連れでもいいよ」
その一言に背中を押され、私は今の会社でアルバイトとして働き始めた。
アルバイトからパートへ。
パートから正社員へ。
事務、営業、現場管理、広告、イベント企画や運営。
気がつくと、ほぼすべての業務に関わるようになっていた。
忙しさは増したが、頼られること、任されることが増えるのは嫌ではなかった。
仕事を優先することが、いつの間にか当たり前になっていた。
今年三月、会長が「胃の調子が悪い」と話していた。
検査をすると聞いても、正直なところ、誰もがたいしたことはないと思っていた。
だが二度の検査の結果、胃がんだと分かった。
手術は行われたものの、がんは全身に回っており、すべてを取りきることはできなかった。
術後は一見元気そうに見えたが、体調の悪い日が続き、やがて入院。
会長は、延命や積極的な処置を望まないホスピスを選んだ。
入院してから亡くなるまで、約二か月。
最期は、眠るように穏やかだったという。
その知らせを聞いたとき、胸の奥に静かな空白が広がった。
人は、いなくなって初めて、その存在の大きさに気づく。
そして同時に、「時間は待ってくれない」という事実を突きつけられる。
海外に行きたい。
英語を話せるようになりたい。
その夢は、昔から心のどこかにあった。
本当は、子どもが二十歳になったら退職するつもりだった。
でも、それはできなかった。
会長がいたからだ。
支えてくれた人がいる場所を、簡単には離れられなかった。
夢を諦めたわけではない。
ただ、「まだ先でいい」と言い続けてきただけだった。
会長がいなくなってから、時間の感じ方が変わった。
「今じゃない理由」を探すのではなく、
「今なら何ができるか」を考えるようになった。
今の私の仕事は、これまでとは少し違う。
新しいことを増やすのではなく、
自分が担ってきた役割を整理し、次につなぐことだ。
私の代わりを見つけること。
それは、単に後任を探すという意味ではない。
仕事の進め方や判断の軸、積み重ねてきた経験を、
どう残していくかを考える作業でもある。
去る立場になって初めて、
「続いていくこと」の大切さが見えるようになった。
自分がいなくなっても、会社が滞りなく動くこと。
それは、これまで関わってきた者としての、
最後の責任だと思っている。
退職の期限を決めたのは、感情が先ではなかった。
会社の決算は三月。決算処理が落ち着くのは六月。
その流れを止めたくなかった。
十月、社長に退職の意思を伝えた。
社長もまた、会長を亡くしたあと、
会社のこれからや後継者のことを考えていたようだった。
二〇二六年六月。
それは終わりではなく、次につなぐための区切りだ。
四十代最後の一年は、何かを成し遂げた年ではなかった。
けれど、人生を変えるために立ち止まり、方向を定めた一年だった。
走り出すのは、これからだ。
この一年は、そのための、静かな助走だったのだと思っている。