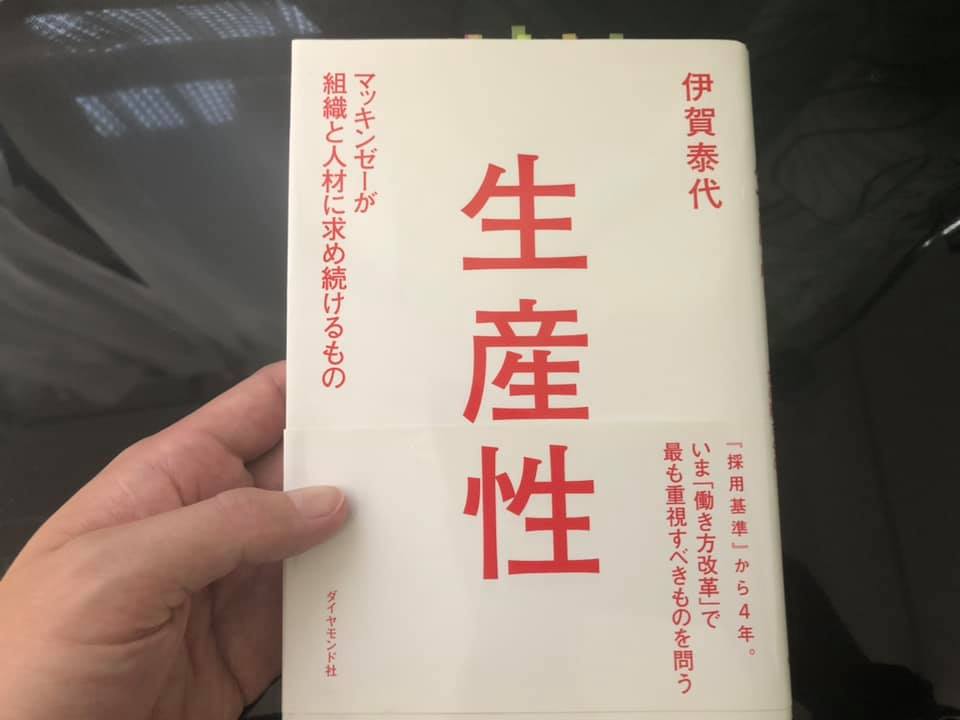千三から始まった三方良し《 週刊READING LIFE Vol.52「生産性アップ大作戦!」》

記事:高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
千三(せんみつ)という言葉がある。
千に三つくらいしか話がまとまらないという意味である。
28年間に及ぶ百貨店生活の最後の4年間、私は千三の商売の真っ只中にいた。
私は密かに同僚や上司たちから、「千三(せんみつ)営業」と呼ばれていた。
仕事は法人外商、いわゆる法人営業である。
百貨店の外商は、「まいど」に代表される。
なにかごようございませんせか?式の「御用聞き営業」は30年以上前のこと。
バブル崩壊、リーマンショックを経て、百貨店の法人外商はクライアント企業に対しての企画提案型営業にシフトしていた。
具体的には、3つのポイントがある。
ひとつにはクライアントの業績向上、次に企業イメージアップ、さらには問題解決に役立つ仕事であること。
この3つのポイントのビジネスを提案しない限り、ご注文をいただけない状態になりつつある。
従来の百貨店の範疇を越えたビジネスを行う必要に迫られていた。
極端な話、この3つの条件をクリアーして、クライアントのCIに沿った品物なら、いつでもどこでもオファーをいただるのである。
社内公募で法人外商本部に異動した私は、この「なんでもあり」の営業活動こそ、いままで培った経験と情報を発揮するときだと信じていた。
しかし、法人外商マンとして歩み始めてから、なかなかクライアントのご要望に沿うことがカンタンではないことだった。
私の担当するクライアントは、複数の大手飲料メーカーさんだった。
主なビジネスは、ペットボトル飲料に付ける販促ノベルティ、「おまけ」である。
決まったときの売上高は大きいものの、決して効率が良いとは言えなかった。
たとえば、携帯電話のアクセサリーの場合、
単価30円✕100万個〜200万個=3000万円〜6,000万円
生産は、工賃の安い中国をはじめとする新興国で行われた。
現地に生産を委託する以上、さまざまな問題が発生した。
当初との色の近い、仕様の違い、納期遅れなどが日常、至るところで発生した。
そんなリスクとの背中合わせのなか、毎日、朝8時〜夜10時過ぎまで、営業の準備と営業、そのフォードバックに費やすことになった。
仕事は面白く毎日がまたたく間に過ぎていく感じだった。
しかし、千三であることに変わりはなく身体は疲弊していた。
そんなある日、いままで1人で営業していた私は、ベテランの社員と組むことになった。
その人の名前は、山本(仮名)さん。
法人外商一筋に生きてきたたたき上げの人だった。
見た目は強面で、初めて会った人はだれでも引きがち。
酒は一滴も飲めないが、無類の競馬好きだった。
同行営業初日、なぜかこちらから話しかけることはなかった。
2日目になり、移動の合間、山本さんは言った。
「てめぇ見ていると、こっちまで息苦しくなっちまうよ」
さらに、
「お客さまがおめぇに会うとどんな印象を持つと思う?」
驚いた。
いきなりこんな問いをもらうとは思わなかった。
良かれと思いながら、千三の営業活動をやっていたに過ぎなかったことに気づいた。
「おめぇの営業活動を見てると、目が点になってんだよな」
お客さまがそんな姿を見て、喜びを感じながら注文するか?というものだった。
「おれがお客だったら、おめぇみたいな営業って付き合いづらいなぁって思うだろうな」
私は憤慨した。いくらなんでも、そんなひとことってないよ。
そうは言っても、ではどのように修正するか?という答えも持ち合わせていなかった。
「今、時間あるよな」
その日、クライアントに営業する予定は終了していた。
「ちょっとオレに付いてきな」
先輩であり、同行営業のペアである以上、最初が肝心である。
黙って山本さんについていくことにした。
東京メトロ銀座線の銀座駅で下車した私たちは、松屋デパートの脇を昭和通りに向かって歩き始めた。
表通りの中央通りはさすがに洗練されたファッションやブランドショップが大流行である。
しかし、路地に入るとそこは、銀座でも別の一面が顔を出し始めた。
なにか雰囲気がちがうのである。
しばらく行くと、数十人規模であろうか。中高年の男性たちが続々とあるビルに入っていくのである。
(なんだ、なんだ、この人数とこの喧騒は?)
アルファベット3文字が見えた。
JRA
競馬。そう、場外馬券売り場だった。
「構わねぇから、試しに買ってみろよ」
1−2でも2−3でもいいから買ってみるという山本さんからの指示である。
どの競馬場かわからない。何レースさえも知らない状態である。
生まれてこの方、ギャンプルは避けてきた。
幼いころ、祖母から言われた「賭け事をしちゃいねかいよ」ということばが私を支えていたともいえる。
山本さんとはそもそも価値観自体が同じじゃない。
しかし、相手は先輩である。
単価200円の馬券を1枚買うだけにした。
すかさず脇から、「おめぇ、それでも男か?」というツッコミが入ったが無視した。
私たちは、1ブロック先のカフェに入った。
山本さんは左手に競馬新聞、右手に赤鉛筆。目の前にはカフェオレ。
仕事場では見せない真剣な表情になった。
沈思黙考すること約5分。
山本さんは新聞から目を上げると、席を立って場外馬券売り場に向かった。
30分後、山本さんはムッとした表情で戻ってきた。
右手には馬券を3枚持っている。
「おめぇ、この馬券を1万円で買わねぇか」
1枚200円が3枚で600円の馬券である。
(冗談じゃない。この期に及んで馬券をこれ以上買ってたまるか)
先輩とはいえ、正直言って無視した。
「じゃぁな、1万5千円でどうだ?」
安くするなら分かる。それを逆に値上げして提示するとは意味が分からなかった。
(ひょっとして、当たってんの?)
しかし、私のモットーは賭け事はしないである。
「買いません!」
山本さんは私の目をじっと見つめた。
「じゃぁ、行こか」
私たちはカフェを出た。
なんと山本さんは、またしても場外馬券売り場に行くのである。
仕方なくついていった。
そこは換金の場所だった。
3枚の馬券を差し出すと、75,000円也の金額が手渡されているではないか。
(当たったんだ)
金を手にした山本さんは何も言わずに私を見た。
かすかにニヤッと笑ったかと思うと、銀座駅に向かって歩き始めたのである。
「千三もいいけどよ」
銀座通りを4丁目の交差点に向かって歩きながらの山本さんの何気ないひとことだった。
その途端、異なる価値観が私の中でうずまき始めていた。
それまでの私はプロセスが大事とばかり、人がいいと言ったことはすべてやろうとしていた。
どんなに労が多くても、結果を出すためには手数が必要だとばかり思っていた。
しかし、目の前で展開された山本さんのギャンブルの結果。
その日山本さんが買った馬券は10枚の2,000円。それが75,000円となったのである。
いままでの法人外商で行ってきた商売とは真逆の世界があることを実感し始めていた。
欲しい結果のためには、道はいくつかあるんだということの証である。
しかし、自分の生き方を即変えられるものではない。
社に戻った私は、翌日の提案に備えて、いつものルーティーンを始めていた。
山本さんは何も言わなかった。
上司である部長のもとに行った山本さんはニコニコしながら財布から1万円札を3枚ほど取り出して、部長に手渡したのである。
受け取った部長も何もいわずにアイコンタクトを山本さんに送っていた。
千三の世界にいる自分は、なにか要領が良くないことを感じ始めていた。
その日の夜8時、私は引き継いだクライアントの1つ、大手新聞社の営業部あての提案の準備をしている最中だった。
いつも終業のベルと同時に退社する山本さんはなぜかまだ会社の残っていた。
見積もりとサンプルを整理している脇で山本さんがつぶやく声がした。
「オレたちはお客さまに喜んで、お買い上げいただいてナンボの世界なんだからな」
苦々しくなった。
営業でペアを組んでいる関係から、少しでも協力してくれてもよさそうなのに、山本さんは一切手伝おうとはしなかった。
(そんなこと、何百回言われようと売上ができなくちゃしょうがないじゃないか)
翌日アポイントを取っている新聞社の営業部長の顔が浮かんだ。
今も昔も、新聞社は購読者を一世帯、一名でも増やすことが喫緊の課題である。
そのために、新聞社の営業部は少しでも新聞販売店の販売促進にプラスになる品物はないか?と血眼になっていた。
ご家庭の奥さんが「気が利いているじゃない!!」と言ってくれるような品物を提案するようにと口酸っぱく言われていた。
事務所の片隅の通称、ダッグアウトと呼ばれるフリースペースでは、前任者からの引き継ぎいだ、家庭用の洗剤、歯磨き、食品ラップ、さらには、家庭用の洋服ブラシなどのサンプルが所狭しと置かれていた。
見積もりの作成も終わろうとしていた時、山本さんがやってきた。
「代わり映えしネェなぁ」
と言いながら、翌日の営業用の洗剤とラップをしげしげと眺め始めたのである。
「かったるい営業だよなぁ」
思わず腹が立った。
(山本さん、そりゃないでしょ。一緒のペアなのに)
と言いながら、私はフリースペースの片隅にあるダンボール箱を整理し始めた。
大型のダンボールは、ズシリとくるほどの重さだった。
(あれ、これって?)
箱の中を見ると、先日、食品メーカーの営業が持ってきた調味品セットだった。
お中元用に、食品メーカーが用意した1個あたり、小売価格3,000円相当の品物が4セット入っている。
サラダ油、オリーブオイル、健康サラダ油、調味品といった内容。
かつてのお中元、お歳暮の花形だった調味品セットは昔日の面影はまったくない状況で、
実態は、3,000円の品物が、食品メーカーの倉庫に5,000セットほど残っているとのことだった。
いくら消費期限が長いからと言っても、食品メーカーにとって、この在庫は死活問題と言っても過言ではない状態だった。
食品メーカーの東京支店長直々に、「どなたか売りさばいてくれませんか」と泣きが入っていたのである。
私が調味品セットをダンボールから出して、片付けようとしていたときである。
「おまえ、この品物っていくらだったら売れるんだ?」
通常よりも安くするとは聞いていたが、果たしていくらになるかは分からなかった。
「このメーカーの営業に今すぐ連絡を取れ」
なんのことやらさっぱり分からなかった。
先輩の言うことである。
強面の山本さんの横顔を見るとなにやら考えていることが分かった。
場外馬券売り場近くのカフェで、競馬新聞を見ているときのあの目だった。
食品メーカーの百貨店の担当営業はまだ社に残っていた。
「代われ」
私から受話器を奪い取るように取った山本さんは、いきなり言った。
「この品物2ヶ月で全量売りさばくから、その代わり原価はいくらまで下げされる?」
私は耳を疑った。
全量を買い取って販売するとのことである。
山本さんはさらに営業にインタビューを続けた。
5,000セットの在庫というのは、私たちに紹介した1アイテムの数量。
実際には、中元用に企画した5アイテムを合わせると12,000セットを在庫しているとのことだった。
山本さんは電話口で交渉を始めた。
先方はどうやら部長が出てきたらしかった。
具体的な数量と金額の詰めに入っていた。
メモと電卓を片手に品物の原価、納期、そして送料などの問題をひとつ1つ詰めている。
「じゃぁ、それで行きましょう」
取引成立だった。
なんのことやら、さっぱり分からないが、仕事という列車は動き始めた。
そこからである。
私は山本さんさんの指示で、調味品5アイテムのカタログにある写真を、A4サイズのコピー用紙に切り貼りすることになった。
山本さんは、その紙の上に、「オール1,000円」と書いた。
売れ残りとはいえ、3,000円の品物をすべて1,000円で販売するという企画である。
食品の利幅は、アパレルに比べて小さい。
1,000円で販売してもなお、儲けがあることを意味した。
そればかりではない。
お客さまから注文を受ける最低単位は、30セットからという条件を付けたのである。
いったい誰にこの品物を販売しようとしているんだ?
理解するのに時間はかからなかった。
相手は私がたった今まで提案準備をしていた大手新聞社だった。
今まで用意した家庭用品、洗剤、ラップは事実上の却下。
見積もりの必要もなければ、サンプルも必要がなかった。
用意するのはA4サイズ紙1枚のカラーコピーが100枚。
紙の一番うえには、山本さんが墨で書いた「◯◯新聞販売店の皆さま」と描かれている。
内容は、私が切り貼りした調味品セット5アイテムのカラーコピーだけである。
もともと3,000円〜3,500円の調味品セットが売れ残っていたばかりに価格はすべて1,000円。
なにかなんだか分からなかった。
ただ分かったことは、山本さんが交渉の末、12,000セットすべてを1,000円で営業するということ。
翌日、新聞社の営業部長にカラーコピーを見せたところ、目が変わったのが分かった。
早速、営業社員を通じて、首都圏ならびに北関東全域の同社の販売店にカラーコピーが回ることになったのである。
お客さまに見せるわけではない。
その日の午後から私たちのオフィスに注文が入り始めた。
ここでも山本さんの組み立ては抜かりなかった。
送られてきたFAXを気の利く女性アシスタントにとりまとめさせて、1日に2回メーカーに発注する。
品物は最低30セットという条件で、食品メーカーから販売店に直送される。
同じく会社の会計に頼んで、請求書を発行するというものである。
お客さまからの注文を受ける
メーカーに発注
品物をお届け
お客さまである新聞販売店に請求書を送る
という一連の流れを一発で行うという仕組みである。
新聞販売店80箇所からの注文がひっきりなしに入ることになり、
千三営業と呼ばれた私も合理的営業の尖兵として動き始めていた。
なによりも売れ残った品物を2ヶ月もしないうちに、完売することになったのである。
リサイクル営業と人は呼んだ。
しかし、まわりを見渡すとお客さまが喜ぶ品物が必ずあるという証である。
それは常に、「なぜ?」という視点で見続けることをおしえてもらった。
千三営業から、気がつくと、三方良しの営業をしている自分に気づくことになった。
◻︎ライタープロフィール
高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
ベストメモリーコンシェルジュ。
慶應義塾大学商学部を卒業後、三越に入社。
販売、仕入をはじめ、24年間で14の職務を担当後、社内公募で
法人外商を志望。ノベルティ(おまけ)の企画提案営業により、
その後の4年間で3度の社内MVPを受賞。新入社員時代、
三百年の伝統に培われた「変わらざるもの=まごころの精神」と、
「変わるべきもの=時代の変化に合わせて自らを変革すること」が職業観の根幹となる。一方で、10年間のブランクの後に店頭の販売に復帰した40代、
「人は言えないことが9割」という認識の下、お客様の観察に活路を見いだす。
現在は、三越の先人から引き継がれる原理原則を基に、接遇を含めた問題解決に当たっている。
http://tenro-in.com/zemi/97290