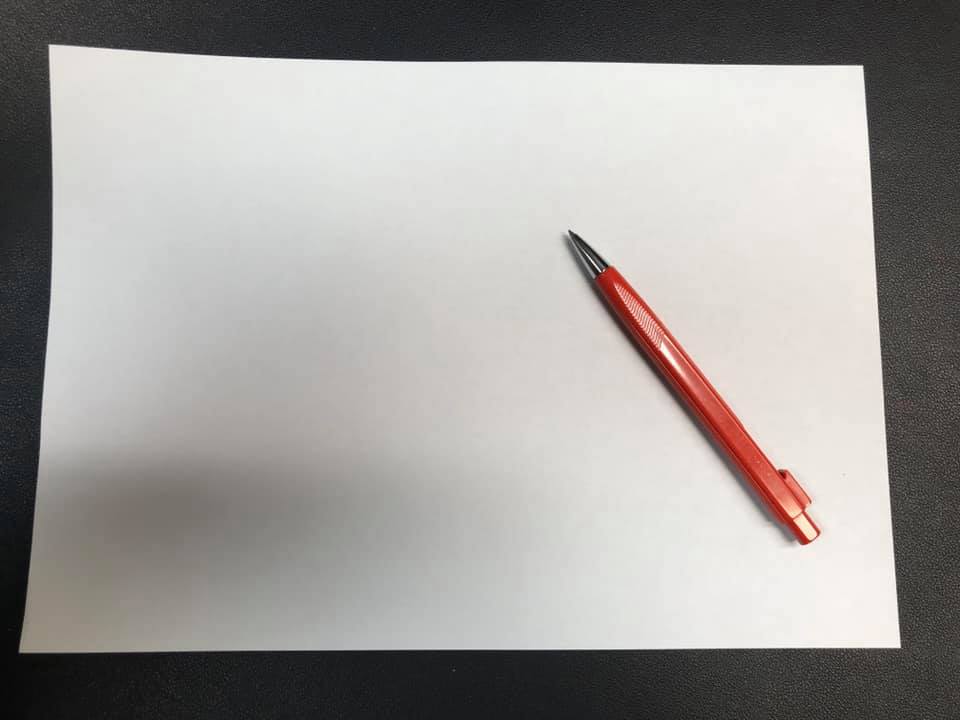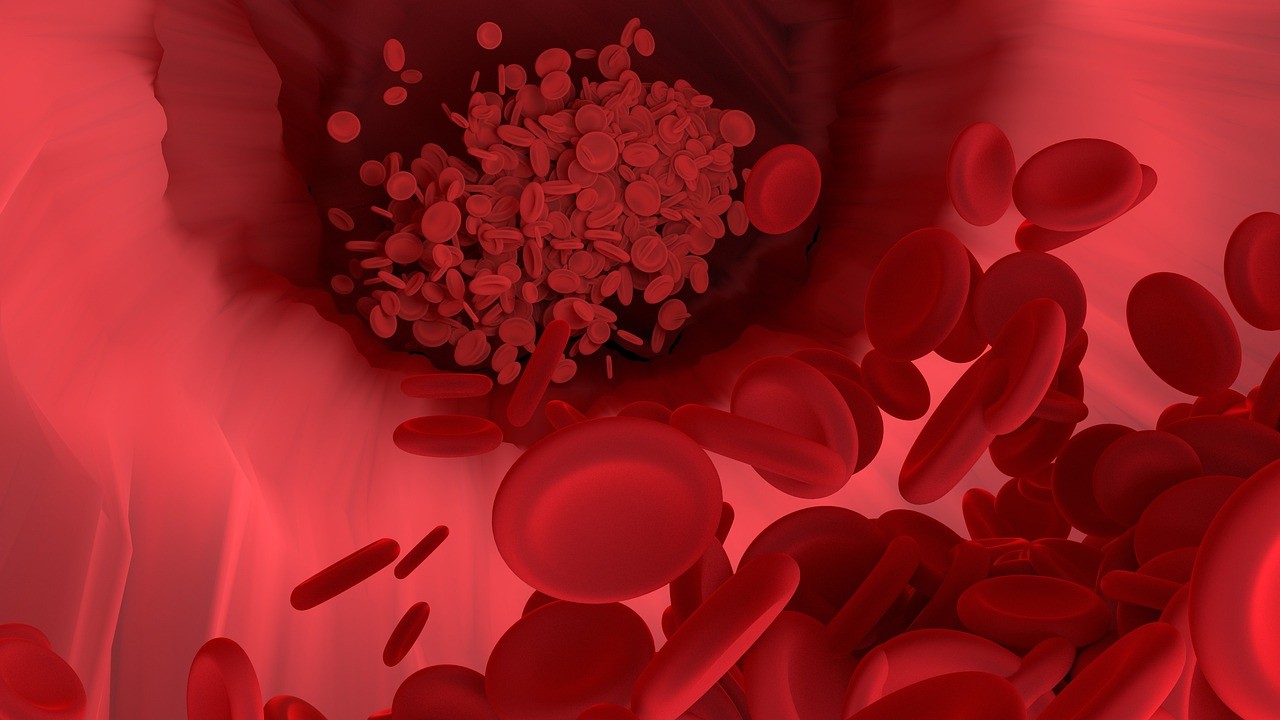チンキ壜の中でゆれるもの《週刊READING LIFE Vol.57 「孤独」》

記事:青木文子(天狼院公認ライター)
毒にも薬にもなる草がある。
それを人は毒草と言ったり、薬草といったりする。
孤独とはいわゆるそういうものだ。
誰にとっても孤独という言葉と自身の体験がはじめて結びつく時期がある。ぼんやりとしたさみしさや、ひとりぼっちの心持ちは、その名を与えられてはじめてその輪郭を持つ。
藍子にとって孤独が輪郭をもったのは小学校5年生の頃だった。
両親が離婚した原因はまだ11歳の藍子にも薄々わかっていた。父親は新しいパートナーのところに行った。母親は働くのに精一杯という理由で、藍子を田舎の大叔母に預けたのだった。ただ、本当の理由は何であったかはわからない。
大叔母は母方の大叔母であった。藍子はその大叔母には今まで一度しかあったことがなかった。一度は親戚の葬式の時だった。子どもにとって、大人が自分を受け入れてくれるのか、受け入れてくれないのか、はたまた無関心であるかは肌でわかるものだ。
葬式の短い時間であったが、藍子に向けられた大叔母のゆったりとした微笑みは、この大人は頼って良いというやわらかいものを藍子の心に残していた。
藍子が預けられた先は群馬の山間の山村であった。母方の大叔母である玲子は大騒ぎをするのでもなく、かといって無関心でもなく、藍子が一緒に住むことを受け入れてくれた。
山村で、静かな二人暮らしが始まった。都会から田舎の小学校に転校してきた彼女にはおきまりのやっかみといじめとが待っていた。今時の小学生は田舎の子どもであってもスマートホンを持っている。小学校5年生にもなれば、クラスのライングループがあるのは当たり前だ。ラインのグループで藍子にこれみよがしのチクチクした言葉が投げられるようになるには、転校してからさほど時間はかからなかった。
藍子はそのことを苦にはしなかった。人にとって苦しさは相対的に感じられるようにできている。より苦しいものが心の底に澱のようにたまっているとき、人は目の前の苦しさに鈍感になる。苦いものを口にしたときに次に口にした苦さがそれほどでもないように、感受性とは今感じているものとの差でその刺激がきまる。
やっかみや、いじめのしんどさは別段困るわけでもない。そんな藍子の大人びた対応は、田舎の同級生にとって、さらに格好のいじめの対象になっていた。
一緒に住み始めた大叔母の玲子はもう70歳をとうに過ぎているはずだった。しかし、藍子とお笑いの番組をみて、コロコロと笑い転げる姿は少女のようであったし、いつも髪をアップにして小綺麗にしている様子は彼女を10歳は若く見せていた。藍子は玲子のことを「玲子さん」と呼んでいた。水くさいようだが、なんと呼んで良いかわからなかったのだ。その呼び名は、二人の小さな距離の象徴にも感じられたが、同時に藍子が玲子にもつ尊敬や憧れの響きも表していた。
玲子はときおり、藍子を誘って裏山にのぼることがあった。早くになくなった大叔父が受け継いだという山は人の手が入らなくなり荒れていた。人の手の入らなくなった山は海原のようだ。すこしの時間で、空間があっという間に草や低木の茂みに沈んでいく。
裏山に登り、めざす場所は山の中腹のすこし開けた草原だった。ほんの十畳ほどの山間の空間は、そこへの山道とおなじように、山の草の海には沈まず、いつも開けて平らな面を見せていた。上っていく山道はそこだけ下草が分けられ、いつも人が上ってくることを待っているように一筋の空間が開いていた。山の中腹の草原も、山道も空間を保っているのは、玲子がこまめに草を刈っているからだった。
平日の夕方や、日曜日の早朝。玲子は思いついたように藍子を誘って、裏山に登った。20分ほど山道を登っていくとその空間にたどり着く。それは藍子とクラス前からの玲子の日課であったのだろう。山間の空間についても特になにをするわけでもなかった。下草に腰を下ろして、南に開けている空と眼下の家の屋根を眺めるのだった。藍子にとって山道の時間は好きな時間であった。山間の空間は木に囲まれて、安心できる場所であった。
山道を歩きながら、時折玲子が立ち止まることがあった。決まっている場所で決まっている草を摘んで腰の小さなかごに入れるのだ。その草はあるときは夕食の天ぷらの材料になり、あるときはチンキ壜の中に水中花のようにアルコールにひたされてゆれていた。
玲子は山の中の恩恵である食べられる草や薬草の知識があった。街から来た藍子にとってそれは物珍しいものだった。そのうちに藍子は見よう見まねで、草を摘んだり、その薬草の保存の手伝いをするようになった。
「玲子さん、この草は食べられるの?」
草に興味を持った藍子に、玲子は小さな図鑑をひとつくれた。『薬草・食草図鑑』だった。その図鑑をもって山道を登るのが藍子の楽しみの一つになった。
その図鑑には薬になる草や、食べられる草が載っていたが、同時に毒草も載っていた。食べられる草と、それに似た毒草を間違えないようにという配慮だろう。薬草になる草には食べ方によっては毒草になるものもあった。そのことが藍子には不思議でならなかった。
9月のある夕方、玲子に誘われて、藍子はいつものように山道を登っていった。この時間であれば西に沈んでいく夕日が見えるだろう。
山間の空間に並んで腰を下ろして、秋のはじまりの夕日を眺めていた。藍子はいつも心に思っていることを玲子に尋ねた。
「玲子さん、ひとりで暮らしていて寂しくないの?」
玲子は夕日を見たままだった。
「そうねぇ」
そう言ったきりだった。
それは否定でもなく、同意でもなかった。ただ、それをわざわざ言葉にする意味も興味もあまりないという風であった。
「人ってくっついたり、離れたりするのよね」
それは藍子の両親のことを言っているわけではなさそうだった。
「人ってひとりなのよ。それって良いことでも悪いことでもなくて、ただ、そうであるというだけだから」
藍子はまだ自分はそうは考えられないと思った。
両親のことなり、クラスで自分に向けられている視線なり、人と自分の関わりは、平気なように見せていても藍子の生きている世界の大半を彩り、自分が一喜一憂する事柄の一つだった。
「図鑑にね、載っているでしょ。薬草って使い方を間違うと毒にもなるのよね」
「草って草としてあるだけで、それが自然なことなのよね」
「毒になるとか、薬になるというのは私たち人側がそう決めているだけなのよ」
藍子には玲子が言おうとしていることがすこしわかる気がした。
夕日が大分地平線に近づいてきていた。そろそろ帰らないと、山道が暗くなるからといって玲子は立ち上がった。
立ち上がって玲子が言った。
「ひとりでいることってね、人の心を癒やすこともできるし、心が蝕むこともあるの」
「ただ、それは良い悪いではないのよね。ただ、そういうものと言うだけね」
藍子にはその区分けがわからなかった。でも自分の経験からそれが正しいということはわかった。自分も玲子の歳になったらそのことがわかるのだろうかと思った。
玲子の持っているやわらかさや人の心にずかずかと踏み込んでこない振る舞いは、今まで藍子の会ったどの大人とも違っていた。
草を薬草とも毒草とも決めずに、ただ、そこにある草としてみることができれば。そしてそれをあるときは薬草として使い、あるときは毒草として遠ざけることができるなら。自分はすこし玲子さんに近づけるのかもしれない、と藍子は思った。
山道を降りていく玲子の背中を夕日が照らしていた。
◻︎ライタープロフィール
青木文子(あおきあやこ)(天狼院公認ライター)
愛知県生まれ、岐阜県在住。早稲田大学人間科学部卒業。大学時代は民俗学を専攻。民俗学の学びの中でフィールドワークの基礎を身に付ける。子どもを二人出産してから司法書士試験に挑戦。法学部出身でなく、下の子が0歳の時から4年の受験勉強を経て2008年司法書士試験合格。
人前で話すこと、伝えることが身上。「人が物語を語ること」の可能性を信じている。貫くテーマは「あなたの物語」。
天狼院書店ライティングゼミの受講をきっかけにライターになる。天狼院メディアグランプリ23rd season、28th season及び30th season総合優勝。雑誌『READING LIFE』公認ライター、天狼院公認ライター。
http://tenro-in.com/zemi/102023