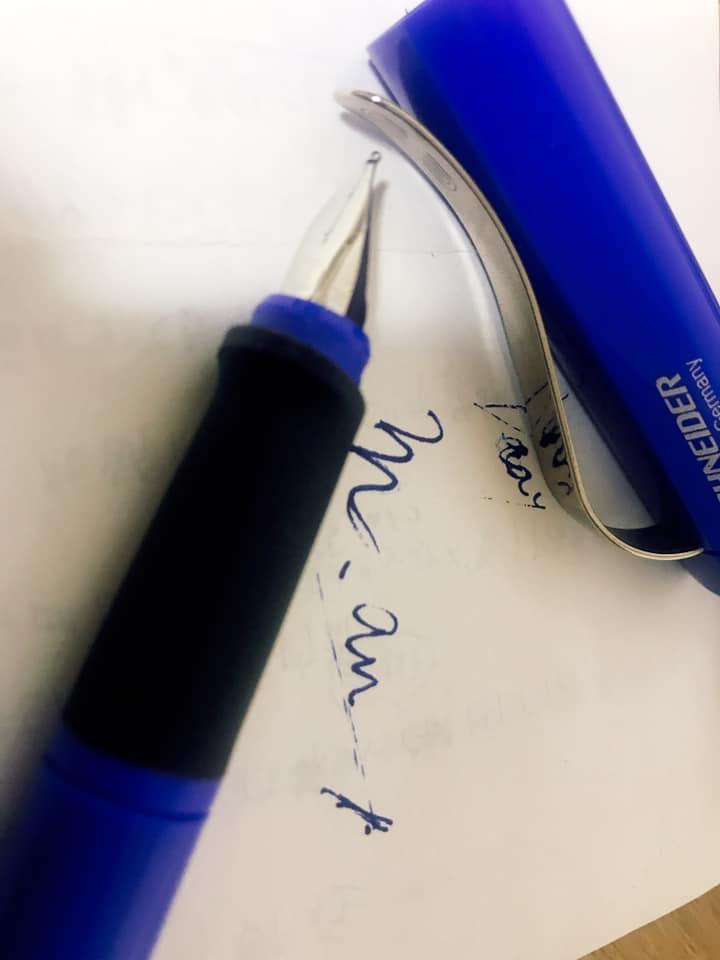思い出は、甘すぎるくらいがちょうどいい ~「習慣と思考法」は環境によって変わるというお話~《週刊READING LIFE vol.18「習慣と思考法」》

記事:戸田タマス(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
「 12月31日で閉店なんですか!?」
レジ前の小さな張り紙を見た私は、思わず声を上げた。
レジにいたアルバイトの若い女の子は、怪訝な顔をして「え? はい」と言った。
去年の6月、実家の母にがんが見つかった。
昔から病気ひとつしなかった母に突然のがん宣告。その衝撃波はなかなかの威力で、家族親戚全員がてんやわんやとなった。来なくていいと言う母の制止を振り切り、私は月に1回新幹線に乗り、実家を手伝いに行く生活を半年ほど続けた。
最初の数ヶ月は、母の体調やこれからの心配が頭の中をぐるぐる回り、とてもじゃないが外出する余裕がなく、文字通りの実家と家の往復だった。だが11月下旬の治療にて、医者より母の抗がん剤治療はかなり順調に効果が出ていることが告げられた。
単純な私は大喜び。とりあえずのお祝いでケーキでも買おうと思い立ち、私が子供の頃から馴染みにしている洋菓子屋「山口屋」に立ち寄ったところだった。
山口屋さん、閉店するのか……。
最近人気のオシャレな洋菓子屋とはほど遠いが、私の地元ではかなり大きい部類に入る「山口屋」。
洋菓子店といいつつ和菓子やおせんべいまで幅広く作っているので、どんな好みの人でも必ず好きなものが見つかる。ラインナップも非常にオーソドックスで、また懐かしい味のものが多い。私の地元では根強いファンが多く、皆この味で大きくなったとも言えるおふくろの味だった。
我が家も山口屋が大好きであった。どんな思い出の端っこにも、山口屋のケーキやお菓子が登場するように思う。
子供の頃、父はとても厳しい人で、とにかくよく怒られた。
箸の持ち方が悪いから始まって、数日前のささいなことまで引っ張り出しネチネチ怒るくせに、普段はほとんど喋らない。はっきり言って不気味な存在であった。
そんな父も山口屋が好きで、卵、牛乳、砂糖だけのシンプルな固いプリンを好んで食べていた。
あれは中学生の頃、夜皆で山口屋のお菓子を食べながらテレビを見ていた時のこと。
テレビといっても我が家のチャンネル権は父にあり、大体ニュースかNHKばかりであった。その時見ていたのはニュースのお天気コーナーで、キャスターの女性と男性がホワイトボードの前で中継をしていた。
淡々とコーナーが進む中、突然ホワイトボードが風にあおられて倒れ、2人の後頭部を直撃した。キャスターの2人は全く同じ角度で前につんのめった。怪我をするような事件ではなく、いかにも年末のハプニング番組などで取り上げられそうな笑えるものだった。
あまりに突然の出来事に皆ポカンとしていたその時、突然父が大声で笑いだしたのだ。
よっぽどツボに入ったのか、ヒイヒイ言いながら腹を抱えて涙目になっている。
普段笑わない人間の爆笑には感染力がある。母も兄も私もつられて大爆笑になり、家族全員で転げまわって笑い合った。普段は父に怒られまいと張りつめている我が家では初めてのことだった。
私はその時「父も人間なんだな」と強烈に思い、どういうわけか、父が食べていたプリンの減り具合、テーブルに置かれた銀色のスプーンの角度までしっかり覚えているのだ。
それからというもの、私にとっての山口屋のプリンは、家族全員の爆笑という思い出と深く結びついて、食べれば思わず笑いがこみ上げてくるアイテムになった。気分が滅入っている時、このプリンを食べてほっこりすることがひそかな習慣になった。
もともと食い意地が張っている上に大の甘党なせいもあるのかも知れないが、私の脳内では、山口屋のお菓子を食べると、芋づる式に色々な思い出がズルズルと引っ張り出される仕組みになっている。向田邦子さんの「父の詫び状」の中で、「食べ物と記憶がダブルスになっている」という表現が出てくるのだが、昭和の大作家と比較するのはおこがましいけれど、それを読んだ時「私と同じだ!」と嬉しくなったのを思い出す。
新卒の頃、実家から会社に通っていたのだが、毎日何かしら怒られて落ち込む日が多かった。そんな日は帰宅時、最寄駅に着くと自然と山口屋に足が向き、閉店ギリギリの店内で残ったプリンを1つだけ買い、こっそり夜中に食べていた。
もともと要領のよいタイプではない上にかなりのネガティブ思考な私。プリンを食べるくらいでは何も解決しないことは分かっていたし、ゲン担ぎにもならない変な習慣だったと思う。
ただ、ほんの少しでもよい思い出の力を借り、ほの明るい気持ちを持って眠りにつくことで、ネガティブに陥りがちな思考をストップさせることができた。
これが私なりのネガティブ思考回避法だった。
プリンの他にも様々なものと記憶がリンクしている。
チョコレートケーキは誕生日の味だ。年に一度の少しだけ大人になる日に相応しく、ちょっとラム酒の匂いのするずっしりとしたケーキは、今でも何かを始めたりする時に食べたくなる。
白いホールケーキは大学合格。寝るときも机の上に突っ伏して、という猛勉強の末だった。生まれて初めて父が「でかした!」と褒め、特大サイズを買ってきてくれた。泣きながらお腹いっぱい食べた歓喜の味だ。
卵が先かニワトリが先かではないが、習慣と思考法にはどちらが先というものはないと考えている。その証拠に私の場合は、爆笑の思い出から習慣と思考法が同時に誕生している。ただ、そのためにはまずプリンを食べなければならない。なんとも現金な思考法だと思う。
どちらかというと、その習慣と思考法に強く関わってくるのは「環境」ではないだろうか。
なぜなら、学生時代を過ごした町などに帰ってくると、そこに身を置いているだけであっという間に当時の自分が顔を出してきて、行動や考え方も当時のものに戻ったりするからだ。
私の場合は、新人と言われることがなくなってもプリンの習慣はなかなか変えられず、体重計とにらめっこをする時期もあったのに、結婚と同時に地元を離れたとたん、プリンの習慣なんて綺麗さっぱりなくなった。なくなったことにも気づかなかった。
アルバイトの女の子に礼を言い、私はお菓子を物色するふりをして店内を歩き回る。
厨房の様子が店内から見えるようにガラス張りになっていて、子供の頃、会計をしている母を待つ間、よくここで職人のおじさん達の魔法のような手さばきを見ていた。
古い焼き釜からはいつもバターの香りが漂い、焼きたてが出てくる時間になれば、黄金色に輝くマドレーヌや、指で押したら指紋が付くんじゃないかと思うくらいフワフワのケーキスポンジが出てきた。
今日の分はもう焼き終えてしまったのか、厨房には誰もいない。あと1ヶ月で閉店してしまうということは、この釜だって廃棄されてしまうのか。電気の落とされた釜がひっそりと悲しそうに見えてくる。子供の時は大きいと思っていたけれど、こんなに小さかったっけ……。
「お姉さんすみません、ここにあるケーキとプリン、全種類1つずつください」
気づけばそう叫んでいた。
家に帰り、開口一番に母親に報告する。
「お母さん聞いて! 山口屋さん年末で閉店するんやって! びっくりやわ、めっちゃ寂しい。今度からどこでケーキ買えばいいんやろなあ~」
1人で喋りまくる私に、母は何をいまさら? という顔をして、こう言った。
「あんた知らんかったん? そんなん知ってる知ってる。噂やけど、駅の反対側に新しくできたケーキ屋さんお客さん取られたんちゃうかって。え、新しいケーキ屋さんのこと言ってへんかったっけ? お母さんも今はそっちの方が好きやねん。山口屋さんのお菓子って甘くて重たいやろ? 新しいケーキ屋さんはもっとサッパリしとってな。
ていうかあんた、こんなにたくさん甘いもの買ってきてどうすんの。母親になったんならもうちょっとお金の使い方を……」
途中から小言に変わった母の言葉を聞き流しながら、思う。
どんなに地元が田舎でも、日々進化しているのだ。ここで生きている両親にとっても、環境が変わったらまた新しい習慣と思考法が生まれるのだ。
私のように、時々しか帰らないくせに変わってしまうことを悲しむ、というのは身勝手というものだろう。よい思い出というのは、ブリザードフラワーのように美しいまま保存しておいて、力を借りたい時だけ取り出して眺めるくらいがちょうどいいのかも知れない。
次の日、母に聞いて新しいケーキ屋さんに行ってみた。都内で人気のパティスリーのようとまではいかないが、山口屋と比べるとかなりオシャレなお店だった。並ぶお菓子も小さくて可愛らしく、店内は学生から子連れの親子まで賑わっていた。
今でも、幸せな思い出の力に頼りたくなることはある。でも、これから作られる思い出だって、きっともっと素晴らしいに違いない。私にとっての山口屋さんがおふくろの味だったように、ここのケーキ屋の味で大きくなる子供が必ずいる。
私自身、東京で夫と娘と共に生活をしながら、どんどん幸せな思い出をアップデートしているのだ。おそらく東京では、プリンを食べて家族で爆笑した思い出に浸ることはないだろう。でも、今度は夫や娘との思い出の中で「習慣と思考法」が生まれていくに違いない。
買いすぎた山口屋のお菓子の処理は、東京に帰るまでの私の役目になった。
久しぶりに例のプリンを食べてみると、とたんにあの夜の爆笑の思い出が、手でつかめそうなくらいに蘇ってきた。でも母の言う通り、どうも甘すぎるような気がしてならない。それは、もしかしたら思い出のせいだろうか。
私は、一口ずつゆっくりと、噛みしめるように口に運んだ。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/66768