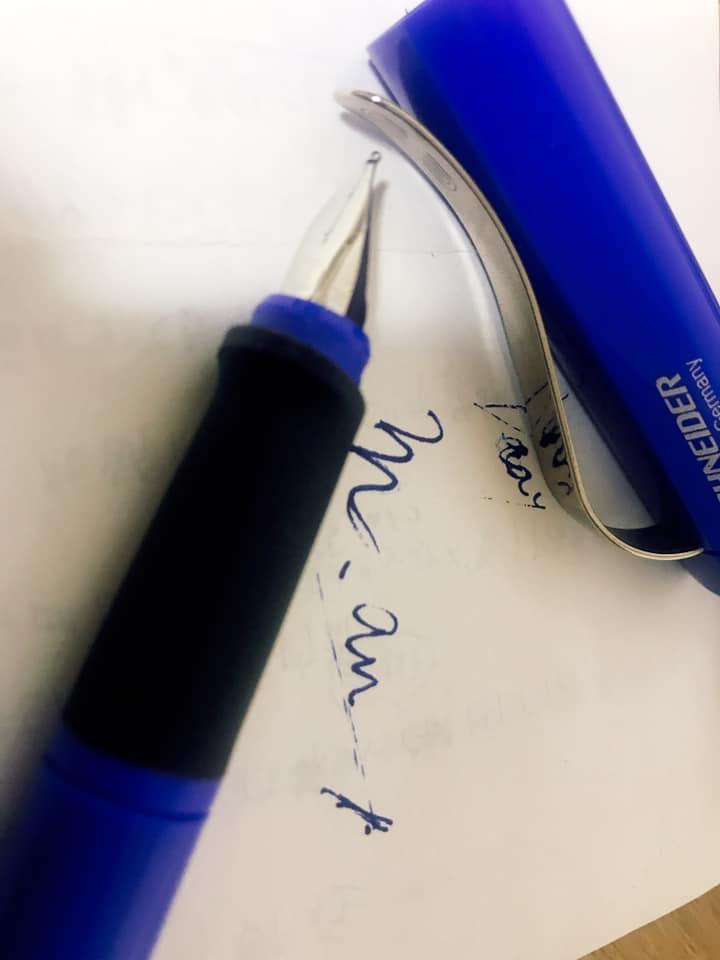アイスコーヒーに教えられたこと、それは?《週刊READING LIFE vol.18「習慣と思考法」》

記事:高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
最初は現実逃避からだった。
次第に毎日のステート(心理状態)を整え、仕事の確認をするようになっていた。
いつの間にか、心と身体が一体化していることに気づかせてくれた。
気持ちが落ち込んでいるときは励まし、気分が高揚しているときほどクーリングダウンの間(ま)となった。
そんな存在が、仕事場に入る前の一杯の「アイスコーヒー」だった。
大学を卒業して入社した百貨店は、徒弟制度の巣窟だった。
午前10時の開店から逆算して仕事は決まっていた。
仕事の順番が覚えられない私は先輩たちの格好の標的だった。
「ぼやぼやしてんじゃねぇよ」
「その品物じゃねえだろ、このボケ!」
「グズだなぁ、おめえほんとに大学出てんのかよ?」
「もう忘れたのか!! 昨日言ったばかりだろ、このマヌケ!!」
容赦なかった。入社年度がすべてだった。
1年でも先輩なら、年齢は関係なかった。
仕事は力関係だった。
大学卒の社員がフロアの1割にも満たないなか、身体で覚えていくしかなかった。
体育会出身の私にとって、配属後3週間は、オドオドすることの連続だった
「身体に自信があります」なんてとても言えなかった。
1時間以上の開店準備、午前10時の開店から始まる接客の本番、そして一日の締めまで気を抜けない日々が続いた。
仕事場に入る前、気持ちは萎えがちになっていた。
「辞める」という選択肢はないものの、行き場のない迷路のような状態だった。
相談するにも、周りには誰もいなかった。
それはいつもより1時間早く出勤する日だった。
早出(はやで)と呼ばれていた。
東京駅から徒歩で日本橋に向かう途中だった。
その日に限って、メイン通りから一本中に入った路地を歩いていた。
すると目の前に、世にも奇妙な看板が見えてきた。
『こーひー』
筆だろうか、白地の板に、黒くひらがなで書かれていた。
喫茶店だった。
何か吸い込まれるようにドアを開けた。
学生時代、体育会陸上競技部に所属していた私は、コーヒーを飲んだことがなかった。
甘味喫茶に入ったことはあっても、コーヒーが飲める喫茶店とは無縁の生活を送っていた。
「い〜らしゃいませ!」
ドレミファソのソの音階だった。
通る声だった。これから何かが生まれる予感がした。
40代のご夫婦が経営されている喫茶店だった。
《アイスコーヒー 250円》
無意識からだろうか、目に留まった。
メニューの書かれたボードの上から3番めだった。
躊躇(ちゅうちょ)しなかった。
「アイスコーヒーお願いします」
初めての出会いとなった。
ほろ苦いなかにも酸味のあるブルーマウンテンだった。
過去の人生になかった味覚だった。
味覚とともに、香りを感じたとき、一瞬の間(ま)が生まれた。
早出を前にした私の脳が、かすかに、まさに1/10000ミリ未満だったかもしれないが、覚醒した瞬間だった。
何かが違った感じがした。
仕事場の風景は同じ。先輩からの注意や罵声は変わらないものの、自分のなかのなにかが感じ始めていた。
その日が初めの一歩だった。
その日以来、仕事に入る前にその喫茶店に立ち寄ることになった。
《一杯のアイスコーヒー》
それは、立ちっぱなしの通勤電車から解放された新入社員にとって、これから始まる一日のバトルフィールドの前の、束の間の癒やしとなった。
ただ、知らず知らずにアイスコーヒーを飲むことは、自分だけの「間(ま)」となっていた。
気分をニュートラルにできる瞬間だった。
それは百貨店マンになったものの気が利かなかった私が、毎日の仕事の前に行う自分だけの儀式だった。
「アイスコーヒーを飲む」
それは、誰がなんと言おうと私の心の喜びだった。
仕事前の一杯は、7月や12月の超繁忙期であったときほど、私に落ち着きをもたらしてくれた。
夏だけではなかった。冬もアイスコーヒーを飲み続けた。
雪の影響で山手線が普通になったときも、地下鉄都営浅草線で日本橋経由で通った。
雪が降ろうが、台風が来ようが、毎朝8時半のセレモニーだった。
アイスコーヒーを飲みながら、いつのまにか、会社から支給された手帳に書くようになった。
別の意味で、手帳はかけがえのない相棒となりつつあった。
その手帳が3冊目になったとき、異動となった。
異動先は銀座だった。
人、モノ、カネの回転が日本一、いや、場合によっては世界一かもしれない街、銀座。
異動の辞令をもらったその日、早速、喫茶店探しを行った。
銀座には銀座のコーヒーがあった。
中央通りからすずら通りを入った細い道沿いにその喫茶店はあった。
店内は狭かった。
60代と思われるオーナーがコーヒーをドリップしていた。
アイスコーヒーの豆はモカだった。
コクのある風味。
まるでそのコクが、「よいも悪いもない」と教えてくれるようだった。
商売のスピードとともに、すべてを受け入れるだけの心の余裕が芽生えつつあった。
1989年4月、消費税の施行とともに横浜に異動となった。
首都圏でありながら、多摩川、鶴見川を越えただけなのに、異質の文化圏だった。
ビール、アイスクリーム……
横浜には数多くの日本初の品物やビジネスがあった。
神奈川全体からのアクセスが集中していることもあって、人が集まる街だった。
異動の翌日の朝、格好の喫茶店を見つけた。
それはライバル店の横浜高島屋の目と鼻の先、ダイヤモンド地下街の片隅にあった。
「コノ字型」のカウンター、映画『アメリカン・グラフィティ』に出てくるカフェの内装さながらの店舗だった。
アイスコーヒーはほろ苦く、マイナスからの逆襲の香りがした。
どんなに頑張っても、黒字化できない店舗だった。
10の努力が20や、場合によっては100の結果となる銀座に比べて、ここ横浜では、10の努力が、2、下手をすると1にも満たないことがあった。
それでも毎日、カウンターでその日をシミュレーションするようになっていた。
なにより真摯に努力することを教えてくれた。
アイスコーヒーの豆はコロンビアだった。
その頃になると、朝の一杯のアイスコーヒーは、心と身体を整えるものになっていた。
体調が芳しくないときは、舌が教えてくれた。
なにより、努力がちぐはぐになって、気持ちが焦っているときほど、私にバランスの大切さを教えてくれた。
業績は決して高くないなか、アイスコーヒーを前に新たなビジネスを創出した。ハウスクリーニングサービスだった。
全社的にはまったく目立たなかった。話題にも上らなかった。
しかし、自分のなかでは手応えがあった。
そんな「一杯のアイスコーヒー」だったが、1つの異動が、コーヒーと私との関係性を変えることになった。
百貨店の法人外商(法人営業)のクライアントは食品メーカーだった。
そのうちの一社に、日本を代表するコーヒー飲料メーカーがあった。
ごあいさつにうかがったとき、先様の部長さんから問われた。
「お客さまへの品物の景品として、ご家庭でコーヒー豆を挽いて、それをドリップしてアイスコーヒーをとして召し上がれるようなものを作れないものかねぇ」
家庭用のアイス・レギュラーコーヒーだった。
最初は言っている意味は分からなかった。
ただし、ものは試しとトライしてみた。
自宅で、コーヒー用のポットに氷を一杯いれて、上からコーヒーをドリップするのである。
当然、氷に溶けることを想定して、必然的にいつものアイスコーヒーより濃くなった。
以来、毎朝自宅でアイスコーヒーを作ることが日課となった。
専門店ほど上手くはできかったが、自分でドリップしたアイスコーヒーのファンになった。
「コーヒーはポリフェノールの影響で身体によい」
自分で勝手に解釈していた。
朝、出社する直前に飲むだけだったのが、いきなり家庭生活の一面になった。
コーヒーがより身近になった気がした。
実はそれは、「問題」の始まりでもあった。
三越を離れ、転職のエージェントをししていたときだった。
百貨店の赤字店であってもそれなりの結果が出たのに、なかなか成果が出せないでいた。
気持ちは次第に焦っていた。
以前なら、仕事の前の一杯のコーヒーが、心と身体に落ち着きをもたらしてくれたのに、変化はなかった。
それどころか、朝からすでに何杯も飲んでいたせいか、かえって胸がドキドキしてくる感じがした。
さらに、仕事上でエージェントの代表との意見の相違から、自分が直面する問題や制限、さらには失敗を隠すようになっていた。
私にかかってくる電話、着信メールの音を耳にするだけで身体に緊張が走った。
その気持を抑えようと取った行動は、コーヒーを飲むことだった。
過剰なコーヒー摂取、「コーヒー依存症」だった。
明らかに不快な状況だった。
とうとう身体が悲鳴を上げた。
朝、起き上がれないのである。
気持ちは頑張ろうとしても、身体がついていかなくなっていた。
仕事をストップせざるを得ない状況になった。
心療内科で処方された薬は内蔵への負担が大きかった。
人生初の「引きこもり」となった。
毎朝、ドリップしていたコーヒーは、見えないところに置いた。
自分にとっての飲み物は、ミネラルウォーターだけだった。
あせってもしょうがなかった。
できることをしよう。
『空海 人生のことば』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を毎日一つずつノートに書いていった。
なにか心が洗われるような気持ちになってきた。
時間が止まったかのように見えても、水はやさしかった。
時間はかかっても身体は、徐々に徐々に変化していった。
気がつくと、家内とささやかなビジネスを始めていた。
目に見えないスピードで変化は続いていた。
一年後のある冬の朝だった。
ファミリーレストランに入った私は、久しぶりにアイスコーヒーを注文したくなった。
以前付き合っていた彼女に出会った感じがした。
もう会わないと思っていたのが、距離を置いていただけだったような気がしてきた。
アイスコーヒーは、酸味も苦味もバランスが取れていた。
初めて出会ったような感覚だった。
アイスコーヒーとの新たなつながりができた瞬間だった。
「付かず離れず」
適度な距離感を持つことが人に対しても大事なように、離れていたからこそ、コーヒーとの関係性に気づくことになった。
すべての原因は自分にあった。
心と身体は常に一体であることを、身をもって知ることになった。
うまくいかないことがあっても、それは自分にとっての最大のフィードバックである。
何よりも、自分を信じ、変化し続けることへ責任を持つことの大切さを学ぶことになった。
すると、この問題は自分の人生にとってのチャンスだと思った。
新たな思考が生まれた瞬間だった。
良いも悪いもない
時間はかかったが、コーヒーは私に、「間(ま)」の大切さを教えてくれた。
❏ライタープロフィール
高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)接遇の伝道者。慶應義塾大学商学部を卒業後、三越に入社。
販売、仕入をはじめ、24年間で14の職務を担当後、社内公募で
法人外商を志望。ノベルティ(おまけ)の企画提案営業により、
その後の4年間で3度の社内MVPを受賞。新入社員時代、
三百年の伝統に培われた「変わらざるもの=まごころの精神」と、
「変わるべきもの=時代の変化に合わせて自らを変革すること」が職業観の根幹となる。一方で、10年間のブランクの後に店頭の販売に復帰した40代、
「人は言えないことが9割」という認識の下、お客様の観察に活路を見いだす。
現在は、三越の先人から引き継がれる原理原則を基に、接遇を含めた問題解決に当たっている。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/66768