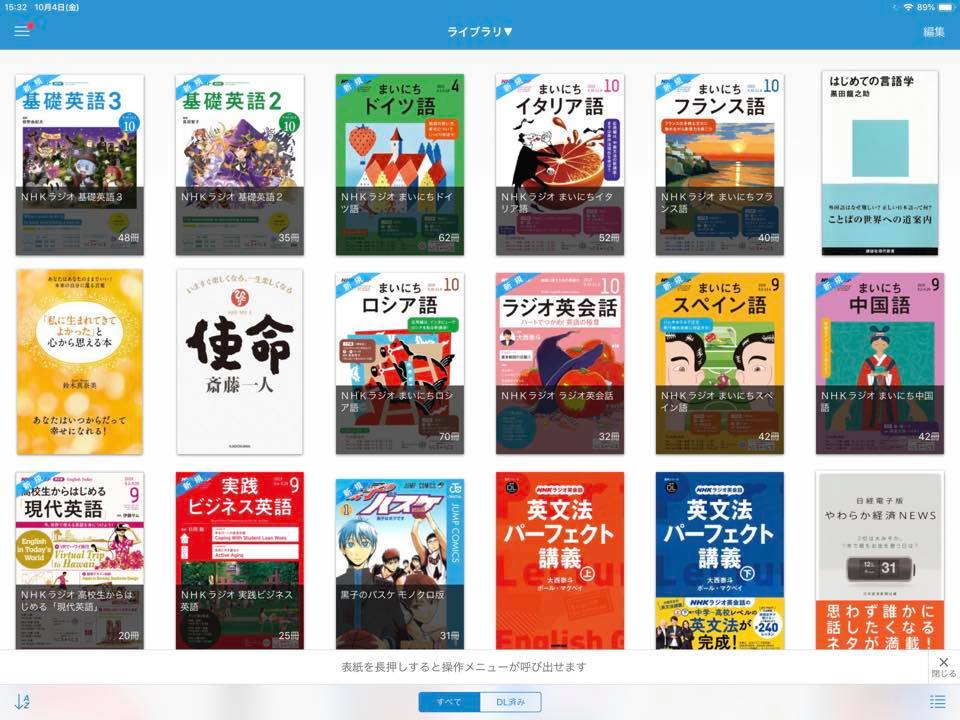一杯のアイスコーヒーから《 週刊READING LIFE Vol.53「MY MORNING ROUTINE」》

記事:高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
はじめは逃避からだった。
百貨店に入社した私にとって、新人時代、販売以上に大事な役目があった。
それは、店頭での販売の準備である。
店舗の開店は午前10時。しかしその2時間以上前から準備が始まる。
私が配属されたのは、バーゲン会場。
『男はつらいよ』の寅さんの口上よろしく、「いらっしゃいませ〜」という声の飛び交う中、安価な品物が販売されている特別な場所である。
そこは、スピードと、熱気と、音の空間である。
新人の私は、先輩たちから人足(にんそく)と呼ばれた。
その人足の第一の仕事は、表に現れない販売の準備だった。
毎朝、バーゲン会場には、その日販売する目玉商品をはじめとする大量の品物の納品がある。
午前7時半ともなれば、店舗に横づけされた大型トラックから、品物の入った段ボールが台車で次から次へと運ばれてくる。
朝一番に仕事場に入る私にとって、先輩たちが来る30分以上前に、段ボールを仕分けするという大事なミッションがあった。
次に仕分けした段ボールから品物を出して、ケースに並べるのである。
品物をケースに並べたあとは、空の段ボールを廃棄するという流れである。
「いらっしゃいませ」という接客はあくまでも表の世界。
表に現れない真実があることを入社後数日で体感することになった。
私が入社した1977年、百貨店をはじめとする小売業の現場はまだ徒弟制度の名残があった。
年齢が下でも入社年度が1年でも早い先輩の言うことに絶対服従の世界である。
良いも悪いもないのである。
動きが早いとはいえない私は先輩たちからの格好の標的となった。
「早くしろ」
「おい、ボケ」
「ナマクラ」
なかには、
「おめぇ、ほんとに大学出てんのか?」まで。
先輩が現場に来る午前9時前後までに、新人としての仕事を完了していなければならないのである。
毎日が、この納品の仕分けから始まる準備で必死となっていた。
正直言って、午前10時の開店のときはエネルギーを大方使い果たしている状態だった。
ただし、自分の意思とはべつに転機がやってきた。配属されて2ヶ月目のことだった。
その日、午前8時前から始まった準備はいつもより早く終わっただけでなく、包装紙などの備品の用意も完了。
あとは開店を待つばかりとなった。
いつもひとこと多い先輩たちも「準備はいいな」とばかりに喫煙をするため、一斉に社員休憩室に向かった。
当時の喫煙率は高く、分煙もないばかりか、午前9時には社員休憩室は「煙の殿堂」と化していた。
しかし、タバコを吸わない私にとって、開店の前に先輩と一緒に休憩することは、ある意味「拷問」以外のなにものでもなかった。
なによりも、会話に「間(ま)」が持てなかったのである。
タバコを吸うために休憩室に行く先輩たちの後ろ姿を見ながら、なぜか私は無意識のうちに社員通用口に向かっていた。
百貨店の販売員にとって、用もないのに店舗の外に出るのはご法度である。
いつもは、「すみません」と頭を下げているばかりの私は、胸を張って通用口のガードマンさんの目を見た。
「納品トラックの確認に行きます」という言葉が口をついて出た。
なぜか、はっきりと言えたのである。
表に出てみると、そこはビルの谷間から陽が差し込む光の世界だった。
以前見た映画『パピヨン』で、主演のスティーブ・マックイーンが獄門の島から脱出するシーンが頭に浮かんできた。
東京は日本橋。店舗の表玄関の向かいの路地に入ってみた。
表通りとは打って変わって人通りの少ない場所。
そこでは、目立たないながらもさりげない人々の営みがあった。
たまたま時間が空いた10分間。
ぼんやりと歩いていくと、地味ながらも商店主やサラリーマンがコツコツ働いているエリアだった。
同じ日本橋でも、なにか別世界のような気がしてきた。
そのときふと、目の前に《COFFEE》という文字を認めたのである。
路地裏の喫茶店。
なにげなくドアを押して入ってみた。
「チリーン」
ドアのカウベルが気持ちに張りを与えてくれた。
カウンターが8席と、テーブルが2つあるだけの決して大きくはない喫茶店だった。
学生時代、体育会陸上競技部に所属していた私にとって、初めての「1人喫茶店タイム」である。
「いらっしゃいませ」
カウンターの向こう側では、人の良さそうな親父さんとおかみさんが微笑んでいた。
「アイスコーヒーをお願いします」
カウンターに座った私は、無意識から言葉が出た。
季節は5月。朝とはいえ気温は高かった。朝の開店準備をした身体は、冷たい飲み物を欲していたのである。
アイスコーヒーが運ばれてきた。
銅製のカップ。脇にはミルクの入ったポットとガムシロップ。
カフェオレのようにミルクを注ぎ、ちょっと多いかなとおもうくらいにガムシロップを入れてみた。
ふと脇の壁を見ると、【アイスコーヒー モカ・ブレンド】と書かれたメニューが貼られていた。
カウンター席は、私のほかはサラリーマン風の男性2人がいた。
1人はホッとコーヒー、もうひとりはアイスコーヒーで、いずれもモーニングを頬張りながら新聞を読んでいた。
店内の照明は決して明るくなく、それが私の心をいつもよりも落ち着かせることになった。
ほんの5分ほどのコーヒータイムだった。
アイスコーヒーを飲みながら、自然に、入社してからその日までを振り返っていた。
今から思うと恥ずかしいばかりだが、開店準備に必死になっていた自分は、それだけが1日の仕事すべてだった。
冷たく、ほのかに甘いコーヒーを口に含みながら、開店準備は、あくまでも全体の一部であることを認識し始めていたのである。
自分にとっても、他の先輩にとっても、午前10時からのお客さまに対しての販売こそ、”本番”なのである。
アイスコーヒーを飲みながら、あくせく働いている自分を、天から眺めているような感覚が生まれていた。
いままでにない視点。
不思議な瞬間だった。
「とんでもないとこに入社しちまった」という印象が、一杯のアイスコーヒーから、「ちょっと待てよ」という状態にシフトし始めていた。
ステート(心理状態)の変更。
なぜだろう?
それは、その日飲んだアイスコーヒーが、苦味ではなく、いままで経験したことのない風味だったからかもしれない。
翌日から、午前7時から開いているというその喫茶店に立ち寄るようになった。
飲むのはアイスコーヒーだけ。
まろやかで酸味のある味覚に魅せられ始めていた。
3ヶ月後、
一杯のアイスコーヒーが私にとっての「空(くう)」の瞬間を作り出していた。
開店準備の煩雑さを少しでも忘れようとしていた私が、いつしか、コーヒーを飲みながら手帳を開くようになっていた。
たとえ5分であっても、読みかけの文庫本を開くときもあった。
今から思うと、仕事の本番前の一杯のアイスコーヒーによって、感情が解放されるようになっていたのかもしれない。
感情が解放されると、その日行う仕事の目的が明確になってくる。かつてはあれほど好きではなかった開店準備でさえ、その意味を知ることになっていた。
目的が明確になると、なぜか自分から行動をするようになっていた。
バーゲン会場のケースにまだ品物があったとしても、当日の売れ行きを見ながら、自分から倉庫に行って補充するようになったのである。
お客さまからクレームを言われると、いままでだったら、モジモジしてしまったのが、責任を持って、「私が承ります」と言えるようになっていた。
アイスコーヒーから始まる「空(くう)」の瞬間で、自分のなかでプラスのサイクルが回り始めていたのである。
1人でエネルギーをチャージできる場所であり、リラックスできる空間。
不思議なものである。朝、一杯のアイスコーヒーを飲むことで、今までだったら何気なく見えていた人の顔が同じではない見え方となるときがある。
たとえとして、アナログの白黒放送のシーンが、解像度高くまるで4Kのデジタルテレビを見ていうるように感じるときである。
他の人の顔の変化に気づくだけではない。
何気ない表情のなかに潜む、その人にしかない微笑みに接することで、こちらの気分も同様に高揚するのである。
28年間の百貨店生活で12のセクションを経験することになったが、出張しても、転勤しても、朝一杯のアイスコーヒーから1日が始まった。
福岡天神に新規に大型店舗を開店するとき、直前の3日間は毎日2〜3時間睡眠だった。
深夜に近くのホテルに仮眠しに帰るだけ。
それでも午前6時に出勤した私は、警固公園脇の片隅で、テイクアウトのアイスコーヒーを飲みながら、5分間の「空(くう)」を確保した。
開店前日の早朝、警固公園のベンチでアイスコーヒーを飲んでいたときである。
それまでは、開店という決して軽くない責任を感じていながら、やるべき仕事の多さに辟易していた。
すると、上空350メートルという低空で、福岡空港に着陸姿勢を取っているジャンボジェットの爆音が聞こえ、機体が間近に見えた。
そのときである。私の中でなにかが弾けた。
すると、翌日の開店を前に、渡辺通りを歩いている1人1人の人たちの表情の見え方が変わったのである。
「この方たちは、私たちの百貨店の開店を心待ち人たちなんだ」
だから自分は「開店させるんだ」という使命感のようなものである。
福岡の人々が急に身近に感じ始めたのである。
一杯のアイスコーヒーとの出会い。
はじめは、現実からの逃避だった。
それが、いつの間にか自分のなかで、かけがえのない時間であり、空間に変わっていた。
朝、一杯のアイスコーヒーを飲むことで、心身ともにリラックスして、本来の自分のミッションを思い起こさせてくれるときがある。
すると、まだやりきっていない問題でも、「できる」「できている」前提で、どうすればできるようになるか?というステートに変換するのである。
My Morning Routineとは、「一杯のアイスコーヒーを飲むこと」
アイスコーヒーに、あるときは励まされ、またあるときは腰を押されて、さらには、気持ちをほぐされる。
それは私にとって、人生の伴走者のようなものかもしれない。
◻︎ライタープロフィール
高林忠正(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
ベストメモリーコンシェルジュ。
慶應義塾大学商学部を卒業後、三越に入社。
販売、仕入をはじめ、24年間で14の職務を担当後、社内公募で
法人外商を志望。ノベルティ(おまけ)の企画提案営業により、
その後の4年間で3度の社内MVPを受賞。新入社員時代、
三百年の伝統に培われた「変わらざるもの=まごころの精神」と、
「変わるべきもの=時代の変化に合わせて自らを変革すること」が職業観の根幹となる。一方で、10年間のブランクの後に店頭の販売に復帰した40代、
「人は言えないことが9割」という認識の下、お客様の観察に活路を見いだす。
現在は、三越の先人から引き継がれる原理原則を基に、接遇を含めた問題解決に当たっている。
http://tenro-in.com/zemi/97290