さいぼうのこえ《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
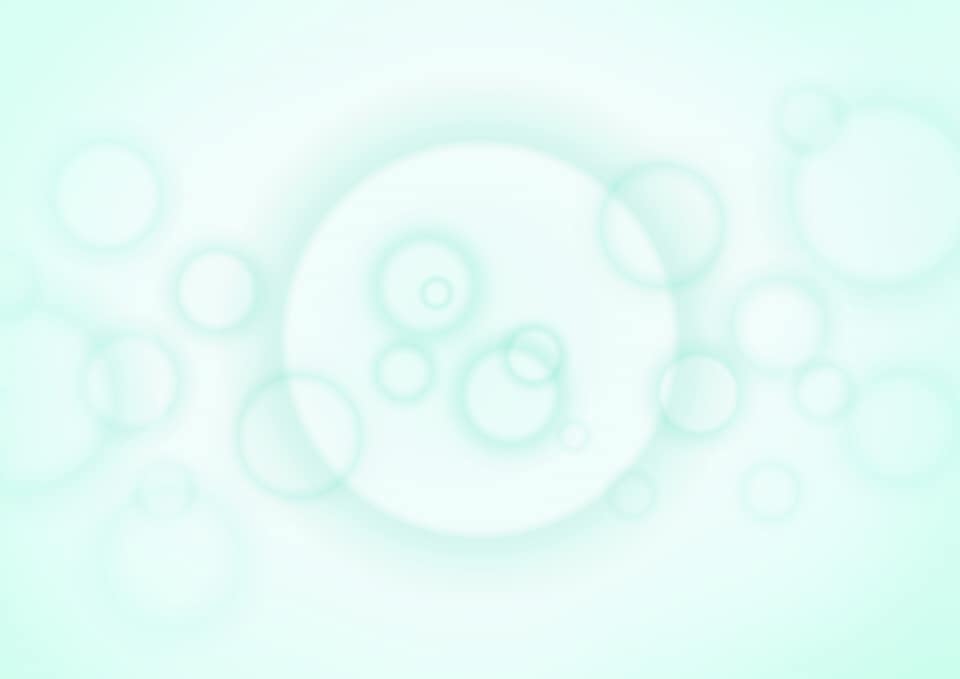
記事:藤原華緒(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
※この物語は実話をベースにしたフィクションです。
その写真のことはよく覚えている。
11月の終わり、私は1週間の休暇を取って、青森の実家に帰省していた。
そろそろ終活を始めたいという母に頼まれ、実家にある自分の荷物を整理するためだ。
年末の忙しさの直前、このタイミングしか休暇をとれるタイミングがなく、親孝行もかねての帰省だった。
すこしずつ片づけを進めていると、たくさんの写真の中から小学2年生の時の集合写真が出てきた。
8歳の私は、すこし緊張した表情で紫色のノースリーブのワンピースを着ている。
確か母が買ってくれた妹と色違いのワンピースだったと思う。
髪の毛は肩まで伸ばしていて、まだつやのある黒髪が印象的だった。
片づけをしているうちにあっという間に休暇も終わり、私は東京での忙しい日常に戻った。
休みでぼんやりしていた頭はいつもの仕事モードに戻るまである程度時間を要する。
何とか自分を奮い立たせてベッドから起き上がり、出勤の準備をする。
「ん……。なんだろう。頭痛いなあ」
そんな独り言が出るほど、頭が痛かった。あと1週間で生理が始まる。PMSかな? 生理前の頭痛だと自分にいいきかせて家を出た。とりあえず、会社に行こう。会社に着いたらすぐに、鎮痛剤を飲もう。そうすればいつものように少しは痛みが治まるはずだ。
そう思いながら、電車に乗って会社へ向かった。
いわゆるIT企業といわれる会社で、人事・労務担当として転職して以来5年になる。
この5年、いろいろなプロジェクトを担当しそれなりに成果も出してきた。
会社が上場してからは、障がい者雇用のプロジェクトでその体制を作り、運用に乗せたときには社内表彰もされた。仕事は特段好きではないが、責任感は強く、最後までやり遂げる力は持っていた。
朝の京王線は、いつも混んでいる。ましてや今日は中央線が人身事故でストップした影響で京王線に人が流れ、殺人的な込み具合だった。飯田橋までの通勤時間は30分。けれども、こんな日はたった30分程度の通勤時間が半日にも感じる。さらに、ひどい頭痛だ。
ようやく会社に到着した時は、すでに始業時間を1時間ほど過ぎていた。
それでも、あたたかい飲み物で、少しでも疲れた体と気持ちを癒そうと会社の入っているビルの1階のスタバでチャイティーラテを買う。
頭はまだ痛い。
席についてPCの電源を入れ、鎮痛剤を飲んだ。
メーラーを立ち上げて、30件ほどのメールを確認し、処理する。
今、走っている業務改善のプロジェクトの進行状況が思わしくないので、進捗の確認をしようと部下を呼んだ。
「千夏さん、顔色が悪いですよ」
部下の舞子にそういわれて、全くおさまらない頭痛がさらにひどくなった気がした。やっぱり今日は体調がおかしい。
「ごめん、今日やっぱり帰るわ。朝から頭が痛くて。大したことないと思うけど、一応病院行ってから自宅に戻るから。PCも持って帰るからメールは見るようにする。あ、さっきのプロジェクトの進捗は、また報告して」
「わかりました。千夏さん、ホントに顔色が悪いんで気をつけて帰ってくださいね」
「ありがとう」
舞子とそんな会話を交わして会社を出た。
すでに頭痛は頭をちょっと動かすだけで首まで痛みが走るほどになっていた。いつもの生理痛やPMSとは完全に違う痛みだ。
会社を出て自宅近くの内科に立ち寄った。
1時間近く待合室にいたが、あまりの頭痛に待合室で待つことができなくなり、処置室のベッドで横になりながら順番を待った。いくつかの問診と触診をしてもよくわからないと、近くの脳神経外科への紹介状を書かれた。駅前でタクシーをつかまえて、その脳神経外科へ行った。問診ではないかで話したことを繰り返す。もう何も話したくないほど意識が朦朧としてきた。
そうして、私は「髄膜炎の疑いあり」との診断をされ、そのまま入院をすることになった。
検査結果はやはり髄膜炎だった。
これは、身体の免疫力・抵抗力低くなり、健康体であれば入らない菌が脳の壁を越えて侵入するという病気だ。
入院生活のはじめ1週間は、点滴に縛られ、頭痛がなかなか引かず、食事もとれないほどだったけれど、しばらくすると薬が効き、食事もとれるようになり、少しずつ元気になってきた。それでも退院はできない。主治医には1週間で退院したいと訴えたが、あっけなくNGが出た。自分の病気があと少し診断が遅れると後遺症が残ったり
死に至る病気であることを説明され、その事実に愕然とした。
そういえばずっと夏頃から体調が悪かった。
仕事は年明けから大きなプロジェクトを担当していた。部下や同僚と進めてはいるが、何せ初めてのことばかりでプロジェクトマネジメントだけでなく、同時に自分の知識もつけなければいけなかった。それでも、休日はあまり休むこともせず、遊びに出かけたりしていた。こうして身体は酷使され、休むことも許されない状態が続いていた。
病院というのは不思議な空間だ。
自分が健康で元気な時に、お見舞いなどでそこを訪れる感覚と、病気の自分がこの場所にいる感覚はまるで違う。そして、元気に生きている人間と一時的にでも死に近づいている人間はそもそもの波動が違う。
今の私はそんな死の波動をまとった人間になっていた。
そして、この病院という場所は、そんな私に最も適した場所になっていた。
入院生活も1週間を超えてくる頃になると、テレビにもネットにも飽きて、日々、病院の窓から乾いた冬の空気が見せる青空を眺めていた。青の濃い部分と薄い部分の境界線、時おり流れる雲の形を見ているうちに、世の中から遮断され、隔離されている自分を嫌でも意識するようになってくる。
入院生活は、いわば社会人としての「強制終了」だ。
突然、会社に行かなくなり、社会との接点を失う。
そして、私ごときがいなくなったからといって世の中は何も止まることはなく、淡々と動いていく。
私はそうやって、社会との接点がなくなっても、それに対しての焦りは不思議と出てこなかった。
むしろ焦りがないことに焦っていた。
私は、何をしたかったんだろう?
私は、何が好きだったんだろう?
今まで仕事と遊びと、少しの恋愛をして毎日を充実させ、自分なりに精いっぱい生きてきたつもりだった。それでも、いつの間にか身体から抵抗力が失われ、気が付くと病気になっていた。
自分の人生史上最も死に近い波動と環境の中で、私は日々ぼんやりとそんなことを考えていた。
入院生活は2週間となる目前で、最後の検査を行った。
苦しい検査と治療を経て、数値が正常に戻っていることを確認し、ようやく主治医から退院の許可が出た。
そして、退院を翌日に控えた、病院で過ごす最後の夜。
9時の消灯にあわせって目をつむった。
うっすらと眠りに入りかけようとした時、突然病室のドアが開いた。
「看護師さんかな?」
そう思って入り口の方向に目を向けると、小さな女の子が立っていた。
すこし緊張した表情で紫色のノースリーブのワンピースを着ている
「あれ? この子、見たことがある」
そう思った瞬間、私は彼女が写真に映っていたあの小学2年生の自分であることに気が付いた。
「ごめんね、わたし、ごめんね。大切にしてあげてなかったね。わたしの体の、さいぼうのこえを聞いてあげてなかったよね。いつも後回しにしてごめんね。わたしを後回しにしてごめんね。こんどはちゃんとするから。ちゃんとするから……」
そういって、彼女はドアを閉めて立ち去った。
私は恐ろしくなった。
それは、彼女が見えたことに対する怖さではなかった。
細胞が全力で声を上げていることを無視し続けていた自分への恐れ、そして「私の本当」を無視していたことへの恐ろしさだった。自分の奥底にあるものから目をそらして無理をし、身体が一生懸命発信しているメッセージを無視していたこと。私はいつの間にか私の人生を生きていなかったこと。好きなことでもないことに時間を使い、ただ、自分の欲と欲求を満たすだけの日々だったこと。
自分のやっていることが、好きなことならよかったけれど、病気になるぐらいだ。
きっとそうではなかったのだ。
これは夢ではない。それは、私自身がいちばん自覚していた。
あの小学2年生の私は、あのころのまっすぐな自分に戻ることを教えに来てくれたのだ。
翌日。
私は予定通り退院した。
タクシーで帰る車の中でから、凝りもせず空の濃い部分と薄い部分の境目を探していた。
そして、家に帰ったら一番にすることを決めていた。
私の再生の物語は、ここから始まる。
そんなことを思いながら、私は「心を込めて」辞表を書きだした。
❏ライタープロフィール
藤原華緒(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
1974年生まれ。2018年より天狼院書店のライティング・ゼミを受講。20代の頃に雑誌ライターを経験しながらも自分の能力に限界を感じ挫折。現在は外資系企業にて会社員をしながら、もう一度「プロの物書き」になるべくチャレンジ中。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/70172
関連記事
-

その瞬間が、ターニングポイントになるかもしれない《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-
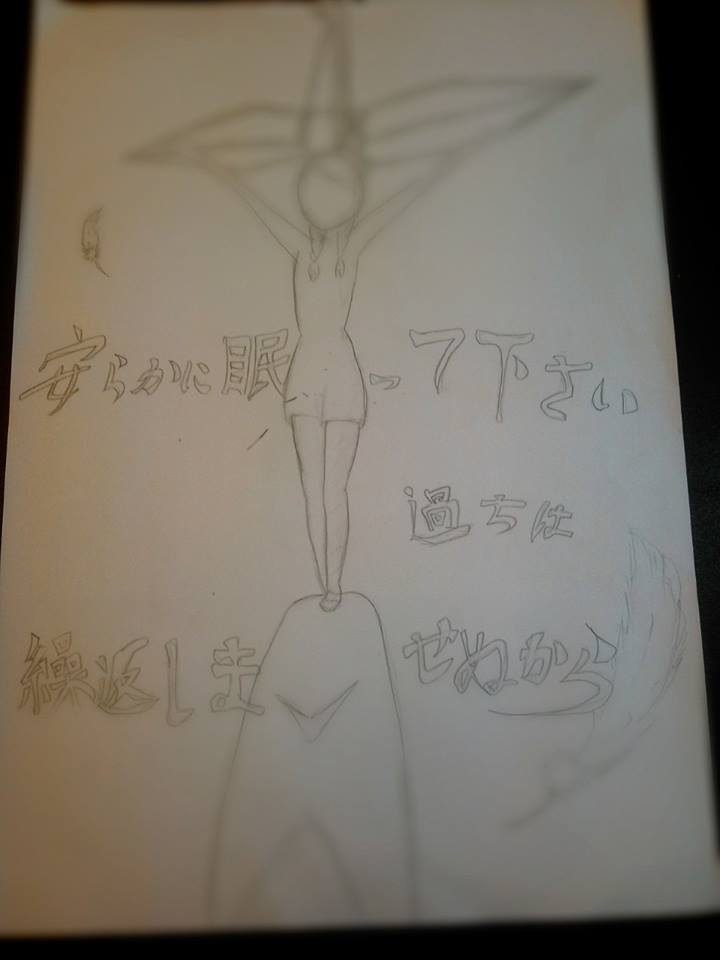
絶対反対を心に決めた時《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-

誰が為に鐘は鳴る!《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-

人生の転機は雨とともに突然やってきた《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-

転機は天真爛漫な笑顔とともに~5歳の少女が教えてくれた私の生きる意味~《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》



