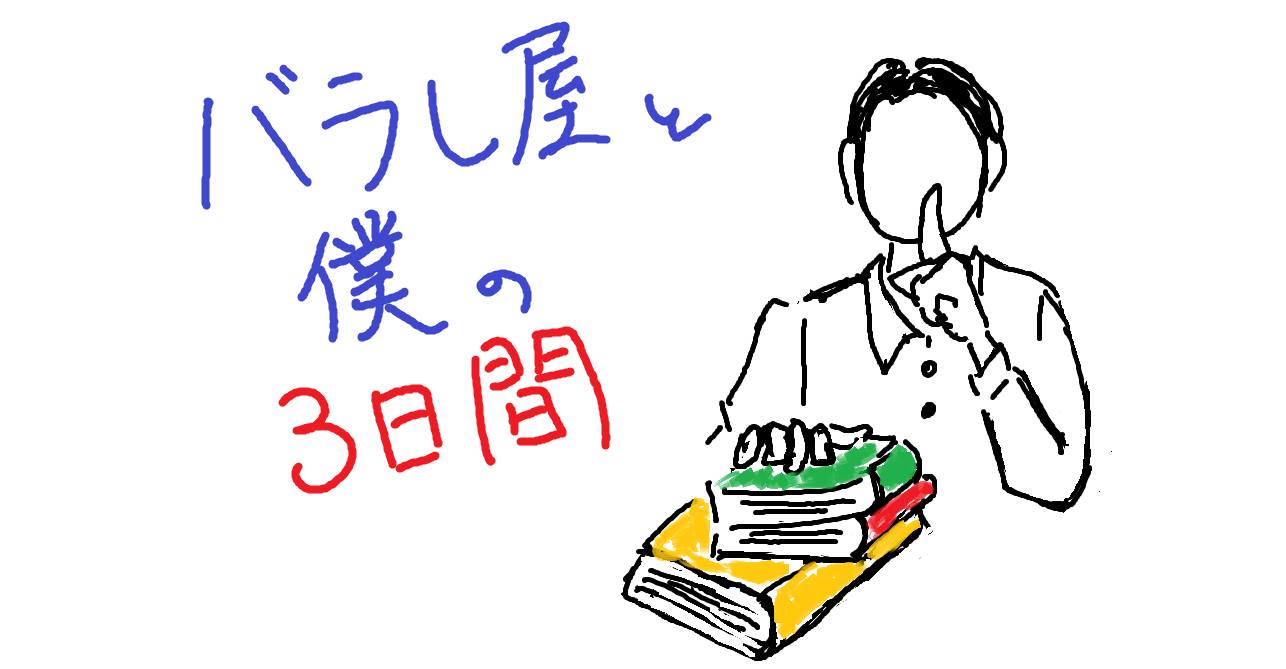食べるのが仕事です《 週刊READING LIFE Vol.42「大人のための仕事図鑑」》

記事:服部動生(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
今日はこれで4食目、腹はとうに満たされているが、まだ入れようと思えば入る。もう慣れたものだ。飲食店に勤めていれば食事の回数は自ずと多くなる。最近はもろに体重が増えるようになってきた。いくらでも食べられた学生の頃とは、既に体が違っている。
私の母は飲食店を経営している。母は料理人ではないので、自分では作らない。しかし、料理を作る職人にあれこれと指示を出さなくてはいけない。母には理想がある。彼女の脳裏に焼き付いている『美味しい』という記憶の再現だ。同じレシピでもその日の仕入れによっては思い通りの味にならないことがある。数字で表すのが難しい『味』を、いかに記憶しておくかが、飲食店で一番上に立つ人間としては大事なこととなる。
母はまだ学生の私を連れて、様々な料理屋に足を運んだ。有名なところというよりもむしろ、市井に潜む『美味しい』を探して、いつもさ迷い歩いていた。
私は食べ盛りだったので、出されれば出されるだけ食べた。そして母も同時に食べる。時には私よりも多く食べることもあった。狂ったように食べては、お店にごちそうさまと言って出ていく。そのあとから始まる時間が、私にとっては苦痛だった。
「最初のお通しはひどかったね」
品評会が始まる。二人だけの品評会だ。身近な店に足を運ぶので、知り合いの店も多かった。美味しかった時は素直に褒めるが、期待外れだったときは、このように開口一番爆弾が飛び出す。爆弾の所在はだいたいわかる。母は気に入らない料理があると、明らかに食べ方が雑になる。平気で残すし、時には私に食べるなとまで言うときもある。
私はそこまで過激には思わない。多少期待外れだろうが、ちゃんとお店を経営できている以上は、並程度のおいしさはある。よほど不味くなければ食べきるのも礼儀だと思うのだが、母ははっきりと意思表明する。
「でも魚は臭みもなかったし、すっと食べられた」
自分と感想が一致したときはほっとする。とりあえず過激な発言は一休み。
「でもつまらない。普通の味だ。もっと裏切りが欲しい」
と思ったらすぐこれだ。刺身でどう裏切れというのか。学生時代の私には何もかもわからない世界だった。
今でもこのやり取りはあり、どこかに食べに行くと必ずある。夜は自分の店の営業があるので、大体はランチタイム。そして一通り感想を言い終えると、自分の仕事に戻る。
私は母の店で経理の仕事をしている。営業開始が17時なので、それまでには仕事を終わらせるようにする。
「ちょっと食べていけ」
帰ろうとしたとき、母に呼び止められた。新しいメニューができたので、それの味見をするらしい。正直お昼を食べすぎたのでお腹が空いてないが、断れない。
店の入り口から一番近い席で待つこと数分、料理が出てきた。最近母が苦心している穴子丼だ。上手くいけば店の新商品になるのだが、今回はどんなもんだろうか。
穴子は煮てある。箸で穴子を切り、下の白飯とともに口に入れる。煮汁が米にしみこんでいてこってりと甘い。穴子も良く煮えて柔らかい。だが、肝心の味がダメだ。まず穴子に十分味が通っていない。穴子が必要以上に淡白で、口の中で味わおうという気にならない。それに、煮汁が甘いのは王道だが、甘いだけだ。少し粘り気が足りない。
まとめると、総じて物足りない。体裁を整えるための必要最低限のものがあるだけだ。私は母を呼び出して感想を述べる。母は「そうか」といって厨房へと戻っていった。
仕事ではあるのだが、こんなことを考えながら食事をとるのがそもそも苦痛だ。もっと気楽に、何にも考えずに食べたり飲んだりしたい。今となっては、友人たちの集まりでさえ、出てくる料理に色々と寸評している自分がいる。
今回の様に、不味い料理を不味いとはっきり口にしなくてはいけないのは変なプレッシャーがかかる。この料理も作ってる人がいると考えると、どうしても気が引ける思いだ。ただ、仕事なので言わなくてはいけない。
もやもやした気持ちのまま家路につく。個人経営でも色々な形態があって、私たちの家は店舗と別にある。ほんの十分ほどの道のりだが、ぶらぶらと外を歩く。
賑やかな街なので色々な店が目に映る。だが、興味を引く店は極端に少ない。色々な場所で食事をした弊害か、料理名と値段で味は予想がつく。写真があればもっと正確にわかる。たとえ初めて食事をする店でも、この予想が裏切られることはまずない。たとえ世間では美味しいとされていても、予想がつく以上驚きはなく、食事の楽しさは半減される。
映画でも小説でもそうだが、意外性はエンターテイメントとして最高のスパイスだ。日常家庭で食べる料理ならともかく、店で食べる食事は、栄養補給以上の意味がある。
かつて母が言っていた。
「私たちは栄養を食べるのではない。文化を食べている」
店の料理に求められているのは、栄養補給を超えた美味しさだ。食事は摂らなければ死んでしまう。そんな中で、栄養補給を忘れさせるような美味しさを体現するには意外性が不可欠だ。
ただ私の場合は、意外性の実例を母とともに見て回ったせいで、大抵の仕掛けでは動じなくなってしまった。どんな店の料理も、栄養補給に見える。さもなければ研究対象だ。いずれであっても、楽しいとか嬉しいとか、感情とは切り離された理性の世界だ。
もっと純粋に、『美味しい』と思って食事がしたい。これは世間的に『美味しい』とか、自分の好みだが、世間的には『美味しくない』なんて考えずに食事がしたい。
「私の理想は、私の母の料理です」
母は常連のお客さんにこういう話をたまにする。母の母、つまり祖母のことだ。ウチは郷土料理、高級な割烹などとは違う。祖母の味の再現こそが、郷土料理の完成を意味する。ただ、祖母の料理だけを食べていてもダメらしい。祖母も民宿を経営していて、お客さんに自分の料理をふるまっていた。その料理は、その日にある食材でとにかくお客さんをお腹一杯にする料理。必ずしも土着の食材だけというわけではない。ただ、お客さんは皆満足して帰っていく。祖母の精神を探求するには、とにかく世間に散らばる『美味しい』を収集しなくてはいけない。
「お前はもっといろいろな料理を知れ」
母には祖母の料理という目標がある。大きな指針がある。それと同じものを、私も用意しなくてはいけないらしい。母が家庭では料理をしない人なので、とにかく色々なものを取り込む必要があるようだ。
で、そのためにはまた食べなくてはいけない。自分の目標を見つけるためには必要な作業のようだが、やはり食事は楽しくない。そういう気持ちが心の中では支配的だ。
今日も今日とて食べに行く店に目星を付ける。近場の店は行きつくしたので、雑誌などを参考に少々遠い土地のも行くことがある。ただ、自分たちにとって参考になる料理かどうかは、実際食べてみないと判断しかねる。ネット上の口コミサイトなどもだいたい同じ。最後は足で探すしかない。
と、今日については知り合いの紹介の店に行くことになっていたので、探す手間が省けた。二駅ほど離れたところに、知り合いの行きつけの店があるらしい。
雨の降る中、最寄り駅で私と母は知り合いを待つ。雨が降ると店の売り上げは大抵落ちる。外出したくないのは当然の心理だ。それは今の私もそう。だが、仕事なので雨の中だろうが食事のためにわざわざ電車に乗らなくてはいけない。
知り合いの女性はすぐにきた。どうも同じ電車に乗っていたらしく、すぐさま店に向かう。
たどり着いた先は古びた商店街。閉まっている店もちらほらあり、なんだか不安になる。
「あそこ」
知り合いが指さした先には、商店街に似つかわしくない活気を放っている店が、小さな扉を全開にして佇んでいた。
「いらっしゃい。珍しいね、一人じゃないなんて」
「今日はお友達連れてきた。この人原宿でお店やってるのよ」
「あらら、それは気が抜けないね」
店に入ると、気のよさそうな板前が一人カウンターの中にいた。カウンターが8席、座敷に6人ほど座れる。カウンターに座れば隣の人と肘がぶつかりそうになるほど小さな店を、人が埋め尽くしている。
知り合いが母の紹介をすると、板前さんは早速料理に取り掛かる。私は半ば思考停止して、鮭定食を頼んだ。値段は950円。これで一体何が出てくるというのか。
料理を待つ間、私は板前さんの手つきを見ていた。ある意味この時間が一番すくいがある。動いている物を見る、ただそれだけのことがほんの少しの楽しみだ。
私の鮭が焼き台の中に放り込まれる。小さくて魚が二人分しか入らないほどだ。明らかに非効率だが、この店はそれで回っている。板前さんの技量のたまものだ。
「はい、鮭の人」
カウンター越しに板前さんがお盆を渡してくる。私はすかさずそれを受け取る。こんなに混んでいる店内に一秒でも長く居座ることが憚られたから、さっさと退散しようと思ったのだ。
「あっ」
私はお盆を目の前において一息ついたとき、一瞬動きを止めてしまった。予想と違う。鮭が私の概算よりもはるかに分厚い。遠目で見たときはさして注目していなかったからわからなかったが、骨がそそり立ち、皮もちょうどよく焦げがあり、立派な鮭だ。もっと薄い鮭が出てくると思っていた私の中で、一瞬にして光明が差した。
技量の高さはなんとなくわかっていた。そしてこの鮭、見た目から格が違うとわかる。それから導き出される答えは
「美味しい」
久しぶりに食べた。こんなに美味しい鮭は久しぶりだ。私は可能な限り丁寧に骨をほぐし、皮ごと身を切り、口に頬張る。皮の香ばしさと、すっきりとしたたる油。いくらでも米がすすむ。
気が付けばおかわりしていた。味は予想できると思っていたけれど、その予想を裏切る存在に出会えた時、私は真に『美味しい』を発見できた。
「お前がそこまで言うって珍しいね」
母は母で、頼んでいたカレイの煮つけを絶賛していた。どうやらこの店はまれにみる大当たりらしい。
あっという間に食べ終えると、次の仕事の時間となっていた。私は母を置いて先に店から出ると、早足で自分の店に向かう。
そう、今日みたいなことはごく稀にある。私が絶望しきったときにいつも天啓の様に現れる。そしてそれは意外なことに、値段だとか、有名店かどうかなどは一切関係ない。ごく身近にありそうなところに、驚きは隠されている。これからも私は、憂鬱とした食事を続けるかもしれない。けれど、もしこの驚きが一年に一度でもあるなら、仕事のための食事もする意味があるかもしれない。
「お前、お客さんの前に出せないから痩せろ」
気合が入りすぎて、少しばかり太ってしまったのはまた別の話。けれど食事の量は減らせないので、今は運動をして体形を保つようにしている。
◻︎ライタープロフィール
服部動生(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
原宿に店を構える飲食店経営者家族の一員。主に経理担当。一日に二食は外食。現在は通っているジムから体脂肪率をとりあえず5%落とすように指示されている。
http://tenro-in.com/zemi/86808