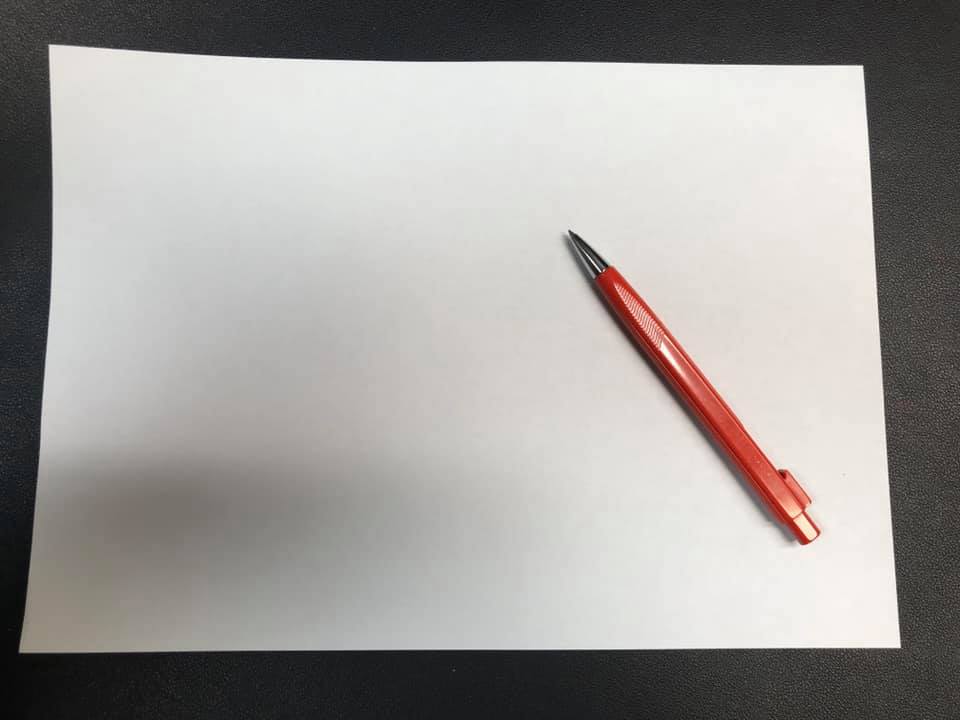黒い液体があるから、それをコーヒーと呼ぶのは間違いである《週刊READING LIFE Vol.57 「孤独」》

記事:千葉とうしろう(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
いじめの話をしよう。孤独の最たるものがいじめだと思うからだ。孤独には良い面も悪い面もあるが、悪い面が凝縮されたものがいじめだと思っている。最終的には、どうすればいじめを克服できるか、ということを、私の経験から話せればと思う。
それと、私は別にいじめに会った経験が特別なものだと思っているのではない。誰にでもあることだと思っている。私だっていじめられたし、いじめる側に回った経験だってある。おそらく意図せずにいじめていたことも多々あったと思う。「ひどい目に会った」とは思うが、それが特別だったとは思っていない。どこにでもあるいじめに対して、その時たまたま私がソコにいただけだ。
私がいじめにあったのは、小学校高学年のころだ。あんまり思い出すのも嫌だが、クラスから除け者にされたのが、かなりこたえた。小学生のとき、グループになって勉強をする時間が会ったと思う。5〜6人のグループに分かれて、理科の実験をしたり、どこか課外活動に行ったり。そんな時がひたすらつらかった。というのも、自分がグループに入ろうとすれば、そのグループがいじめる側のターゲットにされるからだ。だから、私は迷惑をかけたくなかった手前、どこにも入れずに、一人でグループ作業の時間が過ぎるのを待っていたのだ。
それと小学校のとき、私はクラブ活動で野球をやっていたが、いじめっ子が同じ野球部のクラスメートだったことも、こたえた原因だった。逃げ場がなかったのだ。私が野球部に入ったのは小学校5年になってからで、遅い方だった。野球部に入るときはまだいじめられていなかったので、野球部に入ったあとに立場がつらくなるなんて思っていなかったのだ。いじめっ子は野球がうまく、私が野球部に入ったときは、私との実力差はかなりのものだった。おそらく小学校低学年から、クラブ活動で野球をしていたと思われる。
放課後に校庭で野球の練習をしている野球部員を見て、ユニフォームを着てボールを追いかけている姿を見て楽しそうだなと思って入ったのだが、「野球がうまくならなければ立場がなくなる」ことまでは頭が回らなかった。私はバッターボックスに入っても打てず、守備で守ってもボールを取れず。三振やエラーばかりの私に対しておそらくイライラが溜まっていったのだろう。「コイツなら強くあたっても構わないだろう」と思われたのだと思う。
さて、そんな私も中学校に上がる段階になって、完全にいじめから逃れることができた。小学校のうちに、先生やお互いの両親が介入してくれて、直接的ないじめは無くなっていたが、いじめていた人間に対して苦手意識がずっとあったのだ。小学校の間、「自分はまたいつ、いじめられてもおかしくない」とビクビクしていた。
だが中学に進学して環境が変わって、ずいぶんと楽になった。学年全体の人数が増えたおかげでいじめっ子との接点も無くなったし、何より広い世界を見られるようになったからだ。どうして広い世界を見られるようになったのか。それは、哲学入門の本を呼んだからである。私は哲学の本を読み、哲学を知り、それまでの自分の世界がいかに狭かったか気づいた。「いじめなんて大したことではない」と、強く考えられるようになったのだ。
スイスの言語学者で哲学者の、フェルディナン・ド・ソシュールの、言語と存在についての話を読んでからだ。ソシュールは、言語を「差異のシステムである」と指摘した。
たとえば今、私の目の前には、マグカップが置いてあり、その中には黒い液体が入っている。私たちはこの黒い液体のことを「コーヒー」と呼んでいる。この「コーヒー」であるが、私たちは、どうやってこのコーヒーを「コーヒー」と呼ぶようになったのだろうか。普通に考えれば、コーヒーという黒い液体があって、それを他と違う名前で呼ぶために「コーヒー」という言葉を持ち出したと考えるだろう。コーヒーでなくてもいい、携帯電話があって、それを他のものと違う名前で呼ぶために「携帯電話」と呼び出したのだ。テーブルというのがあり、これを他のものと違う名前で呼ぶために「テーブル」という言葉をつくりだしたのだ。
けれど、これは実はそうではないのである。逆なのだ。日本語では「コーヒー」だし、英語では「coffee」であって、言語は日本語でも英語でもフランス語でも中国語でもなんでもいいのだが、黒い液体を「コーヒー」などの名前で呼び出したのは、そこに黒い液体があったからではない。それを「コーヒー」などの名前で呼び、他と区別し始めたため、そこにコーヒーが区別されるようになったのだ。
たとえば私は、目の前にあるこの黒い液体をコーヒーだとわかっているから、その液体の名前を呼ぶことができるのだが、その黒い液体をコーヒーだとわかっていない人にとっては、それはもはや存在しないものなのだ。
たとえば日本人は、英語のRとLの発音を聞き取れない人が多い。日本人にとってRとLの発音の区別ができないのは、日本語に「ら行」のような発音は「らりるれろ」の5文字しかないためだ。だから、「rigtht」と「light」だとか、「rice」と「lice」だのと話されたところで、「それってどう違うの?」「同じだよね?」としか思えないのである。
たとえば私は味オンチな方で、味を細かく分けることができない。私の舌は、細かい味の違いを区別できないのだ。私にとってコーヒーはコーヒーでしかないし、緑茶は緑茶でしかないし、白米は白米でしかない。しかし現実には味を細かく判断できる人もいて、コーヒーを「コロンビア・エメラルドマウンテン」とか「エチオピア・モカ」などと種類分けできる人もいる。私にとっては、コンビニで売っている緑茶はどれも緑茶であって、パッケージの違いでしかないが、「綾鷹」と「生茶」と「おーいお茶」について「まったく違う」という意見を持っている人もいるだろう。私にとって白米はどれも同じ味に感じるが、「ひとめぼれ」と「こしひかり」と「あきたこまち」を明確に区別できる人もいるのだ。
NHKのアニメで「おじゃる丸」というのを、子どもの頃に見ていたが、このアニメに「カズマ」という登場人物が出てくる。カズマは石を集めるのが趣味で、道に落ちている何でもない石でも、カズマにとっては色とりどりの宝石のように見えるのだ。下校途中に石を拾ってきては自分の部屋に並べ、「この石のこんなところがいいだろう」と話始めるのである。我々にとって、石は石でしかない。手触りがツルツルでもスベスベでも、形が三角でも四角でも、大きさが大きくても小さくても、確かに言われればなんとなく違いがわからなくもないが、「その違いがどうしたの?」というレベルである。そんな違いは違いのうちに入らず、言われなければ気づかない。我々にとって、石は石でしかないのだ。
知っている人も多いと思うが、「ベルセルク」という漫画がある。中世ヨーロッパを舞台にして、剣と魔法とモンスターが入り乱れるバトル漫画だ。この漫画にガニシュカ大帝という敵キャラがいた。ガニシュカ大帝は、転生して超巨大なモンスターになってしまい、人間を他と区別することができなくなってしまった。ガニシュカ大帝が歩くと、多くの人たちが潰されてしまうのだが、ガニシュカ大帝にはそのことがわかっていない。歩きながら、潰されて血みどろになった足元を見て「おお、足元から赤い花が咲いた」とか言っている始末である。我々のような普通のサイズの人間から見れば、人間という存在がわかるが、ガニシュカ大帝にとって人間は存在しないのである。
つまり、エメラルドマウンテンでも、ツルツルした石でも、人間でもいいのだが、言語によって呼び、他と区別することができるから、その人にとっては存在するのであって、区別することができなかったら、エメラルドマウンテンも、ツルツルした石も、人間も、存在自体が「ない」のである。
舌が肥えた人間にとっては、エメラルド・マウンテンもエチオピア・モカもあるのだが、私にとっては「ない」のだ。カズマにとってはツルツルした石もスベスベした石もあるが、我々にとっては「ない」のだ。我々にとって人間はそこに存在しているのだが、ガニシュカ大帝にとって人間は「ない」のだ。
ソシュールが言語を差異システムと言ったのはこのことで、ものを呼び区別することができるから、その人にとっては存在するのであって、この世界の本来の姿は、何も区別されていない混沌とした世界なのかもしれない。人によってその区別するものが違うだけ、差異できるものとできないものがあるだけであって、人によってまちまちである差異をなくしてみたら、この世界には何も存在しないことになるのだ。
このソシュールの話を中学時代に読んだ時、私ははじめて、いじめというものを客観的に見ることができた。それまで小学校でいじめにあって、「どうして自分はいじめられたのか」「どうして、いじめる側といじめられる側がいるのか」などと考えていた私にとって、いじめも、このソシュールの言語学の話も同じに思えたのだ。
それは、いじめるからいじめられる側が出てくる、ということだ。当たり前のようだが、そうではないと思う。たとえば、能力が劣っている者と勝っている者が始めにいて、そこにいじめが発生するのではない。いじめという行為をするから、そこにいじめる側という差異が出てくるし、いじめられる側という差異も出てくるのだ。ソシュールの話は私にとって、「世の中は平等である」「世の中の人間は平等である」と言っているように聞こえた。そう私は解釈したのだ。
「どうして自分はいじめられたのか」「自分の何が原因でいじめられる側になったのか」「自分の何が間違っていたり劣っていたりしたのか」と考えていた私にとって、「元々この世界は混沌としていて、区別なんてものはそもそも無い」という考えは救いだった。そこで初めて「いじめとはそういうものか」と一歩外側から世界を見ることができたのだ。
いじめを克服するには、いじめを外側から「いじめとはそんなものか」と客観視できるようになることが必要である。そのための方法は、哲学を知るのがいいのではないかと思っている。哲学は自分が見えている世界に疑問を抱かせてくれる。それまでに客観だと思っていたものが、実は主観だったと気づかせてくれる。客観の客観、そのまた客観……と、どんどん視野を広くしてくれるのだ。悩んだり傷ついたりして、出口がわからなくなっている状態。視野が狭くなっている状況を克服するには、最適な方法だろう。もし、孤独を感じているのなら、孤独を克服したいと思っているのなら、私は哲学をおすすめする。
◻︎ライタープロフィール
千葉とうしろう(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
宮城県生まれ。警察に就職するも、建前優先の官僚主義に嫌気がさし、10数年勤めた後に組織から離れてフリーランスへ。子どもの非行問題やコミュニケーションギャップ解消法について、独自の視点から発信。何気なく受けた天狼院書店スピードライティングゼミで、書くことの解放感に目覚める。
http://tenro-in.com/zemi/102023