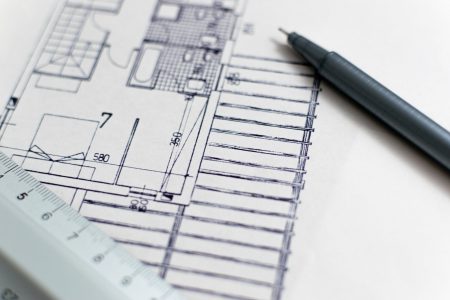そのカレーこそが、私のカレーだから《週刊READING LIFE Vol.79「自宅でできる〇〇」》

記事:和辻眞子(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
カレーが好きだ。
世の中にはいろんなタイプのカレーがあるけど、特にどのジャンルが好きと言うこともなく、満遍なくカレーそのものが好きなのだ。
欧風カレー、インドカレー、タイカレー、お蕎麦屋さんのカレー、小麦粉多めのカレー、2日目を迎えてコクが出てきたカレー、どれも好きだ。何なら、日替わりで毎日何かしらのカレーを食べても全然飽きないんだと思う。
という訳で、今まで、数え切れないほどのカレーを食べてきた。
私は味覚が単純なので、振り返るとどのカレーも本当に美味しかったし、食べて後悔したカレーは1つもないと記憶しているけど、強いてどのカレーが一番印象的だったかと訊かれたら浮かんでくる味が1つだけある。恐らくだけど、自分で作った回数も一番多いはずだ。多分この先、自分史上、このカレーを超えるものは出てこないだろうという確信めいたものがある。
新卒で入った職場を2年勤めたところで、私は結婚した。
結婚というものはとても面倒くさいと思う。お互いの気持ちの維持云々だけじゃなく、色々な決め事が山ほど発生する。
仕事はどうする、住むところは、引っ越しは、式は、披露宴は、二次会は、周りの挨拶は、ドレスは、招待状は、……。うんざりするほど決め事が降ってくると、そのこと自体が面倒になってくる。今だから言えるけど、結婚にまつわるいろんなことって、絶対にしなきゃいけない訳じゃない。むしろ、しなければしないで節約にもなるしシンプルにもなる。だけど、みなさんと同じように昔は私も若かったし、結婚に対しての一種の憧れもあったから、そういうことを一通り考えてしまう、ごくごくありふれた人間だった。
期日までに色々決めないといけない、どうしようどうしよう。あの当時、私は目がつり上がってるくらい、他のことが見えていなかった。ケッコンケッコンケッコンケッコン、夜も日も明けず準備に追われ、あくせく考えていた。
あまりにも色々なことに時間を取られていたせいで、肝心なことを決めていないまま準備が進んでいた。新居が決まっていなかったのだ。普通そういうことって最初に決めない? と思うかもしれないが、結論が出ていなかった。
理由は、夫の職場と私の職場が離れているからだった。
結婚しても仕事は続けたかったが、私の職場は実家から通うと近いけど、夫の職場の近くからだとうんと遠くなってしまう。通勤時間が3倍くらいになるのは正直辛いので避けたかった。では中間地点で住んだらどうか? と物件を探したが、条件的にいいものが出てこなかった。迷っているうちに、式が近づいていた。
「あなたたち、住むところどうするの?」
顔を合わせる度に、義母は私たちに訊いてきた。
「今、いろいろ見て回ってるんですけど、なかなかいいところがないんだよ」
「そろそろ決めないと大変よ? 日曜に見に行ったやつはどうだったの?」
「あれね。何軒か行ったんだけど、川沿いだったり日当たりが悪かったり、家賃が高かったりで、結構無理だった」
「何やってんのよ」
夫に、新居の決まり具合を尋ねたあと、義母は切り出した。
「実はね、こないだ近所の森さんと話していた時につかんだ情報なんだけど」
その切り出し方に、ちょっと嫌な予感がした。義母はいい人だけど、いい人すぎてお世話がすぎるのだ。
「今度、4月から森さんご一家がロンドンに転勤になるんだって。それで海外にいる間、家をどうしよう、空き家にしておくのも物騒だし、その期間だけ誰かに貸すっていうのもそうそう都合よく決まる訳じゃないしって言っててね」
そこまで一気に喋ってから、さらに畳み掛けるように続けた。
「それでこれは提案なんだけど、その間、あなたたちがそのおうちに入ったらと思うんだけど、どうかしら。眞子ちゃんは職場が遠くなっちゃうから家事が大変だと思うけど、私も近所にいるし、いろいろ手伝ってもいいわよ」
えー……。
正直あんまり気が進まなかった。職場からめちゃくちゃ遠くなるし、通勤のしんどさも半端ないからだ。でも夫にしてみれば、実家から近いし、職場も近い。それって私にあんまりっていうか、ほとんどメリットないじゃん!
「考えておくよ」
そう答えて、夫は一旦話を引き取った。
「さっきの話、どうする?」
2人でカフェに入った時、夫は私に尋ねた。
「うーん。正直ちょっとどうなのとは思う。通勤めっちゃ大変だし座れないだろうし。帰ってきてから夕飯の支度する気力がないと思う」
「でももうこのままだと時間がないし、なかなかいい物件がなかったし、どこに住むかでまだ決まってないし、厳しいと思うんだよね」
その時点で、式まであと1ヶ月を切っていた。他にも決めないといけないことがあったし、仕事も通常通りあったし、とにかく時間がなかった。
「通勤は、僕が車を出す時間を早くするから、駅まで送ってあげるよ。僕が少し早く出勤すればいいだけだから。お袋も、夕飯のおかずくらいなら作ってあげるって言ってたし」
あの頃は、いろんなことに、自分はNOを言ってはいけないのではないかと思っていた。嫁に行くのだからという妙な使命感とともに、従わないといけないという縛りのようなものがあった。まだ平成の初めの頃は、思いっきり昭和というモンスターのような時代を引きずっていたから、考え方も昭和の風習に寄ったものが普通だったかもしれない。こうして夫側から外堀を埋められると、何にも言い返せないような気持ちになった。そんなこともあったけど、とにかく式の後に住むところが決まっていなかったのだ。
「……そうね。森さんは私も知ってるけど、あの人ならいい人だし、お義母さんもそう言ってくれるなら、お言葉に甘えようかな」
なんとなくだけど、半分白旗を上げたような気分で、私はその家を借りることを承諾した。
こうして、夫の実家近くの借家が新居となり、新しい生活が始まった。
新居は私鉄の、各駅しか止まらない小さな駅が最寄りで、そこから歩いてたっぷり15分はかかった。それまでターミナル駅から徒歩数分という環境で育った私にとっては、電車が10分に1本しか来ないということからして結構なストレスとなった。電車などというものは、2分くらい待っていれば勝手に来てくれるもんだと思っていたのに、ここじゃ1本乗り遅れたら長々と待たないといけない。
結婚後は、夫があらかじめ言っていた通り、朝は最寄り駅まで車で送ってくれたのでとてもありがたかったが、買い物も不便だし駅からも遠いし、坂だらけだし、車の免許も持っていなかったし、思うようにならないという気持ちが強かった。今思うと、適度に郊外に住む人の方が絶対多いのに、便利であることが身に着いてしまった私は、そんな風にしか考えられなかった。
あの頃、私はまだ若かった。
若いなりに、自分を取り巻く環境に思い切っていろいろと言い出せなかった。今なら図々しくも「これだけは譲れない!」と言えるのだろうけど。
もし今の自分があの時の自分に会ったとしたら、「絶対それは譲っちゃだめ!」って肩をゆさゆさと揺さぶって言ったに違いない。
そして近くに夫の実家があるというのも、良し悪しだなと思っていた。義父母は私たちのことを逐一聞いたり、こちらの生活にずかずかと入ってくるようなことはなかったが、平日私の帰りが遅くなった時などは実家で夕飯をいただくこともあった。休みの日などに用事で訪ねることや、一緒に買い物に出かけることもあった。一応別居はしているけど、気持ち的には半分同居のようなものだった。普段お世話になっているという負い目もあってか、何となく窮屈だなという気持ちを意識しないようにする癖がついていたように思う。
そんな日々が続いた、秋のことだった。
その日は、夕方から強い雨が降っていた。
傘を持たないで出勤した私は、帰宅するのに15分や20分歩いたらずぶ濡れになるし、どうしようと思っていた。最寄り駅は小さな駅なのでタクシーは入っていない。雨宿りをするファストフード店や喫茶店も全くない。
もし夫が家にいたら、駅まで迎えにきてもらえるかもしれない。まだ携帯電話というものが一般に普及する前のことだったので、最寄り駅の公衆電話から自宅に電話をした。自宅は誰も出なかった。夫はもしかしたら実家に寄っているのかもしれないと思い、実家のダイヤルを回した。
「もしもし、眞子ちゃん?」
電話に出たのは義母だった。
「もしもしお義母さん、もしかしてそちらに健さんお邪魔していませんか?」
「こっちにはいないわよ」
「わかりました。もしいたら駅まで車で来てもらえたらと思ってお電話したんですけど、そしたら歩いて帰りますね」
傘買って歩いていけばいいかな。そう思って電話をおしまいにしようと思った。
「ちょっと待って、今どこにいるの? 駅にいるんなら、私が途中まで歩いて行くから、傘持って行ってあげるわ」
「いやいやお義母さん、それは申し訳ないので大丈夫です。歩いて帰りますよ」
「ううん、いいのいいの、傘持って行くわね」
「大丈夫、1人で帰りますからー」
最後の言葉が終わらないうちに10円玉がなくなって、電話が切れてしまった。一応ちゃんと断ったし、雨結構降ってるし、来ないよねお義母さん。そう思いながら、私は家への道を歩き始めた。
最寄り駅から家へは、1本しか経路がない。
駅からの細い道を歩き終わって、見通しの良い国道に出た。左に曲がってしばらくすると信号があり、そこを渡ってさらに歩き始めた時だった。
「……まこちゃーん」
誰かに呼ばれた気がした。
「……まこちゃーん! ここよ!」
今、私が渡ってきた信号の向こうの方から、義母が私の名を呼んでいた。国道の反対側にいるらしい。
おかあさーん、来なくていいって言ったのに。
私、1人で帰れるのに。
ちゃんと断ったのに、迎えに来てしまった義母を横目で見てどうしようかと思ったけど、その時の私は何となく素直に寄り添えない気分だった。わかっていたけど、義母に気がつかないふりをした。それから何回か、義母は私の名前を呼んだけど、私はそれには答えず歩き続けた。距離も遠くて雨が強くて声がかき消されてしまったと思ったのか、そのまま義母は名前を呼ぶのはやめて、国道の反対側を私と平行に歩いて行った。
そのまま自宅近くまで歩いてきて、義母と出会った。私はそこで初めて義母が迎えに来てくれたことに気が付いたようなふりをした。
「あら、お義母さん、迎えに来てくれてたんですか? 雨の中、すみません」
本当はとっくに気が付いていたのに。
意地悪だなあ、私。
「何回か呼んだんだけど、通りの向こう側歩いてたから聞こえなかったのよね。お帰りなさい。雨降って疲れたでしょう。夕飯、よかったら食べてって」
「ありがとうございます。あとで伺います」
せっかく親切に迎えに来てくれていたのに、それを無視して、でもご飯はいただこうって、なんて都合のいい自分なんだ。そう思った。それでもそう言われて、1日たっぷり働いてきて、自分の分のご飯が用意されている魅力には勝てなかった。
「今日はね、料理教室で習ってきたものを作ってみたのよ」
のこのこと実家に行った裏表のある私に、義母は優しかった。
「あ、美味しそうですね」
それまでモヤモヤしっぱなしだったことなんて忘れて、私は食卓を見た。そこには、ドライカレーがあった。ひき肉、玉子、サラダ、ご飯、色とりどりのご飯が、ぱあっと華やかに用意されていた。
「初めて作ったからどうなのかしら。でも野菜もたっぷり摂れるし、見た目もいい感じでしょう?」
「見た目、本当に美味しそうですよね。いただきます」
いただいたドライカレーは、本当に美味しかった。それまで普通のカレーばかりで、ドライカレーを作ったことがなかった私は、ちょっと感動してしまった。
「これ、いいですね。よかったらレシピ教えてください」
「いいわよ、プリントがあるから、あとでメモしてね」
そんな会話があって、黙々とドライカレーを食べていると、何となく義母に対して申し訳ない気持ちになった。雨が突然降ってきて、息子もまだ帰宅してないからということで、困っているだろうと傘を2本持って歩いてきてくれた義母。それを気が付いていながら知らんぷりしてしまった自分。おまえは、呑気に夕飯をご馳走になれるとでも思うのか? 天からそんな声が降ってきたような気がした。
「ちょっとすみません、手を洗いに行ってきます」
その場にいたたまれなくなって、私は席を立った。何となく、泣きそうになっていたからだ。普通に夕飯を食べているのに突然泣き出したらおかしいから。
洗面所で少し涙を拭いて、考えた。
もし実家だったらあんなことは絶対にしないだろうし、もし自分の娘がそんなに底意地が悪かったら、親は思いっきり叱るに違いない。
お義母さん、ごめんなさい。もう2度と、そんなことはしないから。
あれから相当の月日が経った。
私たち夫婦に家を貸してくれた隣人は程なく帰国し、私も新卒で入った職場を退職して、転居もした。そのほか、色々な人生の転機があった。
義母とは離れて暮らしている。車で30分くらいの距離だ。まだ健在だけど、時々介護が必要だ。相変わらずよく気がついて、時には鬱陶しいと思うこともあるけど、あの時に、大事なことを教えてもらった気がする。
カレーが好きな私は、レパートリーもだいぶ増えた。何なら、毎日自宅でカレー屋さんやってもいいくらい、種類が作れるようになったと思う。
私はとびっきり辛いカレーが好きだけど、家族は辛すぎるカレーは苦手だ。全然味の好みが違うのに、何故だかあの日の義母のドライカレーを出すと、文句なくたいらげてくれる。簡単に手早く作れて、栄養バランスもよくて、おまけに美味しい。献立を考えるのが面倒な時は決まってドライカレーにしちゃうくらいだ。多分、一番多く作っているカレーがそれだ。
そして作るたびに、義母のことを思う。そのカレーこそが、私のカレーですと、胸を張って言おう。
□ライターズプロフィール
和辻眞子(わつじ まこ)(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
天狼院ライターズ倶楽部所属。
東京生まれ東京育ち。3度の飯より映画が好き。
フルタイム勤務、団体職員兼主婦業のかたわら、劇場鑑賞した映画は15年間で2500本。
パン作り歴17年、講師資格を持つ。2020年3月より天狼院ライターズ倶楽部に参加。
好きなことは、街歩き、お花見、お昼寝、80年代洋楽鑑賞、大都市、自由、寛容。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
★10月末まで10%OFF!【2022年12月開講】人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ《土曜コース》」