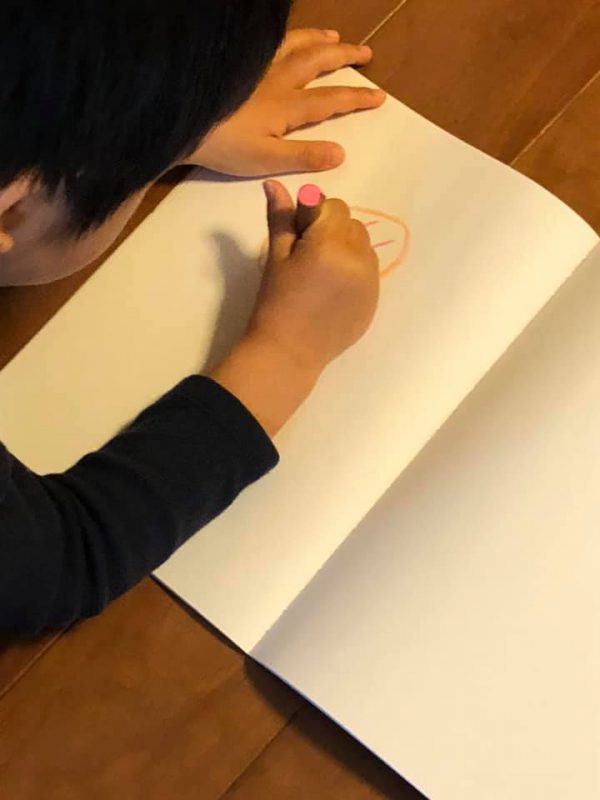無題のストーリー《週刊READING LIFE vol.119「無地のノート」》

2021/03/15/公開
記事:ユウスケ(READING LIFE編集部ライダーズ倶楽部)
※この物語はフィクションです。
きっかけは大学の友人が持って来たアルバイト誌だった。
「葵、バイト探してるって言ってたでしょう? はい、駅にあったフリーペーパー持ってきてあげたわよ」
私はその時、大学の講堂の一番後ろの席に座って、授業が始まるのを待っていた。隣に座っていた友人の茜が、フリーペーパーを差し出した。
「ありがとう」
バイトを探しているのは本当だった。前やっていた居酒屋のバイトは人間関係がうまくいかず、3か月で辞めてしまって、ちょうど次を探そうとしていたところだった。
間もなく授業が始まった。私は授業を聞いているふりをしながら、こっそりと机の下で茜が持ってきてくれたフリーペーパーを広げた。
世の中にはいろんな仕事があるんだな、とつくづく思う。塾講師、カフェスタッフ、書店員、引っ越し、などなど……。でも、なかなかこれだ、というのが見つからない。
パラパラとめくっていると、最後のページに、一枚のチラシが挟んであった。メモ用紙くらいの大きさの紙にこう書かれている。
『文字起こしの仕事。時給・勤務形態は面談時にご相談。お問い合わせは以下の番号まで。090―××××―○○○○』
シンプルなメモだった。裏には何も書かれていない。
「ねえ、茜、このメモ、ひょっとして、あなたが挟んだ?」
私は小声で、隣に座って授業を受けていた茜に聞いてみる。
「え? 何それ?」彼女はそう答えた。
しばらく私はその紙をしげしげと眺めた。心の奥の何かが、その紙に惹かれていた。
授業が終わると、私は講堂の外に出て、メモに書かれた番号に携帯で電話をかけた。スリーコール目で、相手が出た。
「あの、『文字起こしの仕事』のチラシを見て、お電話差し上げたのですが」少しうわずった声で私は言った。
電話口から聞こえたのは、女性の声だった。
「はい。お電話ありがとうございます。では、まずお名前を頂戴できますか?」
女性はいくつか事務的な質問をし、私はそれに答えた。面接は次の土曜の10時からに決まった。彼女は面接場所を告げ、私はメモを取り出し、その住所を書き留めた。
「では、当日、お待ちしております」
女性はそういうと、電話を切った。
指定されたのは、駒込のとある豪邸だった。六義園の裏の、閑静な住宅街にある和風の邸宅で、周囲を漆喰の壁で囲まれている。江戸時代の大名屋敷みたいな趣があった。
本当にここであっているのかしら? そう思いながら、私は大きな門の横にあるインターホンを押し、面接に来た旨を伝えた。間もなく門が開き、中から黒いワンピースを着た初老の女性が出てきた。
「お待ちしておりました。満島葵さま。どうぞ、中にお入りください」
それは電話口と同じ声だった。声色は柔らかい印象を受けたが、厳格な雰囲気がにじみ出ている。数年前にやっていたテレビドラマの家政婦みたいだ、と私は思った。
玄関を入り、長い縁側を通り、奥の間へ通された。そこは書院造の大きな部屋で、中央に木製のテーブルが置いてある。テーブルの奥には車いすに座った老婆がいた。
老婆の髪は真っ白で、スモックのような白い洋服を着ていて、首からはコハクのペンダントをぶら下げている。大きくて黒いサングラスをしていて、顔の表情が全く分からなかった。
「奥様、面談予定の満島葵さまをお連れしました」
さっきの家政婦がそう言った。
奥様と呼ばれた老婆はゆっくりと頷いた。
「ありがとう。山岡さん。後は私が話をするわ。下がっていいわよ」
そういうと、家政婦は一礼して、部屋から出ていった。
家政婦が部屋を出ていくと、老婆はこういった。
「まず、ごめんなさいね。サングラスをかけながらお話させていただいて。実は目に障害があって、外すことができないの。我慢して頂戴ね」
私はかまわないと答えた。
「さあ、まずはあなたのことが少し知りたいわ。自己紹介をしてもらえないかしら」
予期しておらず、うろたえたが、つっかえながらも私は少しずつ話をした。
実家が仙台で、高校まで地元の学校に通い、大学から東京に出てきたこと。今は私立大の文学部で勉強していること。あとは、高校時代に入っていた部活のこと(新聞部)、などなど。なんとも平凡な人生だな、と自分で話ながらそう思った。
けれども、老婆は時々相槌を打ちながら、非常に熱心に話を聞いていた。私はなんだか、自分が裸にされているような、そんな気恥しささえ覚えた。すべて話終わったところで、老婆はこう聞いた。
「文学を学んでいらっしゃるの? ご専攻は?」
「えっと、大学一年生で、専攻はまだ決まってません。でも英米文学について学びたいと思ってます」
「そう……シェークスピアとか、ディケンズとか、モームとか?」
「はい。そんな感じです」
「ちなみに、パソコンはできる? といっても、専門的なものではなくて、ブラインドタッチができればいいんだけど……」
「はい。問題なくできると思います」
私はそう答えた。高校の新聞部で原稿を書くときはパソコンを使っていたからだ。
「よかったわ。じゃあ、仕事となったら、いつ来られるかしら?」
平日は大学の講義が5時までだからそれ以降、土日と祝日はいつでも問題ない。私はそう答えた。
「そう。十分ね。ありがとう。じゃあ、あなたを採用します」
と老婆は言った。
「えっ! もういいんですか?」非常にあっけなかったので、私はついそう言ってしまった。
「ええ、十分よ。あなたのこと気に入ったわ。じゃあ、仕事を始める前に、少し私のことを話しておかないとね」
そして、彼女は話し始めた。
彼女はSというある有名な女流作家だった。顔を世間に公表していないものの、多分本が好きな人は誰でも彼女のことを知っている。どこの書店に行っても必ず彼女の本は置いてある。そんな作家だった。
世間には公表していないが、彼女は数年前から目が見えなくなっていた。けれども、まだまだ語りたいストーリーが頭の中にあり、手助けしてくれる人を探しているということだ。そのためにあのビラを用意し、駅のフリーペーパーの数冊にこそっと、挟んでおいたらしい。
「本当はいけないことかもしれないけど、家政婦の山岡がうまくやってくれたわ」
そして、私が応募してきて、(どこが気に入ったのかわからないが)私を採用したいということだった。
「で、私は、何をすればいいんでしょうか?」
「あなたには私が話すストーリーをパソコンで文字に起こしてほしい。もちろん必要な機器はこちらで用意するわ。週に何回か、この部屋に来て、私が話す物語を書きとってほしい。ただそれだけでいいの。さっきも話した通り、私は目に障害がある……だけど、頭の中にはまだまだストーリーがある。それをあなたに、形にしてもらいたいの」
彼女はそこまで言うと、一度言葉を切って深呼吸をした。
「どうかしら? 受けてくださる?」
あまりにも壮大な話に巻き込まれ、私はしばらく呆然としていた。
でも、すでに心の中では答えは決まっていた。
「やります! ぜひ、お手伝いさせてください」
気づいたら、私はそう言っていた。女流作家のSは口元をほころばせて、こういった。
「よかったわ。ありがとう……山岡さん、いらっしゃるー?」
そういうと、さっきの家政婦がまた部屋に入ってきた。
「山岡さん。この方、満島葵さんを雇おうと思います」
「かしこまりました、奥様」
そして、Sは私のほうを向くとこういった。
「じゃあ、細かいことは山岡から話をさせます。できればすぐ取り掛かりたいわ! 頭の中にストーリーがたっくさんあるの」
彼女は楽しそうにそう言った。
それから、私は山岡さんと、勤務について話し合った。私は月曜日と木曜日の夕方、それから、日曜日の午前中にSの邸宅に来て、『文字起こし』をすることになった。
そして、私は次の月曜日からは「仕事」をすることになった。
それから、毎週私は決められた時間にSの邸宅に行き、そこで彼女の物語の『文字起こし』をした。
私には新品のノートパソコンと、ボイスレコーダーが用意された。基本はパソコンで文字起こしをするのだが、もちろん取り落とす箇所が出てきてしまう。そのバックアップとしてボイスレコーダーを使うことになった。
「聞き取れない箇所をもう一度話していただくことは、だめなんですか?」
「だめなの。こういうのって、一度流れが止まると言葉が出なくなっちゃうものなの。だから、申し訳ないけど、聞き取れなかったところは後でレコーダーから拾ってくださる? あ、パソコンはあなたに差し上げるから、私用で使っていただいても問題ないわよ」
私は毎週S宅に行くと、パソコンと、ボイスレコーダーを起動して、彼女の物語を形にしていった。彼女は非常に明瞭に、ゆっくりとしたスピードで、物語を語っていった。Sが言った通り、彼女の頭の中にはストーリーがパンパンに詰まっているようで、淀みなく言葉が口からあふれ出た。私はその言葉をひたすらすくい上げていった。
基本的にSはどんなに長くても一時間半しか語らなかった。どうやらそれが彼女の集中力の限界らしい。どんなに物語が途中でも彼女は、ぷっつりと一時間半で作業を区切り、後は二人で、部屋でお茶をしたり、話をしたりした。
彼女との雑談も、彼女の作品に劣らず、とても面白かった。日常の観察力に優れ、ユーモアがある。私は彼女と仕事をし、交流を持つことで、どんどん彼女の世界に取り込まれていった。
実際、その日々は充実していた。私は、Sの家に行くのが待ちきれなくなっていて、終わると喜んで仕事を家に持って帰り、その日聞き漏らした箇所がないかどうかをボイスレコーダーでチェックしながら、Sのストーリーにどっぷりとはまっていった。
それは日曜日の午前中のことだった。Sはいつもの通り語りはじめた。
40分が過ぎ、それまでストーリーを語っていたSが急に中断した。
「ちょっと……待ってちょうだい」
私は最初、パソコンの画面に集中していて、Sの異変に気がつかなかった。私が顔をあげて、Sのほうを向いたときには、Sの顔は青ざめていて、額には脂汗がにじみ、頭を押さえていた。
私は大声で、山岡さんを呼んだ。私の叫び声を聞いてすぐに山岡さんは部屋の中に駆け込んできて、Sの様子を見る。そして、私に急いで救急を呼ぶように指示をした。救急車が来て、Sはすぐに病院へと運ばれた。
脳梗塞。それが彼女の病名だった。手術を行い、一命はとりとめたものの、彼女はそれから長い間、意識を失ったままだった。
語りかけのストーリーとともに、私は取り残された。しばらくは何も手に着かなかった。大学に通い、それが終わるといつもSの病院に行って、見舞いを続けた。
「ねえ、私はどうすればいいの? この物語を、どうすれば、いい?」
病院に行くたびに、私はSにそう問いかけた。でも、ベッドに眠ったままのSは私には何も語りかけてくれなかった。
「起き上がって、また私に、物語をつづけてよ……」
私は心の中で何度も何度も彼女にそう呼びかけた。
山岡さんが電話をかけてきたのは、ちょうど午後の授業の最中だった。私はこそっと携帯を見て、それが彼女からの着信だとわかると、周囲の目も気にせず、急いで講堂を出て、電話に出た。
「奥様が、意識を取り戻されたわ! 今からすぐ来られる?」
私は一度講堂に戻ると、鞄をひっつかみ、急いで外へと駆け出した。
病院についたとき、Sは相変わらずベッドに横たわったままだったが、目はうっすらと開いていた。
私は急いで駆け寄る。私のことがわかっているのか判断がつかないが、私の顔を覗き込み、何かを伝えようとしている。
私にはそれが“何か”分かった。物語だ。彼女の中の物語が、あふれ出ようとしてもがいている。でも、彼女はそれを口にすることができない。私は何とか必死に、それを聞き取ろうとするが、それは声にはならなかった。
しばらく彼女はもがいていたが、やがてふっと力を抜いた。
そして、何とか再び力を振り絞ってこう言った。
「続けて……そのまま……あなたが……形を……与えて」
医療機器の音がこだまし、すぐに看護師が駆け付けた。辺りが騒然となり、間もなく医者が現れた。
でも、もう遅かった。Sは亡くなった。
※※※※※※※※
Sの葬儀が終わって一週間後の夕方。
私の部屋の机には、あのパソコンが置かれている。その中には書きかけのストーリーが眠っている。
私はそれに直面したくなかった。私はそれを開けるのが怖かった。
でもそれが、私に与えられた役割だ。私はパソコンを立ち上げ、Sのストーリーのデータを開く。そして彼女が語らなかった、その先を手探りで進み始める。
既に私の頭の中にストーリーは出来上がっている。Sとの交流、対話によって、私の頭の中には“それ”が知らないうちに創り上げられていた。
私は注意深くそのストーリーを読み取る。以前、Sが語るストーリーをすくい上げたみたいに、ゆっくりと、一つずつ。
ボイスレコーダーは使えない。その物語の声は一時的なものであり、そこで拾えなかったら、もう二度と、形にすることはできない。だから速やかに言葉を拾い上げていかなくてはならない。私はとにかくストーリーを前へ前へと転がしていく。
その「声」が命ずるがままに、言葉をひたすらパソコンにタイプし、物語を形にする。
書きながら、私はSが近くにいることを感じる。私がいま紡いでいる物語を通して、私に語り掛けている。そんな気がする。
物語がどう進んで行くかはわからないけれど、Sが近くにいてくれる。
そこになんらかの安心感が存在する。
私はひたすら、その声をパソコンの画面にタイプした。
※※※※※※※
私は、その日夕方から作業を始め、気づいたときには翌日の朝になっていた。何かに乗っ取られたかのように、私はそのストーリーを創った。
それが終わるのを見届けると、私は疲れ果てて、ベッドに倒れこんで、長い長い眠りについた。それは深い眠りだった。夢を見たような気がしたが、内容は覚えていない。
ただ、夢の中で、Sが出てきて、私に満面の笑みで微笑みかけたような気がした。
こうして一つの物語が完成した。それに私は題名を付けていない。
これはSと私だけの、おそらく誰も見ることはない、二人だけの無地のノート。
今でもその原稿は私が大切に持っている。
□ライターズプロフィール
ユウスケ(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
愛知県生まれ。東京在住のサラリーマン(転勤族)。人生模索中。
山と小説と酒が好き。
この記事は、人生を変える天狼院「ライティング・ゼミ」の上級コース「ライターズ倶楽部」をご受講の方が書きました。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325
■天狼院書店「シアターカフェ天狼院」
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-1 WACCA池袋 4F
営業時間:
平日 11:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
電話:03−6812−1984