もし高校バスケの女子マネージャーが顧問の女教師に怒鳴り散らされたら《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》

記事:森野兎(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
「お前は何をやっとんるんじゃい!!!」
バスケットコートで足を滑らせ、選手が派手に転んだと同時に、顧問の怒鳴り声が体育館中に響き渡った。
怒鳴られたのは、転んだ選手ではなく、マネージャーであるわたしだった。
高校時代、わたしは男子バスケットボール部のマネージャーをしていた。
そう言うと、大概の人は、
「ハチミツレモンとか作ってたの? 甘酸っぱいね!」
「タオルとドリンクをプレイヤーに渡して、『頑張ってね!』みたいな? なんかモテそう!」
ひどい人だと、
「男子の部活でマネージャーする女子なんて、男目当てでしょ」
と言われたりする。
確かに入部する前、女子マネージャーには、少女漫画のような青春が詰まっていると期待していた。
「中学生の頃からその頭角を表し、強豪校の誘いを蹴って、名もない我が高校のバスケ部に入部した期待のエース」が同級生。
そんなエースが高校に入学し、初めてのスランプを経験する。
荒れるエース。
「やってらんねえよ、バスケ部なんて辞めたらあ」
そう啖呵を切った彼は、コートを飛び出す。
追いかけるマネージャー。
「待って! それでいいの? あなたが努力を積み重ねてエースになったこと、わたしは知っているよ。それなのに、一度の挫折で今までの努力を無駄にしていいの? 諦めたらそこで試合終了だよ?」
と某有名バスケ漫画の超有名セリフを、ナチュラルにパクって締め括り、エースを引き止める。
その言葉はなぜかエースの心に響き、彼はバスケコートに戻って一から頑張る決意をする。
そして自分を叱咤激励してくれたマネージャーへの恋心に気が付き、
「次の試合で勝ったら、付き合ってくれ」
と言ってシャカリキに練習を重ね、「わたしのためにここまで……」とマネージャーを感激させ、もはや勝たなくても付き合うだろ、みたいな展開になる。
というのはいき過ぎた妄想だが、まあそれなりに楽しい青春が待っていると思っていた。
違った。全っ然違った。
わたしが経験したマネージャーは、そんな浮わついた気持ちでやれるような、甘っちょろいものではなかった。
もともと、わたしが男子バスケ部のマネージャーになったのに、大した理由はなかった。
友達に誘われたからだ。
高校入学当初、少しずつ学校にも慣れてきて、ただ授業を受けて家に帰るのはつまらないなあ、そんな風に漠然と思っていた。
そんなとき友達から、
「男子バスケ部、マネージャーがいなくて、募集してるんだって。見学に行ってみない?」
と声をかけられた。
わたしは中学時代にバレーボール部に入っていたが、高校に女子バレーボール部はなかった。
女子のテニス部やバスケ部はあったが、わたしは当時、経験者に混じって初心者として新しい競技を始めることに抵抗があった。
でもマネージャーなら、経験がなくても大丈夫だろうし、部活に入らなかったら暇だし。
それくらいの想いで男子バスケットボール部の見学へ行き、部員たちの勧誘にまんまと乗せられ、入部した。
しかし待っていたのは、甘酸っぱくもほろ苦くもない、激辛な青春だった。
何十人もいる部員のスポーツドリンクを作る。
部員がぐちゃぐちゃに物を置いているベンチを綺麗に整理する。
ストレッチやアップで笛を吹いてサポートする。
などなど、マネージャーがする仕事としては、別に普通だった。
しかし、男子バスケットボール部には鬼がいた。
顧問である、40代の女教師だ。
顧問自身も学生時代はバスケ選手で、国体出場経験もあり、大学はバスケのスポーツ推薦で進学したという強者だった。体育の教師で、生活指導担当も兼ねる顧問は、学校を代表する「めちゃくちゃこわい先生」だった。
最初のストレッチが一通り終わった頃、顧問は登場する。
その瞬間から、緊張と恐怖でわたしの体はこわばる。
ベンチを一瞥し、
「テーピングは」
とわたしを睨み付ける。
ヤバい。倉庫からテーピングを出してくるのを忘れていた。
ダッシュでテーピングの入った救急箱を取りに行き、顧問に渡す。
救急箱を開けた顧問が、眉間に皺を寄せる。
「キネシオ足りひん。中身確認せえよ」
とわたしを睨み付ける。
キネシオとは、テーピングの一種だ。
ぬおお、2日前まであったのに、いつのまにそんなに減ったんだ。使ったやつ言ってくれよ。
しかし顧問に言い訳など通用しない。
そして練習が始まり、冒頭にあるように、選手がコートの上で足を滑らせ転んだ。
そのとき、顧問がマネージャーであるわたしを怒鳴ったのは、ぞうきんを用意していなかったからだ。
バスケットコートの端には、だいたい絞ったぞうきんが置いてある。これは、コートが滑りやすい時に、ぞうきんでシューズの裏を湿らせて、滑り止めにするためだ。コートが滑りやすいとケガに繋がるので、たかが塗れぞうきんも大事な役目を担っているのだ。
しかし入部した頃のわたしは、
選手が滑る→ぞうきんがない→絞ったぞうきんを用意する
ということも、なぜ自分が怒られたのかもわからず、オロオロするばかりだった。
ベンチにいた選手たちが絞ったぞうきんをすぐに持ってきたことで、自分がやるべきだったことを初めて理解した。
これはマネージャーの仕事として決まっていたわけではないのだが、選手が用意してなかったのなら、それに気が付いてマネージャーが用意しとかんかい、という怒りであった。
入部した年は、そんな日々の連続だった。
ことあるごとに、
「気が利かない」「ボーッとしている」「使えない」
と16歳の少女にしては、散々なことを言われた。
選手が怒られるのであれば、それは自分のプレーが悪いと思えるだろう。
しかしマネージャーが怒られるのは、人間性を否定された気分になった。
わたしは普段問題をおこすタイプではなく、勉強も運動も平均レベルで、それまで教師からまともに怒られたことがなかった。
しかしバスケ部のマネージャーになって、怒られるどころか、毎日のように怒鳴られるのだ。
わたしってそんなにできない人間だったの。ああ、つらい。
わたしをマネージャーに誘った友達は、鬼顧問に音を上げ、早々にバスケ部を辞めてしまった。
バスケ部にマネージャーがいなかった理由を理解した。
選手たちはわたしをとても気にかけてくれ、励ましたり、感謝したりしてくれた。
だがそんなことで相殺できないほどつらく、みじめだった。
それでも辞めなかったのは、もはや意地だった。
わたしは、マネージャーになることを父に大反対されていた。
男子部であることの心配もあっただろうし、「マネージャー」という縁の下の力持ちに、進んでなろうとする気持ちが理解出来なかったのだ。
「お前がそんなことをしなくてもいい」と言われ、それ以上は取り合ってくれなかった。
最初は軽い気持ちで「マネージャーになる」と言っていたわたしだったが、父に反対されればされるほど意地になり、絶対に引かなかった。
父の偏見めいた固定観念に、わたしの青春が奪われてなるものかという想いで、わたしはマネージャーになることを決心した。
父も頑固。その父に似て娘も頑固。
それがきっかけで、父とわたしは丸1年口を利かなかった。
だが反対されることは、エネルギーになったりするものだ。
あれだけ反対した父を押しきってマネージャーになったのに、簡単に「辞める」なんて言えない。いま辞めたら、わたしはただ嫌なことから逃げただけだ。父にも「それ見たことか」と言われるだろう。
わたしは自分の選択に責任を持ちたかった。
このつらい日々を全て乗り越えることで、自分の選択を肯定したかった。
鬼顧問のもとで、自分はちゃんとマネージャーをつとめられるかわからない。
でも辞めたら負けだ。そんなの悔しい。だから、やる。
それまで何かに打ち込んだことのなかったわたしは、ここで初めて、自分が負けず嫌いだったことに気が付いた。
入部した年は相当怒られたが、だんだんその回数は減り、1年経ったころには、怒られることはほぼ無くなっていた。
体育館に一歩入れば、必要なものは全て揃っているか、すぐ判断できるようになった。
バスケのルールもテーピングの巻き方も覚えた。
何十人もいる部員のタオルをニオイで誰のものか判断できるという、後生なにかに活かされることのない特技も身に付けた。
最後の方は、「むしろわたしに気が付かないものがあるとでも?」ぐらいのスタンスになっていた。
マネージャーとしても成長し、あの怒られまくった日々を乗り越えたことが、わたしの自信になっていたのだ。
新しいマネージャーも何人か入部してくれたが、顧問に耐えきれずみんな数ヶ月で辞めてしまった。
結局わたしは引退するまで、1人でマネージャーをやり遂げることになった。
引退試合のあと、鬼顧問から
「最後までありがとう。頼りにしてた」
と言われた。
シンプルな一言だったが、顧問がわたしへ伝えたい感謝も、信頼も、愛も、その一言につまっていた。
わたしは涙がとまらなかった。
社会人になって数年経つが、それを含めても、わたしのことをあんなに怒った人はいない。
いま会社の上司があのときの顧問のように怒鳴り散らしたら、「パワハラ」と言うことができるかもしれない。
しかしわたしは顧問の先生に、心から感謝している。
先生は一度だってわたしを「マネージャーだから」
という理由で手加減したことはなかったのだ。
「マネージャー」を選手と同じように考え、同じ熱量で叱り、同じ熱量で指導してくれた。
こんなに怒鳴られたマネージャーは中々いないだろうが、こんなに熱心に指導してもらえるマネージャーもいないだろう。
鬼顧問は、それまで教師の目にとまることのなかったわたしと、初めて真正面から向き合ってくれた先生でもあったのだ。
「あなたのターニングポイントはなんですか」
と聞かれれば、わたしはこの経験以外に思いつかない。
あの経験がなければ、いまのわたしはなかったし、なんとなくボーッと生きていただろうなと思うとおそろしい。
マネージャーをやってから、
「いまこの場に何が足りない? 何が必要?」
を自然にいつも意識するようになった。
それは仕事だけではなく、日常生活にも必要な視点だ。
例えば飲み会なんかで、
「◯◯さん、遅れてきたから一人だけおしぼりもらってない。店員さ~ん!」
みたいな場面にも活かされたりするのだ。
つらいこと、大変なことにぶつかったとき。
「嫌だから」という理由で逃げない人間になった。
まず、問題に向き合って最善を尽くす。話はそれから。
16歳のわたしにできて、今のわたしにできないことはないでしょう。
自分に自信がないくせに、根性だけは一丁前にあるのだ。
高校時代、バスケ部のマネージャーをやって、顧問に怒鳴り散らされたこと。
この経験は、わたしのターニングポイントであり、かけがえのない財産になった。
❏ライタープロフィール
森野兎(READINGLIFE編集部 ライターズ倶楽部)
普段はOL。2018年10月より、天狼院書店のライティングゼミに参加。
この記事は、天狼院書店の大人気講座・人生を変えるライティング教室「ライティング・ゼミ」を受講した方が書いたものです。ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。
http://tenro-in.com/zemi/70172
関連記事
-

その瞬間が、ターニングポイントになるかもしれない《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-
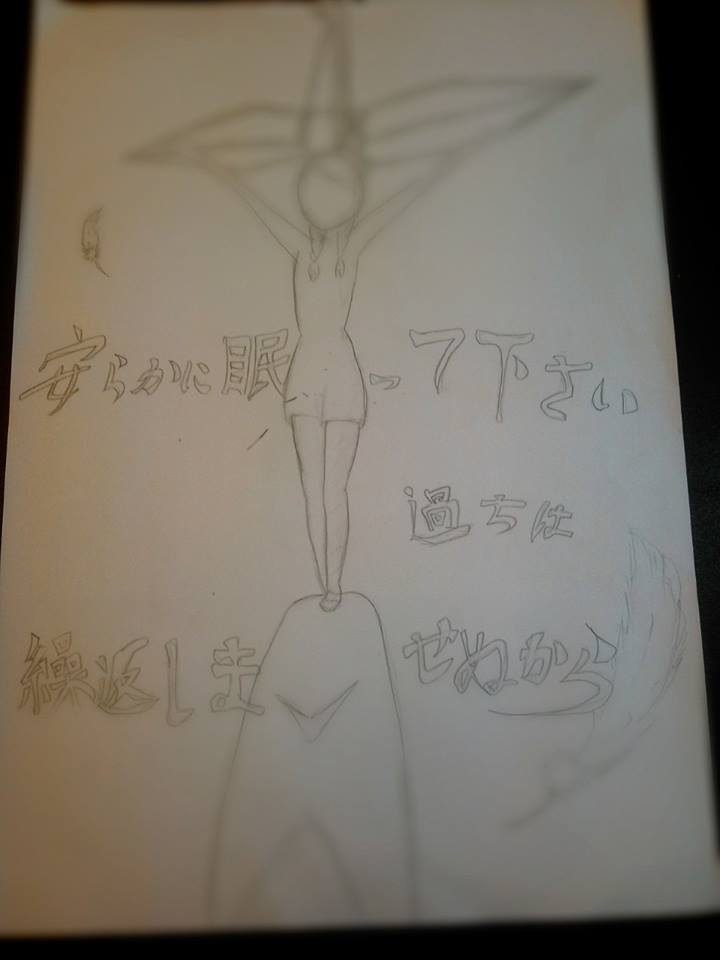
絶対反対を心に決めた時《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-

誰が為に鐘は鳴る!《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-

人生の転機は雨とともに突然やってきた《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》
-

転機は天真爛漫な笑顔とともに~5歳の少女が教えてくれた私の生きる意味~《週刊READING LIFE Vol.26「TURNING POINT〜人生の転機〜」》



