愛を繋ぐバトンが生んだ、ある奇跡の物語《週刊READING LIFE vol.134「2021年上半期ベスト本」》

2021/07/12/公開
記事:今村真緒(READING LIFE編集部公認ライター)
今年も早いもので、半分過ぎた。
6月に入ってからは、2021年上半期のヒットチャートやニュース、はたまたベスト○○ランキングなど、この半年間に話題となったものが次々と発表されていて、早くも振り返りの時期に来たのかと、過ぎゆく時のスピードに改めて驚いてしまう。
おまけに、今週のライターズ倶楽部のテーマが「2021年上半期ベスト本」と聞いて、少々戸惑った。話題になっている本のタイトルくらいは、何となく知っている。けれど、実際にその中で読んでみたものはごくわずか。数少ない中で、どれが私にとって「ベスト」だったか? うーん。勿論良かったと思うものもある。けれど、今年の上半期に「読んだ」ベスト本ということで言うならば、私は、瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』を推したいと思う。
この作品は、2019年の本屋大賞受賞作でもあることから、多くの方が知っているかも知れない。実際に私がこの本を知ったのも、本屋大賞受賞作と銘打ったポップに飾られて、書店の中で一際目立つ場所に陳列されていたからだった。表紙も、濃いグリーンのバックに、一瞬「こけし」のように見える、バトンらしきものに女の子の顔が乗っかっているスッキリとしたものだ。それに合わせたかのように、シンプルなフォントで書かれたタイトルが何とも素朴感を醸し出している。書店のポップと本屋大賞受賞作の帯が掛かっていなければ、見過ごしてしまったかもしれないと思う。
けれど、この本を手に取ったのは、話題作という理由からだけではなかった。少し前に、この作者である瀬尾まいこさんの『強運の持ち主』という作品を読んでいた。その読後感を、私は覚えていた。読んだ後に、じんわりとくる温かさ。そういったものを久々に感じた作品だった。あの作家さんの本ならば、また期待できるかもしれないと思った。それに裏返してみると、この文庫本の帯には「森宮優子、17歳。血の繋がらない親の間で何度も家庭環境が替わりながら、いつも慈愛に満ちた家族に囲まれていた―。」とあった。ちょうど、自分の娘と同じ年頃の女の子が主人公であることと、何度も家庭環境が替わったというシチュエーションに惹かれ購入してしまった。
ところが、いざ買ったものの、この本はしばらくウチの本棚に眠ったままになってしまった。なぜなら、他にも読んでいない本がたくさんあったからだ。順番に、という訳ではないが、ちょっと出番待ちのような状態で、他の本と一緒に重ねてしまっていた。さらに言い訳させてもらうと、本の帯にあったシチュエーションならば、覚悟してじっくりと読んだ方がいいと思ったのだ。
そう思ったのには、私の前職が関係していた。この手の話であれば、あのときに感じたことを、まざまざと思い出すのではないかと、少し怖かったというのが正直なところだ。私は以前、教育や子育てを支援する部署に勤務していたことがあった。だから、現在の子どもを取り巻くリアルな状況というものに、向き合わざるを得なかった。初めは、子どもに関わることができる仕事に喜びを感じていた。昔は、保育士や学校の先生になりたい時期があったくらいだ。ところが、現実の子どもたちの状況を知るにつれて、日々、心が軋むような思いが増えていった。
たまらなく、痛いのだ。
学校の給食と、心配する学校の先生からの差し入れで空腹を満たしている子や、母親の恋人が部屋に来るたびに、暗くなっていても追い出される子、親に厄介者扱いをされ一緒には住むことができない子など、自分ではどうすることもできない子どもに、しわ寄せが行く状況に居たたまれなかった。どうにかしたいと、いくらこちらが思っても、受け入れることを拒む親の心情に深い闇を感じた。親の都合や機嫌でいいように扱われながら、親を純粋に信じ切る子どもの眼差しが痛々しかった。
昔と比べれば、随分家族を取り巻く環境が変化したように思う。多様性という言葉が使われがちな昨今だが、家族環境もまた然りだ。親子関係も複雑で、何度も再婚を繰り返し、片方だけ血がつながっている兄弟が何人もいたり、お互いに連れ子がいる再婚同士というのも珍しくはない。
また、内縁の夫や妻といった方たちもたくさんいるし、パートナーがコロコロ変わるという人たちもいる。
そんな中で、子どもたちが変化に順応していくことは容易ではないと思う。今までとは異なった環境で、落ち着いて生活できるまでには時間がかかるだろう。新しく加わった人が、自分の居場所を脅かす人なのか、それとも安心できる人なのかを見極めなければならない。庇護される側の宿命として、自分を新しい環境に適用させなければならなくなる。本来ならば、条件なしで愛してもらえる存在のはずなのに、こうしなければならないと自らを押し殺す子どももいる。子どもには重すぎる荷を背負わせてもなお、それに気づかず自分本位に振る舞う親さえいる。
しかしながら、家庭環境が複雑だからといって、全てが上手くいかないわけではない。実際に、連れ子再婚した友人がいるが、やはり当初は悩みが多かったようだ。けれど、夫婦でぶつかり合い、お互いの子どもを尊重して本音で接していく姿は、傍から見ていて感心した。血は繋がっていなくても、本気で笑ったり泣いたりする友人を見ていると、実の親子であることが必ずしも親子関係の必須条件ではないと思わされた。もちろん、数々の困難や苦しみを乗り越えて、今の形にたどり着けたことだろう。
家族には、様々な形がある。一緒に暮らすのが、たとえ血の繋がらない他人であったとしても、そこに通い合う情の濃さがあれば、血の濃さを凌ぐものがあり得るのだ。だから、こうまで何度も「家族」という枠組みが替わりながらも、この本の主人公である優子が真っ直ぐに育っていくのは、リアルな現実を見てきた私にとっては、ある意味ファンタジーであり、救いでもあった。優子の健やかな逞しさとしなやかさを育んだ大人たちが、奇跡的に家族として居続けたことに感謝すら覚えるのだ。
愛情というものが、いかに子どもにとって必要な栄養素であるかが分かる。サボテンは話しかけるとよく育つという。植物ですらそうならば、人間であれば尚更だ。無垢な子どもは、良くも悪くも影響を受けやすい。それが身近な人からであれば、言うまでもないだろう。
前職のとき、言葉が出なくて困っているという母親が相談に来られたことがある。よくよく話を伺うと、どうも日常生活の中で、子どものお守りを自分以外にさせているようだった。母親にまとわりついてくる子どもに対して、忙しいからとスマホやタブレットに相手をさせる。機械は玉手箱のように次々と面白いものを繰り出すから、子どもは夢中になる。そして、母親は、子どもが集中して自分を煩わせることがない間、自らもスマホに熱中しているようなのだ。同じ場所にいても、互いに言葉を交わすことが少ないから、必然的にふれあいを学ぶ機会が失われていく。コミュニケーションの不足が、結果的に言葉が出ないことに繋がっているようだった。
実の親子であっても、同じ家の中で断絶が起こるのだ。むしろ、血が繋がっているということに甘えている部分もあるのではないか? 親子だから分かり合えるという幻想に、囚われ過ぎているのではないだろうか? 親子であっても、確たる絆を結ぶのは容易ではない。いくら実の親であっても、馬が合わないことはあるし、性格の違いを互いに受け入れられないことだってある。
だからこそ、主人公の優子を取り巻く「家族」は、稀有な存在だ。ひたすら、優子の幸せを願い、優子に寄り添おうと努力する。それが感じられるからこそ、優子も人に比べれば特殊な環境に育った自分を、「不幸せ」だと思ったことはないのだ。
もしも、家族という枠組みの中でそれが無理ならば、せめて親戚や、隣のおじさんでもおばさんでもいい。学校の先生でも、昔お世話になった保育園の先生でもいい。その子のことを気にかけてくれて、素の自分を見せても大丈夫だと思える大人がいてほしいと思う。温かな眼差しが自分に注がれていることを実感すれば、少しは孤独が薄れ、不安が軽くなるだろう。当時、私の心を締め付けた子どもたちが、あれからそんな人たちに出会えていたらいいなと思う。
私が幼かった頃は、よく近所のおじさんやおばさんが声を掛けてくれた。まだ、昭和の、隣人関係が割と密だった頃の話だ。偏屈なおじさんや、おしゃべりでお節介なおばさんたちなど、サザエさんの中に出てきそうな、キャラクターが際立った人たちが周りにいた。こうやって覚えているということは、それだけ関わることが多かったということでもあると思う。
悪さをすれば、おじさんに大声で怒られ、親が不在の時に蜂に刺されてしまったときは、近所のおばさんが手当をしてくれた。親に叱られて家から閉め出されたときには、心配した隣のおばさんが、とりなしてくれた。共通していたことは、本気で幼い子供だった私と向き合ってくれていたことだと思う。相手の熱はこちらに伝染し、心の中に灯るのだ。
優子とその成長を見守る「家族」の物語は、人との巡り合わせの素晴らしさを教えてくれる。優子の辿ってきた道と、それに寄り添う人々との絆が、目には見えなくとも鮮明に感じられる。物語は、特殊な環境である優子を、特別なものとして扱わない。憐れみや同情のような、ジメジメとしたものは感じられないのだ。それを可能にしているのが、やはり優子のしなやかさと、彼女を包み込む周りの大人たちだ。ラストには、小田和正さんの『言葉にできない』が、物語のエンディングテーマのように、自然と私の脳内に再生された。
家族という形の不安定さに翻弄されながらも、家族となった人達の愛情をしっかりと受け取った優子が、渡されたバトンを今度はどうやって繋いでいくのだろう? 未来に希望を感じさせる終わり方に、また温かな波がひたひたと、私の中に満ちてきた。まだの方には、ぜひ読んでもらいたい。傍らには、タオルかティッシュペーパーの準備をお忘れなく。きっと、優子と「家族」を繋ぐ奇跡の絆に、ほろりとさせられることだろう。
□ライターズプロフィール
今村真緒(READING LIFE編集部公認ライター)
福岡県出身。
自分の想いを表現できるようになりたいと思ったことがきっかけで、2020年5月から天狼院書店のライティング・ゼミ受講。更にライティング力向上を目指すため、2020年9月よりREADING LIFE編集部ライターズ倶楽部参加。
興味のあることは、人間観察、ドキュメンタリー番組やクイズ番組を観ること。
人の心に寄り添えるような文章を書けるようになることが目標。
人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325
■天狼院書店「シアターカフェ天狼院」
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-1 WACCA池袋 4F
営業時間:
平日 11:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
電話:03−6812−1984
関連記事
-

「いい娘」「いい家族」のカタチにハマらないように《週刊READING LIFE vol.134「2021年上半期ベスト本」》
-

苦しみや悲しみを味わうのは覚醒への通過点《週刊READING LIFE vol.134「2021年上半期ベスト本」》
-

東京という地元に縛られる貴族たち《週刊READING LIFE vol.134「2021年上半期ベスト本」》
-
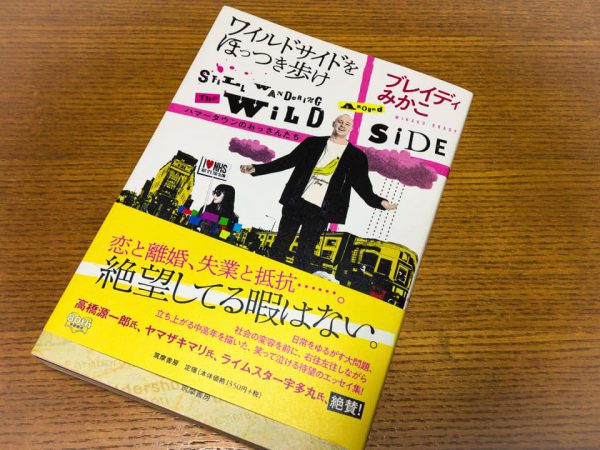
悪あがきの、どこが悪いの?《週刊READING LIFE vol.134「2021年上半期ベスト本」》
-
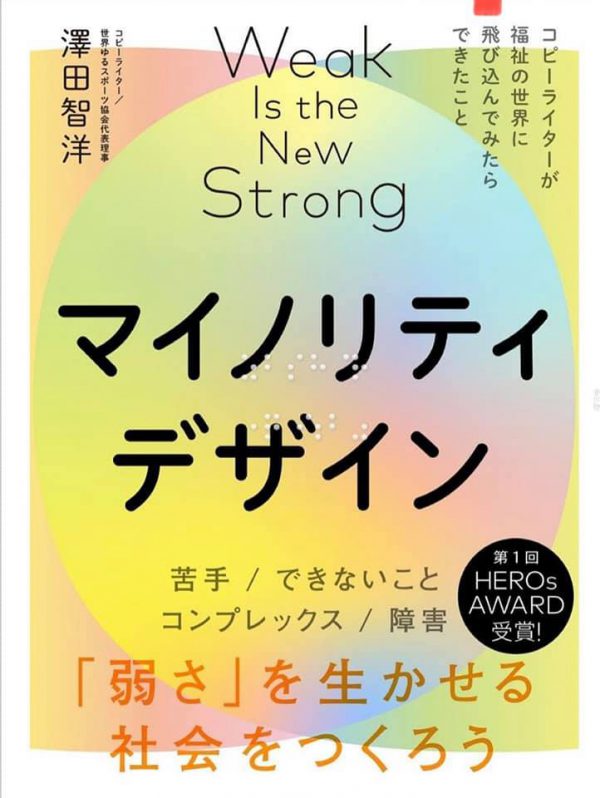
今こんな時だからこそこの本を推します、“弱さを活かす! ”「マイノリティデザイン」《週刊READING LIFE vol.134「2021年上半期ベスト本」》



