ボナペティ ~さぁ、召し上がれ~《週刊READING LIFE vol.142「たまにはいいよね、こういうのも」》

2021/09/06/公開
記事:月之まゆみ(READING LIFE編集部ライターズ倶楽部)
心ひそかに長年、かなえたかった夢があった。
それは年齢を重ねてこそ、試みたかったこと。
伝統あるレストランを訪れることだった。
若い頃、そこへ行くことは大人の証だと聞かされてきた店が、時代とともに様変わりしていく。失われていく手の込んだ料理の技術は、21世紀に入ってから手ごろでよりコストパフォーマンスの良いものと置きかわり、伝統的な店は一つ一つ静かに店を閉じる時代にはいった。
パリという街が一番、面白く感じられる年齢にさしかかった頃、私は思い切って名店と呼ばれる店に足を踏み入れることにした。
時間をかけて調べて選んだ店は18世紀から続く老舗で、現在はミシュランの二つ星も獲得したパレ・ロワイアルにあるフレンチレストランだ。
私と夫は受付で予約名を名乗る。
受付の女性が大きな予約台帳で名前を確認し「お待ちしておりました」と笑顔で迎えると給仕頭のメーテルがすべるように現れた。
彼の後について店内に入ると先に食事をしていた正装の客達が私たちを一目見て、もとの会話に戻っていく。
何度も想定していたシーンだ。
華やかさな新古典主義の内装の大広間を縫うように横切ると黒いタキシードを着た
スキのない身なりのギャルソン(給仕係)が次々と私たちに笑顔で「ボン・ソワール(こんばんは)」と声をかけてきた。
二つほど部屋を通りぬけて奥の落ち着いた窓際の席へ案内された。
テーブルにつく期待感がマックスになる瞬間。
4か月も前から予約していた席は女性像のフレスコ画な華やかな部屋で、黄金色の装飾は19世紀当時のままだ。
隣の席にはすでに先客がいた。こってりとした油絵のなかに、現代美術のコラージュが混じったような少し風変わりな印象のカップルだった。
アメリカ人だとすぐにわかった。
40代の男性はあふれる自信と成功者としての強いオーラを発して、隣にいる美しいフランス人女性の腰に手をまわし、ワインを飲みながら愛を語っていた。
いかにもパリらしい光景だった。
ただ一点の違和感は、男性が白いシャツにジーンズ姿で室内でもカウボーイハットを被っていたことだ。もちろんここまで格式のある店には言わずと知れたドレスコードがあり、子供は入店できず、男女は基本、正装である。
グルメガイドをみて世界からやってくる観光客も多いので、略式でも男性はジャケットにネクタイ着用、女性は華のあるスマートエレガントの装いが主流だ。
なぜならこういう場所のディナーは、奇跡の料理を中心に従業員もゲストも総出で雰囲気をつくりあげる文化があるからだ。
全員が素晴らしいディナーを忘れえぬ完璧な思い出とするために、一定の秩序をもって流れるように食事が進む。
近頃では由緒ある店も、カジュアルな時代の潮流を受けてドレスコードもなくなりつつあるが、その店は、時代に迎合する風潮を超越した伝統のとりでをもって店の雰囲気を守っていた。
にもかかわらずカウボーイハットのアメリカ人がまるでバーでふるまうように地元の女性を口説いている。カウボーイと目が合うと向こうから「ボン・ソワール(こんばんは)」と会釈してきた。
勢いのある自由さからおそらく投資家かIT企業、もしくは新興産業の経営者といったところだろう。
さて私たちもテーブルにつき、役者はそろい一夜の芝居が幕をあけた。
アペリティフを頼み、しばらく店内の様子を見わたしながら、食器の触れあう音や談笑の声に耳を傾け、呼吸を店に合わす。
若い頃、ヨーロッパを旅していた時は、時間があればすこしでも多くの見聞を広めたかった。食費を削っても「視る」経験を増やしたかった。物価も高かったので食事など空腹を満たせばそれで充分だった。
しかしフランスの友人たちは、有名店の前を通る機会があるたびに自国の食文化は世界で最高峰だと誇らしげに教えてくれた。
そして「あなたがいつか成熟したら、美食を体験するために必ず訪れて欲しい」そう目を輝かせて何度も繰り返した。
そう……。私は成熟した自分として店を訪れ、店内を流れる風景の一部になりたかったのだ。そうなるためには長い時を待つ必要があった。自分のストーリーを作るために。
席につくとソムリエが挨拶をして分厚い辞書のようなワインリストをわたされる。
まずは最初の難関である。
美しい筆記体でブルゴーニュ・ボルドー・ロワールの産地の赤・白のワインが何百とならんでいる。価格も一流から天井知らずの超一流までそろう。
ソムリエがお手伝いしましょうかと声をかけてくるが、料理より高くつくのがワインの恐ろしさだ。
私は過去のワインの失敗を踏まえて、ソムリエの甘い誘惑をおしのけて、シャンパーニュで通すことにする。シャンパーニュはどの料理にもあうし価格も扱いやすい。
隣席のカウボーイ紳士はすでに2本目の赤ワインを抜栓したところだ。
店のホームページに紹介されていたシェフのお任せコースを予約したようだった。
品数も料金に見合うほど多く、よほどの食通でないと食べられない量だ。
しかしながら隣を心配している場合ではない。
第二の難関、これまた分厚いメニューから自分たちの料理を決めなければならない。
フランス語は読めないので英語のメニューを開く。
もちろんメニューに挿絵や写真などなく、一品ごとに食材と料理法とソースが2~3行にわたって解説されている。
説明を一つ読み終わるころには、最初の食材が何だったのかわからなくなってしまう上に、女性のメニューには値段の表記がないので、ここは打合せ通り、家族の協力を頼りに予算内に料理を組み立てていく。
まさに真剣勝負だ。失敗など許されない。
料理をすすめるメーテルはささやくように誘うように、身振り手振りを交えてそれぞれの料理の特徴を教えてくれる。その声はエレガントかつ、この上なく料理を愛しんでおり、耳元で口説かれるような甘い声は、いつまでも繰り返し聞いていたいと思う。
鳩の料理法が愛の詩に聞こえたのは初めての経験だ。
経験を重ねたプロの給仕として客の好みをひきだす自信に余裕さえ感じる。
洗練した技巧でつくられた一皿に、ギャルソンの優雅な所作と言葉が魔法のスパイスと
なって特別な世界観をつくっていた。
ふと、その人そのものが魅力を放っていては給仕もずいぶん減ったなと思う。
やっと料理が決まったところで、さてお隣は3本目のワインに突入し、酔いも手伝って絶好調になったところで、私たちは互いの健闘をたたえてグラスをかかげる。
家族と会話を楽しみ、料理を堪能しているとくつろいだ雰囲気になってきた。
一方、隣の席は王族のように次々と料理が運ばれる。肉料理も二品続いたあたりでカウボーイ紳士の勢いが失速しはじめた。
ギャルソン(給仕)が下がると、同伴の女性にこのコース料理はいったいいつまで続くんだとこっそり聞いていた。女性がクスクスとしのび笑う。
最近はやりの軽いフレンチではなく、伝統的なメインの鳩料理のボリュームは十分な満足感で私たちの胃を満たした。
食事のクライマックスも超えて後は下降線をたどるのみ。後はカフェを流し込んで退散するつもりだった。
ところが……。
ここからフランス料理の底力、本当のフレンチ料理の圧倒的なグルメぶりを目の当たりにすることになる。
満腹さはある種の拷問だ。特に気のはる店だと苦行に等しい。早く退散して体を締め付ける靴も服を脱ぎすてて、楽な格好に着替えてすぐにでも横になりたい。
人間は贅沢な生き物だ。刺激がないと刺激を求め、刺激に飽きると今度はリラックスを求めてしまう。
しかし歴史に裏打ちされた店の持久力は容赦なく、私たちをテーブルから離れることを許さなかった。
私たちが断ったフランス産チーズをのせた美しいワゴンが貴族の食卓さながらに隣の席を襲撃する。
20種はあろうチーズの名前を、ギャルソンは立て板に水のごとくなめらかに説明した後、
一拍おいてカウボーイ紳士に注文をうながす。彼の眼の輝きは消え、酔いと満腹でにごりはじめている。
「それとそれ」 彼は体裁程度にチーズを指さした。
「ムッシュ、たったそれだけですか? フランス中の選りすぐりのフロマージュ(チーズ)ですよ。もっとおためしください」と譲らない。
仕方なくまた選びなおすカウボーイ紳士。ここからが本領発揮の連れの女性は全く動じない様子で好みのチーズを複数えらんだ。
店をあげての軽い客いじりが始まっていた。
「アメリカでもこんな量のチーズは食べたことはないよ。一生分のチーズを今日、見たよ」
そう小声で嘆くカウボーイ紳士を尻目に、私たちはもう終わり、そう言いかけた時、
メートルがパティシェ(菓子職人)を連れて私たちのテーブルに現れた。
「ぜひ当店のデサール(デザート)をお試しください。マダム」
「いいえ、私たちはもうお腹一杯。とてもデザートまで食べられないので……」
「マダム、せっかく日本からいらしたのでしょう。私たちが日本に行くことはできない。 私たちのデセールは驚きと高い芸術性に満ちています。きっと満足されると思います。ぜひご賞味ください」
またしても甘く切ない懇願の声に打ち負かされて、名物のデザートを食すこととなった。
しばらくすると素晴らしい造形にデコレーションされたデザートがテーブルの中央に置かれる。
今度は隣のカップルが私たちの行く先を固唾をのんで見守る。
クローシュ(銀のふた)が取り払われると中からは、四角形の大きなチョコレートの塊が現れた。小さな銀のかなづちで角をたたくとチョコレートの壁がくずれて、なかからラズベリーとバラ色の温かいソースがなだれ落ちて皿一杯に甘い香りがひろがる。
華やかな演出に周りから感嘆の声がおこるが、私は恐怖の奈落につきおとされた。
雪崩のようにトロトロとあふれ出るフォンダンの量をみて主人とただ青ざめた。
「ワラ・ポナペティ(さぁ、召し上がれ)」
そういって満足気にさっていくギャルソン。
大丈夫? と苦笑いする隣のカップルをよそに私たちは淡々とデザートを口に運ぶ。
食べたことのない繊細で複雑な味わいにはただ感服するばかりの貴重な経験だが、とにかくデザートは喉がつまる。温かい飲み物が欲しい。
メートルが満面の笑みで話しかけてくる。
「いかがですか、最高でしょう!」
「まるでマリー・アントワネットになったような気分」
「……マダムは愉快なことをおっしゃいますな」
HaHaHa。 Ah、Ha、Ha 周囲が笑いで包まれる。
「ところでコーヒーをそろそろだしてもらえませんか」と主人
「Non(いいえ) Caféは最後です」そう容赦なくいってのけ、メートルは隣のテーブルの食事具合を偵察にいく。
「ムッシュ、チーズを少しも召し上がっていないではありませんか」
たしなめられて子供のようにうなだれるカウボーイ紳士に、入店した時の勢いはもうどこにもなかった。
私たち外国人チームとフレンチ伝統料理の持久戦の対決になっていたが、満腹すぎて戦意も喪失していた。とにかく逃げたい。
今やグルマン(食通)の店から彼らの機嫌を損なわず、無事脱出することが最大のミッションだ。
とうとうカウボーイ紳士もデザートはいらないのでコーヒーを出してほしいと頼み込む。
彼は何度も「Please!」と両手を合わせて頼みこんだ。私はあんなに懇願するアメリカ人を人生で初めて見た。しかしギャルソンは「Non」とはねつける。
名店のしきたりはしきたりなのだ。
もはや泣きそうな顔でカウボーイ紳士が私たちに訴えかけてくる。
「フランス人は変じゃないかい。食事中にコーヒーを飲ませないなんて。もう何も喉を通らないよ」
その切実な声に私たちも深くうなずいた。
その時、私たちの間を割ってはいるように大きなケーキを中央に色とりどりのケーキを乗せた花籠のようなワゴンをギャルソン2人が運んできた。そしてケーキの説明を始める。
「あのぉ、頼んでいないのですが……」
私のけげんな問いにかけに顔色を変えずメートルは返した。
「先ほど、マダムはマリー・アントワネットのようだとおっしゃられた。フランス王妃のマリー・アントワネットは、このワゴンいっぱいのデセールをお召し上がりになりました。そこでマダムには先ほどのデセールでは足りないかと思い、お持ちいたしました。さて次はいかがしましょう?」
「ごめんなさい。参りました……」
私たちの完全降伏だ。
贅沢で優雅なすばらしい夜だったが、それにもましてウィットのある大人の会話を楽しめた夜だった。
ともに戦った戦友のカウボーイ紳士と別れを惜しみながら、私たちが一足先に席を立つ。
世の中には実際に飛び込んでみないとわからないスケールや深さをもつ文化が数多く
存在する。
どんなに事前勉強やリサーチしても本番はその予測を裏切ってアドリブで切り抜けぬけな
ければならないコミュニケーションがある。
私たちの一夜も、皆と楽しみや驚きを分かちあい、食事を通してそれぞれの物語を創った。
料理の味はいつか忘れてしまうが、そこで共有した物語はいつまでも記憶から消えること
はない。
店の外まで見送られながら、受付の女性にいかがでしたでしょうか? と聞かれた。
「映画のDolce Vita(甘い生活)のような夜だった」
そう答えると、メートルは「まさしく」と笑った。
「私共はそれを長きにわたって、伝統として続けております」と言い添えた。
食文化は刻々と時代にそって変化をとげる。どんなに技巧や贅をこらしても、形に残らないはかなさが料理の性質だ。
残らないはかないものだ。
それでもさまざまな時代を生きぬいた店には、その店を存在させ続ける魂のようなものが
宿る。
そんな存在に触れたくて、少し背伸びをしてもたまには伝統という重き扉を押して、その
向こう側にある世界を楽しむ冒険をおかしたいと思う。
□ライターズプロフィール
月之まゆみ(READING LIFE編集部 ライターズ倶楽部)
大阪府生まれ。公共事業のプログラマーから人材サービス業界へ転職。外資系派遣会社にて業務委託の新規立ち上げ・構築・マネージメントを十数社担当し、大阪地場の派遣会社にて現在、新規事業の企画戦略に携わる。2021年 ライティング・ゼミに参加。書き、伝える楽しさを学ぶ。
ライフワークの趣味として世界旅行など。1980年代~現在まで、69カ国訪問歴あり。
旅を通じてえた学びや心をゆさぶる感動を伝えたい。
お問い合わせ
■メールでのお問い合わせ:お問い合せフォーム
■各店舗へのお問い合わせ
*天狼院公式Facebookページでは様々な情報を配信しております。下のボックス内で「いいね!」をしていただくだけでイベント情報や記事更新の情報、Facebookページオリジナルコンテンツがご覧いただけるようになります。
■天狼院書店「東京天狼院」
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-24-16 2F
TEL:03-6914-3618/FAX:03-6914-0168
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
*定休日:木曜日(イベント時臨時営業)
■天狼院書店「福岡天狼院」
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-9-12 ハイツ三笠2階
TEL:092-518-7435/FAX:092-518-4149
営業時間:
平日 12:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
■天狼院書店「京都天狼院」
〒605-0805 京都府京都市東山区博多町112-5
TEL:075-708-3930/FAX:075-708-3931
営業時間:10:00〜22:00
■天狼院書店「Esola池袋店 STYLE for Biz」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋2F
営業時間:10:30〜21:30
TEL:03-6914-0167/FAX:03-6914-0168
■天狼院書店「プレイアトレ土浦店」
〒300-0035 茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦2F
営業時間:9:00~22:00
TEL:029-897-3325
■天狼院書店「シアターカフェ天狼院」
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目8-1 WACCA池袋 4F
営業時間:
平日 11:00〜22:00/土日祝 10:00〜22:00
電話:03−6812−1984
関連記事
-

疲れた時には「アレ」を頼ろう!《週刊READING LIFE vol.142「たまにはいいよね、こういうのも」》
-

旅の迷子はスリリング《週刊READING LIFE vol.142「たまにはいいよね、こういうのも」》
-
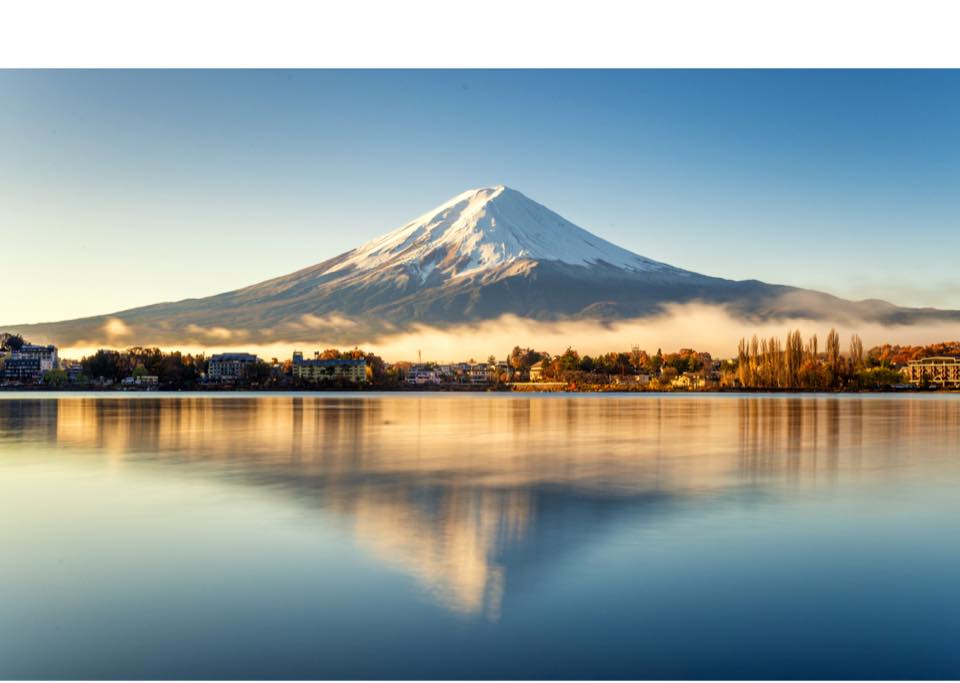
56歳の難病サバイバーおばちゃんが抱く荒唐無稽、抱腹絶倒な夢《週刊READING LIFE vol.142「たまにはいいよね、こういうのも」》
-

ただの不動産好きなおばさんが、日本の空き家問題や地方経済を論じてみた件《週刊READING LIFE vol.142「たまにはいいよね、こういうのも」》
-
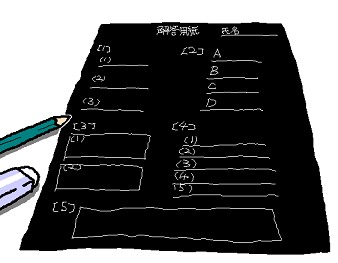
記事が黒く為るには訳が在る《週刊READING LIFE vol.142「たまにはいいよね、こういうのも」》



