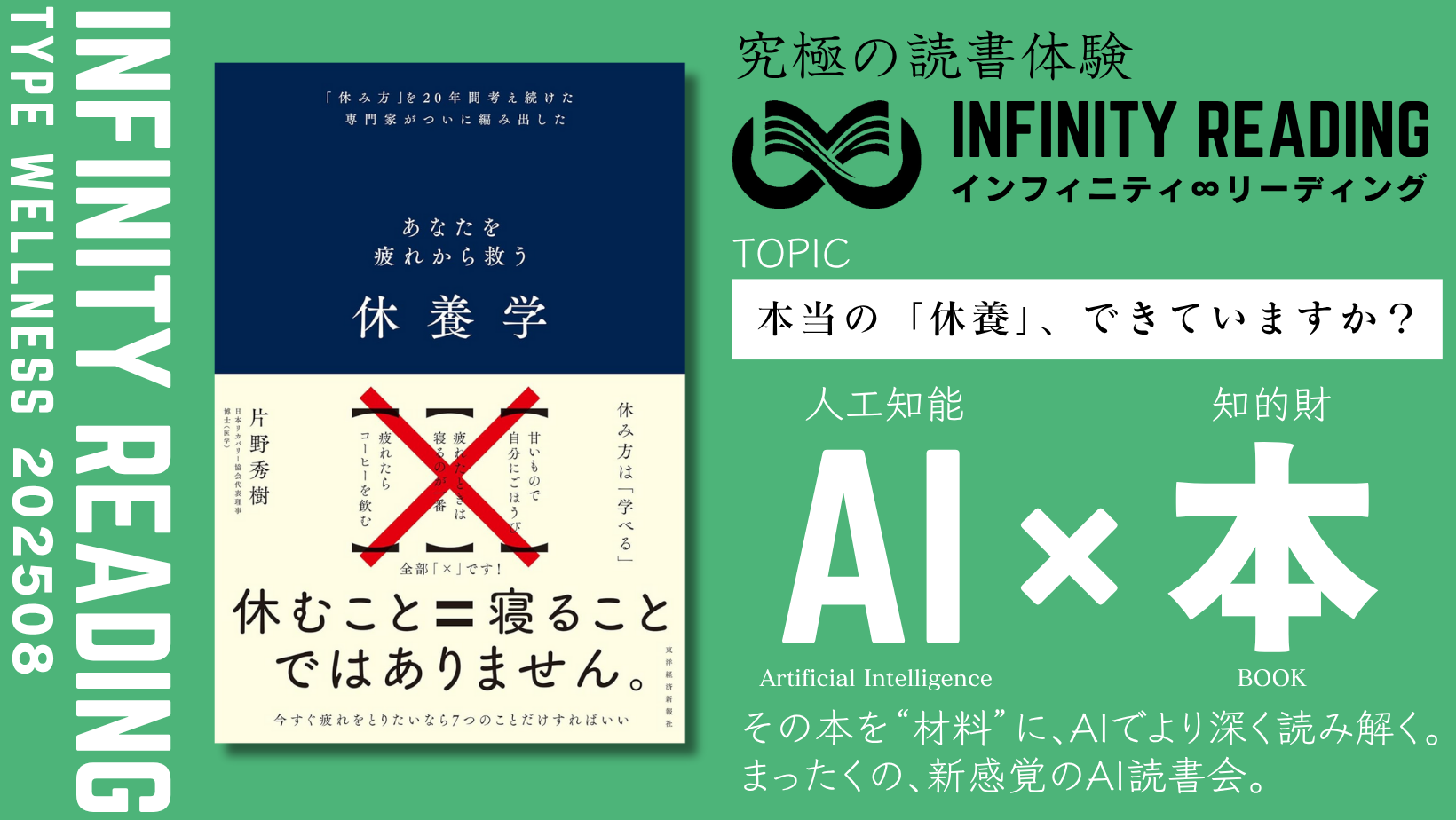【京都天狼院物語〜あなたの心に効く一冊〜】第六話 トラウマを消し去りたいあなたへ 中編≪もえりの心スケッチ手帳≫

文:鈴木萌里(京都天狼院スタッフ)
これまでの人生で、今日この日ほど恥ずかしく、情けない思いをしたことはない。
私は泣いていた。
一人暮らしの部屋の隅っこでも、掛け布団の中でも、公共トイレの中でもない。
京都天狼院書店で店番をしている最中だ。
原因はかつて応募した小説の審査委員長をしていた杉崎という男に、「また小説を書いてほしい」と言われたこと。
なんでそれだけでこんな事態に陥ってしまったのか、私が一番知りたかった。
とにかく、このまま醜い姿を晒しているのはまずいと思って、咄嗟に厨房の奥へ行き、ティッシュやハンカチで顔を拭う。
でもやっぱり、止まらなかった。
涙だけじゃない。心臓がドクドクとけたたましく脈打っていること。はっきりと分かるぐらい、頭に血がのぼり熱くなっていること。それらが全部止まらなくて、「すみませーん」とレジカウンターの前で本を手にしてお客さんに対応することすらできない。
「あのー、すみません」
厨房の奥に引っ込んだままの私を呼ぶお客さんの声が、だんだんと呆れたような声色に変わってゆく。
いけない、お客様を待たせては。ちゃんと接客しなきゃ。
と思えば思うほど、逆に落ち着くことができなくて、焦っている自分がいた。
涙は出るわ、焦燥感に駆られるわで結局うまく立ち回れない私。
どうしよう、本当に。
誰か助けて。
そう必死に神様に言い聞かせたのが通じたのか、タイミングよく現れたのは、写真のイベントを終えて二階から降りてきた女将ナツさんだった。
「お待たせして申し訳ございません」
ナツさんはさっとレジに入り、待っていたお客さんのお会計をさっさと済ませてしまった。
幸い、京都天狼院書店を訪れるお客さんは皆優しくて、ちょっとやそっとのことではお怒りにならない。でもだからと言って、忙しいわけでもないのに、お客さんを待たせて良いわけではなかった。
そのぐらいのことは、私自身、重々承知していた。
だからきっとナツさんも、私が承知していることを分かっていたのは間違いない。
「もえちゃん、ちょっと二階上がってようか」
あまりにもひどい私の姿や接客に呆れさせてしまっただろうか。ナツさんは私に一時休憩に入るように言った。
「はい……」
なんだか前にも、こんなことがあった気がする。
高校生の宮脇沙子という女の子がお客さんとしてやって来た日だ。
私の不手際のせいで、彼女を怒らせてしまった。
その日は一時退避はなかったけれど、「もういいよ」と言われた時は、もうここで働かなくていいよ、という意味だと思って覚悟したものだ。
だがその時は、私の予想とは裏腹に、ナツさんがくれたのは「闘わなくていい」という救済の言葉だったのだ。
しかし今日は分からない。今日こそもう、ダメかもしれない。
そんな、嫌な予感と闘いつつ、私は休憩と称して二階の事務所に閉じこもった。
そこでどれくらい時間が過ぎたんだろう。
私は、規定の一時間休憩どころか、その後のシフトの時間中ずっと事務室に引きこもったままだった。本当はこんなことではいけない。きちんとシフトに入らないと、ナツさんにも迷惑がかかるし、自分自身情けないと分かっていたから、一階に降りて仕事に戻りたかったのだけれど。
事務室に閉じこもって一時間が経つ頃に、ナツさんが事務室のドアを開け、ホットティーを持ってきてくれたのだ。
「心が悲しい時は、温かい紅茶が効くんだって、昔から決まってるの」
ナツさんがたった一言そう告げて、私にそっとくれたホットティーを飲むうちに、私はまたとめどなく流れてくる涙を抑えられなくなってしまった。
「すみませんっ……ありがとうございます……」
悲しいことは一つもないはずなのに、今日は余計に泣いてしまう日だ。ゴシゴシと服の袖で顔を拭いながら、一口ずつ紅茶をまた口に含む。
「それ飲み終わっても、今日は休んで良いよ。また別の日に入ってほしい」
彼女にそう言われなくとも、もう二度も泣いてしまった私は、今日これ以上笑顔で接客できる自信がなかった。だからナツさんの気遣いを、今はありがたく頂戴する。
今度はきっとお返ししよう、と心に決めて。
私が再び事務室から顔を出したのは、それからさらに二時間が経過し、祇園の路地裏が真っ暗になる時間帯だった。午後10時半。京都天狼院書店は毎日夜の10時に閉まる。そこからちょうど30分経って、女将のナツさんが事務作業を終えて二階に戻ってきたところだった。
「お疲れ様です」
ナツさんが階段を登ってくる足音を聞いて、私は即座に事務室から飛び出した。一刻も早くお詫びしたい気持ちでいっぱいだったから。
「あ、もえちゃんお疲れさま。もう大丈夫?」
「はい、おかげさまで、気持ちもだいぶよくなりました。今日はご迷惑おかけして……、ほんっっとうに、申し訳ありませんでした!」
人の誠意って、どうやったら上手く伝わるんだろうかと思う時がある。誰かに謝りたい時、感謝したい時、一番ストレートに気持ちを伝えられる方法を、いつも探していた。考えて考えた結果結局たどり着く答えは、「素直に気持ちを言葉にする」ことでしかなかった。
「いや、いいよ。終わったことだし。それより、ねえ、こっち来て」
ナツさんはやんわりと私の謝罪を受け入れてくれ、それから二階の奥のカウンター席を、トントンと指で鳴らした。
「え?」
私は、なんだろうと訝しがりながらナツさんに言われた通り、カウンター席の椅子を引いて腰を下ろした。
そういえばここは、以前宮脇沙子が『かがみの孤城』を読んでいる間、座っていた席だ。
「今日あったことを、話してほしくて」
ナツさんはそう言いながら私の隣の席に座る。階段に近い向かい合わせのテーブル席ではなく、わざわざ遠くのカウンター席を選んだのは、正面で話すより隣に座って話す方が話しやすいと配慮してくれたからかもしれない。
カウンター席に座ると、その時だけ、“京都天狼院書店のスタッフ”ではなく、ただの女子大生の自分に戻れる。ありのままの私を見せてくれと、ナツさんの瞳がそう訴えている。
私はひどく迷った。もしナツさんに今日の出来事を話すとすればそれはもう、私の悩みの全てを打ち明けることに等しいと考えたからだ。
でもそれ以上に、この時の自分は「誰かに話を聞いてほしい」という気持ちがあった。
きっと、昼間は観光客で賑わっている祇園の街がそうさせているんだ。夜になり、どこか異国の森の中へ迷い込んだかのような、孤独感を募らせ、ずっと胸の奥にしまっていた本当の自分を誰かに打ち明けてしまいたいと思うほどに心が弱っている。一杯の温かい紅茶でも十分気持ちは安らいだけれど、自分と同じ血の通った誰かに、じっと話を聞いてほしいという願望が、募り募っていたから。
私は彼女に促されるがままに「分かりました」と頷いて、今日シフトに入ってから杉崎という男性とどんなやりとりをしたのかをナツさんに話し始める。
「私はもう、書けないんです……」
私は高校三年生の時にとある小説を文学賞に応募したこと、なんということもないその物語が、幸運にも大賞を受賞したこと、その時に審査委員長をしていた杉崎が、私に再び小説を書かないかと直接頼みに来てくれたことを話した。
「書けない? でももえちゃんは、小説家になりたいって言ってたよね」
私が途切れがちに話すせいで聞き取りづらいはずなのに、ナツさんはじっと耳を傾けて、疑問に思ったところをすぐさまぶつけてきた。
そう、私は京都天狼院にアルバイトの履歴書に書いた。小説家になりたいと。
だからナツさの質問は、当然の疑問なのだ。
「ナツさん、私の話、ちょっと長くなるんです。それでも聞いてくれますか……?」
ここまで話すと決めたのは、女将のナツさんが——いや、今はただ優しく話を聞いてくれる彼女にきちんと誠意を見せるべきだと思ったから、ではない。
もう、止まらなかったのだ。
私は一度自分の弱いところを話し出すと、全部全部、聞いてほしいと思ってしまった。ナツさんに全部、吐き出してしまいたい。それがどれだけ自分勝手だと分かっていても、今話すのをやめてしまったら、この先一生誰にも打ち明けることなんてできない気がしたから。
「うん、もちろん」
***
ねえ、おばあちゃんは将来、何になりたい?
——おばあちゃんは“書店員”だから、もう何にもならないのよ。
ええっそうなの? なーんだ、つまんないなあ。
——つまらないだなんて、全くこの子はねぇ。
だって、小学校の先生が言ってたよ。“将来の夢”を持ちましょうって。
——そうかい。それは良い先生だね。もえちゃんは何になりたいの?
わたし? ふふ。わたしは、“小説家”になります!
——へえぇ、そりゃ素敵だ。あ、じゃあおばあちゃんの夢、今決めた。
ほんと! なになに?
——おばあちゃんの夢はね、もえちゃんが書いた小説を、自分の書店に並べることよ。
あの日、私が祖母から教えてもらった児童向けの本を読んでから密かに描いた夢を祖母に語った日。
祖母が言ってくれたその言葉が、照れくさくて嬉しくて。それからずっと私にとって何よりの心の支えだった。
中学、高校へと上がるうちに、部活や勉強で何かと忙しくなり、祖母に会いに行く機会はめっきり減っていた。中学二年生の夏休みに訪れたきり、高校時代、長いお休みがあってもなかなか祖母の住む田舎町まで行くことができなかった。
転機が訪れたのは、高校二年生の冬。
祖母が倒れたという知らせを聞いた。
ちょうど冬休みで「あけましておめでとう」と家族でお祝いをしてからほんの数日経った頃だ。
初詣や初売りには行き尽くしてしまい、「今日はのんびり家にいるか」と家族みんなが家の中でダラダラと休みを満喫していた時だ。
真昼間に電話が鳴って、やることがないからと部屋の掃除をしていた母が受話器をとった。
電話は祖母と一緒に暮らす、母の姉からだった。
私からすれば伯母さんに当たる。
伯母さんからの電話で、「ええ、うん……」と相槌を打つ母が突然、「ええ!?」と驚きの声を上げ、その声に私はビクンと肩を震わせた。
「そ、そう……。分かった」
力の抜けた返事をした母は、そのまま受話器を置いて、各々だらけきった1日を送っていた私たち家族にこう告げた。
「おばあちゃんが、倒れたんだって」
聞くところによると、祖母は在宅中に心臓の病で発作が起き、側にいた伯母が慌てて呼んだ救急車で病院まで搬送されたそうだ。
伯母がたまたま側にいたからまだ良かったものの、もし祖母が一人きりだったら、それこそ祖母は助からなかったかもしれないと思うと、心から神様に感謝した。
「私、ちょっと様子見てくるわ」
あと数日すれば学校が始まる私を連れて行くことなく、母は一人で遠くの病院に入院している祖母の元へと見舞いに行った。
数日経って帰ってきた母は、「うん、とりあえず今は大丈夫みたい」と冷静に言った。その様子とは裏腹に、祖母のことを心配していたせいか、数日前より頰が痩せているように見えた。
かくして祖母が倒れた鈴木家の事件はその年はそれ以上の展開に発展しなかった。もちろんそれはとても喜ばしいことだったため、私もしばらくは心配だったが、新しい学期が始まってからというもの、再び忙しい毎日に追われ、祖母のこともそれほど思い出すこともなくなっていた。
「それで、終わりだと思ったんです」
私は、隣で黙って話を聞いてくれているナツさんに、これから自分が話さなければならない出来事を考えると、心が痛くなる。
「そう……。大変だったんだね。でもそんなふうに言うってことは……まだ終わってないってことだよね」
「はい。終わりませんでした。終わってないというか、まだ始まってもなかったんです」
あの時のことを思い出すと、今でも胸が締め付けられるように痛い。
私は高校三年生になった。
そして夏休み、例によって書き上げた小説『青のまんなか』をあおい文学賞という賞に応募したのだが、それが大賞を受賞してしまった。
それ自体とても嬉しくて、舞い上がりたい気持ちで、母も父も「よかったね」と喜んでくれた。
その後電話で受賞を知らせてくれた杉崎が、3月に行われる授賞式の出欠について再び連絡をくれたため、私は二つ返事で「出席させていただきます!」と威勢良く答えたのだった。
しかし、そんな喜ばしい出来事に今後の夢を膨らませていた時、私たち家族に再び暗雲が押し寄せてくることとなる。
「え、またおばあちゃんが倒れた!?」
知らせを受けたのは、授賞式もすぐそこまで迫った3月始め。
私は大学受験を終え、あとは合格発表を待つのみ、という宙ぶらりんの日々の最中にいた。
後期試験の対策をするにも新生活に想いを馳せるにも、どうにもこうにも心がソワソワして、結局何も手に付かない……という私を尻目に、母は受話器を握りしめたまま硬直していた。
「しかも今度は、もう治らない……」
電話の向こうには、やっぱり伯母がいるんだろうか。伯母も、辛そうな表情でどうしようもない事実を母に告げているのだろうか。
それからしばらく母が「うん」とか「そう……」とか暗い声で頷いて、「じゃあまた……」と電話を切った。
そして、私に向かってこう告げたのだ。
「おばあちゃんの病気、悪くなって……もうあと少ししか生きられないんだって……」
自分よりもうんと年上の祖母がいつかそうなることぐらいは分かっていた。母もきっと、去年祖母が倒れてからずっとそのことを考えなかったわけではないだろう。
でもやっぱり、「あるかもしれない」未来を案じるより、「起こってしまった辛い現実」を直視する方が何十倍も悲しいことだった。
「あと少しってどれくらい……?」
この手の質問をすべきかどうか迷った。
だって、もしこれで「1年」とか「半年」とか言われたら、本当にショックを受けると分かっていたからだ。
だから、バクバクと鳴る心臓を抑えながら、恐る恐る母に聞いた。
「1ヶ月、なんだって」
1ヶ月。
出てきた答えは予想をはるかに上回るほどの短い期間で、思わず「えっ」と声を漏らした。
「そうらしいの……」
「……」
事態はあまりに性急で、現実と思考がやっぱり追いつかない。
けれど、何度聞いても母の口から出てくる言葉は、祖母の命の時間が雀の涙ほどしか残されていないということだけだった。
祖母の容態を聞いてから、母はすぐさま祖母の家に飛んで帰った。
私も、学校に事情を話し、何日かお休みをもらって数日後に母を追いかけた。
「おばあちゃん」
久しぶりに再会した祖母は、伯母さんの家のベッドで安らかに眠っていた。
病院の先生が、残り短い命だからと、祖母を家に帰してくれたらしい。祖母にとっても、残された母や伯母にとっても、その方が良いのかもしれない。しかし私はそれを聞いて、逆に不安になった。
本当に祖母が、もうすぐいなくなってしまうことを、突きつけられた気がしたから。
母や伯母と祖母の様子を見ながら、しばらくの間伯母夫婦の家で生活した。
祖母は時々しか目を覚まさなくて、目を覚ましても、私たちと会話する気力がなく、ただ目を細めて話しかけてくる母や伯母に頑張って笑いかけるだけだった。
「そういえば、もうすぐ表彰式よね?」
そんな生活を続け、数週間が過ぎた日の夜、母が唐突に私にそう言った。
「うん、そうだけど」
そう。第145回あおい文学賞の表彰式が、二日後に迫っていた。
けれど私は、そのことを、伯母の家で一度も口に出しはしなかった。
祖母が大変なこの時期に、私だけのうのうと表彰式に出席するなんて、考えられなかったから。
「あんた、ちゃんと行ってきなさいよ」
「うーん、でも」
「せっかくの機会でしょう? しかも大賞の。あんたが行かなくてどうすんの」
「大賞だろうが何だろうが、出欠は自由だし……それに、こんなときに」
行けるわけないじゃん、と母の前でボソッと呟いた。
「何言ってるの。おばあちゃんだって、あんたの晴れ姿を見たいに決まってるのに」
でも見られない。
だからって、欠席したら、もっと悲しむわ。
「もう、選考委員の人に連絡したから。出られなくなったって」
嘘だった。
あまりに頑なに「出席しなさい」と主張する母を諦めさせるために、私は嘘をついた。
「そうなの? まったく……」
呆れてものが言えない、という様子の母を尻目に、私はほっと安堵する。だって、祖母の身が危険な時に表彰式に出るなんて、罪悪感でいっぱいになるに違いないから。
だから、そんな窮屈な思いをするぐらいなら、表彰式ぐらい欠席する方がましだった。
ましだと、思っていたのに。
「母が、勝手に杉崎さんに連絡していたんです。『やっぱり娘は表彰式に出席します。ご迷惑おかけしてすみません』って」
「そうだったんだ」
頷くナツさんに、私は話の続きを語った。
母は私の話を聞いたあと、私に隠れて杉崎に連絡したらしい。私のスマホの着信履歴でも見たのか、気づいたら表彰式当日の朝、控えめな白いワンピースを手にした母が、私のいる部屋に現れた。
「昨日、杉崎さんに連絡したのよ。そしたら、あんたが欠席するなんて連絡来ていないって言うじゃない。それで嘘って分かったけど。でも、杉崎さんが、鈴木さんにはぜひ出席してほしいって言ってくださって」
電話を受けた杉崎が、私の出席を強く勧めてくれたというのは分かる。
そりゃせっかく表彰式をするのなら、一番の主役がその場にいた方が、式のやりがいがある。
「杉崎さんは、あんたの作品がすごく好きだって言ってた。良かったわね」
「うん……」
もはや抵抗する気力もなく、母の言葉を受け止めた。
なんだかんだ、審査員が自分の作品を「イイ」と言ってくれたという事実は、底知れない喜びを運んでくれたからだ。
「だから、ほら。行ってきて。このワンピース着て」
私は、母から差し出されたワンピースをおとなしく受け取って着替えた。
そして、祖母がいる部屋に行き、返事は返ってこないと知りながら、祖母にこう告げた。
「おばあちゃん。私小説を書いてね、それを文学賞に応募したの。それを良いと言ってくれた人がいて……だから、今からちょっと行ってくるね。帰ってきたら、またどんなんだったか話すから」
高校三年生の私は、子どもの頃の私より、随分とぶっきらぼうで素直じゃなくなってしまった。殊に、家族に接するときには。だからこのときも、もし祖母が元気で普通に会話ができる状態だったら、私はこんなふうに祖母に話しかけることができなかっただろう。
だって、その時だってとても、照れくさかったから。
相変わらず、祖母は何の言葉も声に出して発しなかった。
でも、必死に私の目を見つめ返してくれるその姿から、私に「いってらっしゃい」を言ってくれていると理解した。
だから私は第145回あおい文学賞の表彰式に行くことに決めた。
しかしそれが間違いだったと気づいたのは、表彰式当日、滞りなく進んだ式の終盤に、“あの知らせ”が来るまでだった。
「まさか、その式の最中に……?」
それまで何にも動じずに私の話に耳を傾けてくれていたナツさんが、話の展開を予想して、不安げな声でそう訊いてきた。
きっと今ナツさんが想像していることは、私がこれから話そうと思っていることと、同じだろう。
「はい……。表彰式の最中に、祖母が……亡くなりました」
知らせを聞いたとき、表彰されている学生たちが、写真撮影のために、ステージの上で一列に並んでいるときだった。
「鈴木さん! 今すぐこちらへ……!」
私は脇から出てきた裏方のスタッフに呼ばれ、「こんな時に何だろう?」と不思議に思いながら、しかし最悪の予想が、胸の中に渦巻く状態で、ステージから降りて舞台袖に向かった。
「先ほどお母様からご連絡があって……お祖母様が!」
私に祖母の訃報を知らせてくれたその人も、これまでにない経験だったらしく、とても焦っているように見えた。私にはその人の焦りが、ちょっとだけありがたいと思った。だって、スタッフが狼狽えていなければ、とてもじゃないが、もらった花束をしっかりと手にしたまま、平然と立っていられる自信がなかったから———。
その後のことは記憶が曖昧としていて、私は自分がどうやって伯母の家まで帰ったのか、あまり覚えていない。
どこか現実味のない、フワフワとした感覚のまま、たぶんタクシーにでも乗り込んだんだろう。まだ表彰式が終わっていない会場を後にするとき、審査委員長の杉崎が、私のところまで駆け寄ってきて、肩をしっかり掴み鎮痛な面持ちのまま、私の目を見つめたことだけは覚えている。今考えると、あれは「しっかり」という意味だったのかもしれない。
タクシーで伯母さんの家まで帰り着く。
玄関の扉を開けると、母や伯母さん夫婦が、私の肩を無言で抱いた。母はむろん、泣いていた。
ドクドクと鳴る心臓。だんだんと荒くなってゆく自分の呼吸を必死に鎮めながら、祖母が眠っているその部屋の扉を開けた。
祖母は、まだそこにいた。
白い布切れ一枚をかぶった姿で、眠るように横たわっていた。
ドラマか何かで見たことのあるような光景だった。私はその姿を、魂の抜けた人形のように無言で見つめた。
それからそっと、白い布をめくって、眠っている祖母の顔を見る。
昨日と変わらない祖母の安らかな寝顔が、自分でも思いもよらないほど脳裏に焼き付いた。
その瞬間に、狂おしいほどの涙が、握りしめたままだった花束に、ボタボタと音を立てて落ちてゆく。
祖母がいなくなった悲しみは、自分が祖母の死に目に会えなかったやるせなさへと変わり、やがて表彰式に出席してしまった自分への怒りに変わった。
どうして。
どうして、どうして。
私はどうして、祖母のそばにいなかったんだろう。
どうして呑気に表彰式なんかに出てしまったんだろう。
どうして、書き上げた小説を、あおい文学賞になんて応募してしまったんだろう。
どうして私は、小説なんて、書いてしまったんだろう———。
問いかけても問いかけても帰ってこない答えが、自分の中で罪悪感へと変貌を遂げ、暗い塊のまま心の一番奥深くに棲み付き、離れなくなってしまった。
「だから私は書けないんですっ……」
京都天狼院の女将ことナツは、私の目から見てもはっきりと分かるぐらい困っているようだった。
困る、という表現をすると、私に対して迷惑がっているというようなニュアンスになってしまうが、決してそうではない。
どんなふうに言葉を返したら良いか考えあぐねている、そんな様子だった。
しかしやがて、興奮気味の私を落ち着けるように、私の肩にそっと手を添えて、こう言った。
「書きたくないなら……、書けないんなら……、書かなくてもいいんじゃないかな」
静かな夜の店内に、彼女の声色はあまりに似合いすぎた。
それはまるで、ナツさんが自分自身に言い聞かせているようで、私はテーブルの木目の一点を見ている彼女の横顔を、食い入るように見つめた。
ナツさんの言葉に、私は思わず頷きそうになった。頷きたかった。でも、首を縦に振ろうとしたその瞬間に、気づく。
何かが違う、と。
そう、ナツさんの言葉の中で、一つだけ間違っていることがある。
それが私の“違和感”で、それのために私は今どうしようもない葛藤を抱えているような気がして、言わずにはいられなかった。
「違うんです。“書きたくない”んじゃないんです。“書きたいのに書けない”んです——」
私が本当に悩んでいたこと。
なぜ杉崎が私に「もう一度書いて欲しい」と言ってくれた時に、息苦しさを感じてしまったのか。
「絶対に書きません」とは言わず、「書けない」という言葉を無意識のうちに選んでいたのか。
もしも、私が心から「書きたくないから書かない」と希望すれば、あとから思い悩むこともなかったし、人前で泣いたりできなかった。
だけど、本当は違うのだ。
書きたいのに。
書きたいと願っているのに。
なのに、書けない。
ペンを握って白紙のルーズリーフを前にする時、パソコンの前に座って真っ白な文書を目にした時、吐きそうになって、震えが止まらなくなる。
私が書いたから、祖母の死に目に遭えなかった。
私に物語の楽しさを教えてくれた祖母がいなくなって、どうしたらいいか分からなくなった。それはまるで、突然の嵐に船頭を失ってしまった沈没しかけの船のようだ。
私が書いたから祖母が死んだわけではない。
でも、表彰式に行く前に、寝たきりの祖母が私を見つめて何か言いたそうな顔をしていたのが、何度も脳裏に浮かんだ。それがまるで、「行かないで」と訴えていたかのように思えて仕方がなかったから。
私はそんな祖母を振り切って表彰式に出席してしまったのだ。
だから、神様がきっと、私に天罰をくらわせたのだ。
お前のように家族のことを顧みないやつは、苦しんでしまえって。
その神様の思惑通り、私はあの日表彰式から帰って以降、一度も小説を書いていない。
それは「書きたくない」からじゃない。
物語を書こうとすればするほど、あの日の出来事を思い出して苦しくなるからだ。
祖母のことを、もう私の物語を読んでくれることはない人のことを、思い出してしまうからだ。
けれど、それでも。
それでも私は。
「書きたい……。本当はあの日のことに囚われずに、もう一度書きたい。だけど、指が、動かないんです……。言葉が、浮かんでこない。気持ち悪くなってパソコンの画面を閉じてしまうんです。ナツさん、書きたいのに書けない人は、どうしたらいいんでしょう? 書きたくない人は、無理して書かなくていいと思うんです。だってそれはその人の自由ですから。でも……、でも、書きたいのに書けない人は、翼を引きちぎられた鳥は、どうしたら飛べると思いますか……?」
私は知りたかった。
京都天狼院書店で働き始めてからずっと。
一時は「やっぱりもう、ダメなのか」と諦めようと思いながら、それでもお客さんや人生相談にやってくる人たちと関わるうちに、私はもう一度書けるかもしれないと希望を抱いたこともあった。
しかし、バイトが終わって帰宅し、いざパソコンを開いてみると、まるで私という魂が他の誰かと入れ替わってしまったかのように、指が硬直して動かなくなる。それならばアナログでいこうと思い、パソコンをペンとノートに変えてみたがだめだった。
一体どうして?
私の何が悪いの?
「それは……」
ナツさんは、橙色の照明の下で睫毛を伏せ、私に何を言うべきか、考えている。
けれど私にとっては、もうそれだけで十分だった。
こんなわけのわからない悩みを聞いてくれただけでも、感謝しきれないほどだから。
「すみません。意味わかんないですよね。もう少しだけ、悩んでみます……」
「遅くまで、本当にありがとうございます」と深く頭を下げて、私は椅子から立ち上がった。腕時計を見ると、そろそろ日付が変わる頃だ。
私は荷物をまとめて、階段の方へ歩いた。
まだ座ったままのナツさんが動く気配はしない。
とん、とん、と静かに階段を踏み鳴らしながら、私は心の中でため息をつく。
言ってしまった。
自分の身の上話なんて、京都天狼院書店で働いていて一度もしたことがなかったのに、弱みまで晒してしまった。
これからまたここで働くことを考えると、少し気が重い。
「はあ……」
店から出て扉を閉めた時に、そんな後悔が夜の闇とともに押し寄せていた。
≪第六話 中編 終≫